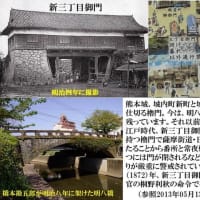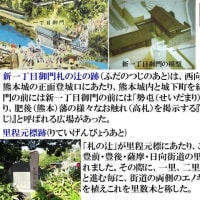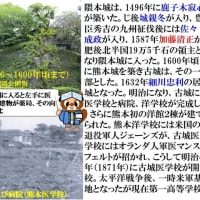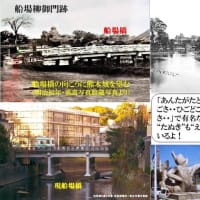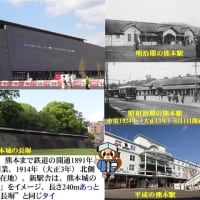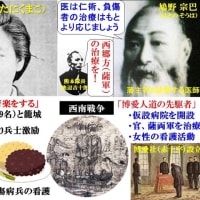おはようございます。
くまもとよかとこ案内人の会のブログにアクセス頂きありがとうございます。
熊本市は2016年7月12日、熊本地震で崩落した石垣から、『人形(ひとがた)』と呼ばれる人物の線刻画が描かれた石を発見したと発表。
この報道を新聞とテレビで知ったとき、自分で目で見たい!と思った。

(2016年7月30日付 熊本日日新聞)
嬉しいことに、 城彩苑の湧々座で公開されることに。
すぐ見に行きました。

生まれてはじめて人形は『こけし』のようです。
これは1600年代前半のものと推測され、加藤時代のものとみられます。
史料が残っていないので、あくまでも推測ではありますが、熊本城調査研究センターによると、『加藤時代の石垣建設における地鎮や祈念の意味があるのでは』とのこと。
400年の築城当時、熊本城の石垣建設は本当に大変だったと思う。山から石を切り出すのも、運ぶのも、そして積み上げるのもすべて人力であり手作業。何度も危険な目にもあっただろう。そういう意味でも、無事工事が終わることを祈るのはよくわかる。
熊本地震で熊本城は甚大な被害を受けたが、築城当時の人々の想いに触れることができ、この貴重な経験は一生忘れないようにしたい。

人形はここから出てきました。
宮内橋横の石垣です。ここは高さ約9メートル、幅約19メートルあり、その大部分が崩落した。
撤去した約400個の石の中から人形がみつかりました。

現在はモルタルが吹き付けられ、ネットで覆われています。


人柱祠(ひとばしらのほこら)
昭和35年(1960)、城下海岸の遊歩道の工事中、日出城の西南端より木棺が発掘された。
棺は岩盤をくりぬいた穴におさめられ、その上に大石が乗せられ石垣の基盤となっていた。
棺の中からは老武士らしき遺体の人骨とともに陶製の翁像が、大石の上からはカブトの金具などが発見された。
大分大学の半田・富来両教授や文化財関係者の調査の結果、日出城築城当時の人柱であろうと推定された。
日出城の築城工事は、城の西南部の地盤が弱く難工事であったと伝えられており、また方位上から城の裏鬼門にあたることなどから、人柱を立てたのではないかと考えられている。
棺の出土した地点の石上には人柱祠が祭られており、その昔の哀れさをしのび、祠に花を飾り香華をたむける人々が後を絶たない。(日出町教育委員会)
熊本地震の数日前、大分の日出城に行った。その時に人柱祠を見た。
熊本城にもこういうことがあったんだろうか? その時は気になったが、地震でそんなこともフッ飛んだ。
それが人形の石が発見され、日出城の人形も再び脳裏に浮かび・・・。
当時、人柱によってお城を災いから守ったのだろう。でも、人柱ではあまりにも、あまりにも・・・。それで人形で代用したのかな。それが日出城はできなかったということかな。

くまもとよかとこ案内人の会は、
熊本城を中心に熊本市のよかとこ!(良い所)をご案内しています。
熊本城下『城彩苑』に平日3名、土日祝日4名が待機しています。赤いジャンバー(ポロシャツ)のユニフォームが目印です。
無料で熊本城を1時間位ご案内致します。
お一人様でも、グループ(7~8名)でもご利用いただけます。どうぞご利用下さい。
城彩苑案内所常駐ボランティアガイド
受付時間 9時~15時
熊本市内のご希望場所へのご案内は事前のご予約をお願いいたします。
ガイド料は無料ですが、交通費としてガイド1名に付き2,000円お願いしております。
観光ボランティアガイド 『くまもとよかとこ案内人の会』
http://www.k-yokatoko.com/
熊本市中央区二の丸1番1-3
桜の馬場 城彩苑 総合観光案内所内
電話 096-356-2333