2018年6月23日(土)
今年の精神神経学会は神戸開催、水曜日にゼミを終えたその足で現地に移動した。月曜日の朝、大阪北部地震が起きて関西のゼミ生の安全を案じたが、今度は気遣われる立場である。学会の主催者からも大学の事務担当者からも注意喚起があったものの、結果的には支障なく予定を終えつつある。福島の原発事故被災地の現状に関するシンポジウムもあり、多くを学んだ。神戸の学会にはとりわけふさわしいテーマに違いない。
ブロック塀の倒壊で小学生が亡くなったこと、出先で会う人々が口々に残念がった。とりわけ神戸で生まれ育った義母は「阪神淡路の時あれだけ言われたのに」と悔しがる。僕は2011年3月11日のことを思った。あの日は金曜日、週明けを待って郡山のE先生に電話で様子を聞いたら、患者さんの動揺や浜通りへの懸念などを語った末、郡山市内はさしたる実害は見えないものの「至るところのブロック塀が崩れて自動車が通れない」と苦笑した。午後2時46分は小学校児童の下校時刻と微妙にずれていただろうか、そのきわどい幸運から学ばねばならなかったのだ。
住宅街の塀がどこもかしこもブロックになったのはいつ頃だろう?おおかた高度成長期かと想像され、利便性・耐久性・経済性などとあわせ遮蔽性という言葉が浮かぶ。物理的には堅牢で用心がよく、心理的にもそこに隔壁があることを強くアピールするのがブロック塀である。裏を返せば伝統型コミュニティの可視的な裁断・分節に一役買ってきただろう。今となっては防災の観点から、人口密集地でのブロック塀の設置を制限する措置が必要と思われる。代わりにどんな素材・工法を使うかは考えどころだが、それこそ日本人の得意とする工夫の領域、コンテスト形式でアイデアを募れば国中の企業や個人から名案・妙案が山ほど出るに違いない。
良い工法が見つかったら亡くなったお嬢さんにちなんで命名し、後世に伝えてはどうだろうか。
***
先だってT教授が今後の日本の課題を「退却戦」に喩えたが、これには一理も二理もある。それで『島津奔る』(池宮彰一郎)というタイトルが以前から気になっていたのを思い出し、Amazon で取り寄せて学会の行き帰りに読んでみた。
薩摩島津は『西郷どん』でまたブレイクしているが、薩摩人集団の独自固有なことは昔から繰り返し話題にされ、司馬遼太郎はとりわけその外交感覚が日本人離れしていると評した。関ヶ原の帰趨が決まった時、「前へ向かって退却した」と評したのも司馬遼だったか。読んでみたら『島津奔る』の冒頭は、まさしく慶長の役における朝鮮半島からの退却戦に始まる。全編が退却戦の歴史的実例のようなものである。
1598(慶長3)年陰暦九月、秀吉存命中から著しく士気の落ちていた日本の諸将は既に半島南端に追い詰められ、明と朝鮮の大軍が復讐に燃えて北から接近しつつあった。海上では名将李舜臣を擁する朝鮮方が圧倒的に優勢で、日本軍は全滅しても不思議のない窮境にある。これでよく無事撤収できたことと以前から不思議だったが、その秘密は泗川(しせん)周辺での島津勢の果敢かつ巧妙な退却戦にあったのだ。不利な水上戦でも巧みな反攻によって敵方の追撃を不能にし、李舜臣はこの戦いで落命している。そもそも文禄・慶長の役なるものが義も理もない侵略行為で、日本史上の汚点であるために注目もしづらいが、ここに描かれる島津義弘と郎党の戦いぶりは見事というほかなく、おかげで日本の全軍が全滅を免れた。これが物語の前半部分。
後半、今度は関ヶ原の「前への退却」である。詳細は略すとして、碁の教える機微が泗川と関ヶ原の島津の戦略に共通しているようだ。攻める時はおおらかがよく、本気で相手の石を取りにいくのは下策としたもので、相手を活かして打つ 〜 活きようとする相手の力を利用して大局の得を図るのが本道。逆に攻められた時はただ逃げ回るだけではいけない、シノぐ時こそ相手の弱点を鋭く衝いて強襲し、刺し違えの脅しをかけつつ活路を見出す。好んで戦争の話をしているわけではない、人生にも社会にも役立つ心得が見つからないだろうか。
退却戦こそアグレッシヴに、そのことである。
***
関ヶ原や家康の天下取りについて書かれたものは数知れずあるが、書く人ごとに何かしら見解の違いがあって面白い。例えば開戦直後の伏見城攻防戦、三成が事を起こせば、まっさきにこの城を落としにかかるのは目に見えている。その伏見城を託されたのが鳥居元忠、今川家の人質時代から艱難を共にした家康無二の腹心で、ここが死に場所と志願の花道というのが大方の解釈だった。
『島津奔る』では天下は家康に傾くと判じた島津義弘が、自分が伏見城に入ることを内々に申し入れ、家康いったんこれを容れた仔細が語られる。難戦には心得のある義弘、100日や200日は寄せ手を悩ます自信が優にあり、その末に全滅を被っても家康に恩を売ることで島津本家は安泰と読んでいる。ところが家康の家臣団がこれを受け入れない。島津が寝返って城ごと西軍に投じたら、東軍は袋の鼠だというのである。あるいは、薩摩本国の島津義久(義弘の兄)が援軍を送らぬ可能性があると謀将本多正信の言。このあたり、島津義弘の人柄を惜しむ家康と排他的な三河家臣団との描きわけが面白い。結果的に家康は内諾を反故にし、東軍入りを拒絶された島津は 〜 「中立」のあり得ない武家の政治力学に従って 〜 心ならずも西軍に与することになった。(ただし関ヶ原当日は、勝敗が決まるまで兵を動かしていない・・・)
それはさておき鳥居元忠、こちらは家康との君臣超えた信頼のゆえに入城したのではなく、頑迷固陋の老将として家臣団の中で敬遠されており、いわばこの機に捨て駒にされたというのが作品の解釈である。島津義弘腹心の新納旅庵(にいな・りょあん)が伏見城に鳥居元忠を訪ねて追い返される場面が印象的で、元忠は言葉の端に島津への哀惜をこめて忠告するが、義弘はその顛末を予見していた。
「元忠の苦衷は察するが、あやつめは一介の武将だ。美しく戦って死花を咲かせ、青史にその名を残すのみである。だが、われらはそれでは事足りぬ。この絶体絶命の境地で、わからずやどもの家と郷国を、いかに残すか。考えるだけでも気が遠くなる、が、まあ見ておれ、わしはまだ、望みを断ってはおらぬ・・・」(上巻 P. 414)
壮絶な退却戦がここから始まる。家康を間一髪まで追い詰めた者が三人あり、先に武田信玄、後に真田信繁(幸村)、その間に島津義弘を加えようか。「前へ退却した」島津の群れは、家康の本陣に肉薄したところでなぜか転進、伊勢路へ脱出した。東軍の猛追に島津方は島津豊久(義久の甥)、長寿院盛淳(ちょうじゅいん・もりあつ、家老)らが身代わりとなって討ち死にし、見事に義弘を薩摩へ落とす。ここでも島津は捨て身の反撃を随時に交え、井伊直政は銃弾を受けて深傷を負い、松平忠吉(家康の四男、秀忠の同母弟)も負傷している。
最も興味深いのは、実はその後の戦後交渉かもしれない。島津は西軍に加わりながら咎めを受けなかったばかりか、本領安堵のうえ琉球支配の許可まで得た。まるで手品のようである。家康を目前に義弘が転進を命じた時、既に戦後交渉が始まっていたと『島津奔る』の筆法。徳川方でこの交渉を買って出たのは、追撃中に被弾しそれが二年後の死の原因になったとされる井伊直政だった。
ことほど左様に不思議の山、「島津の退き口(のきぐち)」と呼ばれるアグレッシヴな退却戦に何を学ぶか、学べるか。

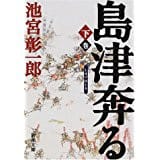
Ω









