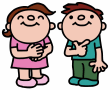以下引用 毎日新聞 2016年6月9日 東京朝刊  http://mainichi.jp/articles/20160609/ddm/004/070/021000c
http://mainichi.jp/articles/20160609/ddm/004/070/021000c

共生社会目指し対話を 静岡県立大教授・石川准氏
障害者差別解消法が4月1日に施行された。障害のある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目的としている。私たちは、この法律をどう生かしていったらよいのか。法制定を求めてきた石川准・静岡県立大教授(59)に聞いた。【聞き手・森本英彦】
−−障害者差別解消法が施行された意義をどう考えますか。
この法律は、障害者に対する「不当な差別的取り扱いの禁止」=1=と、「合理的配慮の提供」=2=を、行政機関や事業者に求めています。障害者が直面する問題を解決していく上で、合理的配慮の提供が極めて重要だということをしっかり法律で規定した点が大きな意義です。過重な負担をしなくても合理的配慮によって障害者の妨げになっている社会的障壁を取り除けるのに、それを提供しないのは「差別」であると位置づけたわけです。
日本は2007年に障害者権利条約に署名した後、条約批准に向けて多くの国内法を改正したり、新法を制定したりしましたが、この障害者差別解消法が最も重要だと思います。
−−合理的配慮という言葉は一般にはまだあまりなじみがありません。
私は少しでも多くの人に配慮の平等という視点を持っていただきたいと考えています。健常者は配慮を必要としない人なのではなく、すでに配慮されている人であり、障害者は特別な配慮を必要とする人というより、十分に配慮されてこなかった人なのです。だから配慮の不平等を解消するためにこういう法律が必要だったのですというように申し上げています。
障害者差別解消法の趣旨は、障害のある人とない人が共に暮らす包容的で共生的な社会を作っていくためのツールとして法を活用していくことにあります。私は「建設的対話」がキーワードだと考えており、同法の基本方針にも取り入れられました。合理的配慮の提供について、どういう方法なら可能なのか、お互いに誠実に話し合い、良い方法を一緒に発見していこうという考え方です。さまざまな関係機関による「障害者差別解消支援地域協議会」も地域ごとに作られることになっており、そうした場などでの建設的対話を通じて社会の理解が深まっていくと期待しています。
−−実際にどういうケースが合理的配慮にあたるのか、分かりやすい物差しを示してほしいという声もあります。
内閣府のウェブサイトにある「合理的配慮サーチ」には、合理的配慮の事例が挙げられています。しかし、何が合理的配慮にあたるのか、何が行政機関や事業者にとって過重な負担なのか、といったことは一義的に決められるものではないので、事細かくルール化するよりも、それぞれの現場で良い方法を一緒に考えていくことが大事です。共生社会を作っていく学習プロセスだと考えてもらいたい。何が合理的配慮なのか、徐々に共通感覚が生まれてくるのではないでしょうか。
−−行政機関や事業者だけでなくわれわれの日常生活にも関わってくるのでしょうか。
今までは「善意」のつもりでやってきたことが「義務」となったのかと、戸惑いを口にされる人は結構います。強いられるような感じで嫌だと……。
しかし、善意の基盤にあるのは、「ここで手をさしのべないのは人として正しくない」という正義についての感覚だと思います。それを法律の形で整えたと考えたらどうでしょうか。負担感だけが増えるみたいな形になると、この法律は生きません。合理的配慮がある社会は、安心で、良心的な人が多く、真面目で、共感力があり、そういう社会の一員であるという感覚は悪くないと思うのです。「誰もが生きやすい社会を作っていく」という法の趣旨を一人一人が実感できるようになってほしいですね。
また、この法律は障害者だけを特別扱いするものではありません。人間は荒々しいむき出しの環境の中で生きていくことはできず、環境を作り替えてきました。暑すぎたり、寒すぎたりする場合は冷房や暖房を使い、夜も行動できるように照明を整え、車が走れる道路を作る−−といった環境整備がそれに当たります。障害者への合理的配慮の提供も、環境と人との不適合状態を解決していくという意味では全く同じことなのです。
−−ご自身は社会的な障壁を実感された経験はありますか。
私は研究者なので本や論文を読む必要がありますが、紙ベースの資料だとそのままでは読めず、情報へのアクセスにおける障壁を痛切に感じてきました。結局、自分で自動点訳ソフトを作ったり、パソコンの画面を読み上げるソフトを作ったり、視覚障害者の歩行ナビゲーションなどの支援機器も開発してきました。
現在勤務している静岡県立大学では1990年代後半という比較的早い段階から、障害のある教員に対して支援スタッフを付けてくれるようになりました。大学によっては、まだできていない所もあります。今回の合理的配慮の義務化で、進展することを希望しています。
−−20年には東京パラリンピックがあります。
日本社会に大きなインパクトを与えるでしょうね。多様な人たちが世界からやって来ます。多様な人たちが住みやすい街づくり、インクルーシブ(包摂的)な都市づくりを進めていくチャンスです。半世紀前の前回大会は、戦後の高度成長が始まり、皆が未来に対する夢を共有していた時期でした。今度は、多様な人々が共に生きる社会のイメージを皆で膨らませ、実現していくプロセスになります。至るところでインクルーシブな社会を作るための建設的な対話が始まることを期待しています。
聞いて一言
Jリーグ初代チェアマンの川淵三郎さんは1960年ごろ、遠征先の旧西ドイツで車椅子の市民がスポーツを楽しむ姿を見て衝撃を受けた。当時の日本では考えられない光景。同じ敗戦国なのに何と幸せなのか−−と。石川教授はそのエピソードを私に紹介し、「多様な人たちが共生するには困難がたくさんある。だから『対話』が必要」と強調した。パラリンピックが4年後に迫る日本。川淵青年が感じたように、訪日外国人がうらやむ共生社会に踏み出していることを願う。
■ことば
1 不当な差別的取り扱いの禁止
行政機関や事業者が正当な理由がないのに、障害を理由として、サービスの提供を拒否・制限することや、障害のない人には付けない条件を付けることを禁止した。正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが求められる。
2 合理的配慮の提供
障害者が社会生活を営む上で妨げとなるさまざまな事象、制度、慣行など(社会的障壁)について、障害者から除去を求める意思が伝えられた際に、負担が重すぎない範囲内で、障害の状況に応じた対応をとること。例えば、乗り物への乗車にあたって職員などが手助けする▽筆談、読み上げ、手話など障害特性に応じたコミュニケーションをとる▽段差がある場合に車椅子利用者を補助する▽自筆が困難な人からの要望を受け、本人の意思を十分確認した上で代筆する−−といったことが考えられる。行政機関には法的義務が課され、民間事業者は努力義務とされた。
■人物略歴
いしかわ・じゅん
1956年生まれ。高1の時に失明し、77年に点字試験受験者で初めて東京大に合格。大学院(専攻は社会学)に進み、97年から静岡県立大教授。内閣府障害者政策委員会委員長も務める。