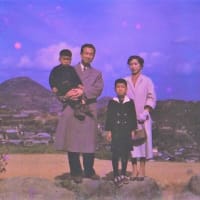新兵器と言っても
決して核の話ではありません。
自転車の話です。
これまで、六甲山サイクリングしていたのは
摩耶山頂の駐車場まで自転車を車で運び、
そから六甲山の山頂までの間を往復するものでした。
もちろん、六甲山のふもとからすべて自分の足で
自転車を漕いで登れたらという気持ちは持ち続けて居ました。
しかし、手をコマネイテいても拉致があかない。
かと言って僕の脚力で攻めても失敗するのは目に見えている。
ウーン、しからばどうするべ。
で出した結論は新兵器。
それは、
電動補助付きサイクリング自転車。

とうとう、手に入れてしまいました。(高かった!グスン)
いろいろと試しながら僕の使い勝手の良いように手を加えて
今回初登場です。
背中にザックを背負っての自転車は性に合わない。
自転車に直接載せても、背負って乗っても
自転車の負担は変わらないから、それなら、
自転車にすべて負担してもらって、僕はザックから解放!
というのが僕の主義だから、まずは
ザックを自転車に取り付けるための補助バーを取り付け

自転車をばらして車の乗せて移動するのを想定して、
スタンドの取り付け位置を変更。

前の方に移動して取り付け、車輪を外しても邪魔にならない場所にということです。
それ以外にもあれやこれやを加工して、いざ出発として定めた目的地は、
三木街道沿いの駅から六甲山山頂!!!
約800mの高度差です。
スタート地点を写真に撮り忘れ、
最初に撮った場所は神戸電鉄木津駅近くの神社。

この辺りは神戸の古い農村ですが、由緒ある神社のようです。

この集落を過ぎると目に入るのは、山陽・徳島道です。

このトンネルの向うに向かって走ると、山陽道で、
そのまま下関につながっています。
車で下関に行くときに最初にくぐるトンネルです。
しばらく行くと、道路の勾配が急にきつくなってきます。
向うに見える道路ガードを見てください。

あとは自転車の電動アシストを頼りに登っていくと、
鈴蘭台の街に着き、さらに鈴蘭台を過ぎると、
有馬街道にたどり着きます。

この先の道路を左右に走っているのが有馬街道になります。
交差点を左に曲がって有馬街道を走ります。
車の多さに恐怖を覚えつつ、進むと、温泉の看板が目に入ります。

下関出身の仲間と六甲山系をハイキングしたときにも利用した温泉です。
さらに有馬街道を進むと、小部(おぶ)峠に出ます。

この交差点を右に進めば六甲山、西六甲ドライブウエーです。
学校などを通り過ぎるとそこは森林浴の世界です。

この先を少し進むと、元町からの再度山ドライブウエーとの合流点です。

右に進めば再度山を経て神戸市街地へ、
左に進めば六甲山方面です。

更に進むと、森林植物園の入り口があります。

もう少しすると、アジサイの季節になります。
更に登っていくと、六甲山牧場にたどり着きます。
そこが摩耶山と六甲山への道の分岐点です。

コースを左にとって登っていくと、
六甲山ホテルの前に出ます。

ハイカーが多く、なかなか良いアングルでも写真が取れません。
すぐ横に、旧館の玄関があります。

更に登って、記念碑台に出ますが、そこには立ち寄らず、
ケーブル山頂駅に向かいました。

なかなかレトロな雰囲気が人気です。
ケーブル駅を過ぎるとかなり急な道路で
写真を撮るゆとりはありませんでした。
なんとか厳しい勾配を乗り越えてようやく六甲山の山頂近くです。

山頂まで一息のところにある茶屋の前です。
サイクリストやハイカーがいっぱいです。
 ★20
★20
山頂までは、勾配がきつすぎて押して登りました。
山頂には大勢のハイカーがいっぱいで、山頂のポール前での
記念撮影も列をなしてましたので、
遠くからパチリでした。
登りに対して下りは楽なものです。
途中、六甲山ならではの注意看板もあります。

ついに、六甲山山頂まで自転車で登ってきました。
電動アシスト車も馬鹿にはできません。
無理して、足に故障を残しても、年よりの冷や水と言われるだけ。
ならば、と選択して取り組んでみたのです。
予備のバッテリーも用意していたのですが、
何とか、最初の一本だけで往復できました。
残量僅かの警告として表示が点滅はしてましたが。。。
でも、なんだか、少々わだかまりが残っているのも確かです。
今度、下関に自転車を積んでいくときは
従来通り、普通のロードバイクにすることでしょう。
火の山に自転車で登ることもないでしょうしね。
6月4日前後、晴れるといいな!!
by W
決して核の話ではありません。
自転車の話です。
これまで、六甲山サイクリングしていたのは
摩耶山頂の駐車場まで自転車を車で運び、
そから六甲山の山頂までの間を往復するものでした。
もちろん、六甲山のふもとからすべて自分の足で
自転車を漕いで登れたらという気持ちは持ち続けて居ました。
しかし、手をコマネイテいても拉致があかない。
かと言って僕の脚力で攻めても失敗するのは目に見えている。
ウーン、しからばどうするべ。
で出した結論は新兵器。
それは、
電動補助付きサイクリング自転車。

とうとう、手に入れてしまいました。(高かった!グスン)
いろいろと試しながら僕の使い勝手の良いように手を加えて
今回初登場です。
背中にザックを背負っての自転車は性に合わない。
自転車に直接載せても、背負って乗っても
自転車の負担は変わらないから、それなら、
自転車にすべて負担してもらって、僕はザックから解放!
というのが僕の主義だから、まずは
ザックを自転車に取り付けるための補助バーを取り付け

自転車をばらして車の乗せて移動するのを想定して、
スタンドの取り付け位置を変更。

前の方に移動して取り付け、車輪を外しても邪魔にならない場所にということです。
それ以外にもあれやこれやを加工して、いざ出発として定めた目的地は、
三木街道沿いの駅から六甲山山頂!!!
約800mの高度差です。
スタート地点を写真に撮り忘れ、
最初に撮った場所は神戸電鉄木津駅近くの神社。

この辺りは神戸の古い農村ですが、由緒ある神社のようです。

この集落を過ぎると目に入るのは、山陽・徳島道です。

このトンネルの向うに向かって走ると、山陽道で、
そのまま下関につながっています。
車で下関に行くときに最初にくぐるトンネルです。
しばらく行くと、道路の勾配が急にきつくなってきます。
向うに見える道路ガードを見てください。

あとは自転車の電動アシストを頼りに登っていくと、
鈴蘭台の街に着き、さらに鈴蘭台を過ぎると、
有馬街道にたどり着きます。

この先の道路を左右に走っているのが有馬街道になります。
交差点を左に曲がって有馬街道を走ります。
車の多さに恐怖を覚えつつ、進むと、温泉の看板が目に入ります。

下関出身の仲間と六甲山系をハイキングしたときにも利用した温泉です。
さらに有馬街道を進むと、小部(おぶ)峠に出ます。

この交差点を右に進めば六甲山、西六甲ドライブウエーです。
学校などを通り過ぎるとそこは森林浴の世界です。

この先を少し進むと、元町からの再度山ドライブウエーとの合流点です。

右に進めば再度山を経て神戸市街地へ、
左に進めば六甲山方面です。

更に進むと、森林植物園の入り口があります。

もう少しすると、アジサイの季節になります。
更に登っていくと、六甲山牧場にたどり着きます。
そこが摩耶山と六甲山への道の分岐点です。

コースを左にとって登っていくと、
六甲山ホテルの前に出ます。

ハイカーが多く、なかなか良いアングルでも写真が取れません。
すぐ横に、旧館の玄関があります。

更に登って、記念碑台に出ますが、そこには立ち寄らず、
ケーブル山頂駅に向かいました。

なかなかレトロな雰囲気が人気です。
ケーブル駅を過ぎるとかなり急な道路で
写真を撮るゆとりはありませんでした。
なんとか厳しい勾配を乗り越えてようやく六甲山の山頂近くです。

山頂まで一息のところにある茶屋の前です。
サイクリストやハイカーがいっぱいです。
 ★20
★20山頂までは、勾配がきつすぎて押して登りました。
山頂には大勢のハイカーがいっぱいで、山頂のポール前での
記念撮影も列をなしてましたので、
遠くからパチリでした。
登りに対して下りは楽なものです。
途中、六甲山ならではの注意看板もあります。

ついに、六甲山山頂まで自転車で登ってきました。
電動アシスト車も馬鹿にはできません。
無理して、足に故障を残しても、年よりの冷や水と言われるだけ。
ならば、と選択して取り組んでみたのです。
予備のバッテリーも用意していたのですが、
何とか、最初の一本だけで往復できました。
残量僅かの警告として表示が点滅はしてましたが。。。
でも、なんだか、少々わだかまりが残っているのも確かです。
今度、下関に自転車を積んでいくときは
従来通り、普通のロードバイクにすることでしょう。
火の山に自転車で登ることもないでしょうしね。
6月4日前後、晴れるといいな!!
by W