Ⅸ
その瞬間、ヤマモトとウィルローゼの二人を包み隠すように、黒い球体が姿を現す!!
あまりの高威力に、攻撃力が爆縮しているのだ。
周囲の光さえ吸い込む重力が、その黒い球体の中にはある。
その異様な光景を目の当たりにしたマイオストは、こう呟いた。
「かつての大戦では、エグラートの防衛に回った私は、
剣皇の奥義を目にしてはいないのですよ。
異界では、このような大技が幾度と繰り出されていたのでしょうな。
ウィルローゼ姫、大丈夫ですか? ヒゲのお父様。」
黒い球体に見入るマイオストに、バルマードは余裕の表情でこう答える。
「ハハハッ、守りの壁が消失していないのが無事な証拠だよ。
もし、ウィルローゼがやられていたなら、私たちごと、あの黒い球体の餌食だよ。」
「なるほど! ごもっともです。」
納得した様子で、マイオストはその黒い球体の観察を続けた。
バルマードの方は、我が子を見守るわりには余裕の表情をしている。
このやり取りは、守りの壁の外側にいるエストにも見えていたが、
エストには一体、何が起こっているのかは理解不能だった。
黒い球体は十数秒にも渡って、安定して存在していた。
中で、一体何が起こっているのかは依然、不明だったが、
禁忌である『ダークフォース』をこの地上にて用いた行為にしては、
静か過ぎるほど状態が安定していると言えた。
通常ならば、即メルトダウンを引き起こし、
半径数百キロメートルの範囲を異界の闇へと没させたことだろう。
世界は、要塞ファールス(エグラートの月)の防御シールドによって覆われている為、
それ以上の被害は、月に眠る天使セリカの『守りの壁』によって保護、修復されるであろうが、
威力でいうなら、星一つを消失させるに十分なほどに高威力だ。
ヤマモトの叩き出した攻撃力数値は『9000』。
物理攻撃力の限界である『9999』に、届こうかという威力である。
攻撃力がその限界数値9999を超えると、物理法則は崩壊する。
攻撃力『10000』は、この宇宙には存在しない。
その存在が確認されていないだけか、
かつて存在した形跡が、歴史から消し去られているだけなのかも知れないが。
(以下の『』内の記述は、削除される予定だったものです。
読み飛ばして下さい。ややこしい解説です。)
『あくまで、要塞ファールスの演算能力による推定(予測値)であるが、
こちら側の世界であれ、
異界と呼ばれる禁忌の世界であれ、
『攻撃力10000』の物理攻撃が行われた時点で、
一つの宇宙(サーヴァ)そのものが消失するというデータがある。
サーヴァとは、
ゼリオスの名で呼ばれる大銀河を、
数千個に分割して構成している宇宙の単位で、
一つ一つのサーヴァの形状は、大小の差こそあるが、
ハニカム構造体(蜂の巣のような六角形)を形成して、
ゼリオス銀河全体を覆っている。
単純に正六角形ではないが、
一つのサーヴァが、六つのサーヴァと隣接するように繋がれており、
有事の際には、その周囲を取り囲む六つのサーヴァが、
崩壊したサーヴァを銀河から隔離(内包)し、
ゼリオス銀河全体への影響を防いでいる。
簡単に言うと、蜂の巣の穴の一つを、
マジックで黒く塗りつぶす感じだ。
このハニカム構造の防御システムは、
『サーヴァナンバー01 アリスアリサ』によって、
構築されたものだと言われている。
銀河の地図全体には、黒で塗りつぶされた幾つものサーヴァがあり、
それは、銀河の辺境の地である、
『サーヴァナンバー05 アークシオン』の周囲に多く在るとされる。
サーヴァ05エリア付近は、ゼリオス銀河でも最大の激戦区である事が、
太古より知られており、ゼリオス銀河の『絶対防衛線』とも呼ばれている。
かの地には、銀河最強と呼ばれる戦士団が存在すると言われ、
12名からなるその戦士団は、名を『グランドクロス』という。
遠い遠い、遥か向こうの神話の存在である。
そのグランドクロスのリーダーである、戦士アークシオンから、
強力な思念波により、数多の星々の戦士たちへ向け発せられた言葉(メッセージ)がある。
「我が名は、アークシオン。
辺境の地にて、『敵』と戦う戦士たちの、その一人。
この声が届いたならば、その呼びかけに応えて欲しい。
我々は、多くの戦士を必要としている。
我が名を冠するサーヴァの陥落は、一宇宙の消滅に留まらず、
ゼリオスの銀河に、かつて無い最悪を招き入れるだろう。
我が想いはただ一つ、
愛する姉上が創造せしこのユニバースを、
冥界(カオスフォース)より、守り抜くこと。
繰り返す、
我が名は、アークシオン・・・。」
この、メッセージの内容を知る者は、
『サーヴァナンバー1725 エルザーディア』の宇宙の中では、
要塞ファールスの建造者である、『覇王サードラル』と、
その彼から、要塞ファールス最深部へのアクセスキーを託された戦士、
四天王筆頭の『マイオスト=ガイヤート』のみである。
要塞ファールスの演算結果が示すように、
限界を超えた力が齎すものは、崩壊、そして破滅である。
攻撃力9000という数値は、
要塞ファールスの誇る512億ビットの演算能力を超えるものではないが、
その破壊力に耐えうる異界(ダークフォース世界)ではなく、
守る事が必然とされるこの脆弱な通常空間では、
安易に発動の許される『力』ではない。』
その圧力の中を、二人は耐えているということになる。
守りの壁の健在が、自身の身の安全を保障するものではないと、
ウィルローゼはヤマモトに言っていたが、
バルマードの黒く鋭いその瞳には、
壁の存在がウィルローゼの健在ぶりを示すものだと映っていた。
見た目は薄皮一枚よりも薄く、透明な存在だが、
バルマードは感じる壁の厚みで、それがウィルローゼのものだと確信する。
高度な錬気能力を持つバルマードには、
対象の防御力を読み取る術に長けている。
バルマードの目には、その壁の物理防御力が、
いまだに5000以上を誇っているのが容易に見て取れた。
バルマードは、攻撃のみに特化した戦士、『剣王』である。
相手の装甲の厚みを読み取れなければ、必殺の一撃を放てはしない。
逆にもう一方のマイオストにとっては、
壁の存在はわかっていても、見分けまでは付かないといった感じだ。
実はマイオストは、戦士としての能力がそれほど高くはない。
彼の戦士LVは、バルマードと同じ『95』である。
その高い戦士LVの割には、高い攻撃力を持つというわけでもなく、
一級の防御力を備えているというわけでもなく、彼の能力は凡庸と言えた。
このクラスの戦士になると、何らかの才に秀でているものであるが、
彼には、その片鱗も無いように見える。
マイオストは、いわゆる『天才肌』の戦士ではないものの、
だからこそ見える風景も違っていたし、
彼の物事を見つめる角度には、誰もが認めるセンスがあった。
多少、おっちょこちょいな面は否めないが。
師であるヤマモトの安否は不明だが、
バルマードは、そちらには興味が無いといった感じで口元をニヤニヤとさせていた。
「我が師、ヤマモトよ。お見事な最期でした。
心より、ご冥福をお祈りしています。」
マイオストは、バルマードのその言葉に驚いたように振り返った。
「えっ!?
お師匠さん、マジで殉職したんすかっ!!」
「ああ、えーーっと、
希望的観測に満ち満ちております。
何せ、いくら我が師とはいえ、
相手は愛する我が子に手を出そうとする変態ヒゲメガネ。
ウィルハルトに、ウィルローゼにとその見境の無さが、
父であるヒゲパパこと私を、非情にさせたとでも言っておこうかね。
師匠に、アレを耐えるだけの防御力はないでしょ。
生命力高めなマイオスト君だって、ギリギリなんじゃないの?」
「あはは・・・、確かに。
セリカの加護無しだと、ほとんど、いや完璧に無理でしょうね。
ヤマモトサン、サヨウナラ。
いい技見せてくれて、ありがとう!!」
次の瞬間、その黒い球体に異変が起こる。
何か、鋭い斬撃のような一閃が、その球体を真っ二つに引き裂いたのだ。
引き裂かれた半球体の黒い物質は、
吸い込まれるように球体の中心があった、元の場所へと消えていった。
その中から現れた影は一つ。
影の主は、その莫大なエネルギーを文字通り吸い尽くして、その姿を現したのだ。
マイオストはその光景に唖然とさせられ、言葉も出なかった。
それは、とても一人で吸収出来るような質量ではなかったし、
一定量の世界を消失してもやむを得ないといった視線で、
マイオストは、成り行きを見つめていたからだ。
マイオストが、バルマードに連れられて来たその理由を、
いち早く、その消失座標をファールスに眠るセリカに伝えられるのが、
自分であるからだと、確信していたからであった。
バルマードの思惑も、まさに彼の読み通りで、万が一の保険として、
絶対防御力への伝達者である彼、マイオストを同行させていた。
だが、その結末に、バルマードは一瞬、苦虫を噛み潰したような顔になる。
静まり返ったその場所に姿を現したのは、
絶大なる攻撃力を宿したままの太刀、第六天魔王を手にした、
無傷のウィルローゼであった。
「ウフフ・・・、素敵でしたわよ、ヤマモトさん。」
ウィルローゼは、右手に握られたオメガを地面に突き立てると、
まるでその漆黒の刃に魅せられたように、満足気に太刀・第六天魔王を見つめていた。
ダークフォースの闇の煌めきの波紋を映す太刀を見ながら、
ウィルローゼはこう呟いた。
「フフッ、これほどの力があれば、
私は、この『ウィルローゼ』で在る状態を、
ある程度は安定させて継続することが出来るかも知れませんわネ。
ウィルハルトという呪縛から解き放たれたいという願望は、
私にとっては、比較的重要度の高い項目ですので。
ウフッ・・・、別に、ウィルハルトに消えてもらおうだなって、
そんな酷い事までは思いませんが、
適当な依代(うつわ)を見つけるまでの間、
私がこの状態で長くこの世界に在れるというのは、
とても素敵なことだと思いますの。
ウィルハルトの中に潜在した状態でも、
ワタクシ、この太刀の煌めきを留めたままでいる自信はございますし、
むしろ、何かを手玉に取るのは得意な方と心得ていますので、ウフッ。
だって、甲斐性なしの弟のウィルハルトに任せていたなら、
何十年、何百年先に、この私だけの命の器を手に入れられるか、
わかったものではありませんから。」
そう言うウィルローゼを、バルマードは押し黙って見つめていた。
バルマードにしろ、マイオストにしろ、
あのヤマモトが敗れるなど、想定外の展開であったからだ。
だが、現実として、二人はヤマモトの存在を、その痕跡さえ探知出来ないでいる。
ヤマモトの存在自体が、完全に消失してしまっているのだ。
バルマードは一呼吸置いて、マイオストに神妙な面持ちをしてこう言った。
「マイオスト君、困ったことに緊急事態、発生だよ。
まさか、この私も、師匠が敗れるだなんて本気で思ってもみなかったから、
ウィルローゼのその高く伸びた鼻っ柱を、
へし折ってもらおうくらいに考えていたのだよ。
多少、師匠にも痛い目を見てもらってね。
・・・だが、結果は見ての通りだ。」
「バルマード殿、
確かに、長くあの剣皇陛下の実力を見せつけられてきた三下の私にしても、
驚きを禁じえない状況だと言えます。
正直、洒落ではすまない非常事態だということは、私にもわかりますよ。
背筋が凍りつきそうなくらい、お強い娘さんをお持ちで。
羨ましいやら、大変そうやら・・・。」
バルマードは、言う。
かつて無いような、真剣な面持ちで。
「残念だけど、私の実力は師匠より格下だ。
情けないことに、我が娘(こ)を止めるほどの力は、この私にはないのだよ。」
そんな『お父様』の様子に、慌ててマイオストは、こう返す。
「だ、だからと言って、
私が協力したくらいで何とかなるものではないですよッ!!
まさか、いまさら、
その為に私を同行させただなんて、言わないで下さいね。
止められないですからねっ!!
あの、無敵の変態ヒゲメガネを退治してしまうほどの化け物、もとい、お嬢様なんて。
私、人生の目標である『長生き』の記録を、
これからもずっと更新し続けて行きたいですから。」
「でもねぇ・・・、
師匠ほど馬鹿デカい戦士の存在が消えたともなると、
私らが見つかるのも、もう時間の問題だと思うよ。
逃げようとしたら、逆に挑発してしまうことだろうねぇ・・・。」
「そ、そんなぁ・・・。」
その瞬間、ヤマモトとウィルローゼの二人を包み隠すように、黒い球体が姿を現す!!
あまりの高威力に、攻撃力が爆縮しているのだ。
周囲の光さえ吸い込む重力が、その黒い球体の中にはある。
その異様な光景を目の当たりにしたマイオストは、こう呟いた。
「かつての大戦では、エグラートの防衛に回った私は、
剣皇の奥義を目にしてはいないのですよ。
異界では、このような大技が幾度と繰り出されていたのでしょうな。
ウィルローゼ姫、大丈夫ですか? ヒゲのお父様。」
黒い球体に見入るマイオストに、バルマードは余裕の表情でこう答える。
「ハハハッ、守りの壁が消失していないのが無事な証拠だよ。
もし、ウィルローゼがやられていたなら、私たちごと、あの黒い球体の餌食だよ。」
「なるほど! ごもっともです。」
納得した様子で、マイオストはその黒い球体の観察を続けた。
バルマードの方は、我が子を見守るわりには余裕の表情をしている。
このやり取りは、守りの壁の外側にいるエストにも見えていたが、
エストには一体、何が起こっているのかは理解不能だった。
黒い球体は十数秒にも渡って、安定して存在していた。
中で、一体何が起こっているのかは依然、不明だったが、
禁忌である『ダークフォース』をこの地上にて用いた行為にしては、
静か過ぎるほど状態が安定していると言えた。
通常ならば、即メルトダウンを引き起こし、
半径数百キロメートルの範囲を異界の闇へと没させたことだろう。
世界は、要塞ファールス(エグラートの月)の防御シールドによって覆われている為、
それ以上の被害は、月に眠る天使セリカの『守りの壁』によって保護、修復されるであろうが、
威力でいうなら、星一つを消失させるに十分なほどに高威力だ。
ヤマモトの叩き出した攻撃力数値は『9000』。
物理攻撃力の限界である『9999』に、届こうかという威力である。
攻撃力がその限界数値9999を超えると、物理法則は崩壊する。
攻撃力『10000』は、この宇宙には存在しない。
その存在が確認されていないだけか、
かつて存在した形跡が、歴史から消し去られているだけなのかも知れないが。
(以下の『』内の記述は、削除される予定だったものです。
読み飛ばして下さい。ややこしい解説です。)
『あくまで、要塞ファールスの演算能力による推定(予測値)であるが、
こちら側の世界であれ、
異界と呼ばれる禁忌の世界であれ、
『攻撃力10000』の物理攻撃が行われた時点で、
一つの宇宙(サーヴァ)そのものが消失するというデータがある。
サーヴァとは、
ゼリオスの名で呼ばれる大銀河を、
数千個に分割して構成している宇宙の単位で、
一つ一つのサーヴァの形状は、大小の差こそあるが、
ハニカム構造体(蜂の巣のような六角形)を形成して、
ゼリオス銀河全体を覆っている。
単純に正六角形ではないが、
一つのサーヴァが、六つのサーヴァと隣接するように繋がれており、
有事の際には、その周囲を取り囲む六つのサーヴァが、
崩壊したサーヴァを銀河から隔離(内包)し、
ゼリオス銀河全体への影響を防いでいる。
簡単に言うと、蜂の巣の穴の一つを、
マジックで黒く塗りつぶす感じだ。
このハニカム構造の防御システムは、
『サーヴァナンバー01 アリスアリサ』によって、
構築されたものだと言われている。
銀河の地図全体には、黒で塗りつぶされた幾つものサーヴァがあり、
それは、銀河の辺境の地である、
『サーヴァナンバー05 アークシオン』の周囲に多く在るとされる。
サーヴァ05エリア付近は、ゼリオス銀河でも最大の激戦区である事が、
太古より知られており、ゼリオス銀河の『絶対防衛線』とも呼ばれている。
かの地には、銀河最強と呼ばれる戦士団が存在すると言われ、
12名からなるその戦士団は、名を『グランドクロス』という。
遠い遠い、遥か向こうの神話の存在である。
そのグランドクロスのリーダーである、戦士アークシオンから、
強力な思念波により、数多の星々の戦士たちへ向け発せられた言葉(メッセージ)がある。
「我が名は、アークシオン。
辺境の地にて、『敵』と戦う戦士たちの、その一人。
この声が届いたならば、その呼びかけに応えて欲しい。
我々は、多くの戦士を必要としている。
我が名を冠するサーヴァの陥落は、一宇宙の消滅に留まらず、
ゼリオスの銀河に、かつて無い最悪を招き入れるだろう。
我が想いはただ一つ、
愛する姉上が創造せしこのユニバースを、
冥界(カオスフォース)より、守り抜くこと。
繰り返す、
我が名は、アークシオン・・・。」
この、メッセージの内容を知る者は、
『サーヴァナンバー1725 エルザーディア』の宇宙の中では、
要塞ファールスの建造者である、『覇王サードラル』と、
その彼から、要塞ファールス最深部へのアクセスキーを託された戦士、
四天王筆頭の『マイオスト=ガイヤート』のみである。
要塞ファールスの演算結果が示すように、
限界を超えた力が齎すものは、崩壊、そして破滅である。
攻撃力9000という数値は、
要塞ファールスの誇る512億ビットの演算能力を超えるものではないが、
その破壊力に耐えうる異界(ダークフォース世界)ではなく、
守る事が必然とされるこの脆弱な通常空間では、
安易に発動の許される『力』ではない。』
その圧力の中を、二人は耐えているということになる。
守りの壁の健在が、自身の身の安全を保障するものではないと、
ウィルローゼはヤマモトに言っていたが、
バルマードの黒く鋭いその瞳には、
壁の存在がウィルローゼの健在ぶりを示すものだと映っていた。
見た目は薄皮一枚よりも薄く、透明な存在だが、
バルマードは感じる壁の厚みで、それがウィルローゼのものだと確信する。
高度な錬気能力を持つバルマードには、
対象の防御力を読み取る術に長けている。
バルマードの目には、その壁の物理防御力が、
いまだに5000以上を誇っているのが容易に見て取れた。
バルマードは、攻撃のみに特化した戦士、『剣王』である。
相手の装甲の厚みを読み取れなければ、必殺の一撃を放てはしない。
逆にもう一方のマイオストにとっては、
壁の存在はわかっていても、見分けまでは付かないといった感じだ。
実はマイオストは、戦士としての能力がそれほど高くはない。
彼の戦士LVは、バルマードと同じ『95』である。
その高い戦士LVの割には、高い攻撃力を持つというわけでもなく、
一級の防御力を備えているというわけでもなく、彼の能力は凡庸と言えた。
このクラスの戦士になると、何らかの才に秀でているものであるが、
彼には、その片鱗も無いように見える。
マイオストは、いわゆる『天才肌』の戦士ではないものの、
だからこそ見える風景も違っていたし、
彼の物事を見つめる角度には、誰もが認めるセンスがあった。
多少、おっちょこちょいな面は否めないが。
師であるヤマモトの安否は不明だが、
バルマードは、そちらには興味が無いといった感じで口元をニヤニヤとさせていた。
「我が師、ヤマモトよ。お見事な最期でした。
心より、ご冥福をお祈りしています。」
マイオストは、バルマードのその言葉に驚いたように振り返った。
「えっ!?
お師匠さん、マジで殉職したんすかっ!!」
「ああ、えーーっと、
希望的観測に満ち満ちております。
何せ、いくら我が師とはいえ、
相手は愛する我が子に手を出そうとする変態ヒゲメガネ。
ウィルハルトに、ウィルローゼにとその見境の無さが、
父であるヒゲパパこと私を、非情にさせたとでも言っておこうかね。
師匠に、アレを耐えるだけの防御力はないでしょ。
生命力高めなマイオスト君だって、ギリギリなんじゃないの?」
「あはは・・・、確かに。
セリカの加護無しだと、ほとんど、いや完璧に無理でしょうね。
ヤマモトサン、サヨウナラ。
いい技見せてくれて、ありがとう!!」
次の瞬間、その黒い球体に異変が起こる。
何か、鋭い斬撃のような一閃が、その球体を真っ二つに引き裂いたのだ。
引き裂かれた半球体の黒い物質は、
吸い込まれるように球体の中心があった、元の場所へと消えていった。
その中から現れた影は一つ。
影の主は、その莫大なエネルギーを文字通り吸い尽くして、その姿を現したのだ。
マイオストはその光景に唖然とさせられ、言葉も出なかった。
それは、とても一人で吸収出来るような質量ではなかったし、
一定量の世界を消失してもやむを得ないといった視線で、
マイオストは、成り行きを見つめていたからだ。
マイオストが、バルマードに連れられて来たその理由を、
いち早く、その消失座標をファールスに眠るセリカに伝えられるのが、
自分であるからだと、確信していたからであった。
バルマードの思惑も、まさに彼の読み通りで、万が一の保険として、
絶対防御力への伝達者である彼、マイオストを同行させていた。
だが、その結末に、バルマードは一瞬、苦虫を噛み潰したような顔になる。
静まり返ったその場所に姿を現したのは、
絶大なる攻撃力を宿したままの太刀、第六天魔王を手にした、
無傷のウィルローゼであった。
「ウフフ・・・、素敵でしたわよ、ヤマモトさん。」
ウィルローゼは、右手に握られたオメガを地面に突き立てると、
まるでその漆黒の刃に魅せられたように、満足気に太刀・第六天魔王を見つめていた。
ダークフォースの闇の煌めきの波紋を映す太刀を見ながら、
ウィルローゼはこう呟いた。
「フフッ、これほどの力があれば、
私は、この『ウィルローゼ』で在る状態を、
ある程度は安定させて継続することが出来るかも知れませんわネ。
ウィルハルトという呪縛から解き放たれたいという願望は、
私にとっては、比較的重要度の高い項目ですので。
ウフッ・・・、別に、ウィルハルトに消えてもらおうだなって、
そんな酷い事までは思いませんが、
適当な依代(うつわ)を見つけるまでの間、
私がこの状態で長くこの世界に在れるというのは、
とても素敵なことだと思いますの。
ウィルハルトの中に潜在した状態でも、
ワタクシ、この太刀の煌めきを留めたままでいる自信はございますし、
むしろ、何かを手玉に取るのは得意な方と心得ていますので、ウフッ。
だって、甲斐性なしの弟のウィルハルトに任せていたなら、
何十年、何百年先に、この私だけの命の器を手に入れられるか、
わかったものではありませんから。」
そう言うウィルローゼを、バルマードは押し黙って見つめていた。
バルマードにしろ、マイオストにしろ、
あのヤマモトが敗れるなど、想定外の展開であったからだ。
だが、現実として、二人はヤマモトの存在を、その痕跡さえ探知出来ないでいる。
ヤマモトの存在自体が、完全に消失してしまっているのだ。
バルマードは一呼吸置いて、マイオストに神妙な面持ちをしてこう言った。
「マイオスト君、困ったことに緊急事態、発生だよ。
まさか、この私も、師匠が敗れるだなんて本気で思ってもみなかったから、
ウィルローゼのその高く伸びた鼻っ柱を、
へし折ってもらおうくらいに考えていたのだよ。
多少、師匠にも痛い目を見てもらってね。
・・・だが、結果は見ての通りだ。」
「バルマード殿、
確かに、長くあの剣皇陛下の実力を見せつけられてきた三下の私にしても、
驚きを禁じえない状況だと言えます。
正直、洒落ではすまない非常事態だということは、私にもわかりますよ。
背筋が凍りつきそうなくらい、お強い娘さんをお持ちで。
羨ましいやら、大変そうやら・・・。」
バルマードは、言う。
かつて無いような、真剣な面持ちで。
「残念だけど、私の実力は師匠より格下だ。
情けないことに、我が娘(こ)を止めるほどの力は、この私にはないのだよ。」
そんな『お父様』の様子に、慌ててマイオストは、こう返す。
「だ、だからと言って、
私が協力したくらいで何とかなるものではないですよッ!!
まさか、いまさら、
その為に私を同行させただなんて、言わないで下さいね。
止められないですからねっ!!
あの、無敵の変態ヒゲメガネを退治してしまうほどの化け物、もとい、お嬢様なんて。
私、人生の目標である『長生き』の記録を、
これからもずっと更新し続けて行きたいですから。」
「でもねぇ・・・、
師匠ほど馬鹿デカい戦士の存在が消えたともなると、
私らが見つかるのも、もう時間の問題だと思うよ。
逃げようとしたら、逆に挑発してしまうことだろうねぇ・・・。」
「そ、そんなぁ・・・。」














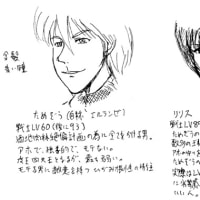

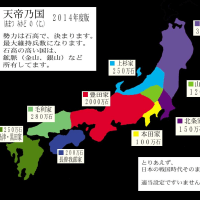










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます