Ⅴ
ヤマモトは、ウィルローゼと名乗る女性が着ている、
その赤いドレスに見覚えがあった。
それは、レトレアの薔薇姫と謳われたバルマードの妃、
レイラ王妃の物である。
彼女、ウィルローゼの姿を見て、さすがのヤマモトも困惑した。
確かにウィルハルトと同一の人物なのだろうが、
その姿はまったくの別人である。
顔立ちも、髪も、瞳の色も、そして背格好もまるで違う。
彼女が『ウィルハルト』の名前を出さなかったら、
本当に区別がつかなかったろう。
そのウィルローゼは、玉座の上から二人の侵入者の様子を伺っている。
まるで品定めでもするような、尊大でいやらしい目付きだ。
ヤマモトは、問う。
「ほ、本当にウィルちゃんなのか?」
ウィルローゼは軽く頷くと、
ちょっと考えるような仕草を見せて、ヤマモトにこう答えた。
「そう言えば、確かに私も『ウィル』ちゃんで間違いないわね。
但し、私はウィルハルトを厄介に思っているから、
そう呼ばれるのは、あまり好まないわ。
どうして、お父様は私に別の名前をつけてくれなかったのかしら。
『ローゼ』は良いのだけれど、
『ウィル』まではいらない気がするわ。」
ウィルローゼはそう言うと、玉座の腕木に頬杖を付いた。
今度はウィルローゼが質問する。
「ところで、あなたたちはここに何をしに来たの?
どうせ、ウィルハルトの知り合いか何かなのでしょうけど。
とりあえず、聞いてみてるだけだから、
まあ、答えなくても別に構わないわ。」
エストは彼女が、
あのウィルハルトであることが信じられなかった。
だが、状況から見て、そうである事は間違いなさそうだ。
エストは、彼女に向かって言った。
「わ、私は、エストです。
別に、やましい気持ちでここに来たわけではありません。
そこのオッサンは、やましいですが!!
・・・まさか『女の子』の日って、
本当に女の子になってるだなんて。
あ、いえ、何でもないです!!」
「ウフフ・・・、
正直で良さそうな娘だこと。
なるほど、ではそちらの黒メガネのおじさんが、
やましい人、というわけね。」
「やましくなんかあるかーーーーッ!!」
ヤマモトは絶叫して、エストの頭をバシッっと叩いた!!
エストもヤマモトを叩き返してやろうとするが、
ヤマモトはそれを素早くかわす。
ウィルローゼは、クスクスと笑いながら二人にこう言った。
「大体、経緯はわかったわ。
ウフフ、・・・女の子の、日ね。
つまり、あなたたちは、私の前で漫才をやりに来たわけね。
エストさんと、やましい人。」
「ワシの名は、ヤマモトじゃい!!
やましい人とか言われると、微妙に傷付く年頃じゃからの、
せめて、名前で呼んでおくれ。」
そこは譲れないといった感じのヤマモトであった。
この時、ヤマモトは、
玉座の上で女王を気取るウィルローゼの、
その力を冷静に分析していた。
エストは気付いてもいないが、
そのプラチナの髪を持つ絶世の美姫は、
このヤマモトにすら気取られる事無く、
そこに姿を現したのだ。
多少、ヤマモトが油断をしていたからといって、
まんまと部屋に閉じ込められ、
ここまで後れを取るとはまずあり得ない。
ヤマモトが強くそれを意識したことは、彼女にも伝わったようで、
ウィルローゼの次の言葉に、ヤマモトは愕然とする。
「あら、怖い。
そんなに身構えなくても、よろしいのに。」
その一言で、ヤマモトは激しくそれを理解する。
目の前に居るのは、ただ華やかに咲く花などではない。
身震いするほど底知れぬ実力を持つ、真の王者なのだと。
彼女は、強い。
ヤマモトがそれを計りきれない程に!!
丸腰のヤマモトが今、
彼女、ウィルローゼに本気になられたら、
まず、勝ち目は無い。
ヤマモトは、何故、バルマードが彼女ウィルローゼを封じ込め、
ウィルハルトとしての人生を選ばせようとしたのか、ようやく理解した。
制御し得ない力は、暴走しているのと同じである。
彼女、ウィルローゼはその生まれ持った力を、
おそらく御しえていない。
故に、月に一度程度しかその姿を顕現出来ないのだ。
これを常時、維持出来るように彼女が成長すれば、
その神の如き美貌と強さを併せ持つ存在になれるであろう。
ヤマモトは、正直、そこにはそそられた。
しかし、今の状態では、
彼女の暴走はヤマモトでも止められない。
彼は、二本の伝家の宝刀を持ち合わせてはいないのだ。
(オメガと第六天魔王があれば、というのは言い訳じゃな。
『守りの壁』の発動を感じる・・・。
転送したくとも、
これではまず阻止されるからのう。)
ヤマモトはその美しき、
『天使』とも呼べる彼女に対する興味を一層強めたが、
触らぬ神に祟りなしの方向で、
長いものには巻かれる戦法を決め込んだ。
ウィルローゼは、
そのヤマモトを見て、残念そうにこう言った。
「とぉーーーっても強い戦士、
ヤマモトさんと戦ってみたいと思っていたけれど、
それじゃ、エストさんが可愛そうだからやめておくわ。
エストさんじゃ、ここにいるだけで消えてしまいそうだから。」
「え、消えるって!?」
エストには、ウィルローゼの言葉の意味が理解できなかった。
ヤマモトは苦笑いをしながら、エストの頭を撫でると、
知らないほうがいい事もあると教えた。
確かにそれを知るには、エストは実力不足だ。
「しかし、ウィルローゼよ。
それだけの力があれば、外の閂など意味はないじゃろうし、
何故、ここでおとなしくなっておるのかのぅ?」
そう問うヤマモトに、
ウィルローゼは口元を少しだけ緩ませてこう答えた。
「それは、ひとえに、
お父様への愛の成せることですわ。」
「何やら、えらくバルマードの事を、
高く買っとるよーな口ぶりじゃの。」
話がバルマードの事に及ぶと
、ウィルローゼは何やら楽しげな素振りだ。
高飛車だった態度も、少しだけ柔らかくなった感じに見て取れる。
「それはもう、世界の何よりも
お父様を愛しております。
私の力が及ばぬばかりに、
長く、ウィルローゼであることが叶わず、
ヘラヘラとお父様の側にいるウィルハルトなど、
いっそ消し去ってやりたいのですが、
お父様の愛は深いのです。
お父様を悲しませる事になるのなら、
ウィルハルトの存在を認める事など、大した痛みではありませんわ。」
「そ、そんなに、バルマードが良いの、かの?」
熱く語り始めたウィルローゼに、
ヤマモトもやや押され気味だ。
「将来の夢という言葉があるのは、ご存知?
私にとってのそれは、
お父様の『お嫁さん』になることなのです。
一言で言えば、后ですが、
別に、正室であることにこだわりなどありません。
お父様の愛を得られるのならば、順位など無意味です。」
その言葉には、
ヤマモトだけでなく、エストも困惑する。
神々しいまでに美しい人(実の娘)が、堂々とそれを言う。
さらには、エストに向かってこうも言った。
「あなたもそれを望むなら、私と共に尽くしましょう。」、と。
エストは、
早くウィルハルト王子に戻ってくださいと言ってやりたかったが、
ヤマモトはエストの口を手で塞いで、その言葉を止めた。
ウィルローゼは、
娘を持つ父親が聞いたら泣いて喜びそうな(?)事を口にしているが、
怒ると怖い人でもあるので、ヤマモトもそこは気を遣った。
ヤマモトの彼女を見つめる視線は、
いずれは『俺の嫁!!』であったが。
そうこうしている内に、話はこの部屋の事にまで及んだ。
ウィルローゼは、言った。
ここは、確かに以前から存在していた通路であったが、
それをバルマードが手を加え、美しく改修したのだという。
母である王妃レイラを追っ手から逃がす目的で、
現在の部屋が作られたのだが、
そのレイラが、水の道しるべを必要としないでいいように、
バルマードは、彼女をよくこの部屋へと連れて来ていた。
そのレイラ自身は、
この場所が王族用の逃げ道と知らずに部屋を訪れていたのだが、
それは、バルマードなりの気遣いであった。
バルマードは、その言い訳に、
「この部屋は、私の秘密の作戦会議の場所でね、
だから、謁見の間を模して作らせたんだよ。」、と言うのだ。
バルマードの言うように、
確かに、この部屋には時折、
屈強な戦士たちが出入りをしていたが、
彼等は、その王妃を守る為に選ばれた、精鋭の戦士たちであった。
だが、母の王妃レイラが他界した時から、
この部屋はその意味をなくしたという。
その追っ手こそ、
主神『セバリオス』であり、
バルマードは、全てをかけて王妃レイラを守り抜く覚悟であった。
だからこそ、
この部屋には父王バルマードの愛が注がれており、
気に入っているのだと、
ウィルローゼは言った。
ヤマモトは、ウィルローゼと名乗る女性が着ている、
その赤いドレスに見覚えがあった。
それは、レトレアの薔薇姫と謳われたバルマードの妃、
レイラ王妃の物である。
彼女、ウィルローゼの姿を見て、さすがのヤマモトも困惑した。
確かにウィルハルトと同一の人物なのだろうが、
その姿はまったくの別人である。
顔立ちも、髪も、瞳の色も、そして背格好もまるで違う。
彼女が『ウィルハルト』の名前を出さなかったら、
本当に区別がつかなかったろう。
そのウィルローゼは、玉座の上から二人の侵入者の様子を伺っている。
まるで品定めでもするような、尊大でいやらしい目付きだ。
ヤマモトは、問う。
「ほ、本当にウィルちゃんなのか?」
ウィルローゼは軽く頷くと、
ちょっと考えるような仕草を見せて、ヤマモトにこう答えた。
「そう言えば、確かに私も『ウィル』ちゃんで間違いないわね。
但し、私はウィルハルトを厄介に思っているから、
そう呼ばれるのは、あまり好まないわ。
どうして、お父様は私に別の名前をつけてくれなかったのかしら。
『ローゼ』は良いのだけれど、
『ウィル』まではいらない気がするわ。」
ウィルローゼはそう言うと、玉座の腕木に頬杖を付いた。
今度はウィルローゼが質問する。
「ところで、あなたたちはここに何をしに来たの?
どうせ、ウィルハルトの知り合いか何かなのでしょうけど。
とりあえず、聞いてみてるだけだから、
まあ、答えなくても別に構わないわ。」
エストは彼女が、
あのウィルハルトであることが信じられなかった。
だが、状況から見て、そうである事は間違いなさそうだ。
エストは、彼女に向かって言った。
「わ、私は、エストです。
別に、やましい気持ちでここに来たわけではありません。
そこのオッサンは、やましいですが!!
・・・まさか『女の子』の日って、
本当に女の子になってるだなんて。
あ、いえ、何でもないです!!」
「ウフフ・・・、
正直で良さそうな娘だこと。
なるほど、ではそちらの黒メガネのおじさんが、
やましい人、というわけね。」
「やましくなんかあるかーーーーッ!!」
ヤマモトは絶叫して、エストの頭をバシッっと叩いた!!
エストもヤマモトを叩き返してやろうとするが、
ヤマモトはそれを素早くかわす。
ウィルローゼは、クスクスと笑いながら二人にこう言った。
「大体、経緯はわかったわ。
ウフフ、・・・女の子の、日ね。
つまり、あなたたちは、私の前で漫才をやりに来たわけね。
エストさんと、やましい人。」
「ワシの名は、ヤマモトじゃい!!
やましい人とか言われると、微妙に傷付く年頃じゃからの、
せめて、名前で呼んでおくれ。」
そこは譲れないといった感じのヤマモトであった。
この時、ヤマモトは、
玉座の上で女王を気取るウィルローゼの、
その力を冷静に分析していた。
エストは気付いてもいないが、
そのプラチナの髪を持つ絶世の美姫は、
このヤマモトにすら気取られる事無く、
そこに姿を現したのだ。
多少、ヤマモトが油断をしていたからといって、
まんまと部屋に閉じ込められ、
ここまで後れを取るとはまずあり得ない。
ヤマモトが強くそれを意識したことは、彼女にも伝わったようで、
ウィルローゼの次の言葉に、ヤマモトは愕然とする。
「あら、怖い。
そんなに身構えなくても、よろしいのに。」
その一言で、ヤマモトは激しくそれを理解する。
目の前に居るのは、ただ華やかに咲く花などではない。
身震いするほど底知れぬ実力を持つ、真の王者なのだと。
彼女は、強い。
ヤマモトがそれを計りきれない程に!!
丸腰のヤマモトが今、
彼女、ウィルローゼに本気になられたら、
まず、勝ち目は無い。
ヤマモトは、何故、バルマードが彼女ウィルローゼを封じ込め、
ウィルハルトとしての人生を選ばせようとしたのか、ようやく理解した。
制御し得ない力は、暴走しているのと同じである。
彼女、ウィルローゼはその生まれ持った力を、
おそらく御しえていない。
故に、月に一度程度しかその姿を顕現出来ないのだ。
これを常時、維持出来るように彼女が成長すれば、
その神の如き美貌と強さを併せ持つ存在になれるであろう。
ヤマモトは、正直、そこにはそそられた。
しかし、今の状態では、
彼女の暴走はヤマモトでも止められない。
彼は、二本の伝家の宝刀を持ち合わせてはいないのだ。
(オメガと第六天魔王があれば、というのは言い訳じゃな。
『守りの壁』の発動を感じる・・・。
転送したくとも、
これではまず阻止されるからのう。)
ヤマモトはその美しき、
『天使』とも呼べる彼女に対する興味を一層強めたが、
触らぬ神に祟りなしの方向で、
長いものには巻かれる戦法を決め込んだ。
ウィルローゼは、
そのヤマモトを見て、残念そうにこう言った。
「とぉーーーっても強い戦士、
ヤマモトさんと戦ってみたいと思っていたけれど、
それじゃ、エストさんが可愛そうだからやめておくわ。
エストさんじゃ、ここにいるだけで消えてしまいそうだから。」
「え、消えるって!?」
エストには、ウィルローゼの言葉の意味が理解できなかった。
ヤマモトは苦笑いをしながら、エストの頭を撫でると、
知らないほうがいい事もあると教えた。
確かにそれを知るには、エストは実力不足だ。
「しかし、ウィルローゼよ。
それだけの力があれば、外の閂など意味はないじゃろうし、
何故、ここでおとなしくなっておるのかのぅ?」
そう問うヤマモトに、
ウィルローゼは口元を少しだけ緩ませてこう答えた。
「それは、ひとえに、
お父様への愛の成せることですわ。」
「何やら、えらくバルマードの事を、
高く買っとるよーな口ぶりじゃの。」
話がバルマードの事に及ぶと
、ウィルローゼは何やら楽しげな素振りだ。
高飛車だった態度も、少しだけ柔らかくなった感じに見て取れる。
「それはもう、世界の何よりも
お父様を愛しております。
私の力が及ばぬばかりに、
長く、ウィルローゼであることが叶わず、
ヘラヘラとお父様の側にいるウィルハルトなど、
いっそ消し去ってやりたいのですが、
お父様の愛は深いのです。
お父様を悲しませる事になるのなら、
ウィルハルトの存在を認める事など、大した痛みではありませんわ。」
「そ、そんなに、バルマードが良いの、かの?」
熱く語り始めたウィルローゼに、
ヤマモトもやや押され気味だ。
「将来の夢という言葉があるのは、ご存知?
私にとってのそれは、
お父様の『お嫁さん』になることなのです。
一言で言えば、后ですが、
別に、正室であることにこだわりなどありません。
お父様の愛を得られるのならば、順位など無意味です。」
その言葉には、
ヤマモトだけでなく、エストも困惑する。
神々しいまでに美しい人(実の娘)が、堂々とそれを言う。
さらには、エストに向かってこうも言った。
「あなたもそれを望むなら、私と共に尽くしましょう。」、と。
エストは、
早くウィルハルト王子に戻ってくださいと言ってやりたかったが、
ヤマモトはエストの口を手で塞いで、その言葉を止めた。
ウィルローゼは、
娘を持つ父親が聞いたら泣いて喜びそうな(?)事を口にしているが、
怒ると怖い人でもあるので、ヤマモトもそこは気を遣った。
ヤマモトの彼女を見つめる視線は、
いずれは『俺の嫁!!』であったが。
そうこうしている内に、話はこの部屋の事にまで及んだ。
ウィルローゼは、言った。
ここは、確かに以前から存在していた通路であったが、
それをバルマードが手を加え、美しく改修したのだという。
母である王妃レイラを追っ手から逃がす目的で、
現在の部屋が作られたのだが、
そのレイラが、水の道しるべを必要としないでいいように、
バルマードは、彼女をよくこの部屋へと連れて来ていた。
そのレイラ自身は、
この場所が王族用の逃げ道と知らずに部屋を訪れていたのだが、
それは、バルマードなりの気遣いであった。
バルマードは、その言い訳に、
「この部屋は、私の秘密の作戦会議の場所でね、
だから、謁見の間を模して作らせたんだよ。」、と言うのだ。
バルマードの言うように、
確かに、この部屋には時折、
屈強な戦士たちが出入りをしていたが、
彼等は、その王妃を守る為に選ばれた、精鋭の戦士たちであった。
だが、母の王妃レイラが他界した時から、
この部屋はその意味をなくしたという。
その追っ手こそ、
主神『セバリオス』であり、
バルマードは、全てをかけて王妃レイラを守り抜く覚悟であった。
だからこそ、
この部屋には父王バルマードの愛が注がれており、
気に入っているのだと、
ウィルローゼは言った。














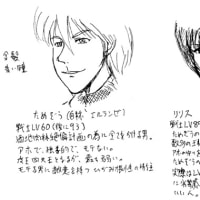

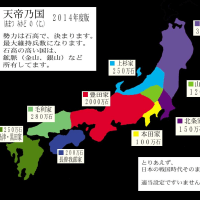









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます