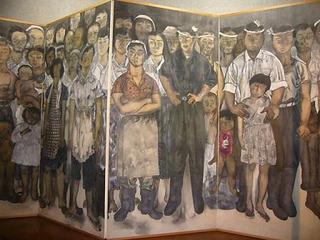6月25日(金)14:40から、神保町の岩波ホールで上映された、フランスのローラン・カンテ監督のカンヌ国際映画祭パルムドール受賞作品「パリ20区、僕たちのクラス」を観てきました。


フランスで1500万人を動員し、観客全員にドキュメンタリーだと思わせた驚異のリアリティと宣伝されている通り、学園ものにありがちなうそ臭さがまったくない、まるでその教室に一緒にいるような緊迫した臨場感がありました。

舞台となる中学校は、保護者との三者面談で、お母さんが「うちの子は名門高校に進ませたい。もっと出来る子に力を入れて欲しい。」と担任に言うそばで、生徒が「ママはいつもこの学校の事を三流校と言っているんだ。」と暴露するような、アフリカ系・中国系・イスラム系の生徒が半分以上を占める教育困難校です。

映画では、国語(フランス語)を教える若い男性の担任教師が、授業で四苦八苦している有様が克明に描かれています。

わからない言葉を説明する時に作った例文に対して、さっと手を上げて「どうしていつもビルとかって、シロ(白人)が主語なの?」「なぜ中世の言葉みたいなフランス語を学ぶの?今使っている“ダサイ”とか“マジ”で通じる。どういう人がそんな言葉を使うのか?」などと、生徒たちの鋭い質問があとからあとから続き、課題は進みません。

それらに対して精一杯誠実に答えようとしている教師なのですが、やはり生徒から突然、理解できない無礼な反応をされると、「君は、今日残って話をしよう!」

その放課後の話し合いでは、どうしても一方的に「申し訳ありませんでした」のような型にはまった敬意を払った謝罪を要求して、生徒を権威の下に屈服させようとします。
なぜ、その生徒が今までと違った態度を取るようになったのかを解明しようとせずに・・・。

多民族のクラスで、彼女の抱えている問題はかなり深刻なものだろうと想像されますが、たった24人のクラスでもその一人一人にどれだけ関われるかは、時間的にも精神的にも体力的にも限りがあることは、自分の乏しい経験からもよくわかります。

感受性の鋭い生徒たちとまっすぐに向き合う、教師の仕事とは、まったく日々命を削るような仕事です。
映画でとても興味深かったのは、フランスでは生徒の生活指導評価・学力評価の委員会に、生徒代表や保護者代表が参加していることです。学力評価にしても、1人の担当が責任持ってクラス全員の成績をつける日本とは違う、つけた点数を話し合う形でした。

授業妨害・暴言・暴力行為などの校則違反に対する懲罰委員会にも、保護者代表が出てきますし、当事者の生徒と保護者も参加して自分たちの言い分を申し述べます。

評価委員会に出席した生徒代表は、会議中、不真面目にくすくす笑ってお菓子を食べていたり、あとでどの先生が誰に対してどんな意見を言ったかなど仲間にばらしたりしますが、そういうありがちな人間的なところも含めて、日常生活に生きている「民主主義」を見る事ができました。

もっとも、そのことで思わず出た失言が重大な事件を引き起こすのですが・・・。
それはともかく、翻って、日本の教育事情はというと、狭い教室に生徒は40名を越え、生徒一人一人の質問や問題行動にじっくり対処すべき教師の時間が、給料を査定される「自己申告書」作成、行事や推薦書作成のたびに要求される「起案書」などの書類作成に費やされ、あろうことか憲法で保障されている“良心の自由・思想信条の自由”を侵害する「日の丸・君が代」強制により、懲戒処分をくだされているのが現状です。

教育関係者にかぎらず一人でも多くの方に、この映画を観ていただいて、日本の教育現場に風穴をあけたいと痛感しました。

(文責/佐藤)

































 もっとも、そのことで思わず出た失言が重大な事件を引き起こすのですが・・・。
もっとも、そのことで思わず出た失言が重大な事件を引き起こすのですが・・・。







 (文責/沖)
(文責/沖)