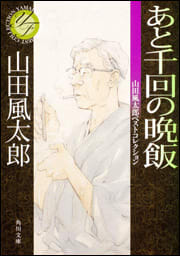2013/04/28
ぽかぽか春庭ブックスタンド>2013年1月~4月の読書メモ(1)
2013年1月~4月の読書メモ。
例によって、何をいつ読んだか忘れていて、本の山の中から、「これは今年になってから読んだ気がする」と思えたのは、以下の通り。
他の人の読書記録を見ると、児童書を中心に読んでいる人、旅行記を中心に読んでいる人、それぞれの好みがあって、とても参考になり、ああ、こういう本をいつか読んでみたいと思うのですが、私の読書は系統だってもいなくて、てんでんばらばらでそのときそのときに目移りした本を読み散らしています。それもこれも100円で手に入った本を読んでいくので、その時々でテーマがバラバラなのです。あえて、広くテーマをいえば、日本語言語文化、社会文化となりますが、これをいえば何でもアリです。
@は図書館本 ¥は定価で買った本 ・は、ほとんどBookoffの定価半額本&100円本。
<日本語・日本語言語文化関連>
@湯沢質幸『古代日本人と外国語』
@蛇蔵&海野凪子『日本人の知らない日本語3』2012メディアファクトリー
<評論・エッセイ、その他>
・辺見庸『いまここに在ることの恥』2006 毎日新聞社
¥田中忠三郎『物には心がある』2011 アミューズエディテュメント
・佐野洋子『がんばりません』2010 新潮文庫
・佐野洋子『覚えていない』2009 新潮文庫
・司馬遼太郎『歴史の世界から』2004 中公文庫
・司馬遼太郎『長安から北京へ』1996 中公文庫
・司馬遼太郎『中国・蜀と雲南のみち街道をゆく〈20〉』1987 朝日文庫
・司馬遼太郎『「明治」という国家 上』2008NHKブックス
・司馬遼太郎・陳舜臣『対談 中国を考える』1983 文春文庫
・松本侑子『アメリカ・カナダ物語紀行』2009 幻冬舎文庫
・田村仁『アンコール遺跡の光』2002 小学館文庫
・米原万里『ロシアは今日も荒れ模様』2001 講談社文庫
・高松宮喜久子『菊と葵のものがたり』2002 中公文庫
・関川夏央『昭和時代回想』2002 集英社文庫
・高山宏『近代文化史入門 超英文学講義 』2007 講談社学術文庫
@荒俣宏『イギリス魔界紀行』2003 NHK出版
@ジル・ネレ『バルデュス 猫たちの王』2006 タッシェンジャパン
・ハーバート・ピックス『昭和天皇上』2002 講談社
<小説・戯曲・ノンフィクション>
・村上春樹『1Q84 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』2009,2010 新潮社
・黒田夏子『abさんご』2013 文藝春秋3月号
・田辺聖子『姥ざかり花の旅笠』2004 集英社文庫
・杉本苑子『雪中松梅図』1985 集英社文庫
・松井今朝子『幕末あどれさん』2007 PHP文庫
¥常見藤代『女ノマド、一人沙漠に生きる』2012集英社新書
『1Q84』は、ブックオフで半額になってから買い、それからしばらく寝かせておいて、やっと読みました。ベストセラー本は、売れる前に読むか、すたれてから読むかで、売れている最中に読むのは気恥ずかしい。年末に『アフターダーク』を読んで、正月に『1Q84』と連続で読んだので、なんだかストーリーがごちゃまぜになって記憶されている。『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』も、読むのはいつになることだろう。
米原万里のエッセイなんかも、百円本になってから読むので、評判になっている最中は読めない。マンガの『日本人の知らない日本語3』もようやく読んだ。講師室の同僚達は1も2も、いち早く読んで「日本語教師にとっては知っていることばかりだけれど、こうしてマンガにすると売れるのねぇ」という感想を聞いてきた。日本語学習者の誤用とか、「日本でびっくりしたこと、初めて見たもの」とか、毎期毎期必ずひとりはいる定番の発言や行動なんだけれど、これをだれが読んでもおもしろく笑える本にしたのは、蛇蔵のお手柄だと思います。
石牟礼道子などと並んで、私が「印税を払わず読むのは申し訳ない」と思える数少ない作家のひとりである辺見庸。『いまここに在ることの恥』は、すみません、古本屋で100円で買いました。私もぎりぎり節約、、、、、家賃払えとUR都市機構が手紙よこして、期日に遅れた分には滞納利子をつけて払えという。辺見さんに印税払うべき分が、家賃の利息になってしまいました。次回は、新刊単行本で買いますから、今回はお許しください。
久しぶりに雑誌を定価で買った『文藝春秋3月号』。いつも1、2冊入っているはずの文庫本が入っていなくて、何でもいいから読むもんと思って駅のキオスクの棚を見ても、読みたいような文庫がない。「文藝春秋」は芥川賞全文掲載っていう号で、そのうち、単行本が古本屋に出回ったら読もうと思っていた『abさんご』を読むことになってしまいました。芥川賞が話題になってベストセラーになれば、単行本売れて、1年後には古本屋に出回るのに、こんなに早く読むことになるなんて。いや、自分に合っている本なら定価で買っても文句は言わないけれど、合わない本だったので。
常見藤子『女ノマド一人沙漠に生きる』は、フォトジャーナリストの「ホームステイ」記録。片倉もと子らの「女性によるイスラム社会」の記録、たとえば『イスラム社会の日常生活』などに比べるとややツッコミが足りず物足りない部分があります。表面上仲良くしていても、実は女同士のあいだに、嫉妬や反感が渦巻いている描写など、そうそう、それがホントよね。妻が4人いても、4人平等に扱われるから妻同士に嫉妬などないと言われていても、現実は違うよねと、同感できる部分もありました。
文章リポートとして足りない部分は、本来写真で表現する人なのだろうけれど、この新書には写真はそう多くは掲載されていません。それで物足りない感がのこったのだと思います。
高松宮喜久子『菊と葵のものがたり』は、高松宮妃の妹、榊原喜佐子『徳川慶喜家の子ども部屋』を読んだときに、「自伝を書くと結局は自慢話になってしまう階級の人(by佐野洋子の評)」の思い出話だと思ったので、皇室自慢話など読んでもなあ、と思ったのだけれど、『高松宮日記』の裏話でも書かれているのかと買って置いた百円本。
東御苑お花見散歩のついでに三の丸尚蔵館で「旧高松宮家と伝来の品々」という展覧会を見たので、そうそうと思い出して読みました。
「秩父宮に松平容保の孫を配し、高松宮に徳川慶喜の孫を配したのは、朝敵賊軍の末裔たち、まつろわぬ者どもをまつろわせるための婚姻だったのだなあ」と、あらためて感じたこと。新島八重も秩父宮妃に容保の孫の勢津子姫が決定したとき「これで会津の名誉が回復した」と感じたと語ったそう。征服者が被征服側から妃を選ぶという「まつろわぬ者」対策は、太古から変わっていないのね。
ハーバート・ピックス『昭和天皇上』
戦後の象徴天皇制度のもとでは「無力で実権なき平和主義者だった昭和天皇」というイメージが全国津々浦々に行き渡ったが、実際は強いリーダーシップを発揮して日本を戦争に導く役割を果たしてきた、という説を出してピュリツアー賞をとった。
10年たった今では、反ピックス説も出そろった。私は出版後に評判になっていたころは特別読みたいとも思わなかったのだけれど、100円本になっていたので、まあころあいかと思って読んでみたら面白かった。
種々の反論も含めて、これから検証していくべき人の伝記。昭和天皇にかかわった人がつぎつぎ鬼籍に入っていく今、側近の日記などがさらなる資料として世に公になることを望みます。周囲の大反対を押し切って、ひとつの記録として「高松宮日記」を公にした喜久子妃は、それだけでも評価できる。
地震後の耐震化で休館していた国立文書館がリニューアルオープンして「近代国家成立時の記録」が展示されていたので、花見がてら見て来ました。晩年の明治天皇の御名御璽のサインの文字が極端に右肩下がりの「睦仁」なっていたのが気になりました。なぜあんなにも仁の「二」が右下がりになったのだろう。晩年の病気のせい?こういうのも、筆跡鑑定と身体状態がわかる人が見れば、わかるのだろうけど。糖尿病悪化の尿毒症で、満59歳での崩御。ワォ、今の私より若くしてみまかったのだわん。その明治天皇を「お手本」として生きた昭和天皇。
さて、「退位なさいませ」だの国内公務もせずにオランダ行きはけしからぬだの、かまびすしい昨今、皇室ウォッチングも忙しい。本日オランダへ向けてご出発とか。リラックスしてすごせるといいですね。
私の頭は一年中リラックスです。そりゃこんな私でも、悩みはありますよ。金がないとか、カネがないとか、かねがないとか、、、、。まあ、せいぜい古本屋の100円本でも買って読めば、悩み事大いなるこのご時世でも、ささやかな楽しみを見いだして生きて行けるというもんです。
橘曙覧の歌三首
たのしみは珍しき書(ふみ)人にかり始め一ひらひろげたる時
たのしみはそぞろ読みゆく書の中(うち)に我とひとしき人をみし時
たのしみは銭なくなりてわびをるに人の来たりて銭くれし時
私にもください。
<つづく>











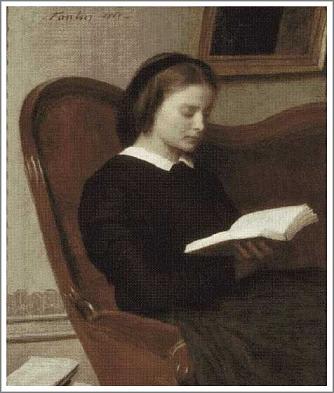 ラトゥール「読書」
ラトゥール「読書」 黒田清輝「読書」
黒田清輝「読書」 浅井忠「読書」
浅井忠「読書」 マリーローランサン「読書」
マリーローランサン「読書」 コロー「読書」
コロー「読書」 フラゴナール「読書」
フラゴナール「読書」  ゴッホ「読書」
ゴッホ「読書」