
正時のニュースが流れる間が休息の時間。司会者と談笑する小菅正夫先生(左)もいれば、次の相談の資料に目を通す篠原菊紀先生(左から2人目)も=2014年8月、望月麻紀撮影

NHKラジオ:子ども科学電話相談 舞台裏は大わらわ
毎日新聞 2014年08月15日 14時46分(最終更新 08月15日 16時50分)
◇回答の先生も汗だく
1984年の放送開始から30年、NHKラジオ第1で毎年、生放送している「夏休み子ども科学電話相談」は子どもたちの素朴な疑問と、懸命に回答する専門家との真剣勝負。大人のファンも多いと聞く。その舞台裏を取材した。
東京都渋谷区のNHK放送センターにあるラジオのスタジオ。記者が訪れた8月7日は午前8時5分放送開始で、最初の質問は小5の女の子の「人にはなぜ笑ったり泣いたりする感情があるか」だった。「心と体」担当の篠原菊紀先生(諏訪東京理科大教授)はまず「どうして思いついたの?」と逆質問。先生は、集団で生きていく中で感情がいかに必要かを、実験結果を交えて説明した。
次の男の子は司会者に「何年生?」と聞かれて「2年1組」。場が和む。相談は「育てているナスに色が付かない」。植物担当の先生は「日は当たってる?」「ほかのナスは色付いた?」と尋ねるが、いずれも「はい」で原因が見当たらず、一瞬、先生も言葉に詰まった。「葉っぱの陰になっていないかな」と繰り出したら「なってる」。スタジオは安堵(あんど)の空気に包まれた。

◇放射線衛生学まで
この日はほかに動物と野鳥の計4分野の質問を受け付けていた。番組は、夏の甲子園の中継期間を除く7月22日〜8月29日の平日午前放送で、日替わりの先生の専門分野に合わせ、質問・回答の分野も入れ替わる。昆虫や天文などは放送開始以来の人気分野。子どもたちの興味関心に合わせて拡大され、11年には恐竜、12年からは東日本大震災による原発事故の発生を受け放射線衛生学も加わった。
番組には「子どもが先生に直接相談する」という鉄則がある。そのため、放送開始1時間前から終了間際まで、スタジオ前の副調整室ではスタッフが大わらわだ。まずは電話受け付けの3人が、子どもたちの相談を聞き取り、採用が決まれば、スタッフが電話を折り返すが、1時間前に質問した子が不在のことも。この日は23人の質問を放送したが、ほかに10人ほどが不在で出演を逃した。
1人5〜6問の回答を終え、午前11時44分放送終了。最後の質問「人はなぜうそをつきたくなるのか」に答えた篠原先生がスタジオを出てきた。シャツは汗でびっしょり。「大変ですね」と声をかけると「危機的状況を回避するためにドーパミンが分泌されて、くせになっているのかも」と笑う。ドーパミンはやる気をかきたてるだけでなく、快感に関係する脳内物質だけに、習慣化させる効果もあるそうだ。電話相談のハラハラドキドキがくせになっているらしい。
◇ 「真実は経験に」
先生たちはよく「自分で見たの?」、動物なら「飼ってるの?」と体験からの質問かどうかを確認する。放送後、動物担当の小菅正夫・旭川市旭山動物園前園長に聞くと「自身の体験に基づく質問であれば、答えは手の中にある。もっと触って、もっと観察してほしい。真実は自分の見たもの、経験にあるのですから」。科学の目を育てたい先生たちのこだわりだった。
話し言葉だけでの説明で、時間も限られ「納得の回答」は至難の業だ。栗田勇人・チーフプロデューサーは「単に知識を教える番組ではありません。先生たちの一生懸命なやりとりが思い出となって、この番組をスタートに『もっと知りたい』と思ってもらいたい」。
今夏は残すところ8月25日からの5日間。先生たちの熱い夏は続く。 【望月麻紀】

追記:8月17日の福井新聞のコラム「越山若水」に下記が載ったので転載します。
タコに骨がないのはなぜ/アサガオには目がないのにつかまるところがなぜ分かるの/犬や猫は夢を見るの―ラジオから園児や小学生の「どうして」「なぜなの」の声が聞こえてくる▼夏休みのNHK「子ども科学電話相談」だ。素朴な疑問に思わず「クスッ」となる。相談は昆虫や野鳥、植物、魚・動物、天文・宇宙、科学と多岐にわたる▼知ったかぶりも「なるほど」「へー、そんなんだ」と、無知を思い知る。分かりやすく丁寧に教える先生たち。電話の向こうで四苦八苦しているであろう姿が浮かぶ▼そして先生、司会者の「勉強して将来科学者になってね」「こんなところも調べてはどうかな」との呼び掛けに、子どもたちへの期待の大きさがうかがえる▼日米中韓4カ国の高校生を対象に実施した意識調査で、自然や科学に関心があると答えた日本の高校生は59%と最も低い。一方、社会に出たら理科は必要なくなるとの回答は4カ国中最多の44%▼自由研究の経験はトップ。小学4~6年がピークで、高校入学後ほとんど経験しなくなる。国立青少年教育振興機構は科学への意識が薄れ、理科離れが進んでいると分析▼調べ学習や体験学習を多くした生徒ほど科学への関心が高い傾向は各国に共通する。子どもたちの探究心を大事にし、科学の芽を育てたい。電話相談の答え、一緒に調べてみてはどうだろう。

この「夏休み子ども科学電話相談」はけっこう好きでカーラジオでしか聞かないんだが、楽しくてしょうがない。やっと電話ができるような子に学者さんが説明するのだから大変だ。
小父さんも今年新発見をした(笑)。科学の全容は先生方が話すのだが、最後に「何何ちゃん分かったー?」とたずねると、たいがい「うん、分かった。ありがとうございました」で終わる。そこでその日の進行しているアナウンサーが説明を付け加えるのだが、そのアナウンサーの話の方がとても分かり易い。子供の持っている語彙での説明だからだ。さすがアナウンサーだなーと感心してしまった。
先生方の回答は分かりやすい説明をされているけど、大人でもなるほどと思うような内容も含まれている。そうか、ラジオでは分からなかったけど回答の先生も汗だくというのは想像がつくね。アナウンサーは時々その回答を通訳されているみたいなとこがある。望月麻紀さんレポート有難うございました。

NHKラジオ:子ども科学電話相談 舞台裏は大わらわ
毎日新聞 2014年08月15日 14時46分(最終更新 08月15日 16時50分)
◇回答の先生も汗だく
1984年の放送開始から30年、NHKラジオ第1で毎年、生放送している「夏休み子ども科学電話相談」は子どもたちの素朴な疑問と、懸命に回答する専門家との真剣勝負。大人のファンも多いと聞く。その舞台裏を取材した。
東京都渋谷区のNHK放送センターにあるラジオのスタジオ。記者が訪れた8月7日は午前8時5分放送開始で、最初の質問は小5の女の子の「人にはなぜ笑ったり泣いたりする感情があるか」だった。「心と体」担当の篠原菊紀先生(諏訪東京理科大教授)はまず「どうして思いついたの?」と逆質問。先生は、集団で生きていく中で感情がいかに必要かを、実験結果を交えて説明した。
次の男の子は司会者に「何年生?」と聞かれて「2年1組」。場が和む。相談は「育てているナスに色が付かない」。植物担当の先生は「日は当たってる?」「ほかのナスは色付いた?」と尋ねるが、いずれも「はい」で原因が見当たらず、一瞬、先生も言葉に詰まった。「葉っぱの陰になっていないかな」と繰り出したら「なってる」。スタジオは安堵(あんど)の空気に包まれた。

◇放射線衛生学まで
この日はほかに動物と野鳥の計4分野の質問を受け付けていた。番組は、夏の甲子園の中継期間を除く7月22日〜8月29日の平日午前放送で、日替わりの先生の専門分野に合わせ、質問・回答の分野も入れ替わる。昆虫や天文などは放送開始以来の人気分野。子どもたちの興味関心に合わせて拡大され、11年には恐竜、12年からは東日本大震災による原発事故の発生を受け放射線衛生学も加わった。
番組には「子どもが先生に直接相談する」という鉄則がある。そのため、放送開始1時間前から終了間際まで、スタジオ前の副調整室ではスタッフが大わらわだ。まずは電話受け付けの3人が、子どもたちの相談を聞き取り、採用が決まれば、スタッフが電話を折り返すが、1時間前に質問した子が不在のことも。この日は23人の質問を放送したが、ほかに10人ほどが不在で出演を逃した。
1人5〜6問の回答を終え、午前11時44分放送終了。最後の質問「人はなぜうそをつきたくなるのか」に答えた篠原先生がスタジオを出てきた。シャツは汗でびっしょり。「大変ですね」と声をかけると「危機的状況を回避するためにドーパミンが分泌されて、くせになっているのかも」と笑う。ドーパミンはやる気をかきたてるだけでなく、快感に関係する脳内物質だけに、習慣化させる効果もあるそうだ。電話相談のハラハラドキドキがくせになっているらしい。
◇ 「真実は経験に」
先生たちはよく「自分で見たの?」、動物なら「飼ってるの?」と体験からの質問かどうかを確認する。放送後、動物担当の小菅正夫・旭川市旭山動物園前園長に聞くと「自身の体験に基づく質問であれば、答えは手の中にある。もっと触って、もっと観察してほしい。真実は自分の見たもの、経験にあるのですから」。科学の目を育てたい先生たちのこだわりだった。
話し言葉だけでの説明で、時間も限られ「納得の回答」は至難の業だ。栗田勇人・チーフプロデューサーは「単に知識を教える番組ではありません。先生たちの一生懸命なやりとりが思い出となって、この番組をスタートに『もっと知りたい』と思ってもらいたい」。
今夏は残すところ8月25日からの5日間。先生たちの熱い夏は続く。 【望月麻紀】

追記:8月17日の福井新聞のコラム「越山若水」に下記が載ったので転載します。
タコに骨がないのはなぜ/アサガオには目がないのにつかまるところがなぜ分かるの/犬や猫は夢を見るの―ラジオから園児や小学生の「どうして」「なぜなの」の声が聞こえてくる▼夏休みのNHK「子ども科学電話相談」だ。素朴な疑問に思わず「クスッ」となる。相談は昆虫や野鳥、植物、魚・動物、天文・宇宙、科学と多岐にわたる▼知ったかぶりも「なるほど」「へー、そんなんだ」と、無知を思い知る。分かりやすく丁寧に教える先生たち。電話の向こうで四苦八苦しているであろう姿が浮かぶ▼そして先生、司会者の「勉強して将来科学者になってね」「こんなところも調べてはどうかな」との呼び掛けに、子どもたちへの期待の大きさがうかがえる▼日米中韓4カ国の高校生を対象に実施した意識調査で、自然や科学に関心があると答えた日本の高校生は59%と最も低い。一方、社会に出たら理科は必要なくなるとの回答は4カ国中最多の44%▼自由研究の経験はトップ。小学4~6年がピークで、高校入学後ほとんど経験しなくなる。国立青少年教育振興機構は科学への意識が薄れ、理科離れが進んでいると分析▼調べ学習や体験学習を多くした生徒ほど科学への関心が高い傾向は各国に共通する。子どもたちの探究心を大事にし、科学の芽を育てたい。電話相談の答え、一緒に調べてみてはどうだろう。

この「夏休み子ども科学電話相談」はけっこう好きでカーラジオでしか聞かないんだが、楽しくてしょうがない。やっと電話ができるような子に学者さんが説明するのだから大変だ。
小父さんも今年新発見をした(笑)。科学の全容は先生方が話すのだが、最後に「何何ちゃん分かったー?」とたずねると、たいがい「うん、分かった。ありがとうございました」で終わる。そこでその日の進行しているアナウンサーが説明を付け加えるのだが、そのアナウンサーの話の方がとても分かり易い。子供の持っている語彙での説明だからだ。さすがアナウンサーだなーと感心してしまった。
先生方の回答は分かりやすい説明をされているけど、大人でもなるほどと思うような内容も含まれている。そうか、ラジオでは分からなかったけど回答の先生も汗だくというのは想像がつくね。アナウンサーは時々その回答を通訳されているみたいなとこがある。望月麻紀さんレポート有難うございました。






















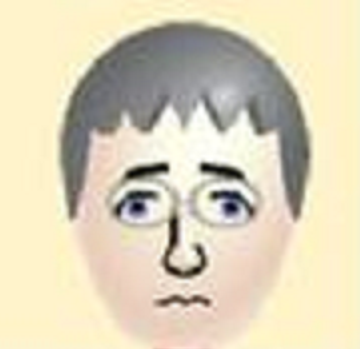





夏休みならではかな^^
そうそう!
子供って『何で?何で?』と
何でも聞きたがる年齢ってありますよね!
回答に戸惑う事も、しばしばありました^^A
でも、子供目線で考えると
ちょっとしたことさえも『???』ってなりますよねf^^
でも、諸先生方が丁寧に教えて下さるって
いいですね~
って。。。
プールトレ、頑張ってらっしゃいますね☆
私は、2日頑張って2日サボってしまいました--
見習わないと。汗
今日はお昼からずーっと出っ放しでさっき帰って来てご飯を食べ終わったのが夜9時です。
この科学相談ってのは娘がすっごい好きそうですよ。
私も子供の振りして電話してみたいです(笑)。
スカイプは近所に住む幼馴染もしない上に、弟が全くPCと言うものをしない&関心ないんです。
親戚でやっているのは東京に住む従弟の嫁さんだけなんですよ~。
Mr.ギャランドゥは時差もあるので、直接電話で10分くらいってのが楽ですね~。
あれっ、知りませんでした?
ということは車に乗ったらきいとFM大阪か、お気に入りのCDを流してあるんでしょう!?(笑)
この番組は古いですよ。
>回答に戸惑う事も、しばしばありました^^A
これ知識は山のようにお持ちの回答者がずらりと並んでいるんですけど、私が聴いていても時々子供には難しい表現が混じることがあるんですよ~。
特に小学校低学年への説明は回答者の先生方も言葉を選ぶのに困ってありますね。
>でも、諸先生方が丁寧に教えて下さるっていいですね~
これはいっしょに聴いている親もとても勉強になりますね。
科学の説明が入りますから・・・。
>プールトレ、頑張ってらっしゃいますね☆
今日は雨降りだし、孫も来たりして階段にもプールにも行きませんでした。
今日は北アルプスで遭難事故が発生しましたね。
とても気になります。
はっはっは、相変わらずてんてこ舞いですね。
忙しい中コメント残していただいて有難いです。
>この科学相談ってのは娘がすっごい好きそうですよ。
これは理科の分野だと最高の番組です。
多分小1から小6くらいが対象だと思いますが、専門家が回答するので学校の先生が聴かれていても役に立つと思います。
私なんぞも「へーっ、そいうことだったのか!」なんてよく思いますよ。
質問は「鳥の中で世界一番早いのは何ですか?」とか
「雷はどうして落ちるのですか」とか「カブトムシはいつ出てくるのですか」などなど。
普通の大人なら適当にごまかして答えますが、これを専門的に説明されると学ぶことは多いです。
>スカイプは近所に住む幼馴染もしない上に、弟が全くPCと言うものをしない&関心ないんです。
はっはっは、そのような状況も想像つきます。
あまりにも便利なツールが出来るとそれに頼りすぎるのも問題ですね。
>Mr.ギャランドゥは時差もあるので、直接電話で10分くらいってのが楽ですね~。
へーっギャランドゥとも電話されているんですか!
アメリカは電話代が安いのかな?(笑)
このような感想を言われる方はたくさんいますが、その言葉の背後に矢島先生の人柄が染み出ていたせいか思わず感動して泣いてしました。シニアの科学電話(メール)相談もお願いしたいほどです。
まだ現役でお勤めでいらっしゃるんですね。
羨ましいかぎりです。
「夏休み子ども科学電話相談」はとても楽しいですね。
私は日頃家でラジオを聞かないし、最近この時間に車にも乗っていないので長いこと聞いておりません。
矢島稔先生も上の写真で確認しました。
そうですか、とても感動的な挨拶だったんですね。
子供の成長って楽しいし、知らないことに気づかされることって多いですね。
>その言葉の背後に矢島先生の人柄が染み出ていたせいか思わず感動して泣いてしました。
私もそのような人生を送りたいですね。
どうも私はいつまでも青臭さが抜けません!
子供はとても好きなんですけど・・・。
>シニアの科学電話(メール)相談もお願いしたいほどです。
はっはっは、「夏休み子ども科学電話相談」がテレビ番組にあったら、私も即録画予約して時間がある時に見ると思います。
この番組は知識が増えるとともに、何とも可愛らしい子供の頭の中が覗けて楽しくなりますね。