映画の世界へ[編集]
子供たちに慕われた小津だったが、映画への愛着を捨てられず、1年で教員をやめて(東京に戻っていた)家族の元へ帰った。父親は初め、映画の仕事をしたいという小津の希望を聞かなかったが、最終的にこれを認めた。1923年(大正12年)の夏、叔父が地所を貸していて縁のあった松竹蒲田撮影所に入社して撮影助手の仕事に就き、月給30円を得た。直後の9月1日、関東大震災が発生。この非常事態に対処すべく、松竹社長大谷竹次郎の女婿・城戸四郎が臨時所長として蒲田撮影所にやってきた。城戸は当時の中心だった映画監督・島津保次郎らと今後の蒲田撮影所の方向性について話し合い、蒲田では現代劇映画をメインにしていくことを決めた。1924年に城戸は正式に所長に就任、新所長の元、松竹蒲田は現代劇の製作スタジオとして次々と優れた作品を生み出していく。城戸は俳優研究所も併設、ここから笠智衆ら新時代の映画俳優たちが生み出されていった。このころ、後の小津組の中核となるシナリオライター野田高梧も蒲田へやってきている。撮影助手時代の小津はまず碧川道夫や酒井健三らの下につき、監督では島津や牛原虚彦について映画製作を学んだ。
1924年12月、小津は当時の徴兵制度に従って一年志願兵として入隊し、翌1925年12月に除隊した。職場に復帰した小津は助監督として大久保忠素のもとにつき、現場で映画製作のノウハウを体得しながら、監督として必須の作業とされたシナリオ執筆に励んだ。そのうちの一本『瓦版カチカチ山』(映画化はされず)が城戸の目にとまった。1927年(昭和2年)8月、「監督ヲ命ズ、但シ時代劇部」という辞令によって小津は念願の監督昇進を果たした。こうして小津は初監督作『懺悔の刃』(同年10月公開)を撮るが、これは小津の長い監督歴の中で唯一の時代劇作品である。小津は撮影スケジュールの調整から始まり、セットづくり、俳優への演技指導と充実した毎日を過ごしたが、完成直前で思いかけず予備役召集がかかり、完成を斎藤寅次郎に託して入隊した。小津は後に「自分の作品のような気がしない」[8]と語っている。
同年11月、城戸の号令によって時代劇部が京都に移転。蒲田撮影所は現代劇に特化することになった。小津もこの方針に沿って次々に作品をつくりあげていく。1928年には笠智衆が初めて小津作品に参加した『若人の夢』以下、『女房紛失』『カボチヤ』『引越し夫婦』『肉体美』の5本、1929年(昭和4年)には『宝の山』、現存する最古の作品である『学生ロマンス 若き日』、『和製喧嘩友達』(現存)、『大学は出たけれど』(一部が現存)、『会社員生活』(現存せず)、『突貫小僧』(一部が現存)の6本を完成・公開している。「一年一作」となった戦後の小津からは考えられないハイペースな製作であった。
<昭和10年代日本版一帯一路・海外遠征:中国戦線、南京、漢口、九江、シンガポール戦線>
小津の戦争[編集]
1937年(昭和12年)に『淑女は何を忘れたか』を完成後の8月、京都から東京に移って東宝で監督業をしていた親友の山中貞雄に召集がかかったことで、小津は身近に迫る戦争の暗い影を感じ取った。
9月にはいると小津も応召し、9月24日に大阪から出航して中国戦線に向かった。
小津は指宿三郎少佐率いる第二中隊に属する第三小隊で班長を務めた。小津の部隊は南京総攻撃(12月10日-13日)には間に合わず、陥落後の南京を越えて奥地へと進軍した。1938年(昭和13年)1月12日、南京郊外の包容で山中と再会、久闊を叙した。山中は同年9月に急性腸炎を発症して開封の野戦病院で世を去ったため、これが2人の別れになった。
6月には伍長から軍曹に昇進して漢口作戦に従事、以後も各地を転戦した。1939年(昭和14年)6月26日、九江で帰還命令を受けて7月13日に神戸へ上陸、原隊に復帰して除隊した。1年10か月におよぶ戦場暮らしであった。
1939年、内務省の指示で映画法が成立し、映画を製作前に事前検閲するシステムなどが導入され、映画が国家に完全に統制されることになった。小津は復帰第1作として『彼氏南京に行く』というシナリオを執筆したが、これが映画法の事前検閲を通らず、映画化を断念した。小津の作品ですら検閲ではねられたこの事件は、映画界に衝撃を与えた。小津はめげずに1941年(昭和16年)に『戸田家の兄妹』を製作し、小津作品として初めての大ヒットとなった。小津は1932年から1934年まで作品が3年連続キネマ旬報ベストテン第1位となるなど批評家からの評価は高かったが、興行的な成功にはなかなか恵まれていなかった。次の作品『父ありき』(1942年4月公開)製作中に日米が開戦。小津の次回作の公開は1947年(昭和22年)まで待つことになるが、『父ありき』ではそれまでも小津作品にたびたび出演してきた笠智衆が初めて主演しており、この時点ですでに戦後の小津作品の骨格が完成していたことがうかがえる。
日米開戦後、小津は松竹が託されたビルマ作戦の映画化『ビルマ作戦 遥かなり父母の国』にあたったが、完成しなかった。
1943年6月、軍報道部映画班に徴集されて福岡の雁ノ巣飛行場から監督の秋山耕作、シナリオ作家の斎藤良輔と共に軍用機でシンガポールへ向かった。
「小津組」のカメラマン厚田雄春も後を追って到着した。シンガポールでは『オン・トゥー・デリー』という仮題のつけられたチャンドラ・ボースの活躍を映画化したものの製作に取り掛かったが、これもやはり完成しなかった。
小津はシンガポールで終戦を迎えるが、同地では「映写機の検査」の名目で大量のアメリカ映画を見ることができたという。その中には『嵐が丘』『北西への道』『レベッカ』『わが谷は緑なりき』『ファンタジア』『風と共に去りぬ』『市民ケーン』などが含まれていた[10]。
終戦後はしばらくの抑留生活を経て、1946年(昭和21年)2月11日に広島港へ上陸して帰国した。











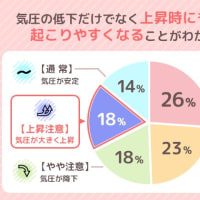



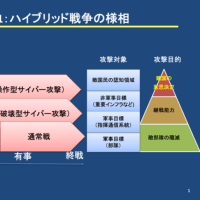

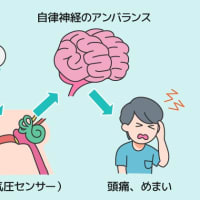
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます