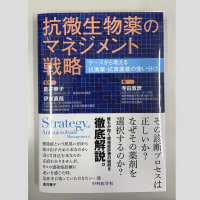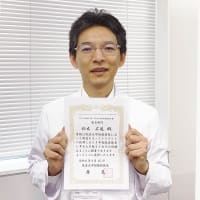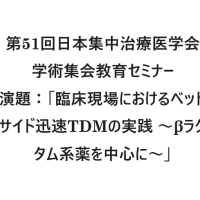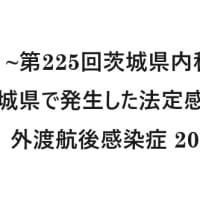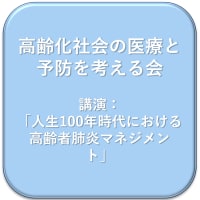日本痛風・核酸代謝学会ガイドライン改訂委員会
2002年の第1版より8年の歳月を経て2010年1月、メディカルレビュー社より出版。2000円。ガラパゴス島医療の象徴の変遷に注目
本ガイドラインは1年後に無料公開予定との事である。
1. 高尿酸血症は、尿酸沈着症(痛風関節炎・腎障害など)の病因であり、血清尿酸値が7.0mg/dlを超えるものと定義する。性・年齢を問わない。2a-B
2. 女性においては、血清尿酸値が7.0mg/dl以下であっても、血清尿酸値の上昇と共に生活習慣病のリスクが高くなる。潜在する疾患の検査と生活指導を行うが、尿酸降下薬の適応ではない。2a-B
3. 高尿酸血症の動向:本邦の成人男性における高尿酸血症の頻度は、30歳以降では30%に達していると推定される。3-C
4. 高尿酸血症は現在も増加傾向にある。 2b-B
5. 痛風の動向:痛風の有病率は、男性にいて30歳以降では1%を超えていると推定され現在も増加傾向であると考えられる。3-C
6. 血清尿酸値が7.0mg/dlを超えてくると、高くなるに従って痛風関節炎の発症リスクがより高まる。2a-A
7. 高尿酸血症の期間が長く、また高度であるほど、痛風結節はできやすい。3-C
8. アルコール摂取量は痛風発症リスクを用量依存的に上昇させる。肉類・砂糖入りソフトドリンク・嘉藤の摂取量が多い集団・BMIの高い集団は痛風になりやすい。2a-B
9. コーヒー摂取量が多い、ランニング距離が長い、適度な運動を日常的に行う集団は痛風になりにくい。2a-B
10. 血清尿酸値はCKDの発症や進展と関係する。2b-A
11. 一般集団において高尿酸血症は腎不全の危険因子である。2b-A
12. IgA腎症において高尿酸血漿は腎機能予後に関する危険因子である。3-B
13. CKDと痛風を併せ持つ症例には体内鉛蓄積が関与している可能性がある。1b-A
14. 尿酸結石の危険因子は、①尿量低下②高尿酸尿(症)③酸性尿である。 3-B
15. 高尿酸血症を有していても、必ずも尿路結石の頻度は増加しない。3-B
16. 高尿酸尿(症)を有すると、尿路結石の頻度が増加する傾向にある。3-B
17. 持続する酸性尿は、尿路結石の最も大きな危険因子である。3-B
18. 尿酸排泄促進薬は、プリン体過剰摂取や酸性尿により、尿酸結石の形成を促進させる。3-B
尿酸降下薬の選択として、尿酸排泄低下型では、プロベネシド、ブコローム、ベンズブロマロンといった尿酸排泄促進が使用させる事が多い。これらの薬剤により、尿中尿酸排泄量が増加するため、プリン体過剰摂取や持続する酸性尿を伴うと尿酸結石が容易に形成させる。
19. 高尿酸血症や痛風に合併する痛風結節は、尿酸結節だけではない、尿路結石で最も頻度が高いシュウ酸カルシウム結石もある。3-B
20. 血清尿酸値の上昇に伴ってメタボリックシンドロームの頻度は増加する。3-B
21. 痛風患者はメタボリックシンドロームの各構成要素を高頻度に有し、メタボリックシンドロームに該当する場合が多い。 3-B
22. 高尿酸血症はメタボリックシンドロームの診断基準に含まれていないが、メタボリックシンドロームの周辺徴候であることが示唆される。3-B
23. 内臓脂肪の蓄積に伴って血清尿酸値は上昇する。3-B
24. 高インスリン血症は腎尿細管における尿酸の再吸収を増加させ、血清尿酸値を上昇させる。2b-B
25. 血清尿酸値は将来における高血圧症発症の独立した予測因子と捉えることが可能である。1b-A
26. 最近の一般住民および高血圧患者による観察研究において、血清尿酸値は独立した心血管系疾患の危険因子と相関するか否かに関して、相反する報告がされている。2a-B
27. 観察研究のサブ解析において、生活習慣病治療に伴う血清尿酸値の上昇及び低下がそれぞれ心血管系イベントの増加及び抑制に寄与する可能性が示唆されるが、血清尿酸値の低下が心血管イベントに与える影響を検討したランダム化比較試験(RCT)の結果は示されていない。2a-B
28. 血清尿酸値は、脳卒中の初発ならびに再発リスク、心不全による予後ならびに再入院の予測因子となる可能性がある。2a-B
29. 血清尿酸値と悪性腫瘍による死亡との間に関連を認めたとする疫学調査がある。2a-B
30. 血清尿酸値のコントロールによって、悪性腫瘍の相対危険度が低下するかどうかについては不明である。2a-B
31. 血清尿酸値は、総死亡のリスクと関連する可能性がある。2a-B
32. 女性においては、高尿酸血症の基準値より低い血清尿酸値から、総死亡の相対危険度の上昇を伴う可能性がある。2a-B
33. 血清尿酸値のコントロールによって、総死亡の相対危険度が低下するかどうかは不明である。2a-B
34. ほとんどの施設で、自動分析装置によるウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法が用いられている。2a-A
35. 測定値の変動は血清成分の影響を考慮して9.0%, 施設間差は2.7%-6.8%である、信頼できる測定法といえる。3-B
36. 高尿酸血症の判定について、採血時期は空腹時でなくてもよいが、恒常的な高尿酸血症の判定には複数回の測定が必要である。3-B
37. 高尿酸血症は、「尿酸産生過剰型」「尿酸排泄低下型」「混合型」に大別される。2b-A
38. 病型分類には、尿酸クリアランスおよびクレアチニン・クリアランス(Ccr)の測定を行う。(尿酸産生過剰型:尿中尿酸排泄量>0.51mg/kg/時、尿酸排泄低下型:尿酸クリアランス<7.3m L/分)2b-A
39. 治療中の病型の変化に注意する。2b-A
健常者の生体内には通常約1200mgの尿酸プールが存在する。尿酸産生量はおよそ700mg/日である。このうち約500mg/日が尿中に排泄され約200mg/日が汗、消化液などに排泄される。
尿酸クリアランス・Ccr試験実施法(60分法)
3日前 高プリン食・飲酒制限
起床後 絶食・飲水コップ2杯
外来 30分前:飲水300ml 0分;30分後排尿(ここから60分の尿を正確にとる) 30分:中間時採決(血中尿酸・クレアチニン) 60分:60分間の全尿採取(尿量測定・尿中尿酸・クレアニチン測定)
尿中尿酸排泄量=尿中尿酸濃度mg/dl ×60分間尿量ml/100×体重 mg/kg/hr
正常値0.496(0.483-0.509)mg/kg/時
尿酸クリアランス
尿中尿酸濃度×60分間尿量/血漿尿酸濃度mg/dl ×60 ×1.73/体表面積
正常値 11.0(7.3-14.7)ml/分
R=尿酸クリアランス/Ccr ×100% = 尿中尿酸濃度×血漿クレアチニン濃度/血漿尿酸濃度×尿中クレアチニン濃度 ×100%
正常値 8.3(5.5-11.1)%
40. 痛風関節炎とは関節内に析出した尿酸塩結晶が起こす関節炎である。2a-A
41. 急性痛風関節炎(痛風発作)は、第一中足シ節(MTP)関節、足関節などに好発する。2a-A
42. 診断には、特徴的症状、高尿酸血症の既往、関節液中の尿酸塩結晶の同定が重症である。3-B
43. 痛風発作中には血清尿酸値は必ずしも高値を示さない。3-B
44. 痛風結節は尿酸塩結晶と肉芽組織からなり、診断に有用である。2a-A
45. 高尿酸血症の診断に際し、必ず二次性の可能性について検討する。2b-B
46. 急性尿酸性腎症および腫瘍誘拐症候群は治癒を目指す緊急疾患である。 1b-A
47. 痛風発作の前兆期にはコルヒチン1錠0.5mgを用い、発作を頓挫させる。痛風発作が頻発する場合には、コルヒチン1日1錠を連日服用させるコルヒチン・カバーが有効である。3-B
48. 痛風発作の極期にはNSAIDが有効であるが、短期間に限り比較的多量を投与して炎症を鎮静化させる(NSAIDパルス療法)。副作用の発現に注意する。3-B
49. NSAIDが使用できない場合、NSAIDが無効であった場合、多発性に関節炎を生じている場合などには、経口にて副腎皮質ステロイドを投与する。1a-A
50. 痛風発作時に血清尿酸値を変動させると発作の増悪を認める事が多いため、発作中に尿酸降下薬を開始しないことを原則とする。3-B
51. 痛風結節の治療では摘出術が考慮させることもあるが、手術した場合も薬物療法は必要である。3-B
52. 高尿酸血症の治療では、予後に関係する肥満、高血圧、糖・脂質代謝異常などの合併症もきたしやすい高尿酸血症の発症に関連する生活習慣を改善することが最も大切である。2a-A
53. 痛風関節炎を繰り返す症例や痛風結節を認める症例は薬物治療の適応となり、血清尿酸値を6.0mg/dl以下に維持するのが望ましい。
54. 無症候性高尿酸血症への薬物治療の導入は血清尿酸値8.0mg/dl以上を一応の目安とするが、適応は慎重にすべきである。3-C
欧米では無症候性高尿酸血症に対する薬物治療に否定的な見解をとっている。状況に応じて薬物治療を考慮するのがよいと思われる。
55. 現在我が国で使用できる尿酸排泄促進薬は3種類あるが、尿酸生成抑制薬はアロプリノールのみである。
56. 尿酸排泄低下型に尿酸排泄促進薬、尿酸産生過剰型に尿酸生成抑制薬(アロプリノール)を選択することを基本原則とする。3-C
57. 中等度以上、GFR 30ml/分/1.73 ㎡ 以下、又は血清Cre 2.0 mg/dl以上の腎機能障害はアロプリノールを選択する。3-C
58. アルプリノールを腎不全の患者に使用するときは腎障害に合わせて投与量を調整する。 3-B
59. 尿路結石の既往あるいは合併がある場合はアロプリノールを選択する。 3-C
60. 尿酸排泄促進薬を使用する場合は尿路結石の発現に注意し、尿アルカリ化薬を併用する。3-B
61. ベンズブロマロンとブコロームはワルファリンカリウムの血中濃度を増加させるため、併用時は注意を要する。4-A
62. 無症候性高尿酸血症の段階で、高尿酸血症を基盤とする痛風関節炎、痛風結節、腎障害、尿路結石の発症を防ぐために血清尿酸値を低下させることが望ましい。3-B
63. 血清尿酸値を下げるために生活習慣の改善を指導することが重要であり、具体的にはアルコール飲料やプリン体、果糖、ショ糖やカロリーの過剰摂取を避け、また過激な運動は控えるように指導する。3-A
64. 生活習慣の改善にもかかわらず血清尿酸値が9.0mg/dl以上の無症候性高尿酸血症では薬物療法を考慮する。また尿路結石、腎疾患、高血圧などの合併がある場合は、血清尿酸値が8.0mg/dl以上で薬物療法を考慮する。3-B
14年の追跡調査において血清尿酸値が7.0-7.9mg/dlで16%、8.0-8.9mg/dlで25%, 9.0mg/dlで90%以上が痛風関節炎を発症。別の15年にわたる健常男性の追跡調査では、追跡開始時の血清尿酸値が7.0mg/dl未満で毎年0.1%, 7.0-8.9md/dlで0.5%, 9.0mg/dlで毎年4.9%の痛風関節炎が発症。
65. 未治療例の痛風関節炎時は尿酸降下薬を投与せず、NSAIDパルス療法で寛解させる。2b-A
66. 高尿酸血症の薬物療法は血清尿酸値を3-6カ月かけて徐々に低下させ、6.0mg/dl以下にし、その後は6.0mg/dl以下に安定する用量を続ける。2b-B
67. 尿酸降下薬は痛風関節炎の寛解薬2週間後から少量(ベンズブロマロン12.5mg, アロプリノール50mg)で開始する。2b-B
68. 尿酸降下薬の投与開始初期は、痛風関節炎を防止するために少量のコルヒチンを併用投与するとよい。1b-B
69. 適量の尿酸降下薬投与時に痛風関節炎が起こった場合は、尿酸降下薬を中止することなく、痛風関節炎の治療に準じNSAIDパルス療法を併用する。
治療目標は6.0mg/dl (尿酸の体液中での溶解限界:6.4mg/dl)
尿酸排泄促進薬の投与時は特にクエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム(3-6g/日、3-4回に分割)を併用投与し、尿p Hを6.0-7.0に保ち、尿酸結石の出現を防ぐ。投与開始6カ月間は毎月検査する事が望ましい。
70. 腎障害合併例、尿路結石保有例では、尿酸降下薬としてアロプリノールを使用する。また、腎障害合併例ではアロプリノールとベンズブロマロンの少量併用も有効である。3-B
71. 腎機能の低下に応じて、アロプリノールの使用量を減じる必要である。3-B
72. アロプリノールによる高尿酸血症治療はCKD患者の腎機能保持に有用である。1b-B
73. ロサルタンカリウムはシクロスポリン治療中の腎移植患者の高血圧・高尿酸血症コントロールに有用である。1b-A
74. 腎移植後の高尿酸血症のコントロールには尿酸排泄促進薬の有用性が高い。3-B
75. 維持血液透析患者におけるセベラマー塩酸塩による高リン血症治療は高尿酸血症対策にもつながる。1b-B
76. 飲水指導は、尿量を2000ml/日以上確保することが目標である。 2b-B
77. 尿路結石を合併する高尿酸血症の治療薬は、アロプリノールが第一選択である。3-B
78. 尿酸排泄促進薬は尿酸結石の形成を促進させるため、原則として尿路結石を合併している症例には使用しない。3-B
79. 尿アルカリ化はクエン酸製剤を中心とし、尿p Hは6.0-7.0の維持を目標とする。並行してプリン体摂取制限などの食事療法が必要である。3-B
80. 高尿酸尿(症)を伴うシュウ酸カルシウム結石の再発防止には、アロプリノールや尿アルカリ化薬が有効である。1b-A
81. 尿酸結石の治療は、ESWLが中心となるが、尿アルカリ化薬アロプリノールによる結石溶解療法も選択肢となる。2b-B
82. 高血圧合併高尿酸血症患者に対しては、高尿酸血症の発症に関連する生活習慣を同時に改善する総合的な臓器のリスク回避を目指し、まず生活指導を行う。2a-B
83. 薬物療法は血圧管理を優先し、可能な限り尿酸代謝に悪影響を及ぼさない降圧薬を優先して用いる事が望ましい。2b-B
84. 生活指導ならびに尿酸代謝に好ましい降圧薬を用いても、血清尿酸値が8.0mg/dl以上の場合は、尿酸降下薬の投与開始を考慮する。治療中の血清尿酸値は6.0mg/dl以下に維持する。3-C
85. 尿酸降下薬の選択は病型分類に基づいて行うが、腎障害の程度、肝障害の有無によって治療薬、投与量を慎重に決定する。又、尿p Hの測定を行い、尿アルカリ化薬併用も考慮する。3-C
86. 高尿酸血症の治療と共に動脈硬化性疾患の一因子となる脂質異常症を治療し、動脈硬化性疾患の軽減を図ることを目標とする。1b-A
87. 診断は動脈硬化疾患予防ガイドライン2007年版の診断基準に従う。すなわち高LDL血症(LDL≧140mg/dl)、低HDL-コレステロール血症(HDL<40mg/dl)、もしくは高TG血症(TG≧150mg/dl)を脂質異常症と診断する。1b-A <br>
88. 高尿酸血症・痛風に合併する脂質異常症の治療は「動脈硬化予防ガイドライン2007年度版」に基づいて行う。1b-A
89. 脂質異常症治療薬の中には血清尿酸値に影響を与える薬剤があるので考慮する。特にフェノフィブラートは高TG血症と高尿酸血症の合併、特に尿酸排泄低下型高尿酸血症の合併には有効な薬剤である。3-A
90. メタボリックシンドロームの治療の最終目標は、本症候群の臨床的帰結である動脈硬化性疾患や2型糖尿病の発症予防と進展阻止にある。判定不能-A
91. 食事療法や運動療法、また喫煙などの生活習慣をまず改善することが、治療の基本である。1b-A
92. 本症候群に伴う各種病態(高尿酸血症を含む)は、食事療法や運動療法により改善し、特に両療法を併せて実践して体重が減量すれば、効果は大きい。1b-A
93. 生活習慣の改善のみで効果が乏しい場合や、十分な効果が期待できない場合に、個々の合併疾患に対する薬物療法を行う。薬物療法に際しては、尿酸代謝への影響も配慮して薬剤を選択する.4-C
94. 基礎疾患の消長に応じて、治療内容を調節する。2b-B
95. 急性尿酸性腎症は及び腫瘍誘拐症候群は治癒を目指しうる緊急疾患である。1b-A
96. 混合型二次性高尿酸血症の治療は、尿酸産生過剰型、尿酸排泄低下型両者の特徴に配慮しつつ、原発性に準じて行う。3-C
97. 尿酸排泄低下型高尿酸血症治療の第一選択は尿酸排泄促進薬のベンズブロマロンである。しかし腎機能低下例では、尿酸生成抑制薬のアロプリノールの併用あるいは単独投与が適応にあるが、その際には腎機能に応じて投与量を減じる必要がある。3-C
98. 高尿酸血症・痛風は代表的な生活習慣病であり、生活習慣の是正を目的とした非薬物療法としての生活指導は、薬物療法の有無に関わらず重要な役割を有する。2a-B
99. 高尿酸血症・痛風に対する生活指導は、食事療法、飲酒制限、運動の推奨が中心となり、肥満の解消は血清尿酸値を低下させる効果が期待される。2b-B
100. 食事療法としては適切なエネルギー摂取、プリン体・果糖の過剰摂取制限、十分な飲水が勧められる。2a-B
101. 身体活動(運動)は、メタボリックシンドロームの種々の病態を改善するため奨励でいる。3-C
2002年の第1版より8年の歳月を経て2010年1月、メディカルレビュー社より出版。2000円。ガラパゴス島医療の象徴の変遷に注目
本ガイドラインは1年後に無料公開予定との事である。
1. 高尿酸血症は、尿酸沈着症(痛風関節炎・腎障害など)の病因であり、血清尿酸値が7.0mg/dlを超えるものと定義する。性・年齢を問わない。2a-B
2. 女性においては、血清尿酸値が7.0mg/dl以下であっても、血清尿酸値の上昇と共に生活習慣病のリスクが高くなる。潜在する疾患の検査と生活指導を行うが、尿酸降下薬の適応ではない。2a-B
3. 高尿酸血症の動向:本邦の成人男性における高尿酸血症の頻度は、30歳以降では30%に達していると推定される。3-C
4. 高尿酸血症は現在も増加傾向にある。 2b-B
5. 痛風の動向:痛風の有病率は、男性にいて30歳以降では1%を超えていると推定され現在も増加傾向であると考えられる。3-C
6. 血清尿酸値が7.0mg/dlを超えてくると、高くなるに従って痛風関節炎の発症リスクがより高まる。2a-A
7. 高尿酸血症の期間が長く、また高度であるほど、痛風結節はできやすい。3-C
8. アルコール摂取量は痛風発症リスクを用量依存的に上昇させる。肉類・砂糖入りソフトドリンク・嘉藤の摂取量が多い集団・BMIの高い集団は痛風になりやすい。2a-B
9. コーヒー摂取量が多い、ランニング距離が長い、適度な運動を日常的に行う集団は痛風になりにくい。2a-B
10. 血清尿酸値はCKDの発症や進展と関係する。2b-A
11. 一般集団において高尿酸血症は腎不全の危険因子である。2b-A
12. IgA腎症において高尿酸血漿は腎機能予後に関する危険因子である。3-B
13. CKDと痛風を併せ持つ症例には体内鉛蓄積が関与している可能性がある。1b-A
14. 尿酸結石の危険因子は、①尿量低下②高尿酸尿(症)③酸性尿である。 3-B
15. 高尿酸血症を有していても、必ずも尿路結石の頻度は増加しない。3-B
16. 高尿酸尿(症)を有すると、尿路結石の頻度が増加する傾向にある。3-B
17. 持続する酸性尿は、尿路結石の最も大きな危険因子である。3-B
18. 尿酸排泄促進薬は、プリン体過剰摂取や酸性尿により、尿酸結石の形成を促進させる。3-B
尿酸降下薬の選択として、尿酸排泄低下型では、プロベネシド、ブコローム、ベンズブロマロンといった尿酸排泄促進が使用させる事が多い。これらの薬剤により、尿中尿酸排泄量が増加するため、プリン体過剰摂取や持続する酸性尿を伴うと尿酸結石が容易に形成させる。
19. 高尿酸血症や痛風に合併する痛風結節は、尿酸結節だけではない、尿路結石で最も頻度が高いシュウ酸カルシウム結石もある。3-B
20. 血清尿酸値の上昇に伴ってメタボリックシンドロームの頻度は増加する。3-B
21. 痛風患者はメタボリックシンドロームの各構成要素を高頻度に有し、メタボリックシンドロームに該当する場合が多い。 3-B
22. 高尿酸血症はメタボリックシンドロームの診断基準に含まれていないが、メタボリックシンドロームの周辺徴候であることが示唆される。3-B
23. 内臓脂肪の蓄積に伴って血清尿酸値は上昇する。3-B
24. 高インスリン血症は腎尿細管における尿酸の再吸収を増加させ、血清尿酸値を上昇させる。2b-B
25. 血清尿酸値は将来における高血圧症発症の独立した予測因子と捉えることが可能である。1b-A
26. 最近の一般住民および高血圧患者による観察研究において、血清尿酸値は独立した心血管系疾患の危険因子と相関するか否かに関して、相反する報告がされている。2a-B
27. 観察研究のサブ解析において、生活習慣病治療に伴う血清尿酸値の上昇及び低下がそれぞれ心血管系イベントの増加及び抑制に寄与する可能性が示唆されるが、血清尿酸値の低下が心血管イベントに与える影響を検討したランダム化比較試験(RCT)の結果は示されていない。2a-B
28. 血清尿酸値は、脳卒中の初発ならびに再発リスク、心不全による予後ならびに再入院の予測因子となる可能性がある。2a-B
29. 血清尿酸値と悪性腫瘍による死亡との間に関連を認めたとする疫学調査がある。2a-B
30. 血清尿酸値のコントロールによって、悪性腫瘍の相対危険度が低下するかどうかについては不明である。2a-B
31. 血清尿酸値は、総死亡のリスクと関連する可能性がある。2a-B
32. 女性においては、高尿酸血症の基準値より低い血清尿酸値から、総死亡の相対危険度の上昇を伴う可能性がある。2a-B
33. 血清尿酸値のコントロールによって、総死亡の相対危険度が低下するかどうかは不明である。2a-B
34. ほとんどの施設で、自動分析装置によるウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法が用いられている。2a-A
35. 測定値の変動は血清成分の影響を考慮して9.0%, 施設間差は2.7%-6.8%である、信頼できる測定法といえる。3-B
36. 高尿酸血症の判定について、採血時期は空腹時でなくてもよいが、恒常的な高尿酸血症の判定には複数回の測定が必要である。3-B
37. 高尿酸血症は、「尿酸産生過剰型」「尿酸排泄低下型」「混合型」に大別される。2b-A
38. 病型分類には、尿酸クリアランスおよびクレアチニン・クリアランス(Ccr)の測定を行う。(尿酸産生過剰型:尿中尿酸排泄量>0.51mg/kg/時、尿酸排泄低下型:尿酸クリアランス<7.3m L/分)2b-A
39. 治療中の病型の変化に注意する。2b-A
健常者の生体内には通常約1200mgの尿酸プールが存在する。尿酸産生量はおよそ700mg/日である。このうち約500mg/日が尿中に排泄され約200mg/日が汗、消化液などに排泄される。
尿酸クリアランス・Ccr試験実施法(60分法)
3日前 高プリン食・飲酒制限
起床後 絶食・飲水コップ2杯
外来 30分前:飲水300ml 0分;30分後排尿(ここから60分の尿を正確にとる) 30分:中間時採決(血中尿酸・クレアチニン) 60分:60分間の全尿採取(尿量測定・尿中尿酸・クレアニチン測定)
尿中尿酸排泄量=尿中尿酸濃度mg/dl ×60分間尿量ml/100×体重 mg/kg/hr
正常値0.496(0.483-0.509)mg/kg/時
尿酸クリアランス
尿中尿酸濃度×60分間尿量/血漿尿酸濃度mg/dl ×60 ×1.73/体表面積
正常値 11.0(7.3-14.7)ml/分
R=尿酸クリアランス/Ccr ×100% = 尿中尿酸濃度×血漿クレアチニン濃度/血漿尿酸濃度×尿中クレアチニン濃度 ×100%
正常値 8.3(5.5-11.1)%
40. 痛風関節炎とは関節内に析出した尿酸塩結晶が起こす関節炎である。2a-A
41. 急性痛風関節炎(痛風発作)は、第一中足シ節(MTP)関節、足関節などに好発する。2a-A
42. 診断には、特徴的症状、高尿酸血症の既往、関節液中の尿酸塩結晶の同定が重症である。3-B
43. 痛風発作中には血清尿酸値は必ずしも高値を示さない。3-B
44. 痛風結節は尿酸塩結晶と肉芽組織からなり、診断に有用である。2a-A
45. 高尿酸血症の診断に際し、必ず二次性の可能性について検討する。2b-B
46. 急性尿酸性腎症および腫瘍誘拐症候群は治癒を目指す緊急疾患である。 1b-A
47. 痛風発作の前兆期にはコルヒチン1錠0.5mgを用い、発作を頓挫させる。痛風発作が頻発する場合には、コルヒチン1日1錠を連日服用させるコルヒチン・カバーが有効である。3-B
48. 痛風発作の極期にはNSAIDが有効であるが、短期間に限り比較的多量を投与して炎症を鎮静化させる(NSAIDパルス療法)。副作用の発現に注意する。3-B
49. NSAIDが使用できない場合、NSAIDが無効であった場合、多発性に関節炎を生じている場合などには、経口にて副腎皮質ステロイドを投与する。1a-A
50. 痛風発作時に血清尿酸値を変動させると発作の増悪を認める事が多いため、発作中に尿酸降下薬を開始しないことを原則とする。3-B
51. 痛風結節の治療では摘出術が考慮させることもあるが、手術した場合も薬物療法は必要である。3-B
52. 高尿酸血症の治療では、予後に関係する肥満、高血圧、糖・脂質代謝異常などの合併症もきたしやすい高尿酸血症の発症に関連する生活習慣を改善することが最も大切である。2a-A
53. 痛風関節炎を繰り返す症例や痛風結節を認める症例は薬物治療の適応となり、血清尿酸値を6.0mg/dl以下に維持するのが望ましい。
54. 無症候性高尿酸血症への薬物治療の導入は血清尿酸値8.0mg/dl以上を一応の目安とするが、適応は慎重にすべきである。3-C
欧米では無症候性高尿酸血症に対する薬物治療に否定的な見解をとっている。状況に応じて薬物治療を考慮するのがよいと思われる。
55. 現在我が国で使用できる尿酸排泄促進薬は3種類あるが、尿酸生成抑制薬はアロプリノールのみである。
56. 尿酸排泄低下型に尿酸排泄促進薬、尿酸産生過剰型に尿酸生成抑制薬(アロプリノール)を選択することを基本原則とする。3-C
57. 中等度以上、GFR 30ml/分/1.73 ㎡ 以下、又は血清Cre 2.0 mg/dl以上の腎機能障害はアロプリノールを選択する。3-C
58. アルプリノールを腎不全の患者に使用するときは腎障害に合わせて投与量を調整する。 3-B
59. 尿路結石の既往あるいは合併がある場合はアロプリノールを選択する。 3-C
60. 尿酸排泄促進薬を使用する場合は尿路結石の発現に注意し、尿アルカリ化薬を併用する。3-B
61. ベンズブロマロンとブコロームはワルファリンカリウムの血中濃度を増加させるため、併用時は注意を要する。4-A
62. 無症候性高尿酸血症の段階で、高尿酸血症を基盤とする痛風関節炎、痛風結節、腎障害、尿路結石の発症を防ぐために血清尿酸値を低下させることが望ましい。3-B
63. 血清尿酸値を下げるために生活習慣の改善を指導することが重要であり、具体的にはアルコール飲料やプリン体、果糖、ショ糖やカロリーの過剰摂取を避け、また過激な運動は控えるように指導する。3-A
64. 生活習慣の改善にもかかわらず血清尿酸値が9.0mg/dl以上の無症候性高尿酸血症では薬物療法を考慮する。また尿路結石、腎疾患、高血圧などの合併がある場合は、血清尿酸値が8.0mg/dl以上で薬物療法を考慮する。3-B
14年の追跡調査において血清尿酸値が7.0-7.9mg/dlで16%、8.0-8.9mg/dlで25%, 9.0mg/dlで90%以上が痛風関節炎を発症。別の15年にわたる健常男性の追跡調査では、追跡開始時の血清尿酸値が7.0mg/dl未満で毎年0.1%, 7.0-8.9md/dlで0.5%, 9.0mg/dlで毎年4.9%の痛風関節炎が発症。
65. 未治療例の痛風関節炎時は尿酸降下薬を投与せず、NSAIDパルス療法で寛解させる。2b-A
66. 高尿酸血症の薬物療法は血清尿酸値を3-6カ月かけて徐々に低下させ、6.0mg/dl以下にし、その後は6.0mg/dl以下に安定する用量を続ける。2b-B
67. 尿酸降下薬は痛風関節炎の寛解薬2週間後から少量(ベンズブロマロン12.5mg, アロプリノール50mg)で開始する。2b-B
68. 尿酸降下薬の投与開始初期は、痛風関節炎を防止するために少量のコルヒチンを併用投与するとよい。1b-B
69. 適量の尿酸降下薬投与時に痛風関節炎が起こった場合は、尿酸降下薬を中止することなく、痛風関節炎の治療に準じNSAIDパルス療法を併用する。
治療目標は6.0mg/dl (尿酸の体液中での溶解限界:6.4mg/dl)
尿酸排泄促進薬の投与時は特にクエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム(3-6g/日、3-4回に分割)を併用投与し、尿p Hを6.0-7.0に保ち、尿酸結石の出現を防ぐ。投与開始6カ月間は毎月検査する事が望ましい。
70. 腎障害合併例、尿路結石保有例では、尿酸降下薬としてアロプリノールを使用する。また、腎障害合併例ではアロプリノールとベンズブロマロンの少量併用も有効である。3-B
71. 腎機能の低下に応じて、アロプリノールの使用量を減じる必要である。3-B
72. アロプリノールによる高尿酸血症治療はCKD患者の腎機能保持に有用である。1b-B
73. ロサルタンカリウムはシクロスポリン治療中の腎移植患者の高血圧・高尿酸血症コントロールに有用である。1b-A
74. 腎移植後の高尿酸血症のコントロールには尿酸排泄促進薬の有用性が高い。3-B
75. 維持血液透析患者におけるセベラマー塩酸塩による高リン血症治療は高尿酸血症対策にもつながる。1b-B
76. 飲水指導は、尿量を2000ml/日以上確保することが目標である。 2b-B
77. 尿路結石を合併する高尿酸血症の治療薬は、アロプリノールが第一選択である。3-B
78. 尿酸排泄促進薬は尿酸結石の形成を促進させるため、原則として尿路結石を合併している症例には使用しない。3-B
79. 尿アルカリ化はクエン酸製剤を中心とし、尿p Hは6.0-7.0の維持を目標とする。並行してプリン体摂取制限などの食事療法が必要である。3-B
80. 高尿酸尿(症)を伴うシュウ酸カルシウム結石の再発防止には、アロプリノールや尿アルカリ化薬が有効である。1b-A
81. 尿酸結石の治療は、ESWLが中心となるが、尿アルカリ化薬アロプリノールによる結石溶解療法も選択肢となる。2b-B
82. 高血圧合併高尿酸血症患者に対しては、高尿酸血症の発症に関連する生活習慣を同時に改善する総合的な臓器のリスク回避を目指し、まず生活指導を行う。2a-B
83. 薬物療法は血圧管理を優先し、可能な限り尿酸代謝に悪影響を及ぼさない降圧薬を優先して用いる事が望ましい。2b-B
84. 生活指導ならびに尿酸代謝に好ましい降圧薬を用いても、血清尿酸値が8.0mg/dl以上の場合は、尿酸降下薬の投与開始を考慮する。治療中の血清尿酸値は6.0mg/dl以下に維持する。3-C
85. 尿酸降下薬の選択は病型分類に基づいて行うが、腎障害の程度、肝障害の有無によって治療薬、投与量を慎重に決定する。又、尿p Hの測定を行い、尿アルカリ化薬併用も考慮する。3-C
86. 高尿酸血症の治療と共に動脈硬化性疾患の一因子となる脂質異常症を治療し、動脈硬化性疾患の軽減を図ることを目標とする。1b-A
87. 診断は動脈硬化疾患予防ガイドライン2007年版の診断基準に従う。すなわち高LDL血症(LDL≧140mg/dl)、低HDL-コレステロール血症(HDL<40mg/dl)、もしくは高TG血症(TG≧150mg/dl)を脂質異常症と診断する。1b-A <br>
88. 高尿酸血症・痛風に合併する脂質異常症の治療は「動脈硬化予防ガイドライン2007年度版」に基づいて行う。1b-A
89. 脂質異常症治療薬の中には血清尿酸値に影響を与える薬剤があるので考慮する。特にフェノフィブラートは高TG血症と高尿酸血症の合併、特に尿酸排泄低下型高尿酸血症の合併には有効な薬剤である。3-A
90. メタボリックシンドロームの治療の最終目標は、本症候群の臨床的帰結である動脈硬化性疾患や2型糖尿病の発症予防と進展阻止にある。判定不能-A
91. 食事療法や運動療法、また喫煙などの生活習慣をまず改善することが、治療の基本である。1b-A
92. 本症候群に伴う各種病態(高尿酸血症を含む)は、食事療法や運動療法により改善し、特に両療法を併せて実践して体重が減量すれば、効果は大きい。1b-A
93. 生活習慣の改善のみで効果が乏しい場合や、十分な効果が期待できない場合に、個々の合併疾患に対する薬物療法を行う。薬物療法に際しては、尿酸代謝への影響も配慮して薬剤を選択する.4-C
94. 基礎疾患の消長に応じて、治療内容を調節する。2b-B
95. 急性尿酸性腎症は及び腫瘍誘拐症候群は治癒を目指しうる緊急疾患である。1b-A
96. 混合型二次性高尿酸血症の治療は、尿酸産生過剰型、尿酸排泄低下型両者の特徴に配慮しつつ、原発性に準じて行う。3-C
97. 尿酸排泄低下型高尿酸血症治療の第一選択は尿酸排泄促進薬のベンズブロマロンである。しかし腎機能低下例では、尿酸生成抑制薬のアロプリノールの併用あるいは単独投与が適応にあるが、その際には腎機能に応じて投与量を減じる必要がある。3-C
98. 高尿酸血症・痛風は代表的な生活習慣病であり、生活習慣の是正を目的とした非薬物療法としての生活指導は、薬物療法の有無に関わらず重要な役割を有する。2a-B
99. 高尿酸血症・痛風に対する生活指導は、食事療法、飲酒制限、運動の推奨が中心となり、肥満の解消は血清尿酸値を低下させる効果が期待される。2b-B
100. 食事療法としては適切なエネルギー摂取、プリン体・果糖の過剰摂取制限、十分な飲水が勧められる。2a-B
101. 身体活動(運動)は、メタボリックシンドロームの種々の病態を改善するため奨励でいる。3-C