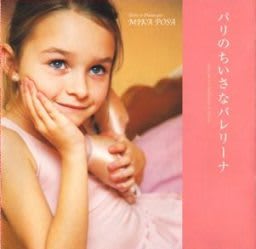全都道府県についてあらゆる角度から見渡せるよう、人口、産業、歴史、おまけのプチ情報、持ちかたまでを網羅。
ちょうど、4年生は都道府県名を社会科で教わったばかり。
こんな都道府県の覚え方もあっていい。
なにしろ、形をしっかり覚えられますからね。
「俺なら、こうやって持つなぁ~!」と、自分で考えたりしていますよ。
私的に一番ウケたのは、鹿児島県。
食パンの袋のクリップになっています。あのプラスチック製の。
鹿児島湾(錦江湾)で袋の口をキュッと絞ります。
巻末には、持ちかたに関する練習問題がついていて、力だめしもできます(笑)
この本が来てからというもの、何を持つにも、
「これを持つとしたら、こう?」
と、言いながら、変わった持ちかたをしてみるのがマイブームの我が家。
ちょうど、4年生は都道府県名を社会科で教わったばかり。
こんな都道府県の覚え方もあっていい。
なにしろ、形をしっかり覚えられますからね。
「俺なら、こうやって持つなぁ~!」と、自分で考えたりしていますよ。
私的に一番ウケたのは、鹿児島県。
食パンの袋のクリップになっています。あのプラスチック製の。
鹿児島湾(錦江湾)で袋の口をキュッと絞ります。
巻末には、持ちかたに関する練習問題がついていて、力だめしもできます(笑)
この本が来てからというもの、何を持つにも、
「これを持つとしたら、こう?」
と、言いながら、変わった持ちかたをしてみるのがマイブームの我が家。