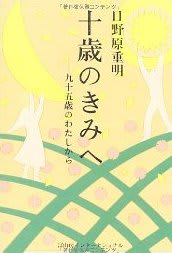寿命とは
平和とは
家族とは
日野原先生の、子どもひとりひとりに語りかけるような優しい文章が、心に沁みます。
「ほかの人のために きみはどれだけ時間をつかっていますか」
「わたしにふりかかった人生で最悪の体験。そのおかげで、いまのわたしがあります」
「きみが今日流したなみだは、だれかのなみだをわかるためのレッスンかもしれません」
「かわりばえしない、なんでもない毎日も、人生の大きな宝ものです」
「毎日のくり返しのなかで、自分の「芯(しん)」になる部分がつくられていきます」
「いいときも、わるいときも、家族はいっしょにいる。そこが、家族のすごいところです」
なにも特別なことがなくても、平凡な穏やかに家族と過ごせる毎日に感謝です。
まだ、読まれていない新5年生の保護者の方は、この機会にぜひご一読を。
なお、「うちの子、もらってきてないわ~、見てないわ~」という保護者の方は、子どもに問い詰めて、本をGETしましょう。
平和とは
家族とは
日野原先生の、子どもひとりひとりに語りかけるような優しい文章が、心に沁みます。
「ほかの人のために きみはどれだけ時間をつかっていますか」
「わたしにふりかかった人生で最悪の体験。そのおかげで、いまのわたしがあります」
「きみが今日流したなみだは、だれかのなみだをわかるためのレッスンかもしれません」
「かわりばえしない、なんでもない毎日も、人生の大きな宝ものです」
「毎日のくり返しのなかで、自分の「芯(しん)」になる部分がつくられていきます」
「いいときも、わるいときも、家族はいっしょにいる。そこが、家族のすごいところです」
なにも特別なことがなくても、平凡な穏やかに家族と過ごせる毎日に感謝です。
まだ、読まれていない新5年生の保護者の方は、この機会にぜひご一読を。
なお、「うちの子、もらってきてないわ~、見てないわ~」という保護者の方は、子どもに問い詰めて、本をGETしましょう。