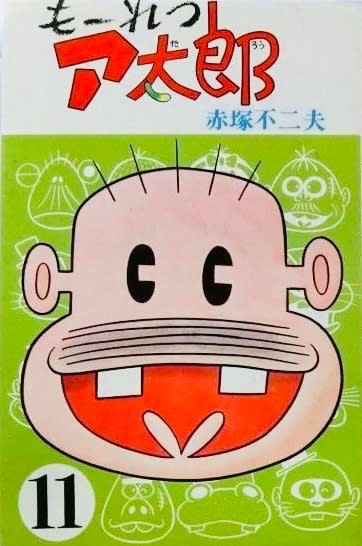
赤塚不二夫といえば、様々な風説、流言飛語が飛び交い、世間一般的には、その実像が捉えきれない漫画家である。
そうした誤情報の大半が、赤塚不二夫という存在を矮小化し、負のイメージを植え付けてやまない、アンチ発信によるネガティブな内容のものばかりであるが、それらとは別に、「実は…」というような、トリビア的な意味合いで捏造されたネタも少なくない。
こうしたデマは、考える力を全く持たない無知や情報弱者の間にて広く伝播してゆく過程で、伝言ゲームのように更なる誤情報が追加されるというケースも多々存在する。
例を挙げるならば、赤塚不二夫が、帝銀事件、三億円事件、グリコ森永事件等、昭和の未解決事件の真犯人であったという語るにも脱力感しか沸かない馬鹿馬鹿しいものから、昭和生まれというのは、全くの出鱈目で、廃藩置県が断行される以前、実は江戸末期の生まれであるといった赤塚マンガ以上にナンセンスなネタまで千差万別なのだが、その中でも、尤もらしい、一廉の知性や教養を持ち得た人間すらも、コロッと騙されてしまう危険を孕んだ虚伝も実際にあるのだ。
そうした中で、今回取り上げたいのは、2010年代に入ってから、ネット等で頻繁に語られるようになった『天才バカボン』の世界観が仏教思想に由来しているという巷説である。
確かに、『天才バカボン』には、バカボンのパパが誕生した頃に焦点を当てたエピソード「わしの生まれたはじめなのだ」(「週刊少年マガジン」72年1号)で、元々は超天才児だったパパが、生まれてからいきなり二足歩行で歩き出し、その第一声が釈迦が誕生時に発したとされる「天上天下唯我独尊」だったりと、仏教思想からのインスパイアを匂わせる箇所もあることにはあるのだが、その後もパパは、賛美歌「もろびとこぞりて」の一節である「主はきませり アーメン」や、ウィリアム・スミス・クラーク博士の金言「ボーイズ ビ アンビシャス」と発語を続けており、あくまで、パパの天才性をアピールするギャグとして、赤ん坊が知る由もない、しかし、大人であるなら誰もが知っているであろうフレーズを口にしたに過ぎないのだ。
しかし、この時のパパによる第一声「天上天下唯我独尊」という言葉のインパクトだけが独り歩きしてしまい、連載第一回目の扉ページの煽り文にあった「天才的なバカなボンボン」、もしくは、生前赤塚が幾度となく語っていたフランス語で放浪者を表すヴァガボンドをイメージして付けられた『天才バカボン』本来のタイトルから甚だしく背理した解釈が、広く世間一般の間でなされてしまった。
その結果、『バカボン』は、釈迦への尊称であり、梵語(サンスクリット語)で、世尊、有徳、賢人を意味する「バキャボン」、則ち「婆伽梵」(「薄伽梵」)を意味するものとして捉えられたのが真相で、バカボンのパパのモデルは釈迦であるといった誤認識が、この十年余り、ネット上を中心に一気に浸透するまでに至ったのだ。
実際、バカボンのパパのモデルは、釈迦などではなく、赤塚不二夫の実父である赤塚藤七その人であり、赤塚自身、その事に関し、エッセイやインタビュー等において、幾度となく語っている。
では、この『バカボン』仏教由来説は、いつ何処で発生したのか……?
無論、諸説あるだろうが、筆者に関しては、1996年、漫画家の古屋兎丸が、江口寿史責任編集によるイースト・プレス刊行のコミック誌「COМIC CUE」(Vol2)に寄稿した『Death Comi』という読み切り短編が、『バカボン』仏教由来説の原典であると踏んでいる。
「梵梵婆伽梵婆伽梵梵」(ボンボンバカボンバカボンボンボン)と題された僅か1ページ4コマの作品で、このタイトルは、アニメ「天才バカボン」の第一シリーズで、アイドル・フォーが歌うオープニング主題歌(作詞/東京ムービー企画部・作曲/渡辺岳夫・編曲/松山祐士)のサビの部分から採られている。
そして、古くはマウリッツ・エッシャーの騙し絵、近年にあっては、1960年代後半に頻出したサイケデリック・アートと軌を一にした芸術性豊かなタッチで、バカボンのママ、ハジメ、バカボン、バカボンのパパが登場し、いずれのキャラクターも、妙蓮華教の世界観を不可避的に想起させるタッチで描かれているのだ。
文字にすると、今一つイメージし難いため、恐縮であるが、例えば、最後のコマに登場するバカボンのパパなどは、大乗仏教より発生した、蓮華座に座る阿弥陀如来像に見立て、描出されているといった按配だ。
加えて、この漫画に、先に述べた生まれたばかりのバカボンのパパが発した第一声「天上天下唯我独尊」のイメージが交わり、更には、パパの決め台詞にして、この作品をシンボライズする流行語にもなった「これでいいのだ」が、あるがまま、ありのままを受け入れるという、仏教本来とも言うべき悟りの境地を表す言葉として、『天才バカボン』仏教由来説が生起するに至ったのではないかというのが、筆者の見解である。
尚、バカボンのパパ、そして、赤塚不二夫の人生観そのものを象徴する「これでいいのだ」は、旧満州で生まれた育った赤塚が、敗戦の際、実の妹を亡くしたりと、幼心に経験した厳酷なる想いをそのままダイレクトに反映させた言葉と言えるだろう。
「これでいいのだ」とは、中国語における「没法子(メイファーズ)」。直訳すると「仕方がない」。それが転じた言葉であるが、決して、諦観に埋没した人生観ではなく、苦しみも悲しみも全てを現実として受け止めた上で、人生をポジティブに生きて行こうという、赤塚の中で幼いなりに構築された独自の人生哲学である。
事実、赤塚は、依然として人気漫画家であった1974年当時、フジオ・プロの経理担当から億単位の金を横領された時も、晩年アルコール依存症や食道癌で身体が蝕まれた時も、「これでいいのだ!!」と言わんばかりに、己と向き合っていたという。
さて、話が横道に逸れてしまったが、古屋兎丸の「梵梵婆伽梵婆伽梵梵」が発表される以前、『バカボン』仏教由来説など、赤塚本人の口からは勿論、メディアにおいても全く語られていなかったこと。更に、側近であったフジオ・プロスタッフや『バカボン』担当だった元「週刊少年マガジン」の五十嵐隆夫記者を含め、そのような証言が一切なかったことが、その根拠として挙げられる。
そうした諸事情からも、赤塚不二夫ディレッタントである筆者が、古屋兎丸によるこの作品こそが『天才バカボン』仏教由来説の原点であるという結論に辿り着いた次第である。
但し、赤塚が逝去して間もない2008年8月26日付けの「毎日新聞」の名物コラム「記者の目」に掲載された「赤塚先生は薄伽梵だった」では、同記事を担当したジャーナリストの荻尾信也が、かつて赤塚と仕事をした際、赤塚からこんな言葉を聞いたとして、備忘録風に記している。
「仏の言葉にバカボンという言葉があるんだよ」「サンスクリット語の「薄伽梵」で薄伽が徳、梵が成就の意味」であり、「煩悩を超えた徳のある存在なのだ」と……。
「サンデー毎日」の元記者で、『赤塚不二夫の読む漫画「これでいいのか」 大変なのだ。ワシは死んでしまったのだ。』(1月16日号〜7月30日号)を担当し、赤塚ともざっくばらんな間柄だった萩尾記者は、「それで、バカボンと命名を?」と訊ねるも、赤塚は何も答えず、ただバカボンのパパと同じ顔をしてソッポを向いていたそうだが、赤塚から明確なアンサーを得られなかったにしても、赤塚もまた、仏教の世界に「薄迦梵」という言葉が存在していること、またその意味について把握していたというエピソードは、後に判明してはいる。
余談だが、「梵梵婆伽梵婆伽梵梵」の掲載誌となった「COMIC CUE」(Vol’2)は、この時、カヴァー特集号と銘打ち、若手、中堅どころの人気漫画家が、かつての名作漫画を独自の解釈でカヴァーするといった企画から、赤塚マンガでは、泉昌之が『おそ松くん』を、朝倉世界一が『天才バカボン』をそれぞれ執筆している。
『天才バカボン』仏教由来説が、広く世間に流布した理由として、2011年1月3日、日本テレビ系列で放映された「たけしの教科書に載らない日本人の謎! 仏教と怨霊と天皇… なぜホトケ様を拝むのか」という特別番組で、『バカボン』が取り上げられた影響が大きかったのではないかと思われる。
筆者は、当番組をオンタイムで一度視聴しただけなので、うろ覚えになってしまうが、とある仏教学者がゲスト出演し、『天才バカボン』仏教由来説を補強する材料として、幕間的に登場するレレレのおじさんが、釈迦の弟子にして十六羅漢の一人、周利槃特をモデルにしているという異説を唱えたのだ。
周利槃特は、あらゆる面において、同じく仏弟子として聡明な資質を持つ兄・摩訶槃特とは真逆で、愚鈍極まりない弟子でありながらも、釈迦より一本の箒を渡され、「塵を払い、垢を除かん」という言葉を授けられたという。
愚者の極みたる周利槃特は、我を忘れて掃除に没頭することで、塵は己の心の汚れ、垢は自分自身への執着を意味するということを悟り、遂には、原始仏教、部派仏教において、修行僧が到達し得る最高位と言うべき四向四果の境地に達したとされる人物だ。
釈迦は、ある時、己の愚かさを嘆く周利槃特に「己が愚か者であることに気付いている者こそ、真に智慧を有した者であり、自身の愚かさに気付かず、自らを賢い者であると、信じて疑わない者こそが、真の愚か者なのだ」と諭したという。
「自分が最低だと思っていれば、いいのよ。一番劣ると思っていれば、いいの。そしたらね、みんなの言っていることがちゃんと頭に入ってくる。」とは、生前、赤塚が発した言葉であり、釈迦が周利槃特に伝えた名言と同一の意味を成していると、多くの人が感じ取っているであろうことは想像に難くない。
つまり、こうした赤塚発による名言ですら、『天才バカボン』仏教由来説を根付かせて余りある後付けとして利用されていると、遺憾千万の想いに駆られるのは、筆者だけだろうか……?
古い漫画ファンにとっては、先刻承知の通りだが、レレレのおじさんは、かつて赤塚が大ファンだったと語るナンセンス漫画の開祖・杉浦茂をオマージュしたキャラクターだ。
赤塚が押しも押されぬ超売れっ子漫画家となった1960年代、世代交代は世の常とはいえ、かつての流行作家・杉浦茂が活躍する土壌は、いつしか奪われてしまっていた。
そうした現状を残念に感じた赤塚は、せめて自作だけでも、杉浦キャラを復活させたいという想いから、『天才バカボン』に、レレレのおじさんなるキャラクターを登場させたに過ぎないのだ。
こうした事実からも、レレレのおじさん=周利槃特がモデルという異説は、単なる後付けに過ぎないことは、安易に理解出来よう。
実際、前述の「たけしの教科書に載らない日本人の謎!!」において、件の仏教学者も、あくまでエンタメの範囲内での仮説に過ぎないと語っており、電話取材を受けたフジオ・プロスタッフも、「公式にそういった(名和註・『天才バカボン』仏教由来説)設定はなく、生前、赤塚がそういった考えに基づき、タイトルを考えたり、キャラクターを作ったという事実はない」といった旨の見解をこの時示している。
因みに、レレレのおじさん=周利槃特モデル説に対し、番組MCを務めたビートたけしは、「そう考えると、『バカボン』も凄く深い作品に感じるな」と感心しきりな所感を述べていたが、これはあくまでこの仮説に基づいた場合を語っているに過ぎず、番組の趣旨としても、レレレのおじさん=周利槃特モデル説を頑なに主張していたわけではなかったのだ。
さて、レレレのおじさん=周利槃特モデル説に続く後付けとして、ハジメちゃんのモデルが、東京大学名誉教授にして、インド哲学の権威であり、勲一等瑞宝章、文化勲章、紫綬褒章を受章した比較思想学者の中村元(はじめ)であるという異説が、近年流布されるに至ったが、ハジメのモデルは、『天才バカボン』の連載が開始された1967年当時、弱冠5歳にして、四カ国語を操り、微分積分をスラスラ解く、IQ210を越える人類史上最高の天才児として、センセーションを巻き起こしていた大韓民国の金雄鎔(キム・ウンヨン)その人である。
こちらの金雄鎔少年、生後三カ月にして言葉を発し、七カ月にしてチェスを嗜むようになったというくらいの天才児ぶりだけに、センセーショナルな話材を痛烈な笑いへと染め上げてゆく赤塚の食指が動いたのも、さもありなんといったところであろう。
さて、ハジメちゃん=中村元モデル説の原点についてであるが、インド文化研究家・伊藤武による大著『図解ヨーガ大全』(佼成出版社、11年)にて、ハジメの名は、中村元に肖って名付けられたと書かれており、これが元となり、ハジメちゃん=中村元モデル説が広く喧伝されるようになったと見ていいだろう。
『図解ヨーガ大全』には、中村元と赤塚不二夫には交友があったとの記述があり、この二人は、仏教学において師弟関係にあったとの所見もネット上にて散見される。
しかしながら、そのような事実は、少なくとも、赤塚本人からは語られておらず、赤塚不二夫ディレッタントを自認する筆者でさえ、その幅広い交友録において、中村元の名前を確認するまでには至っていない。
また、赤塚にとって師匠格である手塚治虫が、後に『ブッダ』を描いたように、仏教に傾倒していた関係から、赤塚が仏教について、手塚から薫陶を受けたとの説もあるが、これなども全くもって根拠のない話であると、言わざるを得ない。
事実、何処にもそうしたソースが存在しないのだ。
さて、本稿では、『天才バカボン』仏教由来説の誤謬について、事細かにメスを入れて来たが、近年、仏教由来説以外にも、『バカボン』というネーミングの由来が、人間爆弾「桜花」をそのルーツにしているとの説が、ネット上を中心にチラホラ囁かれている。
人間爆弾「桜花」とは、太平洋戦争末期、日本海軍が開発した脱出装置のない特殊滑空機で、駆逐艦目掛けて特攻するなど、実戦にて投入されたことで知られている。
事実上、大型の徹甲爆弾に翼と操縦席、固体ロケットエンジンを搭載しただけの生還不能な特攻機であったため、米軍側は「桜花」に対し、「BakaBomb」(馬鹿爆弾)、則ち「バカボン」なるコードネームで呼んでいたとされるが、赤塚不二夫もまた、戦争への強い反対とその著しいまでの人命軽視ぶりに向けた憎悪から、アイロニーを込めて、タイトルに「バカボン」を入れたというのが、『天才バカボン』「桜花」由来説の概要である。
赤塚不二夫は、幼少期の過酷な体験から、戦争に対し、強い憤りを抱くようになったことは確かだし、護憲派としても知られる赤塚は、法学者の永井憲一を迎えて、『「日本国憲法」なのだ!!』(草土文化、83年)なる共著を上梓している。
また、アメリカ側の軍事的介入により、ベトナム戦争が泥沼の様相を呈していた時代、『天才バカボン』(「週刊少年マガジン」68年14号)のカラー扉では、パパと一緒に戦車に乗り込んだバカボンが「大砲をバカバカボンボン撃たずにバカボン読もう!」と、バカボンらしい反戦への想いを愚直ながらも訴えている。
しかしながら、『天才バカボン』が戦争反対のアイロニーから生まれたというのは、全くの見当違いで、赤塚は、超絶的なバカを主役に据え、徹底的なナンセンスを本領とする、未だかつてないギャグ漫画をただただあの時代、世に問いたかっただけなのだ。
赤塚不二夫に関しては、こうした誤情報が次から次へと刺客のごとき現れ、今では、筆者とのイタチごっこの様相を呈するまでになった。
これから先もどんな誤情報が生まれ、また流布されてゆくのかはわからない。
しかし、赤塚不二夫とその作品を文化遺産として遺したいと願う三人といない砦の一人として、あまりにも悪質な、または荒唐無稽も度が過ぎる誤情報に関しては、これからも逐一斧正して行きたい。










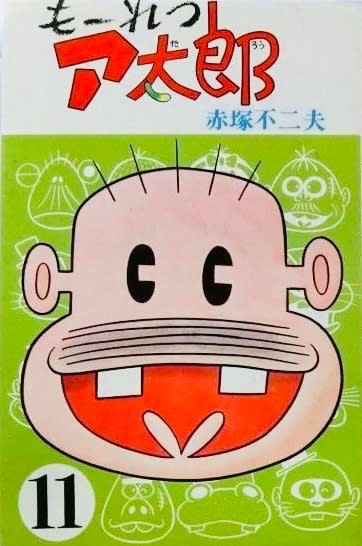
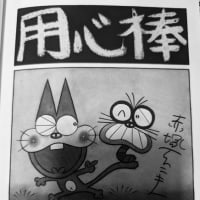
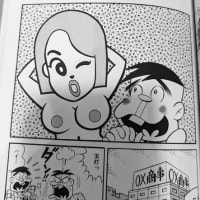
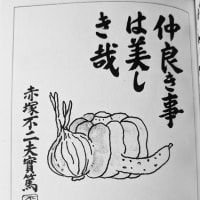
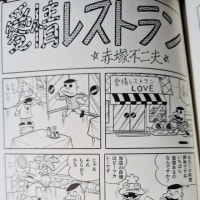

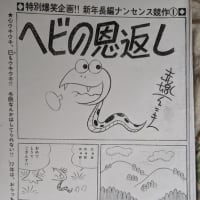
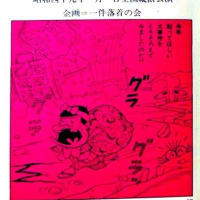



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます