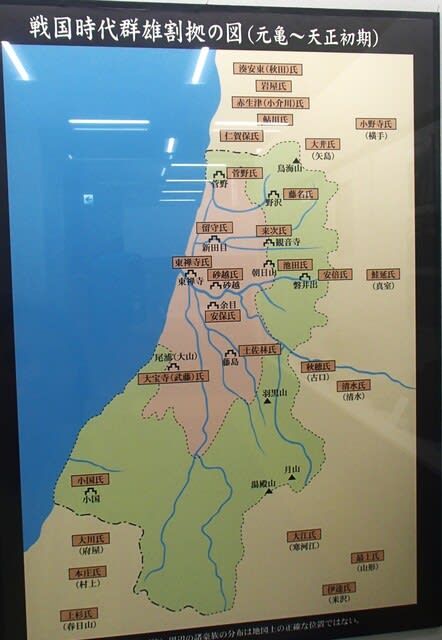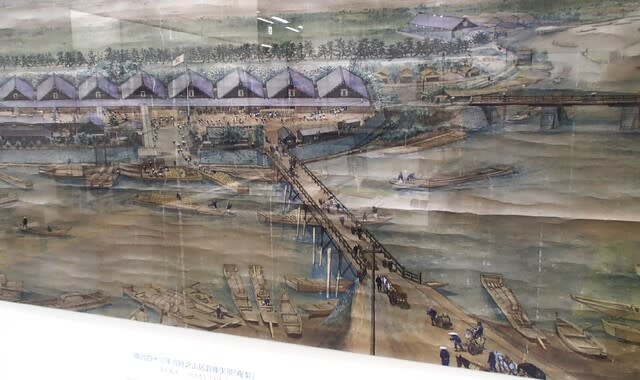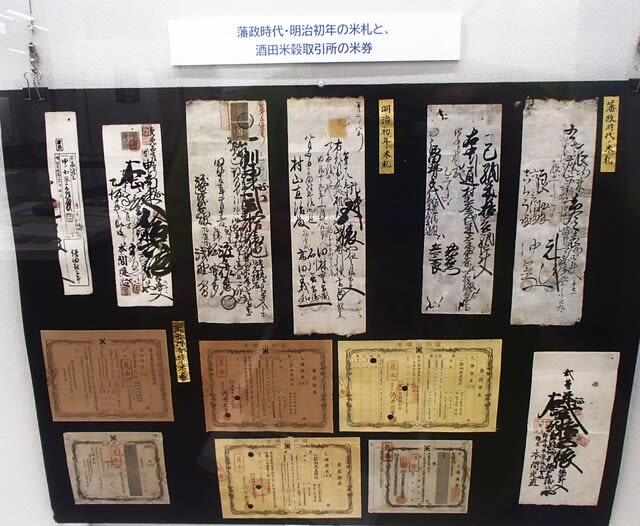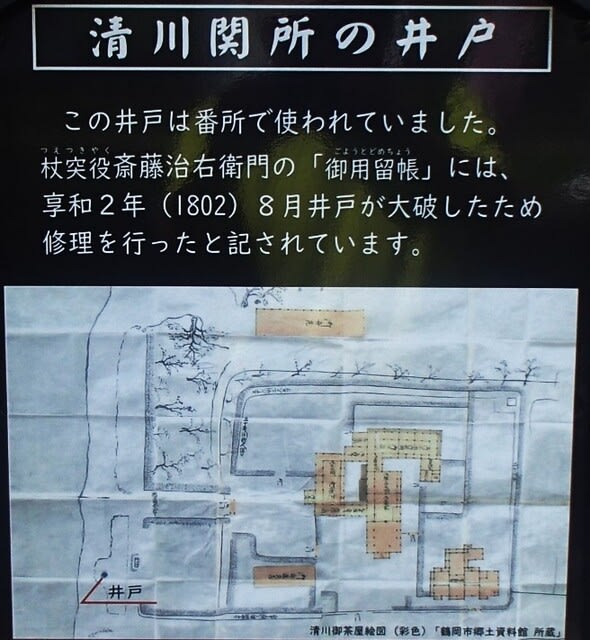国史跡・城輪柵跡(出羽国府推定地)。山形県酒田市城輪嘉平田。
2024年9月10日(火)。
松山城大手門を見学後、北西方向へ進んで、13時ごろ城輪柵跡に着いた。
城輪柵(きのわのさく)は、北東に秀峰鳥海山を背負う庄内平野北半部のほぼ中央東寄りの荒瀬川扇状地に位置する古代城柵で、奈良時代末期に造営された平安時代の出羽国国府と推定されている。
山形県の庄内平野を南北に二分して最上川が流れている。北側の平野部では、出羽丘陵から流出した日向川と荒瀬川が合流し、その合流点附近は、両川の旧氾濫原が形成する微高地が西に向かって張り出している。この微高地は山麓から西に3キロほど張り出しており、この微高地上に大規模な古代の遺跡が集中している。
まずその西端には史跡城輪柵跡が所在する。この遺跡は昭和6年に発見され、方約720mを柵木で囲む遺跡として著名であるが、最近の中心部の調査により整然たる礎石建物等の配置が判明し、平安時代の出羽国庁ではないかとする説も提出されるに至っている。
この城輪柵跡の真東約3kmの丘陵端上には、八森遺跡と呼ばれている官衙風の配置をもつ礎石建物等からなる平安時代の遺跡がみられる。この両者のほぼ中間、城輪柵跡からは東約1kmの位置に堂の前遺跡がある。


総面積52万㎡の城輪柵跡には、一辺約720mの築地塀で区切られた正方形の外郭が設けられ、各四隅には2×3間の小さな櫓状遺構を配していた。内郭の中央には一辺約115mの柱塀や築地塀(ついじべい)で囲まれた政庁が設けられ、政庁正殿や後殿、東西両脇殿等の主要殿舎群が「コ」の字形に配置された。内郭の東西南北各築地の中央には八脚門を構えていた。
外郭の各辺中央にある門からは、政庁中心に向かって幅9mの大路が伸び、政庁の配置もこれにあわせた律令制官衙様式(正殿・後殿東西脇殿や後殿に付属する東西脇殿)となっていた。

遺跡の中心部は自然堤防を核として整地され、周辺より1m程高い。
政庁遺構は、その建築様式において大きく4期に分けられ、前半2期においては掘立柱建物、後半2期では礎石建物へと変わる。また、4期では板塀から築地塀へと変化が見られる。
城輪柵の性格は、江戸時代後期の『出羽風土略記』以来、律令官人の居城、柵戸の遺跡、国分寺、出羽柵、国府などの諸説が論じられてきた。
1931年、発掘調査により、25cm角の角材が密接して並ぶ遺構が検出され一辺約720mの方形を成して、外郭には門や櫓が存在していたことが判明した。1964年の調査では、遺跡中心部の「オ(大)畑」とよばれる、周辺水田よりも1mほど高い台地部分から掘立柱建物跡と礎石建物跡、二つの異なる時代の遺構が検出された。1965年の発掘調査で、正殿、西脇殿、南門など主要な遺構配置が判明した。
遺構のうち、政庁南門、東門および築地塀の一部が復元され、歴史公園となっている。

政庁東門。左奥に政庁南門。

政庁南門。

西方向。

政庁東門。


政庁南門。



政庁南門から政庁東門・鳥海山方向。


国史跡・堂の前遺跡。酒田市法連寺字堂の前。
水田の地帯の狭い車道脇に案内板のみがある。平安時代の出羽国分寺跡と推定されている。
堂の前遺跡は、酒田駅の北東約8kmの荒瀬川左岸、標高約15mの水田中にある。酒田市城輪柵跡の東1.5kmにあたる。遺跡は東西240m、南北265mの溝により四辺が囲まれ、南辺中央に門が検出されている。その内部からは堀立柱建物・礎石建物・井戸・矢板列・溝・土壙等の遺構群が発見された。堀立柱は直径30~50cmの巨大な丸柱で、大形の建物が存在したことを証明するものである。中門の八脚門跡も出土している。遺跡中央部からは筏地形(いかだちぎょう)による建物の基壇が検出された。出土品は須恵器・土師器・赤焼土器・陶磁器等の他、呪術用の木簡等がある。また、革帯用の石帯、鉄滓(てつくず)やフイゴの羽口もある。
堂の前遺跡は、昭和30年、大量の建築材等が発見され著名となった。この材の内には柱材や長押、斗等のほか多数の土器等が含まれており、つづいて昭和48年以降の調査の結果、かつて発見されていた古建築材は、低地帯における建物基壇の基礎工事としての筏風地業であることが判明した。材木層の上に積土層とバラス層を配し、周辺を13m×13.5mの規模で掘立柱列がめぐっている。
この建物の北から西をめぐって南へながれる溝がみられる。基壇建物の西には、4間×2間の南北棟建物2棟がほぼ同位置に営まれている。建物は柱間寸法がそれぞれ15尺、柱径も1尺8寸と非常に大規模であり、柱根自体も3本が遺存している。同位置の別の建物は柱間が14尺程で柱根2列が遺存している。基壇建物の北にも同じく柱間寸法15尺の建物の西妻とみられる柱穴が3個あり、この地域に巨大な掘立柱の建物群があったことをうかがわせる。
これらの建物を囲むように北と東には溝及び埋込みの板の基部が認められ、これに平行する溝もみられる。建物間には溝の他各所に土壙が多く認められる。以上の遺溝のうち基壇建物とその周囲の溝などは平安時代末期以降に属するものとみられ、掘立柱建物は10世紀頃に属するものであることが出土品等より判明している。
酒田市文化資料館光丘文庫の展示より





鳥海山大物忌神社蕨岡口ノ宮。二の鳥居・随身門。山形県遊佐町上蕨岡字松ヶ岡。
随神門。登録有形文化財。江戸時代後期(1751-1829年)。
西面する3間1戸八脚門で、切妻造鉄板葺とする。両脇前寄り1間に床を張り、金剛柵をたてる。円柱で、柱上出組とし、中備に蟇股を入れる。軒は二軒繁垂木。妻は二重虹梁大瓶束とし、前方へ持ち出す。伝統的な手法で手固くまとめられた端正な八脚門である。


鳥海山大物忌神社(おおものいみじんじゃ)の御祭神は大物忌大神で、創祀は欽明天皇25年(564)と伝えられている。貞観四年(862)官社に列し、延喜式神名帳には名神大社として、吹浦鎮座の月山神社と共に収載されている。後に出羽国一之宮となり、朝野の崇敬を集めて、八幡太郎義家の戦勝祈願、北畠顕信の土地寄進、鎌倉幕府や庄内藩主の社殿の造修など時々の武将にも篤く崇敬されてきた。
中世、神仏混淆以来、鳥海山大権現として社僧が奉仕したが、明治3年(1870)神仏分離に際し旧に復して大物忌神社となり、明治4年吹浦口ノ宮が国幣中社に列したが、同13年に山頂本社を国幣中社に改め、同14年に吹浦・蕨岡の社殿を口ノ宮と称えて、隔年の官祭執行の制を定めた。
昭和30年に三社を総称して現社号となった。平成二十年には、山頂本殿から口ノ宮にいたる広範な境内が、国の史跡に指定された。



本殿。登録有形文化財。明治27年(1896)建築、1953年移築。
木造平屋建、銅板葺、建築面積263㎡。桁行3間、梁間6間で、切妻造銅板葺とし、1間向拝を付ける。正面が実長で13.8mに及ぶ大型の社殿で、内部は外陣と内陣に分かれ、さらに内々陣を造る。絵様や装飾的要素は少ないが、木割が大きく、直線的意匠でまとめた、壮大な社殿である。
このあと、酒田市街地にある酒田市文化資料館光丘文庫へ向かった。