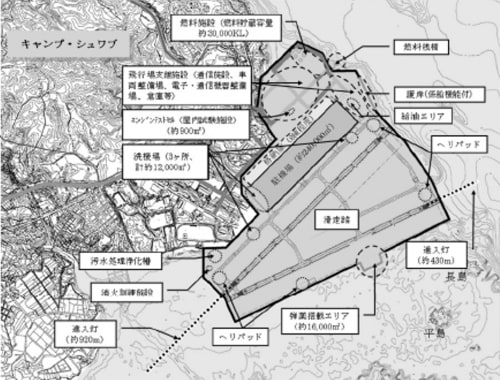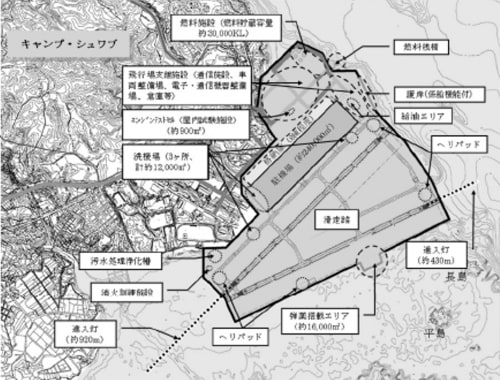 【情報】沖縄と地位協定について考える~日本の戦後が終わらない~:大久保厚④
【情報】沖縄と地位協定について考える~日本の戦後が終わらない~:大久保厚④
①は→
こちら ②は→
こちら ③は→
こちら
5)地位協定に関する問題点について
【空域問題】~前記「関連法令の範囲内」問題を参照。
【排他的管理権】~前記【1951 年 1 月ダレス第 4 次草案】③参照
【第一次裁判権放棄について】
①日本側の裁判権放棄について
行政協定案:「米国は米国安全保障軍が利用する日本国内のすべての施設・区域・区域に対して、排他的管理権を有し、かかる施設・区域内にある米国政府の人・軍属・その家族に対して、また日本人を除く前記施設・区域内にある全ての他者に対して排他的管理権を有する。日本当局は、前記の区域外において罪を犯した米国の軍人・軍属・その家族を米国に引き渡すものとする。
②行政協定(第 17 条 3 項 a)
「日本の当局は、米軍基地の外での犯罪については、米軍関係者を逮捕ることができる。但し、逮捕したあとはすぐにその身柄を米軍に引き渡さなければならない。」
③裁判権放棄(53 年10月28日)と身柄引渡(53 年10月22日)の密約
「日本側は著しく重要な事件以外は裁判権を行使しない。」→(1957 年までに第一次裁判権を有する約 13000 件のうち 97%を放棄)
「米軍関係者による犯罪が公務中に行われたどうかわからないときは、容疑者の身柄を米軍に引き渡す」→2011 年発生の米軍関係者による「一般刑法犯」の起訴率は、13%(沖縄 22%)であり、全国平均 42%に比べ大幅に低い。
④「公務」の定義「56 年3月合意」
「行政協定(第17条3項 a)ii にいう「公務」とは合衆国軍隊の構成員又は軍属がその認められた宿舎又は住居から直接に勤務の場所に至り、また勤務の場所から直接その認められた宿舎又は住居に至る往復の行為を含むものと解釈される。但し合衆国軍隊の構成員又は軍属がその出席を要求されている公の催事における場合を除き、飲酒した時は、その往復の行為は、公務たる性格を失うものとする。
【防衛負担金(558 億円)廃止後の負担分担】
⑤「日本国は、第2条、第3条に定める全ての施設・区域並びに路線権(飛行場及び港における施設・区域のように共同で利用される施設・区域を含む)をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ相当の場合には施設・区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行うことが合意される。」→上記以外は、すべて米国もちであることが明記された。
【沖縄返還時の「その他費用」の負担】
⑥「日本政府は、この取り決めにおいて、とくに定めがない限り、返還された日から 5 年以内に基地の移転費用及び返還に伴って米政府の予算支出を必要とするすべての項目について、合意された物品と役務によって 2 億ドル相当を提供する義務を負う。」→最終的な金額は、修理、保守、修繕、改造、拡張、増築、修正及び米国が許可した施設の新築費用として 6450 万ドルを要求、これを地位協定第24条の解釈の幅を持たせることで支出するよう求めた。
【インフレ及び円高による米軍基地日本人労務費用分担】
⑦「77 年12月、日本側は、法定・任意福利費及び労務管理費の負担、及び賃上げ分の負担(62億円)で合意した。総額 1000 億円の在日米軍基地従業員労務費の 6%に相当した。
⑧「78 年12月、10%の格差給、語学手当、国家公務員水準を上回る退職手当、格差給と語学手当の他の諸手当の参入分を負担する(140 億円)ことで合意した。
【地位協定24条に対する特別措置協定】
⑨その後も日本側の分担額は、80 年:147 億円、81 年:159 億円、82年:164 億円、83 年:169 億円、84 年:180 億円、85 年:193 億円、86 年:191 億円と増加の一途を辿った。そして 87 年1月、米軍基地で働く日本従業員に対する調整手当・扶養手当・通勤手当・住宅手当・夏季手当・年末手当・年度末手当・退職手当の支払いに要する経費の一部を̶̶その二分の一に相当する金額を限度として̶̶負担する特別協定が締結された。
⑩91 年には「新たな特別の措置」協定が結ばれた。その第1条には、以下の全部又は一部を日本側が負担するというものである。
a)基本給、日雇い従業員の日給、特別期間従業員の給与、時給制臨時従業員、劇場従業員の給与
b)調整手当・解雇手当・扶養手当・遠隔地手当・特殊作業手当・夏季手当・年末手当・寒冷地手当・退職手当・人員整理退職手当・人員整理按分手当・通勤手当・転換手当・職位転換手当・年度末手当・夜間勤務手当・住居手当・単身赴任手当・時間調整手当・時間外勤務手当・時給制臨時従業員の割増給、祝日給、夜勤給、休業手当及び時給制臨時従業員の業務上の傷病に対して認められる日給
c)船員の有給休暇末付与手当、危険貨物手当、機関部手当、機関作業手当、消火手当、外国船手当、外国航路手当、出勤手当、小型船手当、油送船手当、引き船手当及び船長・機関長手当。また第2条では、「公益事業によって使用される電気・ガス・水道・下水道、前記を除く「暖房用、調理用、又は給湯用の燃料」に関わる代金または代金の支払いに要する経費の全部と一部を負担することが規定された。
⑫2015 年までに労務費2兆 8663 億円、水道光熱費 6153 億円が予算化された。また 2016 年度から 2020 年までを有効期間として、平均で1893 億円を負担する特別協定が合意された。
【日米合同委員会~密約製造マシン】
⑬ダレスの安保協定案には、日本が 50 年7月にマッカーサーの命令で設けた警察予備隊とは別に軍事組織を創設し、それらの軍事力が有事には米国人司令官による「統合的指揮下」に入るという「集団的防衛措置」があり、日本側は反発した。
⑭日本政府は、条文の削除を要請したが、それは秘密にしてほしいという要請であった。それまで主として、基地の設定、米軍の特権などの関わる準則の設定を想定したが、委員会は、再軍備や「安全保障」計画の策定という日米安保条約に関わるすべての業務へと役割が拡張、機密化することとなった。
⑮55 年の合同委員会の論議は。a)空軍基地 滑走路拡張b)演習場その他の基地をめぐる紛争c)米軍の法的地位と特権d)米軍に雇用される日本人労働者の問題などであった。
⑯c)「米軍の法的地位と特権では、53 年 10 月~55 年 3 月までの米軍人の国内犯罪総数は、9416 件でその内の起訴率 215 件(2.28%)に過ぎない。
⑰d)「米軍に雇用される日本人労働者の問題」では、「保安解雇」の討議はかなりの数に及んだ。つまり労組活動を重大な脅威として、解雇することを指した。そのなかに労組委員長に決定後にその仕事上の能力を理由で懲戒解雇した三沢駐屯軍事件がある。また「第六あけぼの丸」も討議されていた。
⑱合同委員会に提出された 1972 年沖縄返還時に作成された 5・15 メモは、1997 年になって漸く公開された。政府の拒否理由は、a)非公開が前提の討議であり、忌憚のない協議と意見交換が可能である。b)基地をめぐる諸問題には、日米間の国家全体、日本の国内諸勢力、それに基地が所在する地域社会といったさまざまなアクターの利害が複雑に絡みあっており、公表を前提とした協議では、その調整が難しい。
6)地位協定をめぐって~日本の戦後が終わらない~
沖縄は、占領下のもとで統治権を自らの手によって獲得し、日本政府の主権回復を 72 年自らの自決権を獲得すべく本土復帰を果たした。日本は、52 年に「独立」したというが、その主権は占領時代の米軍の駐留支配を安保条約と行政協定に置き換えたに過ぎない。その統治構造に対する闘争は、1957 年の「日本本土の地上部隊の撤退」の到達点のうえに 60 年安保改定阻止闘争をピークに達した。その後の日本の統治に関する闘争は、64 年以降のベトナム反戦運動と 70 年安保、72 年沖縄返還以降、日本本土では基地を抱える地域を除けば、大きな運動となることはない時代を過ごしてきた。
地位協定は、52 年「独立」の負の象徴である。民主憲法の体系どころか、政府が自ら指揮・管理できない米軍に自らの安全保障を委ねるという世界に類を見ない奇形な「統治」形態を 65 年以上続けており、地位協定はその象徴に他ならない。
地位協定27条は「両国はいつでもいなかる条文の改定を要請できる」とする条文をもつ。しかし、この協定は一度も改定された過去をもっていない。それどころか、自衛隊予算の着実な増加という流れになかにあっても、24条の基地費用負担条項を拡大解釈し、77 年以降二度にわたる「特別(措置)協定」を結び、「思いやり」を遙かに超える負担肩代わりのみが貫かれる構造下にある。
さらに日米合同委員会は、極めて高度な秘密組織であり、対米密約の製造機に他ならない。ここにも、日本はその歪な統治構造を内包する国家であることを晒してきた。
2018 年 7 月 27 日、全国知事会は、日米地位協定改定の提言をまとめ発表した。変えても変えなくとも役割の変わらないという改憲などをしている暇はないはずである。
地位協定は、まさに戦後歴代政権の「レジューム」そのものであり、戦後占領政策をそのまま継承する隷属性の強い「レジューム」:「地位協定」の改定からまず着手すべきである。
日本の戦後は 99 年経っても(永久に)終わらない。
[参考文献]
『沖縄戦後民衆史』:岩波現代全書(森宣雄)
『日米地位協定その歴史と現在』:みすず書店(明田川融)
『沖縄と海兵隊』:旬報社:野添文彬・山本章子他