8月10日(土)午後2時から奈良県立図書情報館一階交流ホールで開催の朗読劇(構成・演出…小野小町 出演…言の葉の羽)のお知らせです。
この朗読劇は「列車にのった阿修羅さん」という児童文学(作…いどきえり 絵…マスダケイコ)を一時間に構成して朗読するものです。
この企画は、絵本作家、イラストレーターである、地元奈良出身のマスダケイコさんの、絵本原画展(8/6~18)の関連イベントとして開催されます。
マスダさんとの出会いは、一昨年の奈良町にぎわいの家の全館展示、まるごと美術館企画(キュレーター・浅山美由紀)の参加作家として出会いました。このブログでも紹介しています。ユーモアがあり、ノスタルジックで温かい…絵画作品とオリジナル絵本から、作品を知りました。
そのマスダさんが、児童文学作家のいどきえりさんのお話に絵をつけた「列車にのった阿修羅さん」。タイトルからして、「え?」と思われる方も多いでしょう。ぜひ、本を読んでいただきたいのですが、戦争のために、阿修羅像をはじめとする国宝が、寺を離れ列車で疎開をしたお話で、実話をもとにして書かれています。
戦争末期、大事な仏像が疎開したということは、なんとなく耳にしたことはありましたが、この本は丁寧に取材されていて、当時の様子がとてもよくわかり、「へえ、そんなこともあったのか。」と初めて知ることも多かったです。
子どもの眼を通して描かれる、戦前と戦後の180度変わった世の中への葛藤、怒り、疑問。阿修羅さんと向き合いながら、激動の時代を成長していった主人公。実は、この主人公のモデルとなった方と、私は以前出会っていて、当時、とてもよくしていただいた方とわかった時は、こういうこともあるのだなと、ただただ、びっくりしました。
そんなこともあり、この朗読劇は特別なものになりました。
本来、この本を全て読むと、1時間45分程度になります。それを1時間に構成しました。脚色等は全くせず、整理してつないでいます。
79回目の終戦記念日の前に、戦争の時代のお話を朗読できることの意味と大切さを、ひしひしと感じつつの稽古です。
なお、朗読劇は無料ですが、事前申し込みが必要ですので、奈良県立図書情報館に問い合わせてください。
さて、マスダケイコさんの絵本原画展は8/6より開催です。まずはこちらを是非、ご覧ください。



この朗読劇は「列車にのった阿修羅さん」という児童文学(作…いどきえり 絵…マスダケイコ)を一時間に構成して朗読するものです。
この企画は、絵本作家、イラストレーターである、地元奈良出身のマスダケイコさんの、絵本原画展(8/6~18)の関連イベントとして開催されます。
マスダさんとの出会いは、一昨年の奈良町にぎわいの家の全館展示、まるごと美術館企画(キュレーター・浅山美由紀)の参加作家として出会いました。このブログでも紹介しています。ユーモアがあり、ノスタルジックで温かい…絵画作品とオリジナル絵本から、作品を知りました。
そのマスダさんが、児童文学作家のいどきえりさんのお話に絵をつけた「列車にのった阿修羅さん」。タイトルからして、「え?」と思われる方も多いでしょう。ぜひ、本を読んでいただきたいのですが、戦争のために、阿修羅像をはじめとする国宝が、寺を離れ列車で疎開をしたお話で、実話をもとにして書かれています。
戦争末期、大事な仏像が疎開したということは、なんとなく耳にしたことはありましたが、この本は丁寧に取材されていて、当時の様子がとてもよくわかり、「へえ、そんなこともあったのか。」と初めて知ることも多かったです。
子どもの眼を通して描かれる、戦前と戦後の180度変わった世の中への葛藤、怒り、疑問。阿修羅さんと向き合いながら、激動の時代を成長していった主人公。実は、この主人公のモデルとなった方と、私は以前出会っていて、当時、とてもよくしていただいた方とわかった時は、こういうこともあるのだなと、ただただ、びっくりしました。
そんなこともあり、この朗読劇は特別なものになりました。
本来、この本を全て読むと、1時間45分程度になります。それを1時間に構成しました。脚色等は全くせず、整理してつないでいます。
79回目の終戦記念日の前に、戦争の時代のお話を朗読できることの意味と大切さを、ひしひしと感じつつの稽古です。
なお、朗読劇は無料ですが、事前申し込みが必要ですので、奈良県立図書情報館に問い合わせてください。
さて、マスダケイコさんの絵本原画展は8/6より開催です。まずはこちらを是非、ご覧ください。














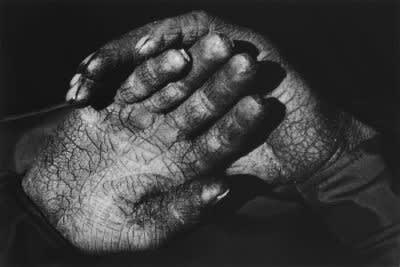




![十六歳 | 作品 || [日本劇作家協会] 戯曲デジタルアーカイブ](https://playwright.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/images/dramas/000568_20231020183558_01.jpg)
