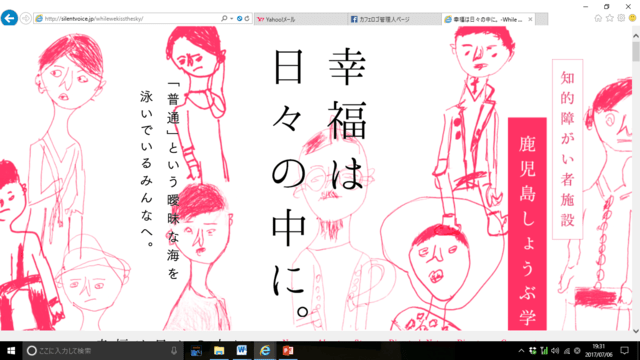鹿児島しょうぶ学園園長・福森伸さんと猪苗代町はじまりの美術館・岡部兼芳さんをゲストに、映画「幸福は日々の中に。」上映後、観客との言論カフェが行われた。
岡部さんには、はじまりの美術館での言論カフェでお世話になったが、恥かしながら福森さんのことを知ったのはこの映画の試写会がはじめてだった。
映画の中の福森さんの強烈な言葉の一つひとつ、そして鮮烈なしょうぶ園のパーカッションバンドotto&orabuの音楽に衝撃を受けた。
その瞬間、とてもこの「障害者」とアート実践の最前線に立つ二人をファシリテートなどできるはずもないことを直感し、その現場を知らないものが知らないものとして臨むしかないことを悟る。
というよりも、もはやこの巨人二人のファシリテートなんて蛇足もいいところだ。
阿部さん、勘弁してくれよ。ファシリテーターを引き受けたことをちょっと後悔した。
というわけで、本番当日。
福森さんの圧倒的な存在感と、それに思いをぶつけようとする岡部さんの真摯な姿勢に気圧される。
予め断っておけば、以下で「障害者」や「障害」という言葉を用いることには違和感以上のものがある。
後々ふれることになるが、「障害者」や「障害」はそもそも存在するのかどうかは、今回問われた大きな論点の一つだ。
その概念を問いにかける以上、さしあたりは括弧つきでこれらの言葉を使用することを確認しておきたい。
福森さんはまず、「障害者」施設における規則の暴力について語るところから始めた。
わずかでも歩けるのに怪我のリスクを懸念して施設利用者の物理的自由を奪うのは、当人にとってどうなのか?
福祉の専門知識はその疑問を論外の思考と排除しようとする。
往々にして、そこでは「障害者」の「幸福」や「自由」が、「健常者」にとってのその基準でもって測られる。
いや、その実、それは何か事をしでかすことへの「恐れ」や「不安」を、「障害者」にとっての「幸福」や「自由」に置き換えながら免責の欲望を働かせているに過ぎない。
そのことを福森さんは、「1%のリスクを回避するために99%の自由を犠牲にすることが果たしていいのか?」と問いかける。
「健常者」の「ふつう」が、生きづらさを抱えている人に不自由を強いる。
介護福祉に携わる参加者の一人は、「なんとか立っていられる」老人を歩かせることは転倒してけがをさせるリスクがあるからと、「椅子に座らせて立たせない」ままにする福祉現場の常識が、利用者とともに職員のストレスの原因になっていることを告げた。
「手で這うこと」を「転んだ」とみなす健常者側の「ふつう」を反転させれば、それは「這ってでも歩く自由」が残されていることでもあるはずだ。
しょうぶ園では週末に利用者が飲みに行ける「居酒屋」が開かれる。
それは福祉の専門家からすれば、「え?そんなことしていいんですか?」という反応を呼ぶ。
だが、福森さんは「俺だって晩酌したいのに、なぜ彼らはダメなのか?」と、逆にその評価を根底から問う。
「健常者」側の「ふつう」でもって規則を作り、彼らの「自由」や「幸福」を測るな。
専門的なリハビリテーションプログラムは、果たしてどちら側の「幸福観」でつくられているのか。
それは本人の「幸福観」に沿っているのか。
もちろん、当事者本人の幸福感そのものは、他者には知りえない。
にもかかわらず、「その人は幸せになるんですか?」と問いかけることによって職員同士が考え、議論し始めることは、どこかその思いが本人に通じていくのではないだろうか。福森さんはそう語る。
それでも介護の現実はどこか転倒している。
なぜ、人は重度の要介護認定評価を得ようとするのか。
もちろん、高い介護サービスを受けるためであろう。
けれど、あえて自分が不自由な状態である不健康を主張し、そのことを公認されることを欲するようなシステムは何かが転倒している。
福森さんは「ふつう」に考えれば「異常なこと」を、システムの側が「ふつう」だといってわざわざ転倒させている事態を問い続ける。
映画の中である職員女性がこんなことをいう場面がある。
私にとってみんな(しょうぶ園利用者)のいるところはどうしてもいけないところ。
私は何色を使うかとか考えてから書いてしまうけれど、彼らが筆を握ってすぐ紙に筆を下すことにあこがれや興味がある。
たぶんわからないんだけれど、近づきたいところがある
行動がすごくおもしろくて興味深い、謎だからそれを知りたい、みんなを見ていると毎日がおもしろい
利用者はなんでも受け入れるから、周りの自由も許してくれるから作業場は楽しい。
福森さんもまた、彼らの「世界」に入りたいけれども入れないという。
otto&orabuの音楽は微妙なリズムや音程のズレを特徴としている。
しかし、その「ズレ」が魅力的に響く。
心に訴えかけてくる感動を覚える。
彼らは「音がずれる」、「音痴」、「奇声を発する」ことが得意だ。
得意?
「ふつう」の基準からすれば欠点や異常と評されるものが、「得意なもの」と反転させることで人々の心を揺さぶる「音楽」になる。
彼らが板に刻む「ひっかき傷」もまた、そこに漆を流し込めば「狙わない美」を生み出す。
この「意図なき技=アート」に福森さんたちは「憧れ」を覚えるのだ。
「ノーマル」な発想を変えると「障害」は消える。
これまで括弧つきで「障害者」や「障害」と記述してきたが、岡部さんはそもそも「障害者はいない」と断言する。
あるとすれば、それは彼らに「理解」や「認知」に困難のあるが、果たしてそれは取り除くべき「壁」なのか。
岡部さんはそう問いながら、「壁を乗り越えようとするときに生じるエネルギー」や「発想力」を強調する。
それに対して福森さんは「修行なき時代」において、逆境をはねのける能力の衰退を指摘する。
いじめが問題になっている昨今、いじめの撲滅は叫ばれるが、いじめに遭遇した時にそれをどうはねのけるかという方法は教えられない。
撲滅する以前に、いじめが厳然と存在する以上、まずはそこを生き抜く仕方を考えなくてはならないはずだ。
しかし、そこが抜け落ちている。
すると、「いじめはなかった」とあることそのものを不問にしようという思考がはたらく。
そのことが見て見ぬふりや、問題の本質的解決に至らない結果を生んでしまう。
それは「障害」も同じではないか?
「壁(バリア)」そのものをなくそうとする思考は、どこか夢想的にすらなる。
福森さんは映画の中で次のように語っている。
社会が居心地が悪いんだったら、社会の中に彼らを出そうというリハビリテーションをやるよりも、居心地のいいところでリハビリしない方が幸福じゃない。
僕はリハビリしなければいけない立場だけれど、彼らをリハビリすると厳しい社会に送り込まなければならなくなるでしょ。
すると難しいわけだね、生き方が。
だからもっと生きやすい社会にしようというけれど、いつになったらって感じなんで。
それより今の時代に生きているんだったら生きやすいところにいていただくという考えの方が、その人を幸福感に満ち溢れて過ごせる時間の方が長いじゃないかというのが僕の考え方
早く外に出して社会復帰して、ノーマライゼーションにのっとってみんなと一緒に暮らすという考え方には簡単に賛成はできないんだよね。
この場面は、映画の中で最もドキッとさせられたところだ。
なぜか?
そこには、いつのまにか「健常者と障害者が共生できる社会」、すなわち「ノーマライゼーション」が望ましいという暗黙の価値観が自分の心に刷り込まれていたからだろう。
そして、その価値観の土台を現場に立つ福森さんの鋭い言葉が動揺を与えるのだ。
「いじめ」がない世界、「戦争」がない世界、「暴力」がない世界、「障害」がない世界。
これらの世界を僕らは理想としている。
しかし、理想としてその世界を目指すことと、現にある暴力状況のさなかをどう「幸福」に生きるかを混同してはいけない。
さもなければ、問題の具体的解決に至らないだけでなく、逆に「やさしい暴力」をふるうことにもなりかねないからだ。
では、この福森さんの言葉を福祉の現場ではたらく人々はどう受け止めるのか。
これについてアールブリュットの美術館を実践する岡部さんも同様の問いを抱きながら、その実践が地域に開かれていくことで健常者/障害者の枠を脱構築する社会の形成を目指していく思いが語られた。
そもそも近代化以前には、その区分なく共生が可能であった。そこへの回帰を課題解決の困難にぶつかりながらも目指していくという岡部さんの思想は、その限られた人生という短い時間の中で個々の「障害者」の幸福を充実させることに重点を置く福森さんと目的を共有しながらも一致しない。
そこが興味深かった。
こうも考えられないだろうか。
「障害者はいない」ということは、むしろ「一人ひとりがなにがしかの障害を抱いているのだ」、と。
8月25日の朝日新聞「折々のことば」には、こんな言葉が紹介された。
知らなかった?お父さんは花粉症だし、お母さんはちくのう症だし、アイちゃんはダウン症。みんな大変なんだよ。
これは小学生の娘に「自分はダウン症なのか?」と聞かれた母親の言葉である。
そこに「障害」の軽重などない。それぞれが抱える「障害」から見える世界が多様にあるという事実だけが示されている。
終盤、岡部さんから今回の言論カフェのテーマが「アールブリュット」であることを指摘された。
えっ!
一瞬、驚いた福森さんと僕の目が合った。
迂闊だった。
岡部さん以外、このテーマを確認していなかったのだ。
このテーマを目的に来場された観客にとっては拍子抜けだっただろう。伏してお詫び申し上げますm(__)m
とはいえ、話題は自ずとアールブリュットをめぐっての議論でもあった。
その一つは、しょうぶ園の利用者たちが皆、「本能」と「五感」で生きていると福森さんが指摘した点である。
岡部さんはアールブリュットを「生のアート」とするが、それはまさにいわゆる左脳的な計算や計画、意図を超えた、ありのままの生である本能から表出される芸術のことである。
発見と訳される「Discover」は「覆いをとる」ということである。
その覆いの下に隠されている「生」を表出させることがアールブリュットの意味であるというのである。
では、その「生」とは何か?
すでにふれたように、彼らは一心不乱に糸を縫い込んだり、板に傷をつけたり、一つのオブジェを作り続ける。
誰かの要望の応えようとか、喜ばせたいとか、評価されたいという「媚」がない。動機がない。
ただただ、その行為自体にのめりこむ欲求それ自体が生み出すもの。
そのようなことが果たして「われわれ」にできるだろうか?
福森さんは、誰からも評価されずただただ孤独にアート制作に取り組みたいというあるアーティストが、「では、果たして誰も存在しない無人島でそれをやり続けることができるだろうか?」と自問した時、「その自信がない」という言葉を紹介しながら、それを成し遂げてしまう「彼ら」の「世界」への憧れを語る。
しかし、そのように語りながらも、福森さんはけっしてアールブリュットを評価したいとは思わないという。
なぜか?
福森さんによれば、アールブリュットの作家の多くは孤独や不幸のうちに作品を制作した人が多く、作品の評価とは別に彼らの生きざまを考えたとき、その一芸術分野として称揚することには賛成できないという。
そもそも、「アールブリュット」という一芸術概念に彼らの作品のすばらしさを包摂させることは、どこか余計な感じがする。
素晴らしい作品は、ただ素晴らしいというだけでいいじゃないか。
今回の映画作品のタイトルは「幸福は日々の中に。」である。
これを各自どう考えただろうか。
ある参加者から福森さん自身は「幸福」をどのように考えているのかという質問が上げられた。
福森さんはしばし考えた後に、「何が思いつくかわからない状態の中で、さまざまな発想ができる状態が幸せ」と応えた。
それは福森さん自身の生きざまを示すような言葉だった。
これが誰かの「幸福」を意味するものではないことは言うまでもない。
自分の「幸福観」で他者の「幸福観」を測ろうとするとき、暴力は発生する。
彼らにとっての「幸福」や「自由」が非社会的であるからといって排除するわけにはいかない。
その「あわい」というか「エッヂ」が立つギリギリのところに立ち続けて、答えのない問いのあいだを生き抜きたい。
そんな「福森伸」というアートに会場は揺さぶられた時間だった。
その人の身体から出る言葉が「生きざま」というアートだとすれば、それはまた岡部さんのアールブリュットにかける熱い語りも同様であった。
お二人の隣でその言葉を間近で聴かせていただけた時間が、何よりボク自身の幸福でもあった。
さて、観客の皆さんにとって「幸福」とはなんであっただろうか。
おっと、この映画に対する個人的な感想を書き忘れるところだった。
観客の多くから「感動した」という声が上がった。
同感だ。
とりわけ、otto&orabu圧倒的な「音」に圧倒され、魅了され、自由を感じ、そしてその姿に「憧れ」を抱いた。
なぜか。
映画の中で福森さんが、彼らをして「仕事場で自分でいられるというのはある意味ですごく贅沢なことかもね」と語る場面がある。
そう、彼らが「自分でいられる」ことに「憧れ」を抱くのだ。
その点からすると、奴隷のように働かされている「ノーマルな人々」の多くは「不自由な世界」を生きているとはいえないか。
どちらが「障害」のある世界なのか。
その観点に立てるならば、福森さんや岡部さんが実践する「障害」をもつ人の能力の全面的な解放とは、ノーマルとされる人々が失った能力の解放のことだという気がしてくる。
「ノーマル」とされる社会で生きるために教育を受ける。
自分の職業(高校教師)に照らせば、そう教育する。
けれど、それで失わせている力は、実は数知れないのではないか。
その「ノーマル」な思考に揺さぶりをかける力を、この映画は確実にもっている。(文・渡部 純)