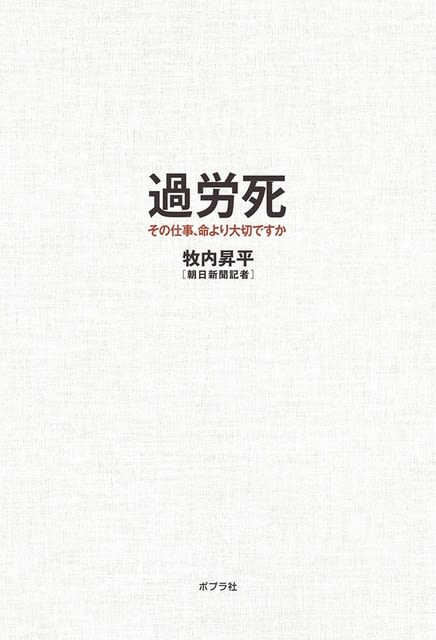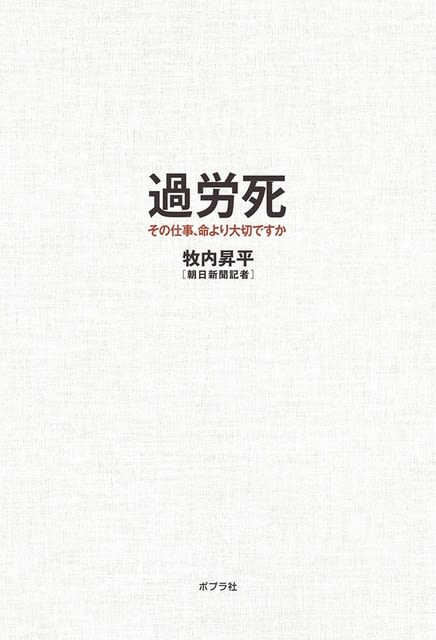
昨日、ペンとノートを会場にゲストに牧内昇平さんを招き、12名の参加者に恵まれて『過労死』を読み、考える会が開催されました。
今回ゲストの牧内昇平さんは朝日新聞記社に記者として15年間勤め、労働問題を中心にパワハラ問題や過労死問題を取材されてきました。本書はそれをまとめたものです。今回、牧内さんの筆致に惹かれた荒川さんのファシリテートで話し合いが進められました。
牧内さんはバリバリの朝日新聞の記者として働いている中で出会った、まーくんの「ぼくの夢」(この会のブログ案内を参照してください)によって過労死が自分ごとになったといいます。過労死の問題を統計的にではない。本書はこのような思いから、被害者・遺族ひとりひとりに向かいながら書かれている本です。それについての感想を述べるところから始められました。
「コラムに「死ぬくらいなら会社を辞めればいい」とあるが、客観的に見ればなぜ辞めることができなかったのかと考えがちだけれど、過労状態になると自分のことがわからなくなる。だから周囲がわかってあげなければいけない」
「過労について自分はそうとうやってきたという自信がある。その経験を踏まえると過労死は時間の問題ではない」
「過労死とは何か。本書の章の並びから受けた印象はあらゆる職業年齢であり、家族構成で過労死が起きていることがわかる。過労は時間ではない複合的な要因で生じている」
「自分は過労というほどではないけれど、いま、職場でストレスを受けている。時間ではなく働く環境の問題。過労という言葉に惑わされすぎではないか」
長時間労働=過労死という固定観念から、必ずしもそうではないという意見は、参加者の体験から語られました。それについて、牧内さんから次のような話がありました。
「1970年後半に医師たちが過労死という言葉を使いはじめ、80年代初めに社会的に使用され始めた。その頃は日本の経済成長が前提とされており、その当時は長時間労働が問題とされ、過労死の被害者は正社員男性30代、40代というパターンだった。けれど、だんだん複合的要因で亡くなる人が増えてきた。それを本書の出版過程で「職場死」という言葉を当てはめるか、ずいぶん迷った。結果、最終的に「過労死」に戻ってしまったのだけれど」
出版の都合上、最終的に「過労死」というタイトルになったというお話でしたが、「職場死」というアイディアには、その現場を取材する過程で従来の「過労死」概念では説明できない実態があったのでしょう。そこには人間関係やその職業、職場独特の文化や価値観が根深く関係しています。それについて学校関係者は次のように語ります。
「学校教員には忙しくする人を是とする文化がある。運動部顧問には土日の休みはほぼない。私的な時間を仕事にもっていかれたくない自分はマイノリティだった。職場では仕事の時間にどれだけ自分の時間を割けるかが問われる。勤め始めの頃は、休日の部活動指導は4時間以上で460円の手当だった。ありえない、と思ったけれど、それに多くの教員たちは「何のために教員になったのか」と口にする。つまり、自分の時間を仕事にどれだけ捧げられるかで一人前の教師になれるという変な文化が学校教員の世界にはある」
「僕の先輩は約10年前、学校現場でくも膜下出血により過労死した。少なくとも僕はそう思っている。過労死が複合的だというのはそのとおりで、当時の彼は教員としての異常な労働時間を呪っていたけれど、同時に自宅では自分の研究にも勤しんでいたし、友人たちと酒を交わす機会も少なくなかった。そうであるがゆえに、ご遺族は「過労死」と訴えることが難しかったのではないか」
「でも、本当は自分の研究時間は確保されてしかるべきだよね。それが過労で削除される国なんて文化社会とは言えない」
「過労死の定義の難しさには本意/不本意という問題があるのではないか。つまり、長時間労働していても楽しくやっている人はいる。本書を読んでいると、不本意ながら労働を強制されている実態が見えるが、仕事をバリバリやりたい結果、長時間労働になっている存在をどう考えるべきだろうか」
「不本意かどうかといわれると、自分は案外楽しんでやっていた。働かされたことはない。自分で働くことを作っていく立場で、自分しかやる人はいないだという思いで働いていた。その意味でいうと、自営業の人たちの過労死にはスポットライトは当てられていない」
「自営業には労災はない。あくまで労使関係において過労死の認定はなされるもの」
「芸術家とか研究職とかがそれに当たるんだろうけれど、それは過労死ではない気がする。自分も過労になって身体を壊したことがある。徹夜は当たり前の仕事だったが、ある朝、社長がやってきて「あんた、仕事が趣味なの?」といわれてハッとし、その会社を辞めた。何とか新しい会社を軌道に乗せようと頑張っていたのに、そんな言葉はないよね」
「自営者の過労死は統計上ない。患者統計と労働者が亡くなった場合の調査のエアポケットになっている」
「組織を活性化させるためには、ある程度時間なんか気にしないで働くことが必要だという面があることも事実」
「本書を読んで3つ思ったことがある。①ケン・ローチの映画に自営業は好きで働いている商売とされ、過労は自己責任に押し付けて利用されていること思い出した。②スーパーで働く自分の息子を見ていると、残業規制は厳しいくせに仕事量が減らない問題がある。③今年から月10万円で午前中だけ働くスタイルになったけれど、最高。ものすごく楽しい」
「波止場の哲学者といわれる港湾労働者エリック・ホッファーは、労働時間を一日6時間と決めていて、それ以上は働く意味はないと決めている。食べるためにはその時間を労働に咲くことは仕方がないとし、それ以外に思考の時間を確保していた。自分もそうしたいが…」
「非常勤講師は時給2,000円でそれはムリ。そんなに安い賃金なのに生徒から求められれば、時間外の放課後まで残って教える先生が一生懸命でいいよねと言われる。管理職に年休を取れと言われるけれど、取ったら取ったで授業交換してから休めと言われる。それってどうなの?」
「嫌われればいい。けれど、来年度も雇われる程度のスキルは必要。そこがジレンマ」
「牧内さんも言うように過労死から逃れるためには顰蹙を買え、ということかな」
「息子が職場で鬱になって長期休暇になったとき、「辞めなさい」と何度も言ったが、彼は「期待されているんだ」と言い続けた。「この仕事楽しいし、自分のためになっているんだ」と言い続けながら、ある朝会社に来ないとの電話があり、布団から出られなくなっている彼がいた。なぜ、自分でそれがわからないのか」
「上司が仕事が楽しく働きまくっている。夜中の二時か三時に出勤して、ふつうに働いている。家のことはよくわからないと豪語する。40,50くらいになって仕事が面白くなって裁量が出てくると、そうなるのかもしれないけれど、一方で家庭のことがわからないってどういうことかと思う」
「仕事が楽しいからと長時間労働する人と、家庭に帰りたくない、あるいは家庭がないという人が残業し続けるという実態はあるよね。とても迷惑な存在だと思うけれど、仕事をバリバリする人を責めることはできない」
「身近なところにこの本の例がいっぱいあることが、みんなの話からわかった」
「最低限のことをできないのは自分のせいとする文化がある」
「なぜ、みんなでカヴァーしないのか。仕事がギューッとなっている。自分が働いていた時期は、社会全体が明るい未来に向かっていた。80年卒業の頃はバリバリ働くことが当たり前。「24時間戦えますか」というCMがあっても、明るい未来が見えた時代だったから、それほど気にならなかったのも事実」
「過労死シンポジウムで労働局の人が言ったことで印象的だったのは、働く側もコンプライアンスが必要になっているという問題。消費者側が厳しいサービスを要求することが、社会の苦しさにつながっている。クレーマーやモンスターペアレンツの問題などはそうだろう」
「システムエンジニアとして働いているけれど、協力(下請け)会社という立場には拒否権がほとんどない。顧客に言われているから仕方がないよね、とみんな受け入れてしまう。それにノーというと鬱陶しがられる。90時間の残業に会社からは残業するなと言われても、顧客からどんどん要求が入る」
「コンプライアンスという言葉が出始めたころからおかしくなっている」
「日本の労働生産性が下がっているといわれるけれど、それは失敗じゃないか」
「昔はストがあったけれど、いまはない。皆どこかおかしいと思っているんだけれど、引っ込めちゃう。なぜ、組合が衰退したのか?」
ここで、牧内さんに過労死遺族への取材に関して聞いてみました。
というのも、いくつかの過労死本を読んできたけれど、そのどれもが尖った社会批判の論調であったのに対し、本書から受ける印象はそれとは異なっていたのが自分の中で引っかかっていたからです。いうなれば、牧内さんの人柄が筆致ににじみ出ていることの本質をつかみたいと思ったからです。それについて次のように答えていただきました。
「はじめて過労死遺族に会いに行くときはもちろん緊張する。ノウハウなどない中で本書に乗っている方々は基本的に社会に発信したいという人たちなので、その意味では取材に応じてもらえるケースだった。自分の中では亡くなられた方々を弔うという気持ちがある。取材対象でも、特に労災を認定されていない人については訴訟リスクが高くなる。けれど、そこをやらないと本当の意味でご遺族も亡くなった方々も救われない」
「弔う」という姿勢がこの本の全体に貫いていることが、他の過労死本から受ける印象と異なるということは、ハッとさせられました。被害者に「寄り添う」という印象がそこにあったと、腑に落ちたものです。
さて、議論は続きます。
「自分の周囲に危機的な人がいるけれど、そういう人に限って自分の仕事を手放そうとはしない。それを奪われると、本当に存在価値を失ってしまうという危機意識からなのか。とにかく周囲が無理だといっても聞く耳をもたない。その仕事を続ければ続けるほど、業務上滞ることが増えるばかりなのに。すると、その仕事だけに自分のアイデンティティを置いてしまうことの危険性がないだろうか」
このことは牧内さんからご自身の経験から次のように語られました。
「承認欲求に囚われるのは危険です。自分も新聞社の初任者研修を受ける前までは、仕事に情熱を持つ方ではなかった。けれど、同期社員がそろって研修を受ける中で少しずつ負けられないという意識が芽生えた。それが夜中の2時、3時まで取材に回るような異常な働きぶりにつながった。それで取材の成果が出たことはあまりなかったけれど、同僚はその姿を見て評価してくれる。そういう中で無茶な働きぶりにつながっていた」
「生きがい、承認欲求で自分のエンジンが回るとやばいところまで行く。ほかの視点を持つのが健全なのかもしれないが、仕事に夢中になっていると俯瞰的になれない。それをどこで踏ん切りをつければいいのか」
「自分の場合、労働基準法の知識がリミッターを切らせなかった。8時間労働でできない仕事内容はそもそもおかしいものだという判断が働いた」
「経済的にカネを稼ぐだけのはずの労働が、なぜかそこにアイデンティティを求めてしまう。働かずに食っていけるのがベストだけれど、そういうわけにはいかないから働く。けれど、そこにプラスαを求めてしまう」
「働き方改革をいうならば、労働時間の短縮という視点だけではなく、労働以外の領域を評価する議論がないといけない。労働時間の短縮だけでは、せっかく短縮されてもすることが何もないという空白が生じるだけ。そうなると結局、休日も職場に来て時間を潰すしかないという悪循環が生まれる。日本は決定的に自分の時間を大切にする文化がない。だから結局、余暇も消費文化にならざるを得ない。労働は所詮生活の必要性のためにするためだけなのに、そこに存在の意味を求めすぎているのではないか」
「それは、まさに近代の労働観念だよね。労働そのものに価値があるという「プロテスタンティズムの倫理」そのものが近代に貫かれている」
「でも、たしかに仕事は100%カネを稼ぐための手段だと思って、自分も仕事を好きにならないようにしてきた。けれど、そうすると、朝職場に来て夜帰るまでのあいだの1日8~10時間も私は何やっているんだと思うことがある。残りの人生どれほどあるかわからないのに、意味を見出せない仕事にこの時間を費やしていいのかと思う自分がいる。すると、完全に仕事は生活のためとは言い切れなくなってくる。このバランスを探している」
「生きがいをもったら搾取される構造の中で、仕事に対する主体性を取り戻すこと」
若い世代からはこんな話も挙げられました。
「失敗することが許されないことばかり。間違えたくない、人からこいつは違うとは思われたくないという意識が強い気がする。一人で抱え込むことが多い。承認欲求はたくさんあって、休みたいとは言えない。」
加害者の側が非を認め、変わるということはあるのだろうか?
牧内さんにこう聞いたところ、
「過労死事件では加害者側が形式的な謝罪はしているケースばかりで、本質的に変わることが見られない中で、長崎のメディカルセンターは変わろうとしている。理事長が変わり謝罪もしているケースがあった」
とのことです。
なかなか加害の側は変われない。この問題をどう考えるべきか、と考えていたところ牧内さんから「皆さんはパワハラをしているという自覚はありますか ?」という問いが投げかけられました。
パワハラの定義については、「職務上優越な立場にあり、職務を超える命令を発し、人格を傷つける」という法律上の定義があります。
これについて参加者はしばし黙考。
考えられるケースとしては、被害を訴えている側が「過剰反応」とか「自意識過剰」という処理の仕方が思い浮かびます。これについては学校現場の「いじめ」の定義を重ねる意見も挙げられました。つまり、いかなる事情があるとはいえ、被害者本人が「いじめられた」と思えば「いじめ」は成立するというものです。しかし、そこには常に主観と客観のズレを問題視する議論があります。しかし、そこにパワハラの自覚を不問にする構造があるとすれば…。冷や水を浴びせられた瞬間でした。
さらに、「コロナ問題」が過労死問題ンどのような影響をもたらすかという問いに対して牧内さんは、「少なくとも大学生の求人が減っていることを考えれば、ここから「働かせてもらえるだけでありがたいと思え」というブラック企業の増加は想像に難くないし、いずれにせよ悪影響が増えることは予想される」というものでした。
非常に重い問いを投げかける本書を議論する展開にハッピーエンドを期待することはムリな話ですが、それでも参加者それぞれの経験から話が止まらない時間でした。コロナが収まるどころか、深刻さを増すさなかにもこうした話し合いの場を持てたことは、闇の中にわずかな光明が差すような時間でした。このような中に牧内さんにゲストにお越しいただけたことはとてもありがたいことです。何より、私自身は過労職場に合って抵抗の意思を示すことに萎えていた自分に活を入れられた思いがしました。牧内さん、ありがとうございました。牧内さんは「過労死」問題のみならず、いま福島の原発事故や双葉町の「伝承館」についても発信し続けています。
詳しくは「
ウネリウネラ」のブログをご覧ください。
こうした問題についても皆さんで議論を続けていきたいと考えていますので、ご参加いただいた皆様も含めて引き続きよろしくお願いいたします。(文:渡部純)