特殊な能力について
結局、今の私は、「情報化」を仕事としている。
とりあえずしばらく関わった仕事もある意味「ひとやま」越えた気がする。個人的には「観賞用」の情報化ぐらいがちょうど
いいのだけれど、まあ、なかなかせちがない世の中なんでそうもいってられない。
実際には、ここからが本番なんだけどね。
ははは、そうなんだよね。好きなことが目いっぱい前に広がるから、それ以外のことを
意図的でもないのだけれど避ける傾向があるよね。
一つは、理系の先端研究者は「なまもの」を扱っているということ。
養老先生は以前「情報」と「情報化」の違いについて教えてくださったことがある。
「情報」というのはすでにパッケージされ、その意味や有用性が周知されているもののこと。
「情報化」とは、「なまの現実」を切り出し、かたちを整えて、「情報」にパックする作業のことである。
文系の学者たちは、情報の操作には長けているが、「なまの現実」を情報化するという作業にはあまり関心がないように見える。
内田樹の研究室
結局、今の私は、「情報化」を仕事としている。
とりあえずしばらく関わった仕事もある意味「ひとやま」越えた気がする。個人的には「観賞用」の情報化ぐらいがちょうど
いいのだけれど、まあ、なかなかせちがない世の中なんでそうもいってられない。
実際には、ここからが本番なんだけどね。
「なまもの」相手のときは、マニュアルもガイドラインもない。
「なまもの相手」というのは、要するに「こういう場合にはこうすればいいという先行事例がない」ということだからである。
どうしていいかわからない。
どうしていいかわからないときにでも、「とりあえず『これ』をしてみよう」とふっと思いつく人がいる。
そういう人だけが「なまもの相手」の現場に踏みとどまることができる。
どうしていいかわからないときにも、どうしていいかわかる。
それが「現場の人」の唯一の条件だと私は思う。
私が知り合った「理系の人たち」はどなたもそういう「なまの現場」に立っている方たちである。
現場にとどまり続けるためには「わからないはずなのだが、なんか、わかる」という特殊な能力が必要である。
そのことを先端研究にいる人たちはみんな熟知している。
だから、その「特殊な能力」をどうやって高いレベルに維持するか、そのことに腐心する。
先に名前を挙げた方たちのふるまいをみていると共通点がある。
それは「やりたくないことは、やらない」ということである。
これは領域を問わず、先端的な研究者全員に共通している。
ははは、そうなんだよね。好きなことが目いっぱい前に広がるから、それ以外のことを
意図的でもないのだけれど避ける傾向があるよね。











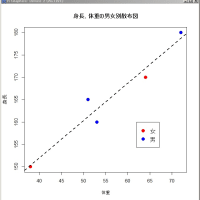

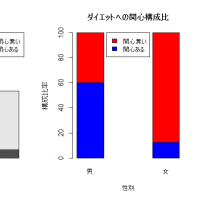

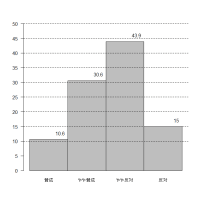

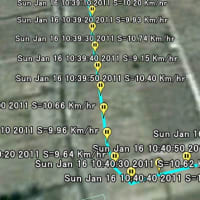

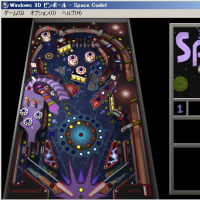




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます