memo
2018-07-10 | 日常
(1) 契約で定まった期限がある確定期限付債権の場合
改正法は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、②権利を行使することができる時から10年という2段階の起算点と時効期間が定められている。確定期限付債権の場合、債権者はよほどの事情がない限り、期限が到来すれば権利行使が可能であるとわかるはずなので、「債権者権利を行使できることを知った時」は「確定期限到来日」でそこから5年で時効が完成する。
(2) 不当利得返還請求権
ある人が法律上の理由なく利益を得て、これによってある人が損失を被った場合に、損失を被った人が利益を得た人に返還を求める場合、債権者がそのことを知るまでに時間的な間隔があく場合が考えられる。不当利得発生から10年、債権者が不当利得を認識してから5年という時効が別々に進行する場合がある。
(3) 共通錯誤とは、改正95条3項2号「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」のことをいう。表意者の意思表示を信頼していたという局面ではなく相手方を保護する必要性は低くなります。ある土地の近隣に近い将来地下鉄の駅が建設されると地主と買主が聞いて相場より相当高い値段で土地売買したが、地下鉄駅の話は事実無根であった場合、地主を保護して相場より相当高い値段で不動産を売却し利益を得させる必要性はないので、買主からの動機の錯誤(共通錯誤)による主張は認められるべき
(4) 登記請求権保全のための債権者代位権の転用
Z社が不動産をY社へ売却し、Y社がそれをX社へ転売した場合、X社としては登記名義をZ社から移転する必要があるが、Y社がZ社に対する所有権移転登記手続き請求権を行使しない場合、Y社のZ社に対する所有権移転登記手続き請求権を被保全債権とし、Y社のZ社に対する所有権移転登記手続請求権を代位行使できる。
X社のY社に対する所有権移転登記手続請求権の保全のみが目的とされているため、Y社の無資力は債権者代位権の要件として要求されません。
(5) 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合のおける時効の取り扱いについて
以下のうち一番早い時点まで時効は完成されない
・その合意があった時から1年を経過したとき
・その合意において当事者が協議をおこなう期間(1年未満のものに限る)を定めた時は、その期間まで
・当事者の一方から相手方に対して、協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でなされ、その通知から6か月を経過したとき。
改正法は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、②権利を行使することができる時から10年という2段階の起算点と時効期間が定められている。確定期限付債権の場合、債権者はよほどの事情がない限り、期限が到来すれば権利行使が可能であるとわかるはずなので、「債権者権利を行使できることを知った時」は「確定期限到来日」でそこから5年で時効が完成する。
(2) 不当利得返還請求権
ある人が法律上の理由なく利益を得て、これによってある人が損失を被った場合に、損失を被った人が利益を得た人に返還を求める場合、債権者がそのことを知るまでに時間的な間隔があく場合が考えられる。不当利得発生から10年、債権者が不当利得を認識してから5年という時効が別々に進行する場合がある。
(3) 共通錯誤とは、改正95条3項2号「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」のことをいう。表意者の意思表示を信頼していたという局面ではなく相手方を保護する必要性は低くなります。ある土地の近隣に近い将来地下鉄の駅が建設されると地主と買主が聞いて相場より相当高い値段で土地売買したが、地下鉄駅の話は事実無根であった場合、地主を保護して相場より相当高い値段で不動産を売却し利益を得させる必要性はないので、買主からの動機の錯誤(共通錯誤)による主張は認められるべき
(4) 登記請求権保全のための債権者代位権の転用
Z社が不動産をY社へ売却し、Y社がそれをX社へ転売した場合、X社としては登記名義をZ社から移転する必要があるが、Y社がZ社に対する所有権移転登記手続き請求権を行使しない場合、Y社のZ社に対する所有権移転登記手続き請求権を被保全債権とし、Y社のZ社に対する所有権移転登記手続請求権を代位行使できる。
X社のY社に対する所有権移転登記手続請求権の保全のみが目的とされているため、Y社の無資力は債権者代位権の要件として要求されません。
(5) 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合のおける時効の取り扱いについて
以下のうち一番早い時点まで時効は完成されない
・その合意があった時から1年を経過したとき
・その合意において当事者が協議をおこなう期間(1年未満のものに限る)を定めた時は、その期間まで
・当事者の一方から相手方に対して、協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でなされ、その通知から6か月を経過したとき。











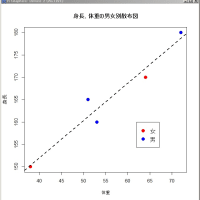

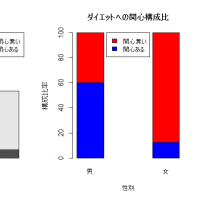

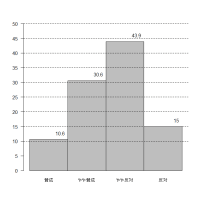

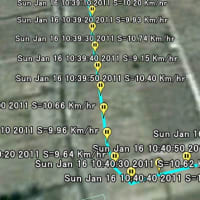

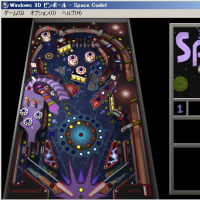




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます