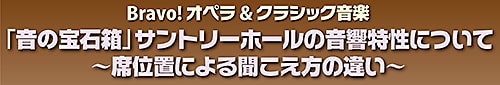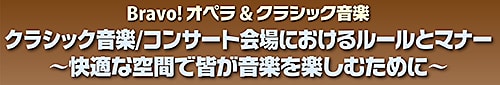全国共同制作プロジェクト
モーツァルト歌劇『ドン・ジョヴァンニ』
2019年1月26日(土)14:00〜 東京芸術劇場コンサートホール S席 1階 I列 21番 10,000円(ピットを造るので実際は2列目)
総監督・指揮:井上道義
演出・振付:森山開次
管弦楽:読売日本交響楽団
合 唱:東響コーラス
【出演】
ドン・ジョヴァンニ:ヴィタリ・ユシュマノフ
レポレッロ:三戸大久
ドンナ・アンナ:髙橋絵理
騎士長:デニス・ビシュニャ
ドンナ・エルヴィーラ:鷲尾麻衣
ドン・オッターヴィオ:金山京介
ツェルリーナ:小林沙羅
マゼット:近藤 圭
ダンサー:浅沼圭 碓井菜央 梶田留以 庄野早冴子 中村里彩 引間文佳 水谷彩乃 南帆乃佳 山本晴美 脇坂優海香
「全国共同制作プロジェクト」というのは文化庁の助成で2009年〜スタートしたオペラを新演出で上演するというプロジェクト。過去には、2015年のモーツァルトの『フィガロの結婚』や2017年のプッチーニの『トスカ』などの実績がある。今回はモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』が採り上げられ、1月20日に富山、26日・27日が東京、2月3日に熊本で公演が組まれた。
プロジェクトの総監督と指揮は井上道義さん。新演出は、現代ダンスの創作で知られる森山開次さん。演奏は、東京での公演は読売日本交響楽団が受け持った。合唱は東響コーラスが参加。
会場となった東京芸術劇場コンサートホールでは、1階客席A〜G列を取り払い、オーケストラ・ピットを配置した。私はI(アイ)列の席だったので実際には2列目。ピットが沈んでいない分、オーケストラの音が大き過ぎてしまったのには困ったが、歌手の皆さんの声は良く聞こえた。もちろん視覚的には最良のポジションである。
ステージには質感の高い舞台装置が設えられ、また衣装デザインもセンスが良く、見ていても楽しい。オペラとしての舞台演出はとくに変わったこともなく、出演者の皆さんに過度な演技を要求するものではなくて歌唱にも影響はなさそうだったのでホットした。演出の最大の特徴は、登場人物とは別に10名ほどのダンサーが様々な衣装で随時登場し、主に登場人物の心情をダンスで表現する。コンテンポラリー・ダンスではあるが、印象としてはオペラとバレエが融合したようなイメージだと思えば良い。その部分はなかなか良くできていて、視覚的な分かりやすさもあるし、歌手の演技的な負担も減るのでうまく機能していたようである。
そして今回ももう一つの特徴は、日本語による上演だという点だ。モーツァルトであるから、歌唱もレチタティーヴォも翻訳された日本語である。そして逆にステージ後方上部には日本語と英語の字幕が映写されていた。この日本語上演というのがクセモノで、考え方としてはオペラを普及させ一般化させるための方法論のひとつであることは間違いないが、私としては違和感の方が強く感じられてストレスが強かったように思う。
ドン・ジョヴァンニを演じたヴィタリ・ユシュマノフさんは、ロシア出身だが日本語には堪能で、日本を中心に活動している人なので、とくに問題はなかった。他の日本人歌手の皆さんも普通に歌っていた。つまり、違和感も元になっているのは、台本の方なのである。
と言っても、台本が良くないとか、翻訳が下手だとか、そういうことを言いたいのではない。要するに、実際の歌唱やレチタティーヴォを聴いていて、日本語がうまく聴き取れないのである(そのことも織り込み済みだったようで、日本語の字幕が付いていたのだろう)。これはディクション(舞台用の発声)の問題ではない。私の場合は『ドン・ジョヴァンニ』はよく知っているので、歌唱もレチタティーヴォも原語であるイタリア語の方が馴染みが深い。どの場面でどの登場人物がどんな内容のことを歌っているか、大体覚えている。日本語の字幕があればなお良しということになる。
あえて日本語歌唱の台本を採用したのであるから、「言葉」の不自由さから聴衆を解放したかったはずである。それなのに、聴いていて日本語が伝わって来ないのは何故なんだろう。
考えられるのは、「言葉」と「音楽」が一致していないことではないだろうか。モーツァルトはダ・ポンテによるイタリアの台本に対して、イタリア語の抑揚やリズム感に合わせた曲を付けている。だから言葉の意味は分からなくても、聴いていると言葉と音楽が馴染んでいるのが分かる。つまり聴いていてもそこに違和感がない。
私たちが、日本語のPOPSや演歌などを聴いた時に、言葉がすんなりとアタマに入って来るのは、ネイティブだからだけではない。日本語の抑揚やリズム感と音楽が一致しているからだ。クラシック分野でも同じことが言える。例えば、北原白秋作詞・山田耕筰作曲の「からたちの花」。出だしの「からたちの花が咲いたよ。白い白い花が咲いたよ。」を音読してみると、言葉のもつ自然な抑揚とメロディが見事に一致しているのが分かる。
つまり、歌唱付きの音楽の中には、言葉の持つ抑揚やリズム感がネイティブに埋め込まれているわけで、翻訳台本でそこが一致しないと、音楽に乗せて歌った時に、耳で聞くと日本語にはならないのである。歌うように語るレチタティーヴォもまた同様である(オペレッタなどのように歌唱以外が台詞になる場合は日本語だと大変聞き取りやすく分かりやすくなる)。
さらに、オペラの台本は内容が複雑だ。ストーリーを説明したり、状況を描写したり、心情を吐露したり・・・・「からたちの花」のようにシンプルではない。だから、翻訳台本はかなり高度な技術の要る仕事だ。
観る人・聴く人に分かりやすくするために日本語上演を試みているはずなのに、かえって日本語字幕を追いかけなければならないくらいなら、原語上演の方が良かったのでないだろうか。つまりはオペラの魅力を正しく伝えることが出来たのかどうかという問題提起なのであるが・・・・。
「音楽」と「原語」の関連については、もっと深く勉強しようと考えているテーマなのであるが、言葉のない音楽、すなわち管弦楽曲や器楽曲においても、メロディやリズムに内包されているその国のネイティブな言語、ドイツ語であったり、イタリア語、フランス語、ロシア語、等々の語感を知らなければ、あるいは感じ取れなければ、音楽の理解にとって重要な部分が欠落してしまうように思うのである。
今回は日本語で上演された『ドン・ジョヴァンニ』を聴いて、「音楽」と「原語」の乖離を感じてしまった。もちろん、色々な人たちが色々な考えでやっていることなので、外野が短絡的に批判したりすることの是非もあるわけで、何が正しいとか間違っているとか言っているのではない。まあ、問題提起だと思っていただければ幸いである。
 ← 読み終わりましたら、クリックお願いします。
← 読み終わりましたら、クリックお願いします。
★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★
当ブログの人気ページをご紹介します。
↓コチラのバナーをクリックしてください。↓
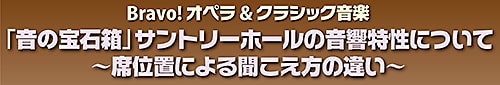
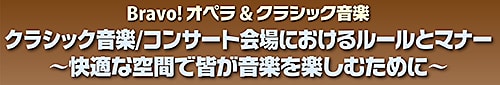
モーツァルト歌劇『ドン・ジョヴァンニ』
2019年1月26日(土)14:00〜 東京芸術劇場コンサートホール S席 1階 I列 21番 10,000円(ピットを造るので実際は2列目)
総監督・指揮:井上道義
演出・振付:森山開次
管弦楽:読売日本交響楽団
合 唱:東響コーラス
【出演】
ドン・ジョヴァンニ:ヴィタリ・ユシュマノフ
レポレッロ:三戸大久
ドンナ・アンナ:髙橋絵理
騎士長:デニス・ビシュニャ
ドンナ・エルヴィーラ:鷲尾麻衣
ドン・オッターヴィオ:金山京介
ツェルリーナ:小林沙羅
マゼット:近藤 圭
ダンサー:浅沼圭 碓井菜央 梶田留以 庄野早冴子 中村里彩 引間文佳 水谷彩乃 南帆乃佳 山本晴美 脇坂優海香
「全国共同制作プロジェクト」というのは文化庁の助成で2009年〜スタートしたオペラを新演出で上演するというプロジェクト。過去には、2015年のモーツァルトの『フィガロの結婚』や2017年のプッチーニの『トスカ』などの実績がある。今回はモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』が採り上げられ、1月20日に富山、26日・27日が東京、2月3日に熊本で公演が組まれた。
プロジェクトの総監督と指揮は井上道義さん。新演出は、現代ダンスの創作で知られる森山開次さん。演奏は、東京での公演は読売日本交響楽団が受け持った。合唱は東響コーラスが参加。
会場となった東京芸術劇場コンサートホールでは、1階客席A〜G列を取り払い、オーケストラ・ピットを配置した。私はI(アイ)列の席だったので実際には2列目。ピットが沈んでいない分、オーケストラの音が大き過ぎてしまったのには困ったが、歌手の皆さんの声は良く聞こえた。もちろん視覚的には最良のポジションである。
ステージには質感の高い舞台装置が設えられ、また衣装デザインもセンスが良く、見ていても楽しい。オペラとしての舞台演出はとくに変わったこともなく、出演者の皆さんに過度な演技を要求するものではなくて歌唱にも影響はなさそうだったのでホットした。演出の最大の特徴は、登場人物とは別に10名ほどのダンサーが様々な衣装で随時登場し、主に登場人物の心情をダンスで表現する。コンテンポラリー・ダンスではあるが、印象としてはオペラとバレエが融合したようなイメージだと思えば良い。その部分はなかなか良くできていて、視覚的な分かりやすさもあるし、歌手の演技的な負担も減るのでうまく機能していたようである。
そして今回ももう一つの特徴は、日本語による上演だという点だ。モーツァルトであるから、歌唱もレチタティーヴォも翻訳された日本語である。そして逆にステージ後方上部には日本語と英語の字幕が映写されていた。この日本語上演というのがクセモノで、考え方としてはオペラを普及させ一般化させるための方法論のひとつであることは間違いないが、私としては違和感の方が強く感じられてストレスが強かったように思う。
ドン・ジョヴァンニを演じたヴィタリ・ユシュマノフさんは、ロシア出身だが日本語には堪能で、日本を中心に活動している人なので、とくに問題はなかった。他の日本人歌手の皆さんも普通に歌っていた。つまり、違和感も元になっているのは、台本の方なのである。
と言っても、台本が良くないとか、翻訳が下手だとか、そういうことを言いたいのではない。要するに、実際の歌唱やレチタティーヴォを聴いていて、日本語がうまく聴き取れないのである(そのことも織り込み済みだったようで、日本語の字幕が付いていたのだろう)。これはディクション(舞台用の発声)の問題ではない。私の場合は『ドン・ジョヴァンニ』はよく知っているので、歌唱もレチタティーヴォも原語であるイタリア語の方が馴染みが深い。どの場面でどの登場人物がどんな内容のことを歌っているか、大体覚えている。日本語の字幕があればなお良しということになる。
あえて日本語歌唱の台本を採用したのであるから、「言葉」の不自由さから聴衆を解放したかったはずである。それなのに、聴いていて日本語が伝わって来ないのは何故なんだろう。
考えられるのは、「言葉」と「音楽」が一致していないことではないだろうか。モーツァルトはダ・ポンテによるイタリアの台本に対して、イタリア語の抑揚やリズム感に合わせた曲を付けている。だから言葉の意味は分からなくても、聴いていると言葉と音楽が馴染んでいるのが分かる。つまり聴いていてもそこに違和感がない。
私たちが、日本語のPOPSや演歌などを聴いた時に、言葉がすんなりとアタマに入って来るのは、ネイティブだからだけではない。日本語の抑揚やリズム感と音楽が一致しているからだ。クラシック分野でも同じことが言える。例えば、北原白秋作詞・山田耕筰作曲の「からたちの花」。出だしの「からたちの花が咲いたよ。白い白い花が咲いたよ。」を音読してみると、言葉のもつ自然な抑揚とメロディが見事に一致しているのが分かる。
つまり、歌唱付きの音楽の中には、言葉の持つ抑揚やリズム感がネイティブに埋め込まれているわけで、翻訳台本でそこが一致しないと、音楽に乗せて歌った時に、耳で聞くと日本語にはならないのである。歌うように語るレチタティーヴォもまた同様である(オペレッタなどのように歌唱以外が台詞になる場合は日本語だと大変聞き取りやすく分かりやすくなる)。
さらに、オペラの台本は内容が複雑だ。ストーリーを説明したり、状況を描写したり、心情を吐露したり・・・・「からたちの花」のようにシンプルではない。だから、翻訳台本はかなり高度な技術の要る仕事だ。
観る人・聴く人に分かりやすくするために日本語上演を試みているはずなのに、かえって日本語字幕を追いかけなければならないくらいなら、原語上演の方が良かったのでないだろうか。つまりはオペラの魅力を正しく伝えることが出来たのかどうかという問題提起なのであるが・・・・。
「音楽」と「原語」の関連については、もっと深く勉強しようと考えているテーマなのであるが、言葉のない音楽、すなわち管弦楽曲や器楽曲においても、メロディやリズムに内包されているその国のネイティブな言語、ドイツ語であったり、イタリア語、フランス語、ロシア語、等々の語感を知らなければ、あるいは感じ取れなければ、音楽の理解にとって重要な部分が欠落してしまうように思うのである。
今回は日本語で上演された『ドン・ジョヴァンニ』を聴いて、「音楽」と「原語」の乖離を感じてしまった。もちろん、色々な人たちが色々な考えでやっていることなので、外野が短絡的に批判したりすることの是非もあるわけで、何が正しいとか間違っているとか言っているのではない。まあ、問題提起だと思っていただければ幸いである。
★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★
当ブログの人気ページをご紹介します。
↓コチラのバナーをクリックしてください。↓