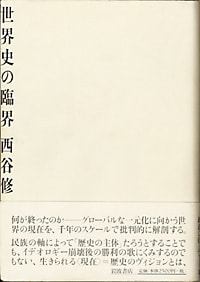昨今のオペラ・ブームを反映してか、このところオペラに関する入門書が数多く出版されている。それらの多くは名曲解説を中心に、オペラの楽しみ方を紹介している。最近ではCD付きのものや、DVDブックも数種類出版されている。そんな中で本書一風変わった入門書となっている。何しろ「講談社学術文庫」なのだから。
NHK BS-Hiの「ウィークエンドシアター」の解説でもお馴染みの堀内 修さんの最新刊である。といっても1989年刊の『はじめてのオペラ』という本を現代のオペラ事情に照らして加筆・改稿されたものである。
「歌劇場は博物館じゃない!」と本の帯に歌われているように、堀内さんは過去の歴史上に生まれたオペラが単なる古典芸術として存在しているのではなく、現代も続いている表現芸術として生まれ変わりながら生き続けている、ことを訴えている。
目次を追っていくと、「序曲」でオペラは一度ハマってしまうと危険な道楽だといい、「第1幕」ではオペラの基本的な楽しみ方を紹介している。さらに「第2幕」では、そうすべきではないといいつつも、オペラの歴史を学ばせてくれる。「第3幕」では海外のオペラ劇場と、その楽しみ方をかなり具体的に紹介。「第4幕」では劇的に進化している現代のオペラ事情を紹介し、現代のオペラの楽しみ方を訴える。それが「歌劇場は博物館じゃない!」ということなのだが…。
この『オペラ入門』は、入門書には違いないが、読んでみると決して初心者向けの入門書ではない。オペラのことをまったく知らない人が、「そろそろオペラでも…」と思ってこの本を読んでも、かなり難解かもしれない。基礎知識がないと、意味のわからないような内容の記述が多いからだ。中級者までとはいわないが、初級を卒業したくらいの人のための入門書というところか。オペラを30曲くらいは聴いたことがあって、有名オペラの作曲家やストーリー、名アリアなどを知っている。また世界や日本のオペラ界の有名な指揮者やオペラハウス、歌手たちの顔と名前はひととおり知っていて、それらの特徴なども感覚的に理解している。これくらいの人が読むと、思わず笑ってしまうような話が満載だ。私も電車の中で読んでいて、思わず吹き出してしまったところが数カ所あった。講談社学術文庫なのに…。
堀内さんの文章はユーモアに溢れていて、堅苦しさがなく、とても読みやすい。オペラを多少知っている人にとっては、とても勉強になるし(著者はそういう読み方を望んでおられないようだが)、巻末に掲載されているオペラDVDの推薦盤(?)のリストなども実践的に役に立つだろう。この本を読むレベルの人は、すでに危険な道楽にハマってしまっている人に違いない。
ここからは私見の「オペラ入門」ですが、これから初めてオペラを劇場で観てみたいと思っている人に、どんなアドバイスをすれば良いかいつも考えさせられる。初めて観たオペラに共感を覚えられれば、その後オペラにハマっていく可能性が大である。いくら字幕があるからストーリーは知らなくても何とかなるとはいっても、最初に観たオペラが「ヴォツェック」だったら、またオペラに行こうと思う人がどれだけいるだろうか。やはりものごとには順序というものがあるから、最初のオペラ体験はポピュラーな演目で、オーソドックスな演出が楽良いと思う。
「フィガロの結婚」「椿姫」「カルメン」「ラ・ボエーム」あたりが無難である。ちなみに私は「椿姫」だった。また、クラシック音楽好きの人が「そろそろオペラでも…」という場合には、好きな作曲家の作品を選ぶという手もある。ベートーヴェン好きの人は「フィデリオ」とか、チャイコフスキー好きの人は「エフゲニー・オネーギン」とか。音楽面から素直にはいっていける。もっともタイミング良く公演があればの話だが…。
ちょうど良い公演がない場合は、DVDでとりあえず鑑賞してみることになるが、こうなると選択肢が多すぎて迷ってしまう。やはり人気演目でオーソドックスな演出が良いと思うが、出演者は一流のもの、そしてできるだけ新しいものが好ましい。ウィーンかミラノかMETあたりでゼッフィレッリの演出ものというところか。
結局、劇場に行くにしても手軽にDVDを観るにしても、初めての人は先達に教えてもらう方が良い。オペラ好きの人は仲間を増やしたいと思っているから、懇切丁寧に教えてくれる。頼まなくても教えてくれる。そうやって、とりあえずオペラを体験してみてほしい。そしてちょっとでも面白いと感じた人は、オペラにハマってしまう可能性が大である。堀内さんのいうように、何しろオペラは危険な道楽なのだから。
NHK BS-Hiの「ウィークエンドシアター」の解説でもお馴染みの堀内 修さんの最新刊である。といっても1989年刊の『はじめてのオペラ』という本を現代のオペラ事情に照らして加筆・改稿されたものである。
「歌劇場は博物館じゃない!」と本の帯に歌われているように、堀内さんは過去の歴史上に生まれたオペラが単なる古典芸術として存在しているのではなく、現代も続いている表現芸術として生まれ変わりながら生き続けている、ことを訴えている。
目次を追っていくと、「序曲」でオペラは一度ハマってしまうと危険な道楽だといい、「第1幕」ではオペラの基本的な楽しみ方を紹介している。さらに「第2幕」では、そうすべきではないといいつつも、オペラの歴史を学ばせてくれる。「第3幕」では海外のオペラ劇場と、その楽しみ方をかなり具体的に紹介。「第4幕」では劇的に進化している現代のオペラ事情を紹介し、現代のオペラの楽しみ方を訴える。それが「歌劇場は博物館じゃない!」ということなのだが…。
この『オペラ入門』は、入門書には違いないが、読んでみると決して初心者向けの入門書ではない。オペラのことをまったく知らない人が、「そろそろオペラでも…」と思ってこの本を読んでも、かなり難解かもしれない。基礎知識がないと、意味のわからないような内容の記述が多いからだ。中級者までとはいわないが、初級を卒業したくらいの人のための入門書というところか。オペラを30曲くらいは聴いたことがあって、有名オペラの作曲家やストーリー、名アリアなどを知っている。また世界や日本のオペラ界の有名な指揮者やオペラハウス、歌手たちの顔と名前はひととおり知っていて、それらの特徴なども感覚的に理解している。これくらいの人が読むと、思わず笑ってしまうような話が満載だ。私も電車の中で読んでいて、思わず吹き出してしまったところが数カ所あった。講談社学術文庫なのに…。
堀内さんの文章はユーモアに溢れていて、堅苦しさがなく、とても読みやすい。オペラを多少知っている人にとっては、とても勉強になるし(著者はそういう読み方を望んでおられないようだが)、巻末に掲載されているオペラDVDの推薦盤(?)のリストなども実践的に役に立つだろう。この本を読むレベルの人は、すでに危険な道楽にハマってしまっている人に違いない。
ここからは私見の「オペラ入門」ですが、これから初めてオペラを劇場で観てみたいと思っている人に、どんなアドバイスをすれば良いかいつも考えさせられる。初めて観たオペラに共感を覚えられれば、その後オペラにハマっていく可能性が大である。いくら字幕があるからストーリーは知らなくても何とかなるとはいっても、最初に観たオペラが「ヴォツェック」だったら、またオペラに行こうと思う人がどれだけいるだろうか。やはりものごとには順序というものがあるから、最初のオペラ体験はポピュラーな演目で、オーソドックスな演出が楽良いと思う。
「フィガロの結婚」「椿姫」「カルメン」「ラ・ボエーム」あたりが無難である。ちなみに私は「椿姫」だった。また、クラシック音楽好きの人が「そろそろオペラでも…」という場合には、好きな作曲家の作品を選ぶという手もある。ベートーヴェン好きの人は「フィデリオ」とか、チャイコフスキー好きの人は「エフゲニー・オネーギン」とか。音楽面から素直にはいっていける。もっともタイミング良く公演があればの話だが…。
ちょうど良い公演がない場合は、DVDでとりあえず鑑賞してみることになるが、こうなると選択肢が多すぎて迷ってしまう。やはり人気演目でオーソドックスな演出が良いと思うが、出演者は一流のもの、そしてできるだけ新しいものが好ましい。ウィーンかミラノかMETあたりでゼッフィレッリの演出ものというところか。
結局、劇場に行くにしても手軽にDVDを観るにしても、初めての人は先達に教えてもらう方が良い。オペラ好きの人は仲間を増やしたいと思っているから、懇切丁寧に教えてくれる。頼まなくても教えてくれる。そうやって、とりあえずオペラを体験してみてほしい。そしてちょっとでも面白いと感じた人は、オペラにハマってしまう可能性が大である。堀内さんのいうように、何しろオペラは危険な道楽なのだから。