【CD】「アンコール!」川久保賜紀(avex CLASSICS / AVCL-25871)
2015年4月22日発売/3,240円
ヴァイオリン:川久保賜紀
ピアノ:江口 玲
【曲目】
クライスラー:プレリュードとアレグロ
クライスラー:美しきロスマリン
クライスラー:中国の太鼓
ガーシュウィン:3つのプレリュード 第1番 Allegro ben ritmato e deciso
ガーシュウィン:3つのプレリュード 第2番 Andante con moto e poco rubato
ガーシュウィン:3つのプレリュード 第3番 Allegro ben ritmato e deciso
サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン 作品20
サラサーテ:アンダルシアのロマンス(スペイン舞曲集 作品22~第3番)
ブラームス:ハンガリー舞曲 第5番
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「棒踊り」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「飾り帯の踊り(ブラウル舞曲)」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「足踏み踊り」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「角笛の踊り(ブチュム舞曲)」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「ルーマニア風ポルカ」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「速い踊り」
ラヴェル:ツィガーヌ
モンティ:チャールダーシュ
(全17曲/57分/録音:2014年11月18日~20日/稲城市立iプラザ)
川久保賜紀さんの待望のニュー・アルバムは、ヴィルトゥオーゾ的小品を集めた「アンコール!」。発売情報を知った時点で予約しておいたものが発売日に手元に届いた。待望といったのは、ソロのアルバムは2011年11月にリリースされた「ライブ・イン・ワシントン」以来、実に3年5ヶ月ぶりになるからである。
タイトルは「アンコール!」だが、収録されている曲は必ずしもアンコール・ピースとはいえないガーシュウィンの「3つのプレリュード」やバルトークの「ルーマニア民族舞曲」のような組曲も含まれている。最近の賜紀さんのリサイタルでは、クライスラーの「美しきロスマリン」やサラサーテの「アンダルシアのロマンス」、ブラームスの「ハンガリー舞曲第5番」、そしてモンティの「チャールダーシュ」などがお気に入りのようで、アンコールによく演奏されている。

どなたかが書いた賜紀さんのプロフィルの一節に「高度な技術と作品の品位を尊ぶ深い音楽性が高い評価を得ている」という表現があるが、これは実に的を射た言い方だと思う。
賜紀さんはアメリカ生まれで5歳の時からヴァイオリンを始め、16歳からドイツに留学、現在もベルリン在住。ガーシュウィンが好きなのもアメリカ生まれというのが影響しているだろうし、ベートーヴェンやブラームスにはいかにもドイツ的な造形のしっかりした演奏をする。2002年のチャイコフスキー国際コンクールで最高位を獲得しているためチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を演奏する機会も多いが、その時は大らかな抒情性を発揮し非常にロマンティックかつドラマティックな演奏をする。サラサーテをはじめとするラテン系の音楽の時は情熱的で熱く燃える。「作曲家の品位を尊ぶ」というのはそういうことなのだ。作曲家あるいは作品の世界観を、ある意味ではとても素直に描き出している。ところが、どんな曲を弾いても、賜紀さんにしか出せない流麗かつエレガントな音楽になっているのが共通点で、それは川久保賜紀流の世界観なのである。
また、今回のような名曲・小品であっても、あるいはヴァイオリン・ソナタやヴァイオリン協奏曲のような大曲であっても、1音1音、1節1節に深い洞察が加えられて、サラリと流すようなところが全くない。すべての音符に明確な意味を与えることをベースに、それが積み上げられ組み立てられて音楽が成り立っている。まさに「深い音楽性」なのだと思う。
そして、それらを支えているのが「高度な技術」ということなのだろう。
「アンコール!」を聴いてみると、クライスラー、ガーシュウィン、サラサーテ、ブラームス、バルトーク、ラヴェル、そしてモンティと、お国柄も曲想もまったく異なる幅広い選曲になっているのに、それぞれの世界観が見事に表現されている。クライスラーは優雅で洒脱に、ガーシュウィンはジャズっぽく、サラサーテは燃えるように、といった風に。しかし共通する川久保賜紀流は、いずれの曲も、流れるようなレガートや、立ち上がりのキリッとした鋭さ、大きく揺らすテンポや自由度が高く即興性に優れた旋律の歌わせ方、そしてあくまで美しくしなやかな音色・・・・。強烈な個性を押し出すのではなく、柔らかく包み込むようで、ちょっと控え目なところもある。これはむしろ「日本的な美」だということができるのかもしれない。
私が賜紀さんのヴァイオリンの一番好きなところは、聴いているとこちらの心(あるいは身体)と共振する感じがすることだ。魂を揺さぶられるような強い感動を得るのではなく、かといって「癒し系」というほど軽くもない。色々な素晴らしいヴァイオリニストを聴き比べれば、感動する人、感激する人、驚愕するひと、泣ける人、笑える人など、様々に感じることがあり、皆さん素晴らしいとその時は感じる。ところが賜紀さんの場合は、マイホームに帰ってきてホッとするような、自分と同じ振幅の音楽に聞こえるのである。だから曲によってはスリリングでドキドキしたり、ワクワクと高揚したり、安らぎを感じたり、様々なことを感じ取り受け止めるのだが、一方的に音楽をもらっているのではなくて、聴いている自分も音楽の一部なのだという一体感を感じるのである。いつもはコンサートホールでしか感じられなかったことが、今日はCDを聴いても同じ感覚になった。Brava!

このアルバムの共演者は江口 玲さん。最高のパートナーである。そして今回の録音に使用されたのは、1887年製のニューヨーク・スタインウェイ、通称「ローズウッド」。カーネギーホールやメトロポリタン歌劇場で使用されていたものが日本に渡ってきて、キャピトル東京ホテルに所蔵されていた時に、来日したホロヴィッツがこのビアノを弾いて絶賛したという、そのローズウッドの渋い装飾のように、ちょっとくすんだアコースティックなサウンドが、得も言われぬクラシカルな世界を創り上げる。最近、江口さんがこのビアノをお気に入りで、私も何度かナマで聴いたことがある。ホールで聴くのと録音て聴くのでは実際にはかなり聞こえ方が違うが、このピアノの音色の本質的なところは見事に再現されていて、賜紀さんの鮮やかなヴァイオリンの音色との対比も見事に仕上がっている。
このアルバムは通常のCDとSACD(Super Audio CD)とのハイブリッド盤。録音がDSD(Direct Stream Digital)方式のため、通常のCDとして再生しても音質が素晴らしい。もちろん今時珍しいことではないが、ダイナミックレンジが物理的に広く、聴いた感じでもホールでナマ演奏を聴いているようなリアルな臨場感がある。かつてのアナログ・レコードを音源とするCDや少し前までのCDのように、音はクリアでスッキリしているのに、演奏会で聴くような深みが足りないのとは一線を画している。何しろ、ピアノの音は固定されているが、ヴァイオリンの音が左右に動くのが分かるくらいのリアルさだ。目をつぶって聴いていると、賜紀さんが演奏しながら身体を振っているのが目に浮かぶようであった。
 ← 読み終わりましたら、クリックお願いします。
← 読み終わりましたら、クリックお願いします。
【お勧めCDのご紹介】
「アンコール!」川久保賜紀さんの最新盤です。聴いてみたい(買いたい)と思った人は、このジャケットをクリック!!
【川久保賜紀さんのディスコグラフィ】
せっかくの機会ですので、賜紀さんのこれまでリリースされたCDを一挙にご紹介します。
■2002年チャイコフスキー国際コンクール・ライヴ(2004年)
コンクールのライブ録音から賜紀さんの演奏を抜粋したものです。メインはチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(ドミトリー・リス指揮/ロシア・ナショナル管弦楽団)です。
■メンデルスゾーン&チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲(2004年)
日本デビュー盤。下野竜也指揮/新日本フィルハーモニー交響楽団による演奏です。
■リサイタル!(2007年)
ガーシュウィンほか名曲を集めた小品集。共演はイタマール・ゴランさん。『レコード芸術』誌の特選盤に選ばれました。
■RAVEL(2009年)
チェロの遠藤真理さん、ピアノの三浦友理枝さんとのトリオによるラヴェルのトリオ曲集。
■ヴィヴァルディ:四季(2009年)
紀尾井シンフォニエッタとの共演によるライブ録音盤。
■ライブ・イン・ワシントン(2011年)
フランクとプロコフィエフの2番という名ソナタを収録。共演はアントニー・ヒューイットさん。
2015年4月22日発売/3,240円
ヴァイオリン:川久保賜紀
ピアノ:江口 玲
【曲目】
クライスラー:プレリュードとアレグロ
クライスラー:美しきロスマリン
クライスラー:中国の太鼓
ガーシュウィン:3つのプレリュード 第1番 Allegro ben ritmato e deciso
ガーシュウィン:3つのプレリュード 第2番 Andante con moto e poco rubato
ガーシュウィン:3つのプレリュード 第3番 Allegro ben ritmato e deciso
サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン 作品20
サラサーテ:アンダルシアのロマンス(スペイン舞曲集 作品22~第3番)
ブラームス:ハンガリー舞曲 第5番
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「棒踊り」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「飾り帯の踊り(ブラウル舞曲)」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「足踏み踊り」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「角笛の踊り(ブチュム舞曲)」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「ルーマニア風ポルカ」
バルトーク:ルーマニア民族舞曲「速い踊り」
ラヴェル:ツィガーヌ
モンティ:チャールダーシュ
(全17曲/57分/録音:2014年11月18日~20日/稲城市立iプラザ)
川久保賜紀さんの待望のニュー・アルバムは、ヴィルトゥオーゾ的小品を集めた「アンコール!」。発売情報を知った時点で予約しておいたものが発売日に手元に届いた。待望といったのは、ソロのアルバムは2011年11月にリリースされた「ライブ・イン・ワシントン」以来、実に3年5ヶ月ぶりになるからである。
タイトルは「アンコール!」だが、収録されている曲は必ずしもアンコール・ピースとはいえないガーシュウィンの「3つのプレリュード」やバルトークの「ルーマニア民族舞曲」のような組曲も含まれている。最近の賜紀さんのリサイタルでは、クライスラーの「美しきロスマリン」やサラサーテの「アンダルシアのロマンス」、ブラームスの「ハンガリー舞曲第5番」、そしてモンティの「チャールダーシュ」などがお気に入りのようで、アンコールによく演奏されている。

どなたかが書いた賜紀さんのプロフィルの一節に「高度な技術と作品の品位を尊ぶ深い音楽性が高い評価を得ている」という表現があるが、これは実に的を射た言い方だと思う。
賜紀さんはアメリカ生まれで5歳の時からヴァイオリンを始め、16歳からドイツに留学、現在もベルリン在住。ガーシュウィンが好きなのもアメリカ生まれというのが影響しているだろうし、ベートーヴェンやブラームスにはいかにもドイツ的な造形のしっかりした演奏をする。2002年のチャイコフスキー国際コンクールで最高位を獲得しているためチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を演奏する機会も多いが、その時は大らかな抒情性を発揮し非常にロマンティックかつドラマティックな演奏をする。サラサーテをはじめとするラテン系の音楽の時は情熱的で熱く燃える。「作曲家の品位を尊ぶ」というのはそういうことなのだ。作曲家あるいは作品の世界観を、ある意味ではとても素直に描き出している。ところが、どんな曲を弾いても、賜紀さんにしか出せない流麗かつエレガントな音楽になっているのが共通点で、それは川久保賜紀流の世界観なのである。
また、今回のような名曲・小品であっても、あるいはヴァイオリン・ソナタやヴァイオリン協奏曲のような大曲であっても、1音1音、1節1節に深い洞察が加えられて、サラリと流すようなところが全くない。すべての音符に明確な意味を与えることをベースに、それが積み上げられ組み立てられて音楽が成り立っている。まさに「深い音楽性」なのだと思う。
そして、それらを支えているのが「高度な技術」ということなのだろう。
「アンコール!」を聴いてみると、クライスラー、ガーシュウィン、サラサーテ、ブラームス、バルトーク、ラヴェル、そしてモンティと、お国柄も曲想もまったく異なる幅広い選曲になっているのに、それぞれの世界観が見事に表現されている。クライスラーは優雅で洒脱に、ガーシュウィンはジャズっぽく、サラサーテは燃えるように、といった風に。しかし共通する川久保賜紀流は、いずれの曲も、流れるようなレガートや、立ち上がりのキリッとした鋭さ、大きく揺らすテンポや自由度が高く即興性に優れた旋律の歌わせ方、そしてあくまで美しくしなやかな音色・・・・。強烈な個性を押し出すのではなく、柔らかく包み込むようで、ちょっと控え目なところもある。これはむしろ「日本的な美」だということができるのかもしれない。
私が賜紀さんのヴァイオリンの一番好きなところは、聴いているとこちらの心(あるいは身体)と共振する感じがすることだ。魂を揺さぶられるような強い感動を得るのではなく、かといって「癒し系」というほど軽くもない。色々な素晴らしいヴァイオリニストを聴き比べれば、感動する人、感激する人、驚愕するひと、泣ける人、笑える人など、様々に感じることがあり、皆さん素晴らしいとその時は感じる。ところが賜紀さんの場合は、マイホームに帰ってきてホッとするような、自分と同じ振幅の音楽に聞こえるのである。だから曲によってはスリリングでドキドキしたり、ワクワクと高揚したり、安らぎを感じたり、様々なことを感じ取り受け止めるのだが、一方的に音楽をもらっているのではなくて、聴いている自分も音楽の一部なのだという一体感を感じるのである。いつもはコンサートホールでしか感じられなかったことが、今日はCDを聴いても同じ感覚になった。Brava!

このアルバムの共演者は江口 玲さん。最高のパートナーである。そして今回の録音に使用されたのは、1887年製のニューヨーク・スタインウェイ、通称「ローズウッド」。カーネギーホールやメトロポリタン歌劇場で使用されていたものが日本に渡ってきて、キャピトル東京ホテルに所蔵されていた時に、来日したホロヴィッツがこのビアノを弾いて絶賛したという、そのローズウッドの渋い装飾のように、ちょっとくすんだアコースティックなサウンドが、得も言われぬクラシカルな世界を創り上げる。最近、江口さんがこのビアノをお気に入りで、私も何度かナマで聴いたことがある。ホールで聴くのと録音て聴くのでは実際にはかなり聞こえ方が違うが、このピアノの音色の本質的なところは見事に再現されていて、賜紀さんの鮮やかなヴァイオリンの音色との対比も見事に仕上がっている。
このアルバムは通常のCDとSACD(Super Audio CD)とのハイブリッド盤。録音がDSD(Direct Stream Digital)方式のため、通常のCDとして再生しても音質が素晴らしい。もちろん今時珍しいことではないが、ダイナミックレンジが物理的に広く、聴いた感じでもホールでナマ演奏を聴いているようなリアルな臨場感がある。かつてのアナログ・レコードを音源とするCDや少し前までのCDのように、音はクリアでスッキリしているのに、演奏会で聴くような深みが足りないのとは一線を画している。何しろ、ピアノの音は固定されているが、ヴァイオリンの音が左右に動くのが分かるくらいのリアルさだ。目をつぶって聴いていると、賜紀さんが演奏しながら身体を振っているのが目に浮かぶようであった。
【お勧めCDのご紹介】
「アンコール!」川久保賜紀さんの最新盤です。聴いてみたい(買いたい)と思った人は、このジャケットをクリック!!
 | アンコール! |
| avex CLASSICS | |
| avex CLASSICS |
【川久保賜紀さんのディスコグラフィ】
せっかくの機会ですので、賜紀さんのこれまでリリースされたCDを一挙にご紹介します。
■2002年チャイコフスキー国際コンクール・ライヴ(2004年)
コンクールのライブ録音から賜紀さんの演奏を抜粋したものです。メインはチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(ドミトリー・リス指揮/ロシア・ナショナル管弦楽団)です。
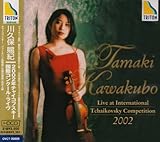 | 2002年チャイコフスキー国際コンクール・ライヴ |
| 川久保賜紀,チャイコフスキー,プロコフィエフ,サラサーテ,リス(ドミトリー),ロシア・ナショナル管弦楽団,ビノグラードワ(イリーナ) | |
| オクタヴィアレコード |
■メンデルスゾーン&チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲(2004年)
日本デビュー盤。下野竜也指揮/新日本フィルハーモニー交響楽団による演奏です。
 | メンデルスゾーン&チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 |
| avex CLASSICS | |
| avex CLASSICS |
■リサイタル!(2007年)
ガーシュウィンほか名曲を集めた小品集。共演はイタマール・ゴランさん。『レコード芸術』誌の特選盤に選ばれました。
 | リサイタル! |
| 川久保賜紀,チャイコフスキー,サラサーテ,ショーソン,ドビュッシー,ガーシュウィン,ショスタコーヴィチ,サン=サーンス,カレンバ,ハイフェッツ,ゴラン(イタマール) | |
| エイベックス・クラシックス |
■RAVEL(2009年)
チェロの遠藤真理さん、ピアノの三浦友理枝さんとのトリオによるラヴェルのトリオ曲集。
 | RAVEL |
| ラヴェル,山田武彦,浦壁信二,川久保賜紀,遠藤真理,三浦友理枝 | |
| エイベックス・クラシックス |
■ヴィヴァルディ:四季(2009年)
紀尾井シンフォニエッタとの共演によるライブ録音盤。
 | ヴィヴァルディ:四季 |
| ヴィヴァルディ,川久保賜紀,紀尾井シンフォニエッタ東京 | |
| エイベックス・エンタテインメント |
■ライブ・イン・ワシントン(2011年)
フランクとプロコフィエフの2番という名ソナタを収録。共演はアントニー・ヒューイットさん。
 | ライブ・イン・ワシントン~フランク、プロコフィエフ |
| avex CLASSICS | |
| avex CLASSICS |




















