
オオデマリ(大手毬)スイカズラ科。日本原産のヤブデマリの園芸種。
固い小さい緑色から始まり、だんだん色が薄く、花が大きくなっていきます。白く大きく、アジサイのようになる前の、この黄緑色が好き。葉脈が深くへこんだ葉は、同じスイカズラ科のガマズミにも似ています。学名はViburnumで、切花に使うビバーナムの仲間です。

オステオスペルマム キク科。南アフリカ原産。
ディモルフォセカととても似ています。これが、ディモルフォセカとして出回ることもありますし、両種とも宿根も一年草もあるし、色も多彩で、区別がつきません。ただ、新しい品種名付きの苗は、オステオスペルマムとなっているので、そうなのね、と思うしかない現状です。どちらにしても、丈夫で多花。園芸向きの優秀な植物です。

ツルニチニチソウ キョウチクトウ科。
放っておいたら、家の裏にめちゃめちゃ増えていました。青紫の花は、摘んで生けようとすると、すぐにぽろんと落ちてしまいます。

ライラック モクセイ科。
札幌市の花。ライラック、ポプラ、ニセアカシア、スズラン、矢車草、百日草、たんぽぽ、ツメクサ、ヒメジョオン・・・札幌の植物の記憶は鮮明です。小学校2年生までしかいなかったのにね。

ハナズオウ(花蘇芳) マメ科。
ひとつひとつの花をよく見れば、マメ科の花です。でも、遠目には、ピンクのぷつぷつがいっぱい。

ボタン(牡丹) ボタン科。
前は確か、キンポウゲ科だったのですが、ボタン科ができたようです。植物たちの科は、今も研究が進むにつれ、変わっていきます。

八重桜 バラ科。
小学校のころ、作った、薄紙の花のような花弁たち。ひらひらと薄くはかなく、でも、まだしっかりと木についています。
夜、お酒を飲んだ夫(マルオ)を迎えに行ったついでに、温泉にはいってきました。市内に温泉が二ヶ所。市営の桜の湯のほうが近いのですが、今日は、利楽温泉です。ここの特徴は、広い露天風呂(西日本一だとか?)と、夜12時まで営業している便利さです。
いつものように歩行浴で、まじめに歩いていると、ちょうど対角線を歩く二人の会話が聞こえてきました。「男湯の歩行浴はこの三分の二くらいしかないんよ。」「それ、目がまう(まわる)。」「岩風呂も小さいし。」「そうなん。」「サウナもな、せまいんじゃけん。」「おんなじ料金払っているのになあ。」「男、気の毒じゃなあ。」・・・会話は、近づいたり、遠のいたりして、果てしなく続いていました。聞くともなく聞いていた(いえ、聞こえてしまうのです。声が大きいので。)私は、途中で、あれ?と気がつきました。何でこの人、男湯のこと、詳しく知っているんだろう??
たぶん、この温泉に勤めていた方なのでしょうね。普通は、男湯ははいれませんもの。そういえば、消防士をしている友人が、温泉から救急の要請があったときの話をしていたことがあります。男にとって女風呂は聖域で、むしろロマンの対象だったそうなのですが、実際はいってみたら、裸のおばちゃんたちに「どしたん(どうしたの)?」「どしたん?」と囲まれて、長年の夢が崩れ去ったとか。あ、倒れた方は貧血程度でたいしたことはなかったそうです。ちゃんと、救急のお仕事をしてからの話です。
広い露天風呂からはぼんやりと、春の星が見えます。いつものように、人魚のポーズで星を仰ぎます。(はは。夜中は人が少ないのです。)
 ←こちらをポチっと押して頂くと、うれしいです。応援ありがとうございます。
←こちらをポチっと押して頂くと、うれしいです。応援ありがとうございます。
 大切な方にお花を贈りませんか。お花のネットショップです。
大切な方にお花を贈りませんか。お花のネットショップです。

![]() ← ← ← いつも応援ありがとうございます。励みになります。
← ← ← いつも応援ありがとうございます。励みになります。

























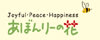

 州浜紋
州浜紋
















