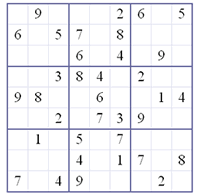ついにこの前、ポリスカーに後からランプを照らされ、道端に止めさせられました。
別に悪いことをしてた分けじゃなくて、抜き打ち飲酒運転検査だったんだけど。
こっちは昔ディスカバリーチャンネルで見てたアメリカ版警察24時で、マッチョな警察官が運転手を地べたに引きずり下ろしてる図が頭に焼きついてたので、停められてから警察官が出てくるまで結構ヒヤヒヤしてたよホント。
そうしたら女性の警察官二人が出てきて免許証のチェックと飲酒運転のチェックをされただけだったんだけどね。
まぁ大晦日で深夜12時過ぎてたので、まぁそういうこともあるのかという感じ。
後日聞いた話では、 あの警察官=怖い というイメージは実はオーストラリアでは皆無らしく、基本的に市民の言い分を聞いてくれる優しい存在らしい。
で、アメリカ映画とかを見てると、警察官に向かって皆"Sir"や"Ma'am"と敬称で呼ぶけど、こちらでは普通は付けない。むしろ付けると喜ばれて大目に見てくれることもあるとか無いとか。
そのついでに思いだしたけど、よく高速道路を走っていると、道端に車が乗り捨てられてるのを見かける。
これは、飲酒運転とかスピード違反で捕まって、免許停止や無効になった場合、オーストラリア(少なくともビクトリア州)では車を運転する権利がその場で剥奪される。
つまり、捕まったらその場で車を乗りすててバスかタクシーかで帰らないといけないというワケ。
この場合、パトカーに乗せて貰えるという選択肢は無く(知り合いに連絡を取らせてくれるらしいけど)、どんな田舎だろうが時間帯だろうが、気合で自力で帰らなきゃいけない…
論理的には正しいけど、厳しい仕打ちだよなぁ。
別に悪いことをしてた分けじゃなくて、抜き打ち飲酒運転検査だったんだけど。
こっちは昔ディスカバリーチャンネルで見てたアメリカ版警察24時で、マッチョな警察官が運転手を地べたに引きずり下ろしてる図が頭に焼きついてたので、停められてから警察官が出てくるまで結構ヒヤヒヤしてたよホント。
そうしたら女性の警察官二人が出てきて免許証のチェックと飲酒運転のチェックをされただけだったんだけどね。
まぁ大晦日で深夜12時過ぎてたので、まぁそういうこともあるのかという感じ。
後日聞いた話では、 あの警察官=怖い というイメージは実はオーストラリアでは皆無らしく、基本的に市民の言い分を聞いてくれる優しい存在らしい。
で、アメリカ映画とかを見てると、警察官に向かって皆"Sir"や"Ma'am"と敬称で呼ぶけど、こちらでは普通は付けない。むしろ付けると喜ばれて大目に見てくれることもあるとか無いとか。
そのついでに思いだしたけど、よく高速道路を走っていると、道端に車が乗り捨てられてるのを見かける。
これは、飲酒運転とかスピード違反で捕まって、免許停止や無効になった場合、オーストラリア(少なくともビクトリア州)では車を運転する権利がその場で剥奪される。
つまり、捕まったらその場で車を乗りすててバスかタクシーかで帰らないといけないというワケ。
この場合、パトカーに乗せて貰えるという選択肢は無く(知り合いに連絡を取らせてくれるらしいけど)、どんな田舎だろうが時間帯だろうが、気合で自力で帰らなきゃいけない…
論理的には正しいけど、厳しい仕打ちだよなぁ。