ヘーゲル『哲学入門』 中級 第二段 自己意識 第三十六節 [恣意の否定と真の服従]
§36
Der eigene und einzelne Willen des Dienenden, näher betrachtet, löst sich aber überhaupt in der Furcht des Herrn, dem inneren Gefühle seiner Negativität, auf.
第三十六節[恣意の否定と真の服従]
しかし、一般的に従僕自らの固有の意志は、よりくわしく見てみると、主人に対する恐怖の うちに、つまり従僕のうちにある否定的な感情の中に消えてしまっている。
Seine Arbeit (※1) für den Dienst eines Anderen ist eine Entäußerung (※2)seines Willens_ teils an sich, teils ist sie zugleich mit der Negation der eigenen Begierde die positive Formierung der Außendinge(※3) durch die Arbeit,
他者に奉仕するための従僕の「労働」は、それ自体が彼の意志の「外化」であると同時に、彼自身の欲望を否定することであって、その労働を通して積極的に「外部に事物を形成」することでもある。
indem durch sie das Selbst seine Bestimmungen(※4) zur Form der Dinge macht und in seinem Werk sich als ein gegenständliches anschaut.
そうすることによって、従僕自身は自らの内的な思いを物の形にまで作り上げ、そうして自分の作品の中に自分自身を一つの客観物として直観するのである。
Die Entäußerung der unwesentlichen Willkür macht das Moment des wahren Gehorsams aus. (Peisistratos (※5) lehrte die Athenienser gehorchen. Dadurch führte er die Solonischen Gesetze in die Wirklichkeit ein und nachdem die Athenienser dies gelernt hatten, war ihnen Herrschaft überflüssig.)
本質的でもないところの恣意を 捨て去ることは、真の服従のために不可欠の要素である。(ペイシストラトスはアテナイ人に服従を教えた。そうしてから彼はソロンの法律を実際に採用した。そうしてアテナイ人が服従を学んだ後は、もはや彼らに支配権力は余計なものになった。)
※1
die Arbeit
前三十三節でそれぞれの自己意識の間に存在する不平等から主人と従僕の関係が必然的に生じ、そこに奉仕や服従が生まれるが、従僕は奉仕のために 労働 に従事することになる。
※2
die Entäußerung
「Entäußerung」もともとドイツ語で「外に投げ捨てる」という意味。
動詞「entäußern」「外部に表す」「(権利や所有権を)放棄する」
従僕は奉仕のための労働を通して、自己の意志や所有権を放棄する。これがこの文脈でヘーゲルが用いた「Entäußerung」の意味である。この労働、すなわち自己の「Entäußerung(外化・疎外)」を通して、個人がどのような事物にどのようにして自己を捧げるか、あるいはそのことで自己を喪失するか、また、それによってどのように他者に対して、社会や国家に対して関わっていくかなど、重要な問題が含まれている。
ちなみに、マルクスはヘーゲルからこの「Entäußerung」の概念を受け継ぎ、労働者が自らの労働力を資本家に売却することをもって、労働者が自己を「Entäußerung(疎外)」するとした。そしてこのことを、いわゆる「資本主義」の根本原理の一つとして捉え、この労働者の「疎外」の克服を社会主義運動の目的とした。
確かにマルクス主義には、そうした部分的な真理と意義は含まれているとしても、しかし総体としては、その目的を実現する手段として「プロレタリア独裁」を主張した点において、この思想と哲学はすでに歴史的にも理論的にも破綻している。
「樹の善し悪しは、その樹の結ぶ実によってわかる。」(ルカ書6:43)という実証主義からもそのことは明らかである。
「Entäußerung(疎外)」の概念については、また別個にさらにくわしく考察する機会があると思う。
※3
die positive Formierung der Außendinge
その労働を通して積極的に「外部に事物を形成」する。
画家や彫刻家はその芸術作品の創造によって、自己の内部の思い「Bestimmung」を、その美や理念を、作品として外部に形成する。
トヨタ自動車は、その企業の従業員の労働を結集して、「レクサス」という自動車(Bestimmung)を商品として完成させる。
哲学者は自己の使命「Bestimmung」を国家において実現する。
内なる「Bestimmung」は「Entäußerung(外化)」される。
※4
seine Bestimmungen
「Bestimmung」「目的」「使命」「役割」「定め」
「bestimmen」動詞「定める」「決定する」
「Bestimmung」は、個人が達成すべき目的や使命、役割を意味する。
人生の意味や目的について考察する際に必要な概念で、哲学や宗教において重要な意義をもつ。「Bestimmung」の概念については、これまでの註解においても、繰り返し取り上げてきた。
※5
Peisistratos ペイシストラトス
ペイシストラトス(Peisistratos、紀元前600年頃 - 紀元前527年頃)は、古代ギリシャのアテナイで重要な役割を果たした政治家。
「本質的でもないところの恣意を捨て去ること(die Entäußerung)は、真の服従のために不可欠の要素である。」
「自我」を捨て去る(die Entäußerung)ことは、他者との関係の中で、労働を通して自己意識が自己を見つけるために経験する過程である。個人は他者との関係の中で自己を見つけ、自己を実現する。
現代日本の教育の根本的な欠陥は、真の自己実現のために、「自我」を捨て去る(die Entäußerung)こと、「本質的でもないところの恣意を捨て去ること、真の服従」を教えないことである。その結果として「クズ的人格」が日本人に生まれてくる。
ペイシストラトス - Wikipedia https://is.gd/dIEdWA












![ヘーゲル『哲学入門』 中級 第二段 自己意識 第三十一節 [自己と他者の自由について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1a/f5/817b90d3f8ac7b90d39847a479009217.jpg)
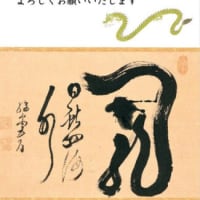
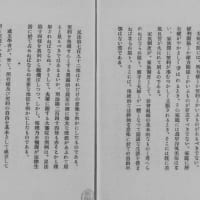

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)

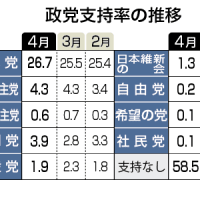










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます