
ルターは、当今流行のいい加減な、軽薄短小の大学(院)教授輩と、比べ物になりません。
Young Man Luther 『青年ルター』p200の第2パラグラフ9行目途中から。
ルターは自分の気まぐれを隠しませんでした(「私は単純に、抽象アブストラクトと具体コンクリートで、韻を踏みました」)し、時に使う力技を隠しませんでした。「堅い殻だと分かるテキストにできることと言えば、その殻を岩にぶつけることです。そうすりゃぁ、一番柔らかい核(nucleum suavissimum)がでてくるよ」。ルターはこういった言葉に欄外に記しを付けて、悦びました。ルターの誠実さは、スコラ哲学の神学者輩の洗練された気まぐれとも、信頼と理性の違いを正当化するお決まりの方法とも、全く異なるものでした。ルターの気まぐれは、現場に役立つ講義の一部ですが、玉石混淆なのは火を見るよりも明らかです。
ルターの講義に、「荒い斑点や光沢」があったんじゃぁない。西平さんの理解も「石、石、石、石…」という感じで、この程度です。ルターの講義は、玉石混交だったけれど、生きるのに役立った。本物は、そういうものです。薬にも毒にもなるもの。「御説ごもっとも」というものではなかった。
















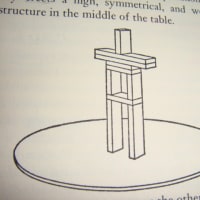











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます