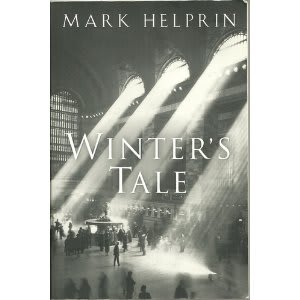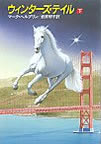・・屋さんを映画で観てきた。
絵、とはいえ、まことにカラフルで、ブリリアントなお寿司達と回転する灯籠のような提灯照明の下にぶら下がった、あかいおとと(もちろん一緒に回っている)、がやたらと印象に残っています。
ゴカイマネキ回避の為に云っておきますと、お付き合いで、運転手兼財布として、ワタシの懐の深い理解力を発揮して来たのに過ぎません。
もっとも、愛着のあるキャラクターは居て、
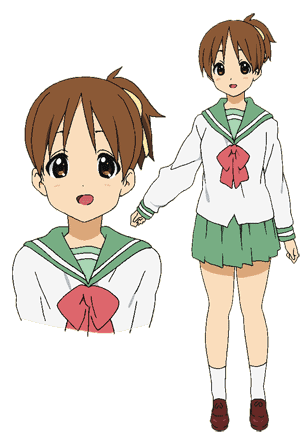 キングオブいもうと、無類のサポート能力と理解力と包容力を高次元で併せもつ、菩薩の顕現のようなキャラ、憂さまであります。
キングオブいもうと、無類のサポート能力と理解力と包容力を高次元で併せもつ、菩薩の顕現のようなキャラ、憂さまであります。
世の中の23%くらいが憂さまのようであったら、世界は平和、慈愛にあふれた人類社会が実現すること間違いなし、なのです。
ハナシはかわって、映画料金が世界一高いと云われる日本ですが、もっと高いのが、飲食物持込禁止の映画館にあって暴利を貪りつくしている売店、ポップコーンやら、コーラやら、ぽてとやら、チュロスやら、を超高嶺で売り付けている悪徳機関であります。
まともなコーヒーならたとえ紙コップでも一杯350円してもおかしくないと思うのですが、コーラとポップコーンのセットが750円なんて、公取委が摘発しないのがフシギです。
日本語を解し、アニメ文化に非常の造詣の深いガイコクジン(オタクガイジン)でも、上記のドリンク&フードの価格には全身全霊で抵抗するといいます。何故、排斥運動や焼き討ちが起こらないのか、一揆という日本の伝統文化は無くなってしまったのか、と憤慨しておられます。
まさに印度人も吃驚!です。
古式ゆかしいオチですみません。
絵、とはいえ、まことにカラフルで、ブリリアントなお寿司達と回転する灯籠のような提灯照明の下にぶら下がった、あかいおとと(もちろん一緒に回っている)、がやたらと印象に残っています。
ゴカイマネキ回避の為に云っておきますと、お付き合いで、運転手兼財布として、ワタシの懐の深い理解力を発揮して来たのに過ぎません。
もっとも、愛着のあるキャラクターは居て、
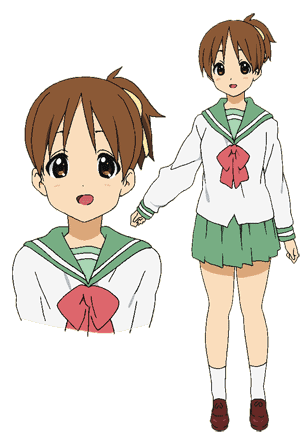 キングオブいもうと、無類のサポート能力と理解力と包容力を高次元で併せもつ、菩薩の顕現のようなキャラ、憂さまであります。
キングオブいもうと、無類のサポート能力と理解力と包容力を高次元で併せもつ、菩薩の顕現のようなキャラ、憂さまであります。世の中の23%くらいが憂さまのようであったら、世界は平和、慈愛にあふれた人類社会が実現すること間違いなし、なのです。
ハナシはかわって、映画料金が世界一高いと云われる日本ですが、もっと高いのが、飲食物持込禁止の映画館にあって暴利を貪りつくしている売店、ポップコーンやら、コーラやら、ぽてとやら、チュロスやら、を超高嶺で売り付けている悪徳機関であります。
まともなコーヒーならたとえ紙コップでも一杯350円してもおかしくないと思うのですが、コーラとポップコーンのセットが750円なんて、公取委が摘発しないのがフシギです。
日本語を解し、アニメ文化に非常の造詣の深いガイコクジン(オタクガイジン)でも、上記のドリンク&フードの価格には全身全霊で抵抗するといいます。何故、排斥運動や焼き討ちが起こらないのか、一揆という日本の伝統文化は無くなってしまったのか、と憤慨しておられます。
まさに印度人も吃驚!です。
古式ゆかしいオチですみません。