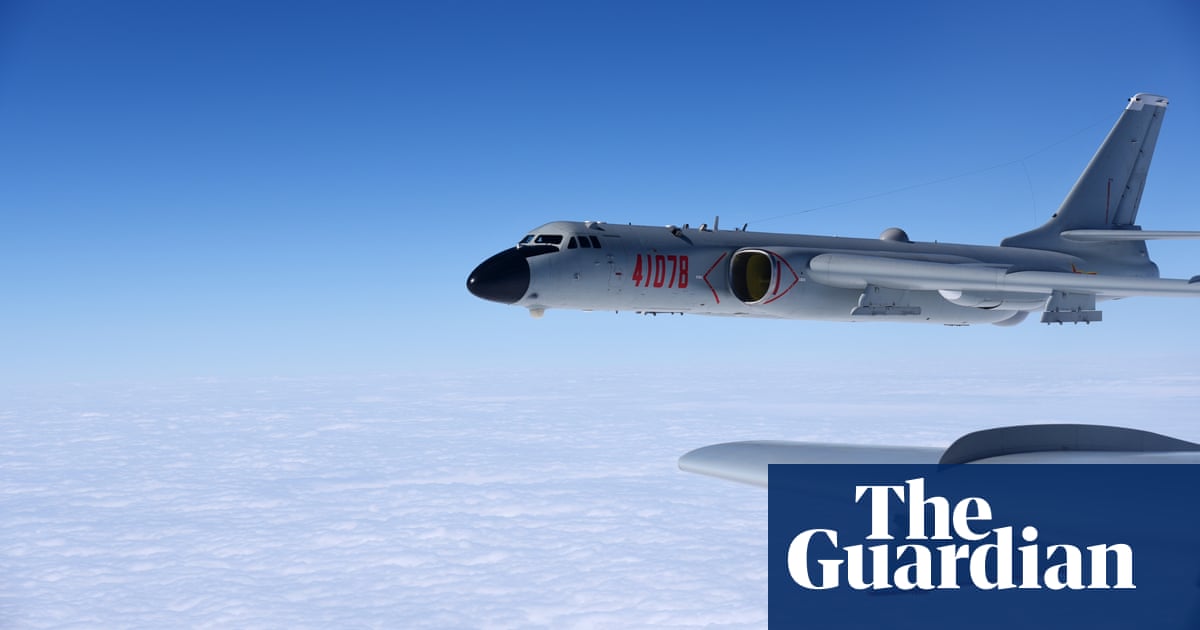ここ数年の「文春砲」のスクープは目を見張るものがある。昨年は、東京高検検事長の黒川弘務の朝日、産経の新聞記者との賭け麻雀、今年になってからは、菅首相の長男、東北新社社員菅正剛の総務省幹部への接待、東京五輪演出責任者佐々木宏の女性芸能人容姿侮辱、その他政治家、高級官僚の関連企業との会食等を立て続けに報道している。勿論、「文春砲スクープ」は政治家や高級官僚だけでなく、数としては芸能人の不倫等の方が多いのだが、与える影響の大きさが比べ物にならないのだ。これらの政治的なスクープは、内閣支持率を押し下げる大きな要因になっているからだ。仮に、これらの記事が赤旗に載ったとしても、誰も驚かないだろう。実際に、赤旗は「桜を見る会」をスクープしたからだ。上にあげた最新号も菅首相や政府が強行開催を目論む五輪への痛烈な打撃となるのは、否めない。
ここ数年の「文春砲」のスクープは目を見張るものがある。昨年は、東京高検検事長の黒川弘務の朝日、産経の新聞記者との賭け麻雀、今年になってからは、菅首相の長男、東北新社社員菅正剛の総務省幹部への接待、東京五輪演出責任者佐々木宏の女性芸能人容姿侮辱、その他政治家、高級官僚の関連企業との会食等を立て続けに報道している。勿論、「文春砲スクープ」は政治家や高級官僚だけでなく、数としては芸能人の不倫等の方が多いのだが、与える影響の大きさが比べ物にならないのだ。これらの政治的なスクープは、内閣支持率を押し下げる大きな要因になっているからだ。仮に、これらの記事が赤旗に載ったとしても、誰も驚かないだろう。実際に、赤旗は「桜を見る会」をスクープしたからだ。上にあげた最新号も菅首相や政府が強行開催を目論む五輪への痛烈な打撃となるのは、否めない。
また、総合誌の文藝春秋4月号では、「マルクス『資本論』が人類を救う」という記事を載せている。これは、マルクス関連本である斎藤幸平「人新世の『資本論』」がベストセラーになっていることから挙げられた記事なのだが、左派の核心的思想のマルクスを記事にすることは、やはり画期的と言える。
文春は「パヨク」?
「パヨク」とは、所謂ネトウヨが使う左派という意味の言葉である。(勿論、ネトウヨには彼らの未熟な知識量から左派の定義づけなどできるわけもなく、「反日」と同様に、彼らと異なる意見を持つ者に対する否定的、かつ侮蔑的な意味を込めての言葉である)この言葉どおり、文春、パヨク(左翼)でネット検索すると、文春は左傾化したという記事が多くみられる。確かに、文春や文藝春秋は以前と比べれば、政権批判の記事が増えているのは、間違いない。しかしそれが、際立って見えるのは、ライバルである新潮社が、「新潮45」が性差別記事で廃刊の憂き目に遭ったように極右路線を変えていないことが大きい。
もともと、文藝春秋社も新潮社も文芸を中心とした総合出版社なのだが、政治的には、大雑把に言って、自民党に近い穏健な保守の立ち位置にあった。それは、読者には自民党支持層が相対的に最も多く、その立場でいることが、経営上好ましいという判断であったと推測できる。しかし、かなり前からの出版不況に加え、近年の紙媒体からデジタル媒体への情報移動のせいで、出版物の経営自体が行き詰まり、それが今までとは別の立ち位置を模索せざるを得なくなったのである。今までの保守層中心から、文藝春秋社は「リベラル」と左派を取り込むことを選択し、新潮社はデイリー新潮で分かるとおり(最新版では、立憲の蓮舫議員への攻撃記事を一番に持ってきている。)極右路線を突っ走る姿勢を鮮明にしたのである。
実際には、文藝春秋社の出している雑誌に保守の立ち位置の記事が消えたわけではなく、保守層も読者としてそのまま維持したいというのが本音だろう。しかし、今までより政権批判の記事を増やしたので、それが目立っているのが実情である。今のところ、読者層拡大する目論見は功を奏して、読者層を拡大しているように見える。スクープの載った文春は売り切れが出ている。その理由の一つが、紙媒体であれデジタル媒体であれ、読者層に左派まで翼(ウイング)を広げているものが少ないからと考えられる。
例えば、新聞でも右傾化しつつある朝日新聞は自公政権批判を弱め、全面的に批判するのは、中国、ロシア、ベトナムなど「権威主義」体制の国である。これは「権威主義国」を批判するから右傾化なのではなく、自国の民主主義の問題を看過し、真っ先に、他国を批判する姿勢が右傾化なのである。コロナ危機においても、朝日新聞が真っ先に批判したのは、日本政府の無能ぶりではなく、中国の強権的コロナ対策だった。(未だに、極右勢力が朝日新聞を左派と見做すのは、恐らく熟読していないからだろう。)
また、紙媒体はもとより、デジタル媒体も右派真っ盛りで、ビジネスオンラインと名前がつくサイトはほぼ右派のコメントであふれている。やや左派色があるのは、日刊ゲンダイや週刊金曜日ぐらいである。
国民の大多数が自公の支持者というわけではないこととは、言うまでもない。むしろ、政権に批判的な国民は過半数を超えている。右派が圧倒的に多いメディアの中で、文春のように「リベラル」や左派層までに読者層を広げる姿勢が受け入れられるのは、極めて自然である。その内、第二、第三の文春砲が現れるだろう。