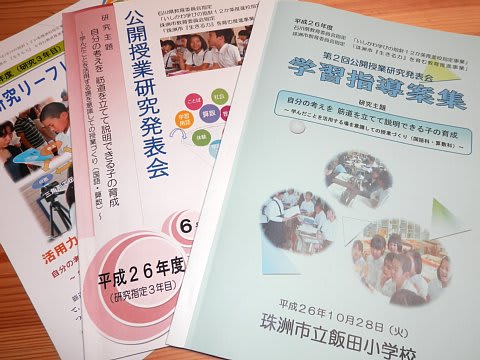
県教委と珠洲市教委の指定研究に取り組んできた飯田小の3年目の研究発表会を参観させてもらう。
研究主題は「自分の考えを筋道を立てて説明できる子の育成」。
まずは4年生の算数と5年生の国語の公開授業だ。
4年生は8人、5年生は16人のクラス。
いずれの授業でも驚くのは、どの子も自分の意見を「考え・理由・根拠」というふうに筋道立ててはっきり話すことだ。
飯田小ではこれを三角ロジックと言っている。
大人でもこんなに論理立てて話す人は多くない。特に議員は

加えて45分の授業時間、どちらのクラスも全員がしっかり集中を切らさず参加できている。
自分の意見を言うだけではなく友だちの意見を聞く姿勢もできているからこそだ。
飯田小ではこうして身に付けた基礎の上に「単元丸ごと活用」という時間を設けて、他の題材や生活の場面で活かせる力をつける取り組みがある。
さらにもう一つ、100文字「言葉のスケッチ」で表現力を高めている。
飯田小だけではなく他の学校でも学びの基礎的な型がある。
先生側にも教える型がある。
そこには校長・教頭の明確な指導方針や先生らの日々の努力の積み重ねがあり、その成果として子どもらの表現力や思考力が着実についていることは間違いないだろう。
だけど昔の学校のイメージから抜けられない私などは、もっとバラバラで個性豊かな子がいた方がおもしろいけどなぁと思うが無理な話か・・・。
さて、公開授業後は参加した各学校の先生が二つの教室に分かれての分科会。
参観の感想や意見交換をしたあと、先生を生徒に見立て「単元丸ごと活用」の模擬授業、そして指導主事からの助言。
こんなふうにレベルアップを重ねているのかと、私のような初めの参観者にもわかる流れだった。
締めくくりは全体会。
印象的だったのは大宮校長先生の閉会のあいさつ。
一つは今後も「凡事徹底」でいくとのこと。
もう一つはあくまで授業が勝負で「授業で活用力をつける!」との決意表明。
・・・過去問を繰り返しやっても本当の「活用力」はつかないということ。
奥能登教育事務所長や珠洲市教育長を前に堂々と言えるのはたいしたもの。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます