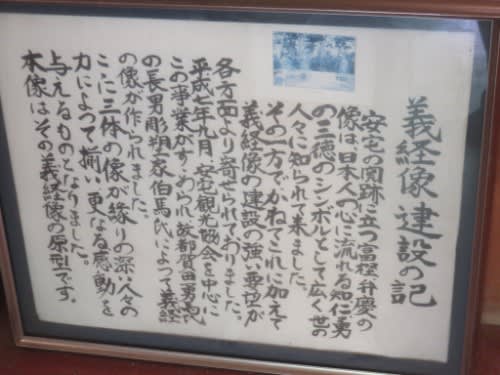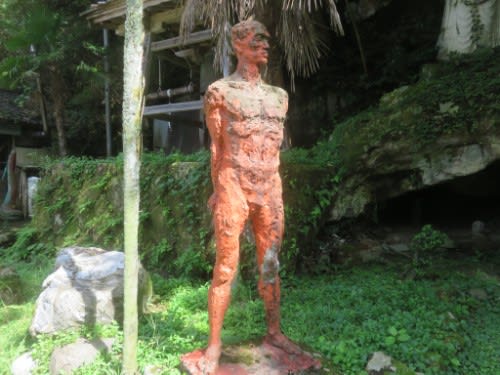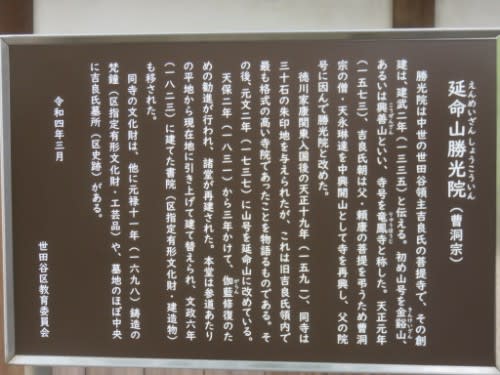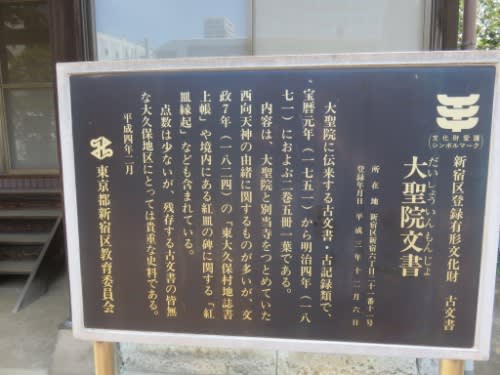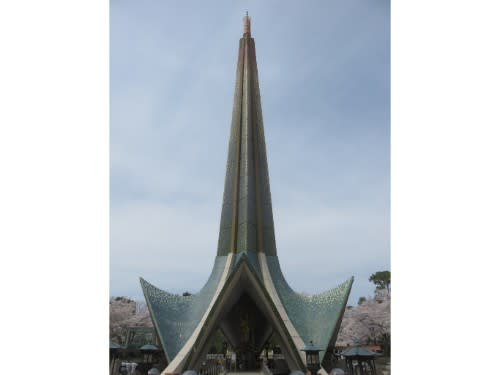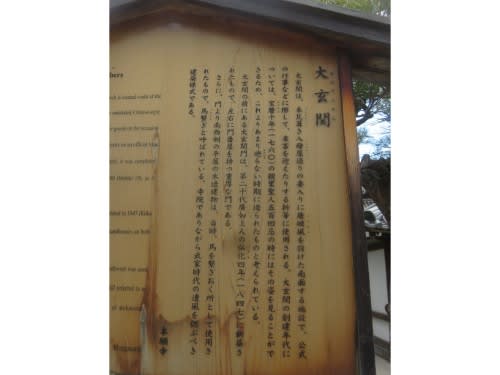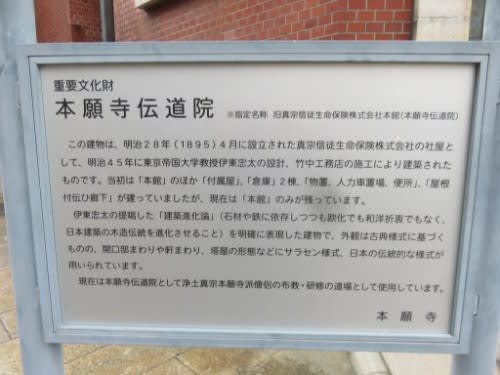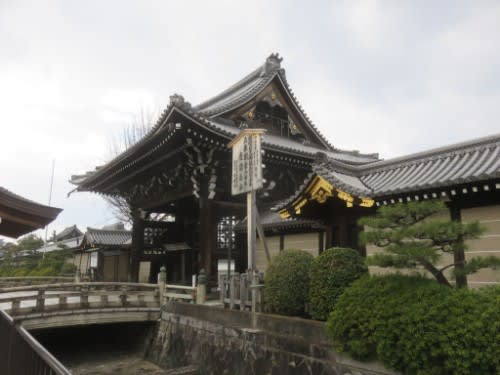こちらがメインの洞窟の入口です。
お寺の入口に必ずいらっしゃる魔を寄せ付けない仁王像。
これはかなり力作で良い作品でした。
あ、作品と言ったらアカンか。(笑)
【洞窟内】

おー、これはなかなか立派な洞窟やん。
もっと狭いかと思ってたけど本格派です。
期待は高まりますね。
【夢牛】

初代院主が夢で見た牛だそうです。
この牛は後に続く阿鼻叫喚の世界の軽いジャブです。
とても可愛いです。(笑)
【大黒天】


外は結構暑かったけど洞窟内はさすがに涼しい。
【銅像】

修験者と奉行様でしょうか。
これはよく分かりませんでした。
というか何でもありですね。
【釈迦一代記】


ここはお釈迦様ゾーンになります。







このレリーフはなかなかの力作だと思います。
しかしお釈迦様最期の涅槃が無いのが残念ですね。
【釈迦誕生仏】


これは顔というか目が怖すぎですね。
【仏像】


【鬼子母神】



【平和地蔵】


【洞窟内】

あの後ろ姿はスーパースターの阿修羅像じゃないですか。
【薬師瑠璃光如来】


【招き猫】

こんな所に場違いな。(苦笑)
【初代院主】
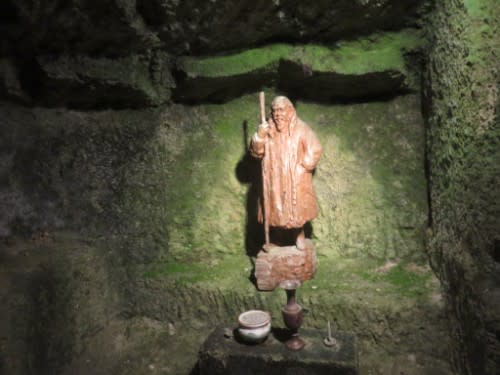
【阿修羅像】



興福寺の阿修羅像の慈悲ある何とも言えない表情とは全然違う。
あの表情だからこそみんなが惹きつけられるんですよね。
【胸像】

誰?
【ドア】

あのドアの先に何か恐ろしい目に見えない異形のモノがいそうで、
さすがにドアを開けませんでした。(号泣)
【彫刻】

ウサギやら仏頭等が安置されていました。
何か常人が分からないコンセプトがあるのでしょうか。

現代アートの走りでしょうか。(^^;
【仏頭】


何ともいえない顔をされています。
【牛頭】

【少年地蔵尊】


少年の地蔵尊は初めて見ました。
まぁ、何でもありです。(笑)
【仏像】

【仏頭】

【ヤクシニー像】





えーと、これは芸術なんでモザイクはかけません。(笑)
【獅子】

【ミトゥナ像】



ヒンドゥー教寺院の建築外観によく掘られるそうで、
インドの宗教は極端に禁欲苦行者がいる一方、
豊潤なエロティシズムの追求も重要とのこと。
勉強になります。(笑)
【石像】


女性の像ですね。


これもヒンドゥー教の影響が色濃く表現された石像です。

この踏まれているのは日本でいう餓鬼でしょうか。
【ミトゥナ像】


エロ表現極まれり。
凄い作品ですね~。
逆さまになっている男は女のアソコを触っているし。(^^;
浄土真宗ならいざ知らず、禅宗の僧侶が見たら卒倒しますね。



こちらもなまめかしい表現です。(^^;

これもよく見れば強烈です。
向かって右側はシックスナインをしてるし、
真ん中は正常位でヤってるし、左側はバックでヤってます。
昔の人もシックスナインやバックでヤってたのか。
うん、勉強になります。(笑)

これにてエロゾーン終了。
ここは子供と来たらアカンやつ。(笑)
【裸婦像】

これが普通に見えてくるわ。(笑)
エロゾーンの次は地獄ゾーンになります。
次回まで少々お待ちを。