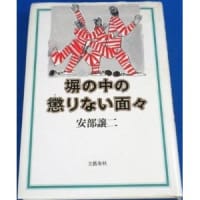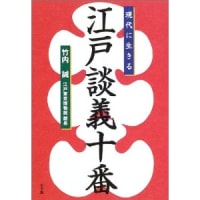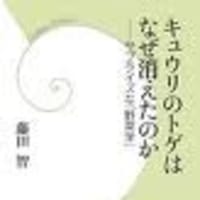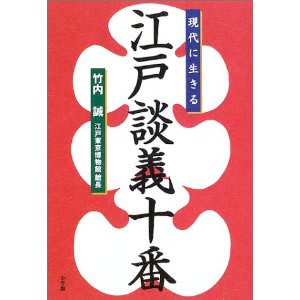
【現代に生きる江戸談義十番】竹内 誠 ・編 小学館江戸談義十番
江戸東京博物館には仕事を含め何回か行っている。その館長さんが江戸について造詣の深い面々と対談したものをまとめた。面白かった。
その中からいくつかを自身の記憶メモとして残したい。
拙稿ブログにメモを残すのはなによりも自分のため。
リタイア生活に入ると5年前の読書感慨などすっかり忘れるものが多い。
だが、こちらは忘れてもブログのほうは覚えていてくれる。
ブログとは必携の生活小道具であると実感することが多い日々となってきた。
■■ 花開いた江戸文化(江戸と上方(森谷尅久)
● 宵ごしの名のほうをとる見栄っ張り
大阪のほうでは「カネにこだわらずに何にこだわるのや」
「大阪の人気は京都四分江戸六分」と馬琴は言っていたと。けちではない。
江戸っ子のほうは、見栄のかたまりとなる。
● 着倒れをするほどおなごもの買わず
江戸の食い倒れ京都の着倒れというが実態はどうか。
西陣の町ではそんな高価なもんは京女は買わない。
収入以上は絶対に使わないケチというかしっかり者が多い風土。
理想的な商家像とは
「主人大阪 嫁は京都 番頭は近江 蔵番は長崎 小僧は江戸」
だとその家はうまくいくそうだ。
● 先斗町 祇園、七条みな廓
これらは島原が全部支配していた
「島原の女郎 江戸の心意気 長崎丸山の衣装を着せ 大阪の揚屋で遊ぶ」
もうひとつのこの時代の男の理想郷。
● 十年づつ大火生まれて急成長
早稲田辺りから出火するとほぼ江戸は丸焼けになったそうだ。
そのたびに復興需要が生まれその都度江戸は発展した。
● 盛り場のハレの世界に足が向き
江戸の盛り場は火除け地、広小路、寺社境内。
浅草・奥山もそうした流れだ。
見世物、芝居小屋、非日常、異界性がある中に猥雑さもある。
戦後の浅草六区界隈にもそうした空気が育って今日まで受け継がれてきた。
唐獅子牡丹の二番がふいと湧いてきた。
(二)親の意見を 承知ですねて
曲がりくねった 六区の風よ
つもり重ねた 不幸のかずを
何と詫びよか おふくろに
背中で泣いてる 唐獅子牡丹
● 非番の日 名所も見たく盛り場も
大藩は3000人から5000人の勤番侍が江戸邸内に在住している。
小藩は数百人の規模。
藩の数は二百数十藩あったそうだから、非番の日はにぎわう筈だ
『幕末単身赴任 下級武士の食日記』
青木直己著 生活人新書 という本があるのを知った。一度読んで見たい。
■■江戸文化の台座浅草寺(清水谷孝尚)
● 天海の進言で将軍祈願所に
浅草の地は古代~中世も交通の拠点であり、もともと民衆信仰の下地があった。
家康の頃、天海が将軍の祈願所として定め、徳川家と浅草の親密な関係は
綱吉の時代まで続いたらしい。
御三家、大名から庶民まで誰でも拝みにやってくる。
● 住職は寛永寺からの天下り
貞享2年(1685)浅草寺は寛永寺の末寺となる。
以後、住職は寛永寺からやってくる
現存する「浅草寺日記」は当時の社会文化を探る貴重な史料とのこと。
● 仲見世は床見世という軒を貸し
元禄の頃、浅草寺掃除賦役の肩代わりとして、朝持ってきて夕方片付けを条件として、仮設の床見世ができた。
これが現在の仲見世の礎となっているそうだ。
★ おおたわけ茶店で腹を悪くする /川柳
浅草仁王門に手前に二十軒茶屋が誕生。
水茶屋となって、きれいな女が茶を運んで世辞を言うから鼻の下が伸びた連中が通う。
何杯もオカワリをし、おおたわけ誕生。
★ 補陀楽の地より極楽北に見え/川柳
この川柳よくできている。
浅草寺近くは田圃。
この浅草たんぼから吉原は丸見え、観音さまの裏にあった。
私はこの正月、カミさんと浅草七福神へ行ったので鳳神社や吉原神社も参拝した。
★女房と雷門で出っくわし/川柳
観音さまへお参りに来たはずの亭主が吉原に向かう途中に雷門でバッタリ女房とであった。とっちめられる亭主の顔が浮かんでくる。
浅草は裏の吉原と聖俗が隣あわせになっている場所だ。
● ありがたや四万六千日御参り
この日にお参りをすると四万六千日分、年数でいけば126年分の功徳があるという。
雷除けの札が渡され「ほおずき市」も立った
桂文楽は「船徳」を演じるまくらで「四万六千日(しまんろくせんにち)――お暑いさかりでございます」の一言だけで、江戸の暑さを語った。
● すりこ木や手桶も売られ歳の市
12月17日、18日の羽子板市の元風景は生活用品の歳の市だったとのこと。
● 坂東の13番目が浅草寺
観音巡礼のピークは元禄期、享保から宝暦の時代、文化文政期がピークだった。
秩父は23箇所があるが狭いところに固まっているから巡礼も二泊三日の旅程で済む
■■ 江戸庶民の暮らし(豊かな江戸庶民の心(山本一力)
● 下町という語は出ない深川史
「深川区史」という本が面白そう。
会社の図書課にも東京の各区史とともにこれも残っていた記憶がある。
● 水の都 辰巳芸者のきっぷよさ
深川は材木の流通を扱う水の都。
「意気」と「張り」を看板にし、舞妓・芸妓が京の「華」なら、辰巳芸者は江戸の「粋」の象徴とたたえられる。
● 不快などあたえぬものが粋と意気
辰巳芸者の意気が粋にもつながっていく。
「おたがいさま」の限度を越えるのは野暮のかたまりとバカにされた。
● 江戸時代 京都に出向くに14日
やじきた道中でいけば京までは14~15日の日程
現在、「のぞみ」でいけば2時間チョイでいける。
それまでは京都までは出張1泊だったが、今の勤め人は日帰り出張などとなって少し辛い。
■■ 江戸の時代的特色と学ぶべき知恵(石川英輔)
● 石高で仕切られていた登城部屋
石高制度が国力財政の基本。
江戸城に上がっても、石高がランクづけとなって広間や部屋が決まっていた。
● 浅葱裏 春夏秋冬 見て廻り
国許から江戸藩邸に詰めている侍。
非番の日は1年中 江戸を見て廻っている。
日本は260年間、イクサがない。徴兵されることもなかったから平和が続く。
川柳にも、
★ まかりこしさんと浅黄へ名を付ける
★ 女には御縁つたなき浅黄裏
などがみえる。
● 町奉行 支配3割農業地
35%は農地であって、なかには風光明媚な観光コースも含まれていた。
● いまはなき向こう三軒両隣
江戸にはあって今はない。
教育には家庭、学校と地域がそろって三位一体となっていた。
江戸から昭和30年ごろ迄の各地の町事情には地域で子どもを育てる向こう三軒の雰囲気がまだ残っていた。
● 坂の上 追っかけた雲 平成へ
「坂の上の雲」を追っていったらいまの時代になった。
これで、よかったか。
江戸っ子には錦絵、洒落本。川柳などの文化があった。
いまの東京っ子に自慢できるものありや、と編者は問う。
■■ 江戸時代は女性のイメージ(田中優子)
● 浮世絵を誕生させた元禄期
菱川師宣 杉村治兵衛ら
● 大名のお抱え力士が多くなり
寛政3年 江戸城内で上覧相撲
● 天保から回向院が定場所に
天保4年 両国橋東詰の広小路にあった回向院が大相撲の定場所となる。
● 吉原は悪所と文化とつなぎ役
先日見た「ぶらタモリ」でも吉原をとりあげ、文学や文化が育った馴染みの空間として位置づけていた。
● 連鎖窓通して差し込む陽のひかり
鎖国といってもいくつかの外窓はあった。
長崎ルート、対馬の宗氏が媒介した朝鮮ルート、琉球ルートからはフィリピンなどの情報が、松前ルートからはアイヌ、ロシアの物質や情報が入ってきていた。
田沼期にあった平賀源内的自由には関心がある。
大石 慎三郎 『田沼意次の時代』(岩波現代文庫)は従来の悪役像を一新していて面白かった。
大正時代に著わされた辻善之助の「田沼時代」も機会あれば読んでみたい。
■■江戸のおいしさ(杉浦向日子)
● 二食から三食になった吉宗期
コメ将軍の時代に人口はさして代わらずもコメ耕作面積は2倍となり収穫量は4倍になった。
● コメの値をあげるためには朝酒も
この頃、江戸の町の酒消費量はうなぎのぼり。
その酒はいま流行りのハイボールみたいなもので希釈したブレンドもの。
ほんとうの酒が欲しい場合は「生一本」を注文する。
江戸東京博物館には仕事を含め何回か行っている。その館長さんが江戸について造詣の深い面々と対談したものをまとめた。面白かった。
その中からいくつかを自身の記憶メモとして残したい。
拙稿ブログにメモを残すのはなによりも自分のため。
リタイア生活に入ると5年前の読書感慨などすっかり忘れるものが多い。
だが、こちらは忘れてもブログのほうは覚えていてくれる。
ブログとは必携の生活小道具であると実感することが多い日々となってきた。
■■ 花開いた江戸文化(江戸と上方(森谷尅久)
● 宵ごしの名のほうをとる見栄っ張り
大阪のほうでは「カネにこだわらずに何にこだわるのや」
「大阪の人気は京都四分江戸六分」と馬琴は言っていたと。けちではない。
江戸っ子のほうは、見栄のかたまりとなる。
● 着倒れをするほどおなごもの買わず
江戸の食い倒れ京都の着倒れというが実態はどうか。
西陣の町ではそんな高価なもんは京女は買わない。
収入以上は絶対に使わないケチというかしっかり者が多い風土。
理想的な商家像とは
「主人大阪 嫁は京都 番頭は近江 蔵番は長崎 小僧は江戸」
だとその家はうまくいくそうだ。
● 先斗町 祇園、七条みな廓
これらは島原が全部支配していた
「島原の女郎 江戸の心意気 長崎丸山の衣装を着せ 大阪の揚屋で遊ぶ」
もうひとつのこの時代の男の理想郷。
● 十年づつ大火生まれて急成長
早稲田辺りから出火するとほぼ江戸は丸焼けになったそうだ。
そのたびに復興需要が生まれその都度江戸は発展した。
● 盛り場のハレの世界に足が向き
江戸の盛り場は火除け地、広小路、寺社境内。
浅草・奥山もそうした流れだ。
見世物、芝居小屋、非日常、異界性がある中に猥雑さもある。
戦後の浅草六区界隈にもそうした空気が育って今日まで受け継がれてきた。
唐獅子牡丹の二番がふいと湧いてきた。
(二)親の意見を 承知ですねて
曲がりくねった 六区の風よ
つもり重ねた 不幸のかずを
何と詫びよか おふくろに
背中で泣いてる 唐獅子牡丹
● 非番の日 名所も見たく盛り場も
大藩は3000人から5000人の勤番侍が江戸邸内に在住している。
小藩は数百人の規模。
藩の数は二百数十藩あったそうだから、非番の日はにぎわう筈だ
『幕末単身赴任 下級武士の食日記』
青木直己著 生活人新書 という本があるのを知った。一度読んで見たい。
■■江戸文化の台座浅草寺(清水谷孝尚)
● 天海の進言で将軍祈願所に
浅草の地は古代~中世も交通の拠点であり、もともと民衆信仰の下地があった。
家康の頃、天海が将軍の祈願所として定め、徳川家と浅草の親密な関係は
綱吉の時代まで続いたらしい。
御三家、大名から庶民まで誰でも拝みにやってくる。
● 住職は寛永寺からの天下り
貞享2年(1685)浅草寺は寛永寺の末寺となる。
以後、住職は寛永寺からやってくる
現存する「浅草寺日記」は当時の社会文化を探る貴重な史料とのこと。
● 仲見世は床見世という軒を貸し
元禄の頃、浅草寺掃除賦役の肩代わりとして、朝持ってきて夕方片付けを条件として、仮設の床見世ができた。
これが現在の仲見世の礎となっているそうだ。
★ おおたわけ茶店で腹を悪くする /川柳
浅草仁王門に手前に二十軒茶屋が誕生。
水茶屋となって、きれいな女が茶を運んで世辞を言うから鼻の下が伸びた連中が通う。
何杯もオカワリをし、おおたわけ誕生。
★ 補陀楽の地より極楽北に見え/川柳
この川柳よくできている。
浅草寺近くは田圃。
この浅草たんぼから吉原は丸見え、観音さまの裏にあった。
私はこの正月、カミさんと浅草七福神へ行ったので鳳神社や吉原神社も参拝した。
★女房と雷門で出っくわし/川柳
観音さまへお参りに来たはずの亭主が吉原に向かう途中に雷門でバッタリ女房とであった。とっちめられる亭主の顔が浮かんでくる。
浅草は裏の吉原と聖俗が隣あわせになっている場所だ。
● ありがたや四万六千日御参り
この日にお参りをすると四万六千日分、年数でいけば126年分の功徳があるという。
雷除けの札が渡され「ほおずき市」も立った
桂文楽は「船徳」を演じるまくらで「四万六千日(しまんろくせんにち)――お暑いさかりでございます」の一言だけで、江戸の暑さを語った。
● すりこ木や手桶も売られ歳の市
12月17日、18日の羽子板市の元風景は生活用品の歳の市だったとのこと。
● 坂東の13番目が浅草寺
観音巡礼のピークは元禄期、享保から宝暦の時代、文化文政期がピークだった。
秩父は23箇所があるが狭いところに固まっているから巡礼も二泊三日の旅程で済む
■■ 江戸庶民の暮らし(豊かな江戸庶民の心(山本一力)
● 下町という語は出ない深川史
「深川区史」という本が面白そう。
会社の図書課にも東京の各区史とともにこれも残っていた記憶がある。
● 水の都 辰巳芸者のきっぷよさ
深川は材木の流通を扱う水の都。
「意気」と「張り」を看板にし、舞妓・芸妓が京の「華」なら、辰巳芸者は江戸の「粋」の象徴とたたえられる。
● 不快などあたえぬものが粋と意気
辰巳芸者の意気が粋にもつながっていく。
「おたがいさま」の限度を越えるのは野暮のかたまりとバカにされた。
● 江戸時代 京都に出向くに14日
やじきた道中でいけば京までは14~15日の日程
現在、「のぞみ」でいけば2時間チョイでいける。
それまでは京都までは出張1泊だったが、今の勤め人は日帰り出張などとなって少し辛い。
■■ 江戸の時代的特色と学ぶべき知恵(石川英輔)
● 石高で仕切られていた登城部屋
石高制度が国力財政の基本。
江戸城に上がっても、石高がランクづけとなって広間や部屋が決まっていた。
● 浅葱裏 春夏秋冬 見て廻り
国許から江戸藩邸に詰めている侍。
非番の日は1年中 江戸を見て廻っている。
日本は260年間、イクサがない。徴兵されることもなかったから平和が続く。
川柳にも、
★ まかりこしさんと浅黄へ名を付ける
★ 女には御縁つたなき浅黄裏
などがみえる。
● 町奉行 支配3割農業地
35%は農地であって、なかには風光明媚な観光コースも含まれていた。
● いまはなき向こう三軒両隣
江戸にはあって今はない。
教育には家庭、学校と地域がそろって三位一体となっていた。
江戸から昭和30年ごろ迄の各地の町事情には地域で子どもを育てる向こう三軒の雰囲気がまだ残っていた。
● 坂の上 追っかけた雲 平成へ
「坂の上の雲」を追っていったらいまの時代になった。
これで、よかったか。
江戸っ子には錦絵、洒落本。川柳などの文化があった。
いまの東京っ子に自慢できるものありや、と編者は問う。
■■ 江戸時代は女性のイメージ(田中優子)
● 浮世絵を誕生させた元禄期
菱川師宣 杉村治兵衛ら
● 大名のお抱え力士が多くなり
寛政3年 江戸城内で上覧相撲
● 天保から回向院が定場所に
天保4年 両国橋東詰の広小路にあった回向院が大相撲の定場所となる。
● 吉原は悪所と文化とつなぎ役
先日見た「ぶらタモリ」でも吉原をとりあげ、文学や文化が育った馴染みの空間として位置づけていた。
● 連鎖窓通して差し込む陽のひかり
鎖国といってもいくつかの外窓はあった。
長崎ルート、対馬の宗氏が媒介した朝鮮ルート、琉球ルートからはフィリピンなどの情報が、松前ルートからはアイヌ、ロシアの物質や情報が入ってきていた。
田沼期にあった平賀源内的自由には関心がある。
大石 慎三郎 『田沼意次の時代』(岩波現代文庫)は従来の悪役像を一新していて面白かった。
大正時代に著わされた辻善之助の「田沼時代」も機会あれば読んでみたい。
■■江戸のおいしさ(杉浦向日子)
● 二食から三食になった吉宗期
コメ将軍の時代に人口はさして代わらずもコメ耕作面積は2倍となり収穫量は4倍になった。
● コメの値をあげるためには朝酒も
この頃、江戸の町の酒消費量はうなぎのぼり。
その酒はいま流行りのハイボールみたいなもので希釈したブレンドもの。
ほんとうの酒が欲しい場合は「生一本」を注文する。