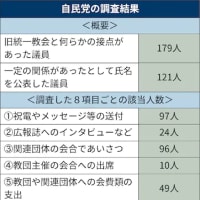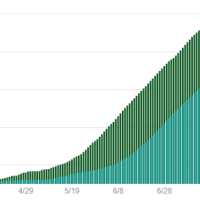二束三文で売られた人々
永禄9年(1566)2月、小田氏治の籠る常陸小田城(茨城県つくば市)は、上杉謙信の攻撃で落城した。落城直後、城下はたちまち人身売買の市場になったという。
その様子は『別本和光院和漢合運』に「小田城が開城すると、謙信の意向によって、春の間、人が20銭・30銭で売買されることになった」と記されている。この一文を読む限り、人身売買が謙信の指示に拠ることは明らかである。つまり、謙信の公認だったといえよう。おそらく城内には、周辺に住んでいた農民らが安全を確保するため逃げ込んでいたのだろう。戦争になると、農民らが城へ逃げ込むことは珍しくなかった。
ちなみに20銭といえば、現在の貨幣価値に換算して、たったの約2000円にすぎない(30銭は3000円)。おそらく、雑兵たちは相当な数の女・子供(あるいは男も)を生け捕りにし、奴隷商人を介して売ることにより、利益を得ていたのだろう。まさしく戦争に出陣する「旨み」であり、将兵にとって賞与のようなものだった。なお、城下での攻防戦で、人や馬が連れ去られた例はほかにも報告されている。
それにしても、20銭、30銭とはかなりの安値である。数が多いので供給過多となり、薄利多売になったのであろうか。フロイスの『日本史』によると、九州ではかなりの安値で売買された例が報告されている。売られた者は家事労働などに使役されるか、あるいはさらに転売されたのかもしれない。人身売買は、過酷な現実であった。また、連れ去られた人々は、金銭を負担することで買い戻されることもあった。
こうした人々は、城下で将兵自身によって売買されたか、あるいは奴隷商人を介して売られたのだろう。奴隷商人にとって、どれだけの利益があったのかは、残念ながら判然としない。戦場では武器や兵糧を取り扱う商人のほか、奴隷を売買する商人も存在した(両方を担当していたかもしれない)。つまり、戦場における人の連れ去りは、大袈裟に言えば、一種の商行為として彼ら商人の懐を潤わせていたのである。
大坂の陣における乱取り
乱取りは、以後の戦争でも止むことがなかった。徳川家と豊臣家の最終決戦の大坂の陣(慶長19年〔1614〕~同20年〔1615〕)でも、乱取りの実態を確認することができる。『義演准后日記』によると、慶長20年(1615)5月の大坂夏の陣で勝利した徳川軍の兵は、女・子供を次々と捕らえて、凱旋したことを伝えている。大坂城内には将兵だけでなく、普通の人々も逃げ込んでいたので、落城後はそうした人々を捕縛して連れ去ったのである。
徳川方に与した阿波の蜂須賀軍は、約170人の男女らを捕らえたといわれている。その内訳は、女が68人、子供が64人とその多くを女・子供が占めていた。40人程度が成人した男だったのだろう。捕らえられた女・子供が多い理由は、これまでの戦争と同じと考えられる。
「大坂夏の陣図屛風」(大阪城天守閣所蔵)は大坂夏の陣を描いた屛風絵で、逃げ惑う戦争難民の姿が見事に活写されている。左隻全面には、戦場から逃亡する敗残兵や避難民だけでなく、徳川軍が略奪・誘拐・首取りする姿が描かれている。なかでも注目されるのは、将兵に捕まった女性たちの姿である。将兵は戦いに集中せず、むしろ人やモノの略奪に熱中していた。それが彼らの稼ぎとなっていたからだ。そして、捕縛された人々は奴隷に身を落とすか、売買されたのである。
こうした地獄絵図のような乱取りは、戦国時代を経て織豊政権期に至っても続き、さらに最後の大戦争となった大坂の陣まで脈々と続けられたのである。
信長公記』に見る乱取り・人身売買
各地の戦場で乱取りや人身売買が横行していたが、織田信長の時代にも見られた現象である。以下、特に売春の例について確認しておこう。
倭寇・人身売買・奴隷の戦国日本史(星海社新書)
天正3年(1575)、織田信長は越前国で蜂起した一向一揆を討伐した。その際、3・4万人に及ぶ人々が、殺害または生け捕りにされたという(『信長公記』)。殺害または生け捕りにされた人々は、将兵だけでなく農民や女・子供も含まれていた。生け捕りにされた農民や女・子供は連行され、奴隷のようにこき使われるか、または売買して金銭に換えられたに違いない。つまり、彼らは戦利品として扱われ、出陣した将兵にとっての賞与のようなものだったのだろう。
ところで、信長が京都を支配しているとき、女性の売買が問題となった。『信長公記』天正7年(1579)9月には、次のような記事がある。
去る頃、下京場之町(京都市下京区)で門役を務めている者の女房が、数多くの女性を騙して連れ去り、和泉国堺(大阪府堺市)で日頃から売っていた。この度、この話を聞きつけ、村井貞勝が召し捕らえて尋問すると、これまで80人もの女性を売ったと白状した。
この女性は、門番の妻という普通の女性だったが、裏では女性の売買に関わり、少なからず収益を得ていた。この場合の女性を騙したという手口が不明であるが、数が80人というから尋常ではない。誰かが京都所司代の村井貞勝に密告したのだろうか。京都所司代には、京都市中を取り締まる役割があった。
わざわざ和泉国堺で女性を売ったのは、商人が多い土地柄ということに加え、堺の商人にとってもその後の転売がしやすかったからだろうか。こうした話は、やがて織田政権下で京都所司代を務める村井貞勝の耳にも入った。織田政権下においても人身売買は禁止されていたので、このあと女性は厳しい処罰を受けたのである(その後、女性がどうなったかは不明)。以下、戦国時代における売春の問題について、もう少し考えてみよう。
室町・戦国時代の売買春
戦場で捕らえられた人々のうち、特に女性の一部は売買春に従事させられた可能性がある。すでに中世においては、売買春のシステムが整っていた。以下、この点を詳しく確認することにしよう。
傾城(傾国)という言葉があり、それは美人・美女を意味するが、転じて遊女を示すようになった。中国の正史の一つの『漢書』外戚伝には、「北方に佳人有り。(中略)一顧すれば人の城を傾け、再顧すれば人の国を傾く」と書かれている。この記述を典拠として、傾城とは「美女の色香におぼれて城や国が傾く」こと、つまり国が滅びることを意味するようになった。中国の春秋時代(紀元前770~同403)における、呉王の愛姫・西施は「傾城の美女」として非常に有名である。
『漢書』外戚伝を出典として、傾城は日本でもたびたび遊女を示す言葉として使用されてきた。したがって、日本の史料であっても「傾城(屋)」と書かれていれば、間違いなく遊女あるいは遊女屋を示す。