お相撲終わってメールチェックしたら
朝のブログを読んだという方からメールが届いていた。
同じ医療のセッションに出ていたらしい。
「このメールがお相撲の邪魔にならないといいんですけど」
大丈夫です。終わってからメールチェックしたから。
メールの内容に「はげどう」です。
なぜ医療の話を聞きに行って
いきなり親学批判を聞かされなきゃいけないのか
それがわかんなかったんですよね。
言葉尻症候群の質問が出た意味もわかんないし
それにまともに取り合うギョーカイメジャーを見て
ああこういう仕事を余儀なくされているから世間から見ると不可思議な要求をいっぱい出すんだろうなと思いましたです。
それを肌身で感じるだけでも、お祭りに行ってよかったよ。
ギョーカイのご本尊はこれです。
「親のせいではない」
これを死守するために
多くのものを犠牲にしていますわね。
なぜなら
「親のせいだ」って言っていない言葉をひとつひとつ言葉尻でいちゃもんつけて(ていうか本当にそう思っちゃうんだろうね。脳汁的に)
親のせいではない、というマントラを唱えないと気がすまない人を「支援」しなきゃいけない立場だと
とにかく人の口をふさぐことになる。
発達援助に関する知識も含めてね。
それがおかしい、っていう感覚をなくしていくんでしょう。
私から見ると「それ、言葉尻だよ」って教えてあげるほうが支援だと思うんだけどね。
「それ言葉尻だよ」って教えることより「なだめる」ことを選ぶ。
それが「死んだふり」の正体なのかもしれない。
だって、人の口ふさいで一番犠牲になるのは、お子さんじゃないのかしら。
さて
昨日別件で神田橋先生に手紙を書いたので
医療セッションに出たこと
具体的にどう患者さんの苦しみを取り除いていくかをしゃべったのは長沼先生お一人でしたとご報告しておきましたよ。

先日の「こころの科学」7月号(買ってね)に神田橋先生はこう書いていらっしゃいましたね。
=====
診断と治療・援助との互助関係が廃れ、一方向の流れ作業と化したために生み出された「マニュアル難民」がボクらの領域に氾濫している。発達障碍については殊に顕著である。専門家は分類作業の精緻化に専念し、現場医師の多くは二次障碍に対する薬物使用だけで、障碍は放置である。援助者は生活の場での不器用を克服するための訓練に工夫を凝らすが、サーカスの犬の曲芸訓練との異同に注目していないようにも見える。
=====
うん。めった斬り。
これ以外にもね、この書評にはなぜ「みんなみんな発達障害なのか」とかが説明されていますので
買う価値ありますよ。
もちろん他の記事も読み応えありますしね。
でもギョーカイメジャーが神田橋療法を取り入れ始めたように
なんとか苦しみを取り除きたい、っていう方向に向かっている心あるお医者さんもたくさんいるはず。
きっとね。

☆☆☆☆☆☆☆☆
気がつけば給金相撲。
心労続きなつもりでいたけど
強くなってるなあ。
あと五日間。
思いっきり、稀勢の里の相撲を取ってほしいです。
なんかいけるような気がするよ。
朝のブログを読んだという方からメールが届いていた。
同じ医療のセッションに出ていたらしい。
「このメールがお相撲の邪魔にならないといいんですけど」
大丈夫です。終わってからメールチェックしたから。
メールの内容に「はげどう」です。
なぜ医療の話を聞きに行って
いきなり親学批判を聞かされなきゃいけないのか
それがわかんなかったんですよね。
言葉尻症候群の質問が出た意味もわかんないし
それにまともに取り合うギョーカイメジャーを見て
ああこういう仕事を余儀なくされているから世間から見ると不可思議な要求をいっぱい出すんだろうなと思いましたです。
それを肌身で感じるだけでも、お祭りに行ってよかったよ。
ギョーカイのご本尊はこれです。
「親のせいではない」
これを死守するために
多くのものを犠牲にしていますわね。
なぜなら
「親のせいだ」って言っていない言葉をひとつひとつ言葉尻でいちゃもんつけて(ていうか本当にそう思っちゃうんだろうね。脳汁的に)
親のせいではない、というマントラを唱えないと気がすまない人を「支援」しなきゃいけない立場だと
とにかく人の口をふさぐことになる。
発達援助に関する知識も含めてね。
それがおかしい、っていう感覚をなくしていくんでしょう。
私から見ると「それ、言葉尻だよ」って教えてあげるほうが支援だと思うんだけどね。
「それ言葉尻だよ」って教えることより「なだめる」ことを選ぶ。
それが「死んだふり」の正体なのかもしれない。
だって、人の口ふさいで一番犠牲になるのは、お子さんじゃないのかしら。
さて
昨日別件で神田橋先生に手紙を書いたので
医療セッションに出たこと
具体的にどう患者さんの苦しみを取り除いていくかをしゃべったのは長沼先生お一人でしたとご報告しておきましたよ。

先日の「こころの科学」7月号(買ってね)に神田橋先生はこう書いていらっしゃいましたね。
=====
診断と治療・援助との互助関係が廃れ、一方向の流れ作業と化したために生み出された「マニュアル難民」がボクらの領域に氾濫している。発達障碍については殊に顕著である。専門家は分類作業の精緻化に専念し、現場医師の多くは二次障碍に対する薬物使用だけで、障碍は放置である。援助者は生活の場での不器用を克服するための訓練に工夫を凝らすが、サーカスの犬の曲芸訓練との異同に注目していないようにも見える。
=====
うん。めった斬り。
これ以外にもね、この書評にはなぜ「みんなみんな発達障害なのか」とかが説明されていますので
買う価値ありますよ。
もちろん他の記事も読み応えありますしね。
でもギョーカイメジャーが神田橋療法を取り入れ始めたように
なんとか苦しみを取り除きたい、っていう方向に向かっている心あるお医者さんもたくさんいるはず。
きっとね。

☆☆☆☆☆☆☆☆
気がつけば給金相撲。
心労続きなつもりでいたけど
強くなってるなあ。
あと五日間。
思いっきり、稀勢の里の相撲を取ってほしいです。
なんかいけるような気がするよ。














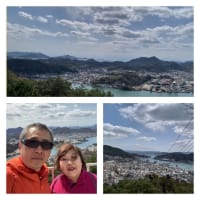





親が子どもの障害に気づいた、あるいは、様子がへんだ、ということで専門家のところに行ったときは、基本的には「それはお母さんのせいではなく、こういう障害ですよ」ということを告げる必要はあると思います。
ただし、その後どう育てていくかということについては、「親のせいではない」ということはできないですよね。
しかしながら、その専門家がその後も、ただ「親のせいではない」と言うだけで、どうしたらいいのかを提示しなかったとすれば、成長させるためのアプローチを親が放棄してしまう可能性はあるようにも思えますので、その場合は「親のせいではない」部分もあるかもしれません。
仰せの通りと思います。でも自閉症の世界は、親のしつけのせいにされた歴史、それと心のどこかで、やはり自分に何か非があったんじゃないかと思い続ける傷が深い人が多く、それを抑えるために、むしろ一般人を抑えこむような言動がなされるのだと今回行って思いました。それで犠牲にしているのは本当に、お子さんの未来なのですよね。
たしかに専門家には非があるかもしれませんが、そういう態度を取らせているのは保護者であり、一方で専門家の事なかれ主義かもしれません。どっちが悪いかという議論にはあまり意味がなくて、私はそこを越えて一歩進みたい人の知る権利をどう保障していくかが大事だと思っているので、そのあたりを次回の自閉っ子通信にまとめようと思います。
またお越しくださいませ。