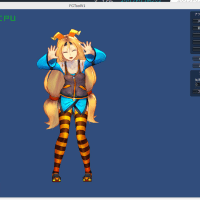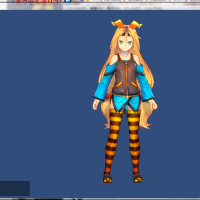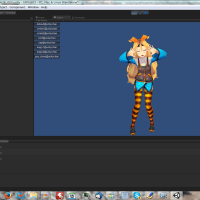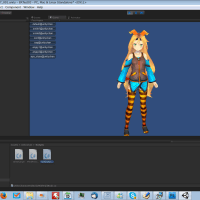今回のタイトル画像はブログと少しだけ関係するかも知れない、現在制作中のそむにうむ式初音ミクversion2(MMDモデル)です。(汗)
・・・・・・・・・・
最近「3Dプリンター」がTV番組等でもよく取り上げられる話題になってきました。
しかしながら、3DプリンターはPC用のプリンターと違って打ち出すものが少ないのが現状です。
プリンターは元来、コンピューターに入れられた大量の数字データや文字データを文書化する手段として開発されたものです。
今では信じられないと思いますが、プリンターの前にキーボードが付いた「テレタイパー」という入出力装置があって、
そこで1文1文データや文字列を入力して、間違っていたら行単位で修正を加える「ラインエディター」と言う文字編集ツールがあったのです。
すなわちプリンターはコンピュータ処理における重要部分を最初から担っていました。
しかし3Dプリンターはどうでしょうか。
3Dプリンターは文書や数値データを印字するためのものではありません。
3DプリンターはPCに保存されている3DCGファイルを、それが画面で3DCG表示された通りの立体物として出力するための装置です。
ならば3Dプリンターには3DCGデータを保存するファイルが不可欠になります。
最近だとThingiverseを始めとする3DCGデータを集積するソーシャルサイトが存在するため、3DCGデータを探し出すことはそれほど困難ではありません。
しかしそれでも自分が出したいと思う「形」がそこにあるとは限りません。
3Dプリンターで自分のほしいものを出したいと思った場合、どうしても必要になるのが3DCGモデルを作成する能力(スキル)です。
しかし、ここでよく考えて欲しいのです。
自分が欲しいと思う1点ものの3DCGデータを作成するためだけに、
膨大な時間と労力を割いて複雑怪奇な3DCGデータの作成方法を1から10まで真面目に学ぶことの必要性についてです。
もしも仮にすでに自分がその能力を有していたとして、
欲しい3DCGデータを作成して3Dプリンターで立体物を手に入れたら、
出力した後の3DCGデータはどうなるでしょうか?
これを考えている人は少ないと思いますし、この問題に言及している人は実際少ないです。
ずばりいうと「忘却します」。
言ってみればこれは粘土をこねて人形を作る行為と大して変わりはないのです。
自分で作って完成品を飾って自分で満足する。
その続きはといわれると、誰もがこう答えます。「新しい作品をまた作るさ」と。
それならば、既に作った作品のための3DCGデータは再び日の目を見る日はほとんどありません。
あるいは3DCGデータなので新しい作品の中に部分的に前に作った形状を再利用することはあるかも知れません。
でも、個人作品で、なおかつ工業製品のように規格部品を大量に使うといったデザインでもない限り、
自作の3DCGデータを使いまわす局面は殆ど無いといっていいでしょう。
例えば鉄道模型においてですら、同時代に作られた床下機器一つとっても数種類のバリエーションがあります。
部品作りが目標ならばともかく、それらの部品を組み上げて1両の鉄道車両をモデリングしていく労力は相当なものがあります。
これについては筆者も既に経験済みなのでぐらい例を上げて説明出来ますが、本題から外れますのでここではそこまで詳しくは触れません。

本題を「3Dプリンターに必要なスキル」に戻します。
すなわち3DCGモデリングの能力を仮に習得したとしても、モデルを制作するための労力は変わらないのです。
1から3DCGモデルを作るということは、1から10まで作らないといけないのです。
仕事でやるならばありかも知れません。もっとも、それもクライアントが作業量として正当に認められればの話ですが。
趣味となるとなおさらです。本来余暇を使って作るつもりが本業並みの労力を投入したのでは本末転倒です。
だから私はこう考えます。
「今3DCGモデリングのスキルを持っていない人は、無理にスキルを習得しようと思わないほうがいい。」
では、その場合自分の欲しいモデルを得るためにはどうすればよいでしょうか?
以下の2つの手段を提案します。
1.自分のゴールに最も近い3DCGモデルをネットから探しだして、最低限の修正で済ませる。
2.完全に自分のゴールと一致する3DCGモデルがネット上にアップロードされるまで待つ。
1は比較的アクティブな方法です。
この場合、3DCGデータを1から作成するスキルは必要なく、極端な話「コピー&ペースト」する能力の習得だけで始められます。
「ポリゴンで形を造形する方法」というのはツールの操作方法を習得する必要性に目が行きがちですが、これは純粋にアートの世界です。
目から入る形の情報を捉えて自分の手で塑像する行為であることを最初に認識する必要があります。
粘土造形と違ってUndo(やり直し)が聞くというメリットは有るのですが、粘土のように指先の微妙な動きで形状を整えたりできないもどかしさもあります。
それでも作成された3DCGデータを自分のためにしか使わないならば、粘土でこね上げて作ったフィギュア像と同じです。
それはその場の唯一人のためのものでしかありません。
そこまでの苦労をしない、あるいはしたくないのであれば、3DCGデータなら既に作られたデータを変更して自分の好みのものに改造するという手段が使えます。
それならば元モデルによりけりですが、少なくとも100%の労力をかけなくても自分の希望の物をゲットできる可能性があります。
しかも改造で必要となるスキルは、1からモデルを作るスキルと比べて最低限のもので済みます。
加えて、
これが一番大事なことですが、
モデルを1から作るよりも改造する方が、3DCGデータをモデリングするスキルを身に付けすいのです。
事実として、MMDにおける利用可能な3DCGキャラクターモデルが爆発的に増えたことと、それによるMMD専用3DCGモデラーの増加がその証左です。
0からのモデリングはゴールが見えなくて挫折しやすいのですが、
MMDのようにゴールとなるモデルが誰にでも見られる状態で存在すること、
モデルの構築ノウハウが手に入れやすいこと、
既に改造やモデルの制作をやった人間がブログ等で情報を公開してること、
最後に、モデルの制作状況を報告したり意見交換できる仲間がソーシャルにいること。
これだけの条件が整っているため3DCGデータ制作のモチベーションが維持できるのです。
逆に一人だけで完成形態もわからず自分の理想とするモデルとのギャップが激しく問題解決の情報もない状況で、
3DCGデータ制作を続けようとするにはとてつもなく強固な意志の力が必要です。
2は後ろ向きな解決方法に思えますが、意外と賢い選択です。
何故なら、あなたがモデル制作のノウハウを勉強してモデルづくりに取り掛かって完成させていく間に、
有名なキャラクターモデルならばきっと誰かが作っていることでしょう。
MMDの場合「まさかこんなモデルはあるまい」と思った3DCGデータが案外存在したりします。
最終的には2に限りなく近い1、あるいは2だけど最後のちょこっと改造を加える程度が理想的だと考えます。
そう考えると3DCGデータに対するモデリングの技術や知識は、
最低限完成品である3DCGデータファイルを読み込んで配置を変える程度の操作でOKと言えます。
それ以上のモデリングテクニックを覚えるのであれば、
時間をかけてゆっくりと作り上げる覚悟で望むのが良いと思います。
間違っても「カネで時間を買う」つもりで自己教育に投資しない方が無難です。趣味の世界ならば尚更です。
そんなことよりも同好の士に会うことに時間と金をつぎ込むほうが100万倍有意義です。(^^)
・・・・・・・・・・
さてここまでの話で、
「それなら3DCGデータを作ったまま放置するより公開して活用してもらった方が皆便利になるのでは?」
と思われた方が少なからずいらっしゃると思います。
と言う前に、MMDが既にそうした有効な3DCGデータの制作サイクルを実現しています。
ただし一方でこう思われる方もいらっしゃいます。
「データを公開したら3Dプリンターの立体物も含めて売ることができなくなるじゃないか!」
確かにその意見にも一理あります。
しかし、筆者も3DCGデータの頒布を行なってきてずーっと思ってきたことがあります。それは、
「3DCGデータって、買った後に活用されることがないとしたら、そのデータに何の価値が有るのか?」
CDは買ってからプレーヤーで聞けば何度でもその内容を聴き直せます。
しかし3DCGデータは、仮に3DCGデータビュワーで見たとして、そこから先の発展性はないのです。
逆に、3DCGデータに他のツールで利用できたり、他の映像に出演できるという付加価値があれば、
その3DCGデータは長く愛される3DCGとして存在し続けることになると思います。
これもまたMMDが証明してしまっていますが、MMD上では確かに長年愛されるべきキャラクターモデルの3DCGデータが存在します。
そこには「3DCGデータの需要」が確かにあるのです。
他のツールでもあるにはあったのですが、3DCGビュワーで見た先の展開はほとんどありませんでした。
(一部のデータはメタセコイア形式で公開されていたためにモデリング技術の伝承に役に立った例はありますが)
・・・・・・・・・・
このように、3DCGデータを公開することで3DCGデータの需要を生み、データを循環させ、改造や部分利用で新しいデータを作らせることには意味があると思います。
しかしこれではデータの制作作業量に見合った利益を3DCGデータ制作者は手に入れることができません。
そこは一部市場原理に判断せざるを得ない部分がります。需要のない3DCGデータを作っても売れないのは当たり前です。
但し、ネットで多数のダウンロードを記録している3DCGデータに関しては、データ作者が個別にパッケージングして頒布することに関しては問題ないと思いますし、
むしろ積極的にそうするべきだと思います。
あるいはここで3Dプリンターによる立体出力物を作者自らが頒布するのもありだと思いますし、
3DCGデータ作者を支援する目的で利用者が集まって3DCGデータを立体出力する行動を起こし、
その際に立体出力化する許可を3DCGデータの作者さんから公式に認定してもらうようにすれば良いと思います。
認定に対する対価をお渡しすることによって、3DCGデータ作者さんへのお心付けができると思います。
このように3DCGデータを立体化することによって生まれるチャンスは様々あると思います。
3DCGデータを作られている方々も、少しアイデアを凝らせば面白い展開を見つけることができます。
また、日頃から3DCGデータにお世話になってる方々は、立体出力で記念品を作ればオフラインイベントで自慢できる上に3DCGデータ作者さんに還元することも出来ます。
3DCGデータ作者さん、3DCGデータの利用者さんのそれぞれが得をすることにより、よりよい3DCGデータ需要を生み出すための好循環を加速させる仕組みが構築できれば
3DCGにとって素晴らしい未来が見えてくると思います。
追記:(2013.03.21 18:48)
3DCGモデリング愛好者の方から、「再利用されないデータには価値はないのか?」というご指摘を頂きました。
ヴィネットのように造形物として完結されている3DCGデータを公開されてらしゃる方はいらっしゃいますし、その作品の素晴らしさも存じています。
今回はそれらが「一度しか見てもらえずに見た後はCD-ROMやHDDの肥やしにされてしまう」ことへの問題提起として書いていましたが、
内容が3DCGデータの再利用に重点が置かれてしまい、作品として完結している3DCGデータについて無配慮な文面になってしまいました。
今回の論点は作品として完成された3DCGデータも含めて、何度でも見てもらい鑑賞してもらうことが再利用の価値であると考えています。
なぜならば、3DCGデータは3DCGツールやビュワーに読み込まれて3DCG表示されなければその中身がわからないものだからです。
ビュワーで見てもらえずHDDのファイルの一つで在り続けることがその3DCGデータにとって幸せなことでしょうか?
そしてファイルで在り続けるがゆえに無限にコピーが作られる可能性があり、オリジナルの保証もままなりません。
3DCGモデルをアートの域までに高めるならば、ビュワープログラムを巻き込んで相応の工夫を凝らす必要があると思いますが、
ビューイング方法を特殊にすればするほど見て貰える人が限られてしまうという矛盾を生じてしまいます。
そのジレンマをどのように打破すべきか、
作品完結型3DCGデータの作者の方々にも問題提起は突きつけられています。