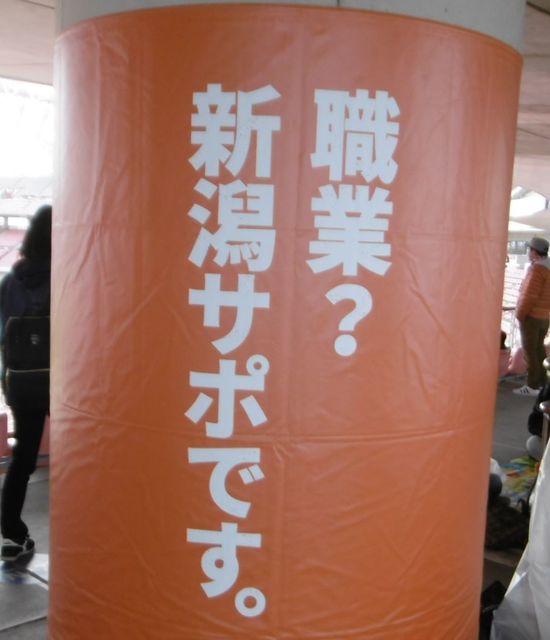今日は土曜でお休み。単身赴任先から自宅に帰ってきたのに、女房は仕事、娘は模擬試験。中年オヤジは昼間からPCの前でブログを書いています。

さて、サッカー観戦をするようになって「ブーイング」というサッカー文化があることを知りました。最初は「何なんだ?これは?」と思っていましたが、観戦を重ねるに連れ「ブーイング」の意味というのも少しずつわかってきました。
僕なりに理解しているブーイングの意味は、
・チームに脅威を与えるような有名選手が相手チームいる時
・かつて自チームに在籍した選手が相手チーム選手として登場した時
・相手選手が乱暴なプレーをした時、シミュレーションが疑わしい時
・自チーム(選手)がふがいないゲームをした時
・審判の判定に不服な時 …ってところです。
もし間違いがあったら、誰か訂正してください。(なんせ素人なんで)
だから「ブーイングが大きいっていうことは、選手自身にとっては名誉なことなんだ…」と教えてもらった時には、「へぇ~なるほどねぇ」とビックリしました。
さて、サッカーというスポーツが国民的に支持され市民権を得ている証明の一つに、子どもたちへのサッカー文化の強い影響があると思います。サッカー人口が増え、選手に憧れ、サッカーのユニフォームを着たりスタジアムに足を運ぶ子どもたちが増えることはとてもいいことだと思います。ただ僕は、子どもたちにあまりいい影響を与えていないサッカー文化の一つが「ブーイング」だと思っています。
学級会で、授業中に、友達や先生が何かを提案したり指導をしたりした時に、それが自分の思い通りでない発言や行動があったりすると、親指を下に向け「Boo」。そんな光景が子どもたちが通う小学校や中学校で時々見られました。安易に、しかも無責任に他人を批判する手段として、子どもたちの中に「ブーイング文化」が根付き始めているのです。これは教育上よろしくない!そして、そのお手本がスタジアムにおける大人たちの行動だとしたら、これもまたよろしくない。…と僕は考えるのであります。
だから僕は(女房も)2004年も2005年も、ブーイングだけは絶対にしないようにしていました。「このやろー、審判どこ見てんだ!」とは叫びましたが(あまり変わりないか? )。
)。
ゲームに負けた時には、ブーイングよりもアルビレックスコールで選手を元気づけたい。中沢や宮本みたいな全日本クラスの有名選手が相手チームにいたら、「らしいプレーを見せろよ」と拍手をしたい。そして、かつてアルビレックスに在籍した選手が相手チームで出場したら、僕はより一層の大きな激励と感謝の拍手を送りたい。
今年のサンフレッチェ戦では、上野や木寺が当然相手チームの一員としてビッグスワンに登場するでしょう。その時僕はブーイングなんてしたくないんです。大きな拍手と上野コールや「守護神・キデラ~」の応援歌で彼らを迎えたいです。
ブーイングよりも拍手を!であります。
「サッカーってそんなもんなんだよ」って言われればそれまでなんですけどね。
素人なりの意見を書きました。いかが?


さて、サッカー観戦をするようになって「ブーイング」というサッカー文化があることを知りました。最初は「何なんだ?これは?」と思っていましたが、観戦を重ねるに連れ「ブーイング」の意味というのも少しずつわかってきました。
僕なりに理解しているブーイングの意味は、
・チームに脅威を与えるような有名選手が相手チームいる時
・かつて自チームに在籍した選手が相手チーム選手として登場した時
・相手選手が乱暴なプレーをした時、シミュレーションが疑わしい時
・自チーム(選手)がふがいないゲームをした時
・審判の判定に不服な時 …ってところです。
もし間違いがあったら、誰か訂正してください。(なんせ素人なんで)
だから「ブーイングが大きいっていうことは、選手自身にとっては名誉なことなんだ…」と教えてもらった時には、「へぇ~なるほどねぇ」とビックリしました。
さて、サッカーというスポーツが国民的に支持され市民権を得ている証明の一つに、子どもたちへのサッカー文化の強い影響があると思います。サッカー人口が増え、選手に憧れ、サッカーのユニフォームを着たりスタジアムに足を運ぶ子どもたちが増えることはとてもいいことだと思います。ただ僕は、子どもたちにあまりいい影響を与えていないサッカー文化の一つが「ブーイング」だと思っています。
学級会で、授業中に、友達や先生が何かを提案したり指導をしたりした時に、それが自分の思い通りでない発言や行動があったりすると、親指を下に向け「Boo」。そんな光景が子どもたちが通う小学校や中学校で時々見られました。安易に、しかも無責任に他人を批判する手段として、子どもたちの中に「ブーイング文化」が根付き始めているのです。これは教育上よろしくない!そして、そのお手本がスタジアムにおける大人たちの行動だとしたら、これもまたよろしくない。…と僕は考えるのであります。
だから僕は(女房も)2004年も2005年も、ブーイングだけは絶対にしないようにしていました。「このやろー、審判どこ見てんだ!」とは叫びましたが(あまり変わりないか?
 )。
)。ゲームに負けた時には、ブーイングよりもアルビレックスコールで選手を元気づけたい。中沢や宮本みたいな全日本クラスの有名選手が相手チームにいたら、「らしいプレーを見せろよ」と拍手をしたい。そして、かつてアルビレックスに在籍した選手が相手チームで出場したら、僕はより一層の大きな激励と感謝の拍手を送りたい。
今年のサンフレッチェ戦では、上野や木寺が当然相手チームの一員としてビッグスワンに登場するでしょう。その時僕はブーイングなんてしたくないんです。大きな拍手と上野コールや「守護神・キデラ~」の応援歌で彼らを迎えたいです。
ブーイングよりも拍手を!であります。
「サッカーってそんなもんなんだよ」って言われればそれまでなんですけどね。
素人なりの意見を書きました。いかが?