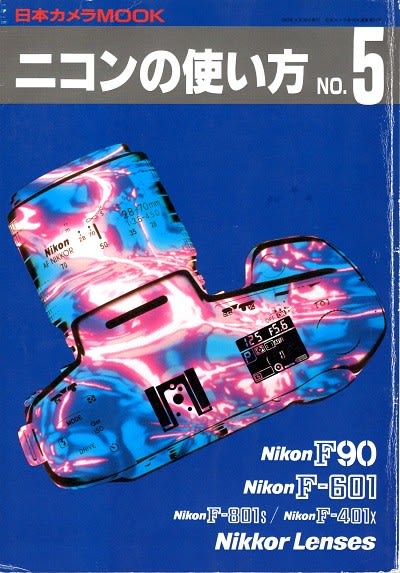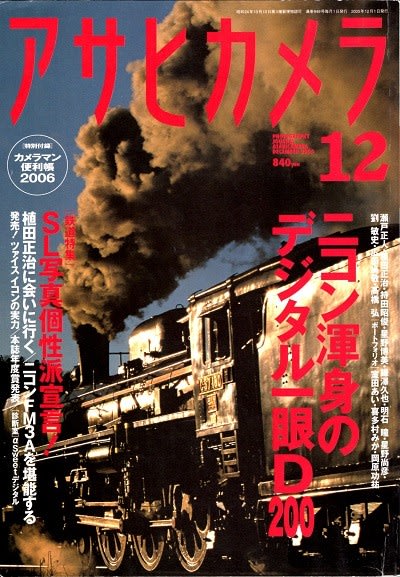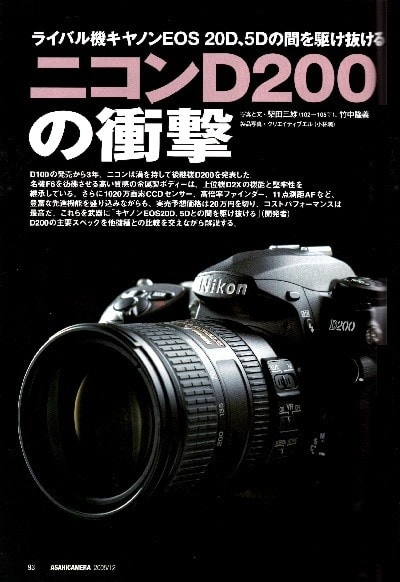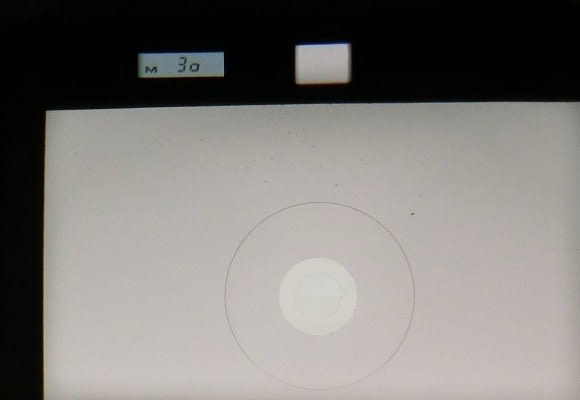窓のすぐ近くに餌台を設置して、そこに集まって来る野鳥をビデオ撮影し、後で見直していたところ、いつもやって来るスズメ、シジュウカラ、キジバトなどに混じって、見慣れない鳥が映っていた。しかもかなり長時間にわたり餌台にいた。
残念ながらこの時の映像はピントが大きくずれてしまっていたが、種の同定は可能であり、「シメ」と分かった。この後、数年にわたり餌台に来る野鳥の撮影は行ってきたが、モミジの木にくることはあったものの、シメが餌台にやってきたのはこの時だけであった。
単独で餌台にやってきたシメであったが、あっという間に常連のスズメに囲まれてしまった。しかし、臆することなく、時にはスズメを威嚇しながら長時間居座り続けた。キジバトがやってきて、スズメと共に一度は追い払われたが、その後今度は、先に来ていたシジュウカラを追い出す勢いでまたやってきて、シジュウカラの大好物である牛脂には目もくれず穀類を食べ続けた。
餌台にきたシメ(2016.2.1 撮影後編集)
庭のモミジの木に止っているところはこの後も何回か見かけたので写真撮影はできた。図鑑によると、シメはエノキやモミジの種子が好物とのことで、これが狙いであったことがわかる。時には散って雨樋の中に溜まっているモミジの種子を熱心についばむ姿も見られた。
ずんぐりした体に、やや不釣り合いに太い嘴が印象的である。羽色は地味だが、なかなか美しいとの印象を与える。ウィキペディアによると、蝋嘴鳥(ろうしょうちょう)という異称があるとのことで、「シー」と聞こえる鳴き声と、鳥を意味する接尾語である「メ」が和名の由来となっているという。
いつもの原色日本鳥類図鑑(小林桂助著、1973年保育社発行)には、シメは次のように記されている。
「形態 体の割合に嘴巨大。嘴峰20~21mm、翼長98~102mm、尾長53~65mm、跗蹠21~22mm。♂は頭上黄かっ色、上頸灰色、翼は光沢ある藍黒色で幅広い白帯がある。目先、腮(あご) から喉中央にかけて黒。尾は藍黒色で尾端に幅広い白帯がある。嘴は白黄色であるが、夏期は鉛色になる。♀は頭上♂よりも著しく淡色である。
生態 渡りの時は小群をなすが、冬期は単独のことが多い。樹枝上に止まり、チチッ、チチッとなく。地上に下りて植物の種子をついばむこともある。
分布 北海道で繁殖し、秋期本州・伊豆七島・四国・九州・屋久島・対馬などに渡来して越冬する。まれに本州中部以北の山地で繁殖するものがある。」
以下、庭のモミジに来ているところを撮影したものを紹介する。

雪の降った朝、庭のモミジにきたシメ 1/2(2016.3.14 撮影)

雪の降った朝、庭のモミジにきたシメ 2/2(2016.3.14 撮影)

庭のモミジにきたシメ 1/11(2016.12.21 撮影)

庭のモミジにきたシメ 2/11(2016.12.21 撮影)

庭のモミジにきたシメ 3/11(2019.1.28 撮影)

庭のモミジにきたシメ 4/11(2019.1.28 撮影)

庭のモミジにきたシメ 5/11(2019.1.28 撮影)

庭のモミジにきたシメ 6/11(2019.1.28 撮影)

庭のモミジにきたシメ 7/11(2019.1.28 撮影)

庭のモミジにきたシメ 8/11(2019.1.28 撮影)

庭のモミジにきたシメ 9/11(2019.1.28 撮影)

庭のモミジにきたシメ 10/11(2019.1.28 撮影)

庭のモミジにきたシメ 11/11(2019.1.28 撮影)
以前にもこのブログに書いたことがあるが(2016年11月11日公開)、我が家にはモミジの木が4本ある。イロハモミジが3本、ヤマモミジが1本である。土地を購入した時にすでにあったもので、2本ある樹高15mほどの大木のうちの1本と、次に大きい10mほどの木とは、建築予定場所にかかっていたので設計・建築士のMさんに相談したところ、これほどの大木を移植するには費用もかなりかかるので、伐りましょうかという答えであった。
我が家よりも先に家を建てて越してきている近隣の人の話では、秋には近くを通りかかった観光客が、この木の紅葉を見に立ち寄り、写真を撮っていましたよ、などと聞いていたし、軽井沢という土地柄、そう簡単に樹木を伐ることもためらわれたので、この土地を斡旋してくれたIさんに相談したところ、造園業のSさんを紹介していただいた。
Sさんによると、移植はそんなに難しいものではなく、費用もMさんから聞いていたものの1/10くらいで済むというし、準備して進めれば絶対に枯れることはないと太鼓判を押してくれた。
そこで、すぐに、Sさんに2本のモミジの移植をお願いし準備に入った。まず最初は、木はそのままにして太い根を切り、1年程度かけて新しく細い根が成長するのを待つことから始まった。
そして、翌年家の建築が始まる時期に合わせて、これらを所定の場所に移動してもらった。この移植からすでに7年ほどが過ぎているが、移植後しばらくは、やや元気がなかった大木のモミジもここ数年で樹勢は回復してきている。そして、移植しないですんだ、他のモミジの木と共に毎年大量の種子をつけ、それを周囲にばら撒いている。
「シメ」がその種子を食べてくれるのであるが、何しろ庭にやって来るシメはこれまでのところ、先に紹介した一羽だけで、とてもモミジの種子の量を減らすことはできない。
おかげで、我が家の庭にはモミジの実生苗が一面に生えてきている。雑草を抜くときに、多少ためらいもあって、そのままにしておくと、すぐに成長して3年目には50cmほどに成長して、周囲の木の根に絡んで手に負えなくなってしまう。
そこで、仕方なく抜いていたのであるが、3年ほど前に、私共のガラスショップの隣で手作り雑貨や朝採りの野菜などを販売しているNさんに、妻がそんな話をしたらしく、モミジ苗を販売しましょうということになった。
しかし、50cmほどに育った苗を鉢に植えて店頭に置いていただいたものの、まったく売れる気配はなかった。そうこうしているうちにNさんは一昨年末に、コロナの始まる前であったが店をたたんでしまった。
相変わらず庭にはどんどん新しい実生苗が生えてきているので、昨年初夏のころ1年から3年目の実生苗を抜いて、小さいものはビニールポリポットに、大きく育っているものは素焼きの鉢などに、捨てないで植えておいたところ、活着しているようであった。
100~200個ほどたまっていたこの苗を、秋の紅葉シーズンが近くなった頃、ガラスショップ前にワゴンを出してその上に並べ、「軽井沢のモミジ苗・ご自由にお持ちください」と張り紙をしておいたところ、大人気で全部貰われていった。

モミジ苗配布用の張り紙(2020年秋に使用)
今年もまた庭の草取りの時期になり、昨年と同じようにモミジの苗を抜き取り、せっせとビニールポリポットなどに移している。夏になり活着が確認出来たら、また昨年同様配布できればと思っている。

庭から抜いてビニールポリポットなどに植えた実生のモミジ苗(2021.5.27 撮影)
私自身も、昨年実家を整理した際に持ち帰ってきた、父が使っていた浅めの植木鉢にモミジ苗を盆栽風に植え、楽しむことにした。

浅い植木鉢に植えたモミジ苗(2021.5.27 撮影)
ところで、このモミジの大木を移植してくれた名人Sさん、集金に来てくれるよう再三にわたり連絡していたが、いまだにその費用を支払えないでいる。
なんでも、当時中軽井沢に建設中であったビル・ゲイツ氏の巨大別荘の植栽を(一部?)請け負っていたそうで、忙しくまた相当な売り上げになっていたので、我が家のゴミのような商売はもうどうでもよかったのかもしれないと思っている。