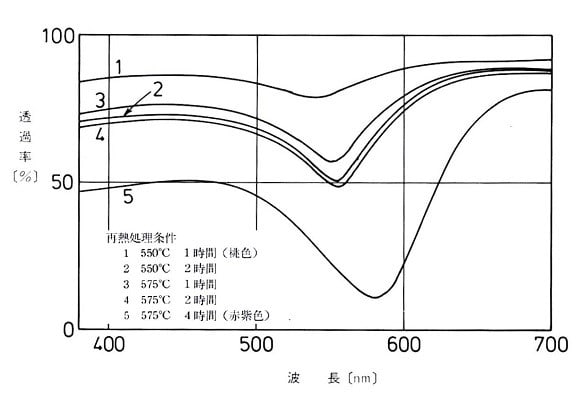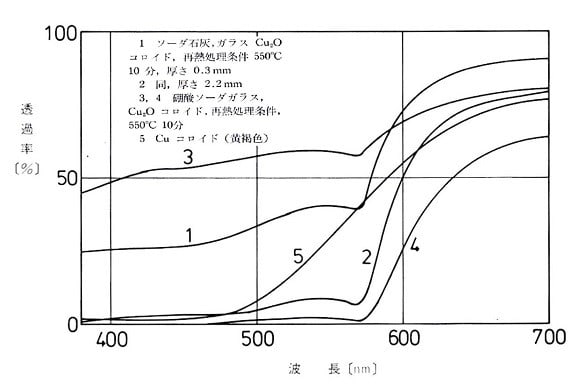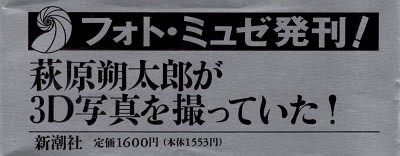軽井沢町が発行している、「軽井沢文化財・歴史的建造物マップ」には、これまでに紹介した事のある旧三笠ホテル、ショーハウス記念館、室生犀星記念館、旧有島武郎別荘「浄月庵」や八田別荘などと共に、旧三井別荘を見ることができる。この旧三井別荘が、最近新聞紙上を賑わした。

旧三井別荘の解体の危機を報じる新聞記事
2019年8月27日付の読売新聞には「三井別荘 解体の危機」と題して、次のように書かれている。
「1900年(明治33年)に建築され、軽井沢町に現存する最古の洋和館別荘とされる『三井三郎助別荘』が取り壊される可能性があることが、関係者への取材で明らかになった。建物を購入した英領バージン諸島の法人が解体の意向を表明しているという。避暑地として約130年の歴史がある軽井沢の別荘文化を今に伝える建造物の保存に取り組んできた町や住民らは解決の糸口を探るが、私有財産の保護には限界もあり、有効な手だては見つかっていない。」
記事では、この別荘について更に次のように解説しているが、この別荘には記事に名前が見られる人たちのほかに、萩原朔太郎も、室生犀星の紹介で滞在していたことがあるという。
「三井三郎助別荘:三井財閥の三井三郎助(1850~1912年)が現在の軽井沢町の愛宕山山麓に建てた。木造2階建ての洋館と和館が連結した造りが特徴。三郎助のおばで、NHK連続テレビ小説『あさが来た』のモデルとなった広岡朝子も利用し、ノーベル文学賞を受賞したインドの詩人タゴール、元総理大臣の西園寺公望も滞在したことで知られる。」

旧軽井沢愛宕山にある旧三井別荘(2019.9.6 撮影)
さて、今回は軽井沢文学散歩に萩原朔太郎をとりあげる。軽井沢には、萩原朔太郎に関連する文学碑などはなく、又彼が別荘を持って住んでいたということもないので、軽井沢町が発行している「軽井沢文学散歩」(1995年発行、11版)には、この萩原朔太郎は登場してこない。
ただしかし、本ブログの軽井沢文学散歩で最初に取り上げた室生犀星とのつながりがとても深く、互いに生涯の友と認め合う仲であり、上記の通り、室生犀星の紹介で「三井別荘」に滞在したとの記録があることや、室生犀星を訪ねて、芥川龍之介などとともに旧軽井沢の宿「つるや旅館」にも滞在していることから採り上げておこうとおもう。
萩原朔太郎については、私たちの世代は中学か高校の国語の授業で学んでいて、今も覚えているのは彼の詩「竹」である。あらためて読んでみると次のようであった。
萩原朔太郎 「竹」(詩集『月に吠える』より)
竹
ますぐなるもの地面に生え、
するどき青きもの地面に生え、
凍れる冬をつらぬきて、
そのみどり葉光る朝の空路に、
なみだたれ、
なみだをたれ、
いまはや懺悔をはれる肩の上より、
けぶれる竹の根はひろごり、
するどき青きもの地面に生え。
竹
光る地面に竹が生え、
青竹が生え、
地下には竹の根が生え、
根がしだいにほそらみ、
根の先より繊毛が生え、
かすかにけぶる繊毛が生え、
かすかにふるえ。
かたき地面に竹が生え、
地上にするどく竹が生え、
まつしぐらに竹が生え、
凍れる節節りんりんと、
青空のもとに竹が生え、
竹、竹、竹が生え。
萩原朔太郎と室生犀星、北原白秋は次の年表に見るように、同時代を生きた。また萩原朔太郎と北原白秋は同年に没している。

明治大正期生まれの文士とその中の萩原朔太郎(赤で示す、黄はこれまでに紹介した文士)
室生犀星は、「我が愛する詩人の傳記」(1974年 中央公論社発行)の中で次のように記している。
「先に死んで行った人はみな人柄が善すぎる、北原白秋、山村暮鳥、釈迢空、高村光太郎、堀辰雄、立原道造、福士幸次郎、津村信夫、大手拓次、佐藤惣之助、百田宗治、千家元麿、横瀬夜雨、そしてわが萩原朔太郎とかぞえ来てみても、どの人も人がらが好く、正直なれいろうとした生涯をおくっていた。・・・」
室生犀星と萩原朔太郎の出会いは、北原白秋の主宰誌である「朱欒(ザンボア、ザボンのこと)」においてであった。犀星はその折のことを「大正二年の春もおしまひのころ、私は未知の友から一通の手紙をもらった。私が當時「ザンボア」に出した小景異情といふ小曲風な詩について、今の詩壇では見ることのできない純な真実なものである。これからも君はこの道を行かれるやうに祈ると書いてあった」と述べている(月に吠えるの跋文から)。
その後の二人の交流についてはふたたび、「我が愛する詩人の傳記」に記されている。
「前橋市にはじめて萩原朔太郎を訪ねたのは、私の二十五歳の時であり今から四十何年か前の、早春の日であった。前橋の停車場に迎えに出た萩原はトルコ帽をかむり、半コートを着用に及び愛煙のタバコを口に咥えていた。第一印象は何て気障な虫酸の走る男だろうと私は身ブルイを感じたが、反対にこの寒いのにマントも着ずに、原稿紙とタオルと石鹸をつつんだ風呂敷包一つを抱え、犬殺しのようなステッキを携えた異様な私を、これはまた何という貧乏くさい瘠犬だろうと萩原は絶望の感慨で私を迎えた。と、後に彼は私の印象記に書き加えていた。それによると、萩原は詩から想像した私をあおじろい美少年のように、その初対面の日まで恋のごとく抱いていた空想だったそうである。・・・」
「萩原と私の関係は、私がたちの悪い女で始終萩原を追っかけ廻していて、萩原もずるずるに引きずられているところがあった。例の前橋訪問以来四十年というものは、二人は寄ると夕方からがぶっと酒をあおり、またがぶっと酒を飲み、あとはちびりちびりと飲んで永い四十年間倦きることがなかった。・・・」
二人が酒を飲んでいたのは、東京でのことであるが、1938年(昭和13年)53歳の時に朔太郎は軽井沢に別荘を借りて住んでいる。先に紹介した三井別荘と思われる。その時のことが同じく「我が愛する詩人の傳記」に記されている。
「1932年に北沢に彼は遺産で家を建てた。まわりは悉く渋いココア色で塗り潰した家である。彼はこの家で若い第二夫人を迎えた。その年の夏、はじめて軽井沢に別荘を借りて住み、私と萩原は夕方五時半の時間を決めて町の菊屋で落ちあい、ビールを飲んだ。若い時分のくせをこの避暑地でうまく都合つけたのも、よい思いつきであった。彼は五時半には菊屋に現れ、私もその時間におくれずに現れた。そしてビールを二本あけると二人は別れた。彼は若い妻のいる別荘へ、私は自分の家へ、そして私達はそれぞれにあらためて家で晩酌の膳についたのである。併し彼の別荘借りは一年しか続かなかった。」
萩原朔太郎が借りていたという別荘は、冒頭紹介した「旧三井別荘」のことと思われるが、その位置は次の地図のようであって、ビールを飲んだという菊屋があったであろう軽井沢銀座通りをはさんで、室生犀星の別荘とは反対側に位置しているので、犀星のこの話のようになるのは理解できる。

旧三井別荘と室生犀星の別荘の位置
萩原朔太郎の年譜「萩原朔太郎全集 第十五巻」(1978年 筑摩書房発行)には、この家の建築と、新妻との別荘生活については次のように記されている。尚、犀星の記述と年譜とでは、新居の住所や軽井沢での別荘生活の期間に相違があるが、これは犀星がその前の住まいの住所と思い違いをしていたり、記憶違いによっているからかもしれない。
「1931年(昭和6年)46歳、9月、世田谷町下北沢新屋敷1008番地(現在の世田谷区北沢二丁目37番地)へ移り、母ケイ、二児、妹アイと一緒に住む。」
「1932年(昭和7年)47歳、11月、世田谷区代田1丁目635番地の2(現在の世田谷区代田1丁目6の5の3)所在の土地147坪6を借地し、自己設計の家の建築にかかる。」
「1933年(昭和8年)48歳、1月、代田の家の新築落成。母ケイ、二児、妹アイと共に入居。・・・新居は木造二階建て瓦葺、一階43坪75、一階以外16坪12、計59坪86。」
「1934年(昭和9年)49歳、9月2日に、軽井沢避暑中の室生犀星に招かれ、犀星と沓掛などに遊ぶ。」
「1938年(昭和13年)53歳、4月、北原白秋夫妻の媒酌で、大谷美津子(当時27歳)と結婚するも入籍せず。 7月から9月まで、室生犀星の斡旋で三井の別荘を借り、美津子夫人と軽井沢に滞在。」
室生犀星の目で見た軽井沢での萩原朔太郎についてはこれくらいであるが、朔太郎自身は室生犀星について、合わせて11編の作品を残していることが、全集には記されている。しかし、朔太郎が軽井沢で借りて過ごしたとされる三井別荘での生活のようすなどはうかがい知ることができない。その三井別荘は現在解体の危機に直面している。解体と共に朔太郎の僅かな軽井沢との繋がりも消えてしまうのだろうか。
次に、軽井沢と直接の関係ではないが、本ブログの隠されたテーマである3Dすなわちステレオ写真と萩原朔太郎について興味深い話題があるので紹介する。
私がこの事を知ったきっかけは、ずいぶん前に読んだ雑誌「サライ」の「文士に学ぶカメラ道」という特集記事であった。これは文士とその愛用のカメラについてのもので、この中に大佛次郎、向田邦子、永井荷風、松本清張、池波正太郎らと共に、萩原朔太郎が紹介されていた。
萩原朔太郎が愛用したカメラはステレオカメラで、彼が撮影したステレオ写真も数点紹介されていた。ステレオカメラ・写真を愛好した文士というのは、後にも先にもこの萩原朔太郎くらいで、強く記憶に残っていた。

雑誌「サライ」2009年2月5日号の表紙
「サライ」の記事を改めて読んでみると、群馬県の前橋文学館には朔太郎の遺蔵書として「写真術全書」、「実地応用最新素人写真述」が含まれているとあり、朔太郎が使っていた立体写真のネガ乾板と日光写真の器具などもここに収蔵されている。また、関東大震災直後の被災地の様子を撮影したステレオ写真もその中に含まれる。
残念なことに、ステレオ写真を撮影した、肝心のカメラは残されておらず、詳しいことは不明だが、彼が書き残した「僕の写真機」(アサヒカメラ昭和14年10月号掲載のエッセイ)の文章があることから、関係者は「朔太郎の撮影した写真には『TOKIOSCOPE』と刻印されたものがいくつかある。これからフランス製立体写真機の『ベラスコープ』を模して製造された国産カメラ『トキオスコープ』を使用したことがわかる。」としている。
この他に、朔太郎がステレオ写真を愛好したことを示す記述を探してみると、萩原朔太郎全集(筑摩書房発行)の年譜の方には記載がないものの、同全集第十一巻には、先の「僕の写真機」が収められており、同じく全集第十五巻の巻頭に次の文章と数枚の写真が紹介されている。
「若い時から朔太郎にはカメラ趣味があり、前橋の風物、東京の大森・馬込、旅行地などの写真が相当数遺っている。妹たちと利根河畔に遊んだ日の利根川の鉄橋風景や、時報の櫓は、その遺品中のもので、今では二枚とも古い前橋の姿を伝える珍しい写真である。」
また、ウィキペディア「萩原朔太郎」の「人物・その他」の項には、1902年(明治35年)16歳の頃のこととして、次の記述があって、ステレオカメラの機種に関しては「サライ」の記事とはやや異なる見解があることを紹介している(注:ここには16歳とあるが後述の年譜では当時の年齢の数え方に合わせて17歳としている)。
「16歳の時最初のカメラを買って写真を始めた。この時従兄である萩原栄次の日記に『朔ちゃんが六五銭の写真機を買って来て、屋根の上から釣鐘堂を撮す』とある。
この頃はパノラマでない通常の、おそらく軽便写真器を使っていたが、明治期に撮影されたと思われるステレオ写真乾板も存在することから写真を始めて10年程ですでにステレオカメラを入手し、その後は特にパノラマ写真を好んだ。ステレオカメラに詳しい島和也によれば使ったカメラはジュール・リシャールのヴェラスコープではないかという。前橋文学館に45×107mm判写真乾板が展示されている。 これらの写真は妹の幸子の家で1972年に発見され、前橋市立文化会館館長で若い頃から朔太郎の詩に魅せられ研究を続けていた野口武久の元に持ち込まれ、7年をかけて撮影年代や場所を特定され、1979年『萩原朔太郎撮影写真集』として出版され、また再編集の上で1994年10月『萩原朔太郎写真作品-のすたるぢや-詩人が撮ったもうひとつの原風景』として出版された。」
ここに紹介されている本「萩原朔太郎写真作品-のすたるぢや-詩人が撮ったもうひとつの原風景」(新潮社発行)を入手することができた。表紙と帯のデザインは次のようである。

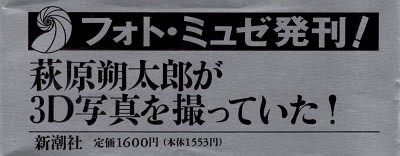
「萩原朔太郎写真作品-のすたるぢや-詩人が撮ったもうひとつの原風景」の表紙とその帯
この本には、朔太郎が撮影したステレオ・ペアを含む写真と共に、前出の「僕の写真機」、朔太郎の長女・萩原葉子さんの「父と立体写真」、葉子さんの子息・萩原朔美さんの「四角い遊具の寂しさ」というエッセイが載せられている。それぞれの文章から、朔太郎がステレオ写真に抱いていた思いを知ることのできる箇所を引用すると次のようである。
「寫眞といふものに、一時熱中したことがあった。しかし僕の寫眞機は、普通のカメラと大いに変わったものであった。・・・レンズが二つあって、それが左右同時に開閉し、一枚の細長い乾板に、二つの同じやうな絵が寫るのである。これを陽画にしてから、特殊のノゾキ眼鏡に入れてみると左右二つの絵が一緒に重なり、立体的に浮き上がって見えるのである。と言えば、すぐ読者にも解るであらうが、つまり僕の愛玩した寫眞機は、日本で俗に双眼寫真と呼んでる、仏蘭西製のステレオスコープなのであった。
このステレオスコープは、日本に来てから随分古い年代が経ち、既に明治初年時代にさへ、大形の物が輸入されていたにかかわらず、どういふわけか、日本では一向に流行しない。僕がこんな機器を持っていることさへ友人たちは軽蔑して、何んだそんな玩具みたいなものをといふ。・・・
とにかく僕にとっては、このステレオスコープだけが、唯一無二の好伴侶だったのである。・・・
元来、僕が写真機を持つてゐるのは、記録写真のメモリィを作る為でもなく、また所謂芸術写真を写す為でもない。一言にして尽せば、僕はその器械の光学的な作用をかりて、自然の風物の中に反映されてる、自分の心の郷愁が写したいのだ。僕の心の中には、昔から一種の郷愁が巣を食つてる。それは俳句の所謂「佗びしをり」のやうなものでもあるし、幼い日に聴いた母の子守唄のやうでもあるし、無限へのロマンチックな思慕でもあるし、もつとやるせない心の哀切な歌でもある。そしてかかる僕の郷愁を写すためには、ステレオの立体写真にまさるものがないのである。・・・
僕は今でも、昔ながらのステレオスコープを愛蔵してゐる。だが事変の起る少し前から、全くその特殊なフィルムや乾板の輸入が絶え、たださへ入手困難だった材料が、いよいよ絶望的に得られなくなってしまった。その上にカメラも破損し、安価の玩弄品以外には、新しい機械を買ふことができなくなった。これは僕にとって、いささか寂しいことである。」(「僕の写真機」)
「父が写真に興味を持ったのは明治三十五年中学生の頃で、写真機を当時六十五銭で買ったそうだが、翌年五月大阪の父の実家へ行った時には、もう立体写真機で、風景を撮ったりしていた。・・・私は、もしかすると小学生の頃から撮っていたかも分らないと思う。・・・
中学時代から、晩年まで立体写真を覗き(外国製の既製品の写真も覗いていた)、亡くなる前、病床に伏してからも枕元に置いてあった。
立体写真機はレンズが二つあり、それで撮った二枚同じ写真を横長の板に並べてステレオスコープで覗くと、立体に浮き上って見えるのである。
四百字原稿用紙大くらいの大きさで、厚みは十センチ余りの箱型で(寸法は、はっきりとは覚えていないが)、覗いてみると、風景や人物が浮き上がって見える。・・・」(萩原葉子「父と立体写真」)
「ステレオ写真機の方は、どんなカメラだったのだろう。・・・
日本カメラ博物館の『パノラマ&ステレオカメラ展』のカタログを見ると、この時期に入手可能なフランス製ステレオカメラは十台程ある。画面サイズからすると『カルブ・ポシェット』と『ステレオ・フィジオグラフ』、『ステレオ・マリン』、『フォト・ブカン・ステレオ』だ。ただし、残された立体写真用ガラス乾板は4.0x10.6センチ。カタログの中のカメラはどれも4.5x10.7センチなのだ。これも、計測の誤差なのかもしれないが、それも今となっては正解がない。・・・」(萩原朔美「四角い遊具の寂しさ」)
以上のように、朔太郎が所有していたステレオカメラについては、撮影用のステレオカメラと、撮影後のステレオ写真を見るためのステレオビュワーとが共にステレオスコープというように表現されているようで、混同されているようなところもあり、確かに本人がフランス製と書き残しているのにもかかわらず、関係者はその他の部材から国産と推定したりしているのであろうと思う。
カメラが破損してしまったという記述もあり、また複数台を所有していたと受け取れる文章もあるので、フランス製のステレオカメラと国産のステレオカメラの両方を持っていたとするのがいいのかもしれない。
さて、もうひとつ私には思いがけないことがあった。朔太郎が大阪に出かけた時に撮影した、阪急宝塚線「石橋駅」のステレオ写真がこの本に掲載されていたのである。石橋駅は私が学生時代に乗り降りをしていた駅であるし、一時期は近くに下宿生活をしていた場所でもある。当時、このことを知っていたら、又違った目でこの石橋駅周辺を眺めていたかと思う。
ところで、ここで、私が撮影した2組のステレオ写真のペアを見ていただく。最初は今年改修工事が終了したばかりの室生犀星記念館。もう1組は朔太郎と犀星が歩いた軽井沢銀座である。ステレオペアは交差法と平行法で配置しているので、立体視のできる方は挑戦していただきたい。

室生犀星記念館のステレオ写真(2019.9.12 撮影、ステレオ・ペアは交差法で配置)

同、平行法で配置

軽井沢銀座通りのステレオ写真(2019.9.12 撮影、ステレオ・ペアは交差法で配置)

同、平行法で配置
最後に、略年譜を記して本稿を終る。
略年譜
萩原朔太郎
・1886年(明治19年)1歳
11月1日、群馬県東群馬郡前橋北曲輪町69番地(のちの前橋市北曲輪町⦅現・千代田町二丁目一番十七号⦆)に、開業医の父・密蔵(35歳、大阪出身)母・ケイ(20歳、群馬出身)の長子として生まれた。名前の朔太郎は、長男で朔日(ついたち)生まれであることから、命名された。
・1890年(明治23年)5歳
妹(長女)ワカ誕生。
・1893年(明治26年)8歳
群馬県尋常師範学校附属小学校に入学。この頃から神経質かつ病弱であり、「学校では一人だけ除け者にされて、いつも周囲から冷たい敵意で憎まれている。」と孤独を好み、一人でハーモニカや手風琴などを楽しんだ。
・1894年(明治27年)9歳
妹(次女)ユキ誕生。
・1900年(明治33年)15歳
旧制県立前橋中学校(現・群馬県立前橋高等学校)入学。妹(三女)み祢誕生。
・1903年(明治36年)18歳
与謝野鉄幹主宰の『明星』に短歌三首掲載され、石川啄木らと共に「新詩社」の社友となる。
・1904年(明治37年)19歳
妹(五女)アイ誕生
・1906年(明治39年)21歳
3月、群馬県立前橋中学校卒業。4月、前橋中学校補習科入学。9月、早稲田中学校補習科入学。
・1907年(明治40年)22歳
7月、高等学校入学試験を受験、第五高等学校に合格。9月、熊本にある第五高等学校第一部乙類(英語文科)に入学。
・1908年(明治41年)23歳
9月、岡山にある第六高等学校第一部丙類(ドイツ語文科)に転校。
・1909年(明治42年)24歳
岡山高等学校を第一学年で落第。
・1910年(明治43年)25歳
4月、六高に籍を残しつつ慶應義塾大学予科一年(J組)に入学するも直後に退学。同年の夏頃にチフスにかかり、帰郷し5月、六高を退学する。6月、大逆事件の群馬県下への波及により、朔太郎の知人坂梨春水が逮捕される。10月、妹ユキ、津久井惣次郎(医師)に嫁ぐ。
・1911年(明治44年)26歳
慶応義塾大学部予科一年(B組)に再入学する。11月、慶大予科を中途退学。津久井惣次郎・ユキ前橋に帰住し、惣次郎は萩原医院の仕事をした。
・1913年(大正2年)28歳、
北原白秋の雑誌『朱欒』に初めて「みちゆき」ほか五編の詩を発表、詩人として出発し、そこで室生犀星作品に感動して手紙を送り、生涯の友となる。
・1914年(大正3年)29歳
東京生活を切り上げて帰郷し、屋敷を改造して書斎とする。6月に室生犀星が前橋を訪れ、そこで山村暮鳥と3人で詩・宗教・音楽の 研究を目的とする「人魚詩社」を設立。
・1915年(大正4年)30歳、
1月、北原白秋が前橋を訪問し、萩原家に滞在。3月、室生犀星、山村暮鳥、萩原朔太郎の3人により、人魚詩社から詩集誌『卓上噴水』創刊。誌名は犀星による。5月、金沢に犀星を訪問。10月、犀星前橋を訪問。
・1916年(大正5年)31歳、
春頃から自宅で毎週一回の「詩と音楽の研究会」を開き、6月に室生犀星との2人雑誌『感情』を創刊。
・1917年(大正6年)32歳、
第一詩集『月に吠える』を感情詩社と白日社共刊により自費出版で刊行。北原白秋の斡旋による縁談の見合いに上京。
・1918年(大正7年)33歳、
『感情』に詩3編を発表したのを境に、作品発表を中断。前橋市でマンドリン倶楽部の演奏会を頻繁に開催し、前橋在住の詩人歌人たちと「文芸座談会」を設ける。
・1919年(大正8年)34歳、
5月、上田稲子(21歳)と結婚。6月、若山牧水来訪。父密蔵(68歳)が老齢のため開業医をやめ、津久井惣次郎が「津久井医院」を開業。
・1920年(大正9年)35歳
9月、長女葉子誕生。
・1921年(大正10年)36歳
7月、室生犀星に電報で軽井沢駅に招かれ、共に妙高山麓の赤倉温泉に遊ぶ。12月、妹み祢、碓氷郡安中町の星野幹夫に嫁ぐ。
・1922年(大正11年)37歳
3月、詩集『月に吠える』アルスより再版。風俗壊乱の理由で初版では削除されていた二編を収録。4月、『新しき欲情』を刊行。9月、次女明子(あきらこ)誕生。8月、室生犀星と伊香保へ赴き、軽井沢に遊ぶ。
・1923年(大正12年)38歳
1月詩集『青猫』刊行、7月『蝶を夢む』を刊行し、8月には妹ユキ、アイと谷崎潤一郎を訪問。
・1924年(大正13年)39歳
2月に雑誌『新興』創刊号に発表した「情緒と理念」により同誌が発売禁止となる。直接の理由は軍国主義の虚妄を衝いた「ある野戦病院に於ての出来事」。5月、妹津久井ユキと関西を旅行。
・1925年(大正14年)40歳
2月、妻と娘二人を伴い上京し、東京府下荏原郡大井町6170番地(現・品川区西大井5丁目)へ移り住む。4月、東京市外田端町311番地(現・北区田端2丁目)へ移転、近隣の芥川龍之介や室生犀星と頻繁に往来する。犀星とは毎日のように会う。8月、妹ユキ、アイと共に軽井沢に行き、つるや旅館滞在中の室生犀星を訪問。芥川龍之介、堀辰雄らと遊ぶ。次いで四萬温泉に行く。。雑誌『日本詩人』の編集を、後に妹・アイが嫁ぐ佐藤惣之助と担当。11月、妻稲子の健康回復のため鎌倉町材木座に転居。
・1926年(昭和元年)41歳、
三好達治、堀辰雄、梶井基次郎などの書生や門人を多く抱えるようになる。三好達治は朔太郎の4人いた妹の末っ子アイに求婚するが断られ、のちにアイが再々婚した佐藤惣之助に先立たれると、妻を離縁しアイを妻として三国町で暮らすが、まもなく離縁する。11月、東京府下荏原郡馬込村平張1320番地(現・大田区南馬込三丁目二十三番)へ移る。
・1927年(昭和2年)42歳
7月、湯ヶ島温泉滞在中、朝食時に芥川龍之介の自殺を知る、10月、朔太郎の奨めで三好達治、大森へ来住し、爾後晩年にいたるまで親しく交わる。
・1928年(昭和3年)43歳
11月、稲子夫人の紹介で、室生犀星、大森谷中1077へ来住。互に近隣住居となり、犀星、朔太郎は田端時代に似て再び頻繁に往来。
・1929年(昭和4年)44歳
2月-3月、室生犀星と帝国劇場、中央映画社試写会、浅草の映画館などに出かけ、その帰りなどに頻繁に飲み歩く。7月、離婚決意を室生犀星あて書簡に書く。同月末、稲子夫人(31歳)と離別。娘二人を伴い前橋の実家に帰り、離婚と家庭崩壊の苦悩により生活が荒廃し始める。10月、『虚妄の正義』を刊行。11月、単身上京、赤坂区檜町六番地(現・港区赤坂八丁目)のアパート乃木坂倶楽部に仮寓。父発病、重態となり前橋に帰る。12月、東京定住を決め、妹アイと住む借家をさがす。
・1930年(昭和5年)45歳
7月、父密蔵死去(78歳)。10月、妹アイとともに上京、牛込区市谷台町十三番地(現・新宿区市ヶ谷台町十三番地)に居住。
・1931年(昭和6年)46歳
5月、万葉集から新古今集にいたる和歌・437首の解説を中心とする『恋愛名歌集』を刊行。9月、世田谷町下北沢新屋敷1008番地(現在の世田谷区北沢二丁目37番地)へ移り、母ケイ、二児、妹アイと一緒に住む。このころ江戸川乱歩を知る。
・1932年(昭和7年)47歳
4月、室生犀星、大森区馬込町東三の七六三に新築移転。犀星に家を建てることを奨められる。11月、世田谷区代田1丁目635番地の2(現在の世田谷区代田1丁目6の5の3)所在の土地147坪6を借地し(地代月17円71銭)、自己設計の家の建築にかかる。
・1933年(昭和8年)48歳、
1月、代田の家の新築落成。母ケイ、二児、妹アイと共に入居。個人雑誌『生理』を発刊。ここで、与謝蕪村や松尾芭蕉など、古典の詩論を発表し、日本の伝統詩に回帰した。 10月、妹アイ、佐藤惣之助に嫁ぐ。
・1934年(昭和9年)49歳、
6月、詩集『氷島』を刊行。同年7月に明治大学文芸科講師となり、詩の講義を担当するようになる。9月、軽井沢避暑中の室生犀星に招かれ、犀星と沓掛などに遊ぶ。10月、室生犀星の斡旋で再婚話がほとんど決定したが、結局まとまらず。12月ころ、一人の女性と交渉があったが、同女はその後昭和十二年頃死去。この女性には犀星は一度も会っていないという。
・1935年(昭和10年)50歳、
4月『純正詩論』、10月『絶望の逃走』、11月には『猫町』を刊行。自らが発起人となって伊東静雄の出版記念会を行った。
・1936年(昭和11年)51歳、
3月『郷愁の詩人与謝蕪村』、5月随筆論評集『廊下と室房』を刊行。前年に雑誌『文学界』に連載した「詩壇時評」により、第八回文学界賞を受ける。10月に「詩歌懇和会」が設立されると役員となる。
・1937年(昭和12年)52歳、
2月、上毛新聞主宰の「萩原朔太郎歓迎座談会」に出席し帰郷。同月下旬、大谷忠一郎の斡旋で、結婚の見合いのため福島県白河市に赴く。朔太郎は見合いの相手よりも、お茶を運んできた忠一郎の妹美津子に強く惹かれた。3月、大谷美津子に正式に結婚を申し込み、同女より交際をした上でという返事を受ける。「透谷会」の創立発起人となり、9月に「透谷文学賞」が設立されると、島崎藤村・戸川秋骨・武者小路実篤と共に選考委員となる。この頃からおびただしい量の執筆・座談会・講演等をこなすようになる。
・1938年(昭和13年)53歳、
1月、「新日本文化の会」の機関紙『新日本』を創刊。3月、『日本への回帰』を発表して日本主義を主張し、一部から国粋主義者と批判される。雑誌『日本』に「詩の鑑賞」を執筆した。4月、北原白秋夫妻の媒酌で、大谷美津子(当時27歳)と結婚するも入籍せず。7月から9月まで、室生犀星の斡旋で三井の別荘を借り、美津子夫人と軽井沢に滞在。
・1939年(昭和14年)54歳、
2月、美津子夫人、萩原家を出て東京四谷区に住む。朔太郎はそこで原稿を書いた。その後、美津子夫人は二・三ヵ所ほどに移り住み、そこへ朔太郎は通った。萩原家、朔太郎、美津子夫人の間が円滑でなかった模様。11月、バノンの会(正式名・詩の研究講義の会)を結成。9月『宿命』を刊行。
・1940年(昭和15年)55歳、
『帰郷者』(第四回透谷文学賞受章)、『港にて』を刊行し、10月『阿帯』を刊行する。この頃から身体に変調を感じ始める。
・1941年(昭和16年)56歳
8月、妹・津久井ユキ宛ての書簡で健康に変調があることを告げ、その後津久井医師の診察を受けるも、格別の病状は認められなかった。9月、明治大学文藝科の講義を、三好達治に代講をあおぐ。
・1942年(昭和17年)57歳、
4月末付で明治大学講師を辞任。同年5月11日に急性肺炎で世田谷の自宅にて57歳で死去。墓所は前橋市榎町政淳寺。法名は光英院釈文昭居士。
完
追記(2019.10.10):冒頭紹介した旧三井別荘が解体されたと、地元の「軽井沢新聞」(2019年10月10日号)が報じた。