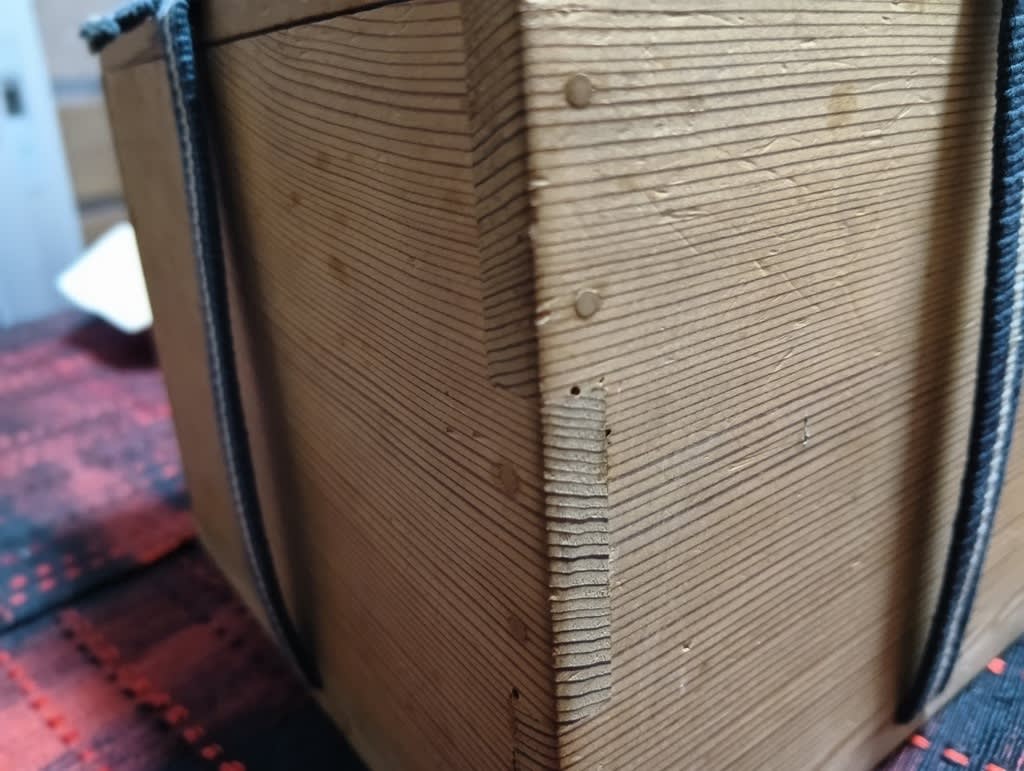濃茶の茶入れ

大きめです
お客様5人でしたので
箱は



茶入れの箱も 組んであります

漆壺齊の椿と水仙
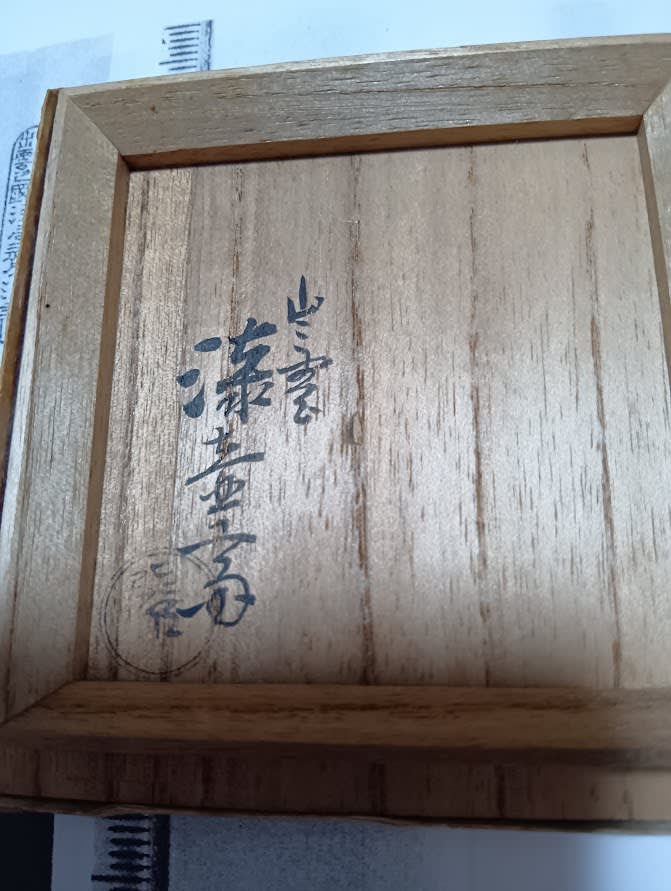
四代 漆壺齊です

水指は三田青瓷 陽刻紋

兵庫県三田市で昭和初期まで焼かれていた青瓷です

寸松庵旧蔵の赤楽 お福

平安時代の三色紙 升色紙 継色紙 寸松庵色紙
堺の南宗寺の障子に36枚張られていたうちの
12枚を佐久間将監真勝が得て
大徳寺の龍光院の隅っこに
茶室を建てたのが 寸松庵
そのために 寸松庵色紙と呼ばれるようになったそうです
茶室の名前ですね
龍光院さんには
小堀遠州が作った国宝の茶室 密庵があります
国宝の天目茶碗もあります
お宝 満載の非公開のお寺です
300年近くそこにあり 非公開だったのが
2017・19・22 に 表に出てきました
今後 出てくるかどうかはわかりません
MIHOの時に行けなかったので
22年の京博は行きました
30分も眺めて
地味だけれど 小粒のお星さまの様にキラキラして
見る角度で きらめきが変わります
見に行けそうなときは
お道具の追っかけです
ブロ友さんからの情報で
岡山県立博物館に
卯花墻が来ています
和物茶碗で2個しかない国宝茶碗
志野の小ぶりの可愛らしいお茶碗です
もう一つの国宝は
光悦の白楽 不二山
サンリツ服部美術館にあります
1年に1回公開という事ですが
昨年はなかったような ?
行きますよ 岡山
バスにするか 車にするか
バス往復だと3時間半ぐらい時間が取れて
車なら 5時間ほど時間が取れて
明るいうちに帰れそうです
休日割引利用して 車かな ?