今日のお稽古

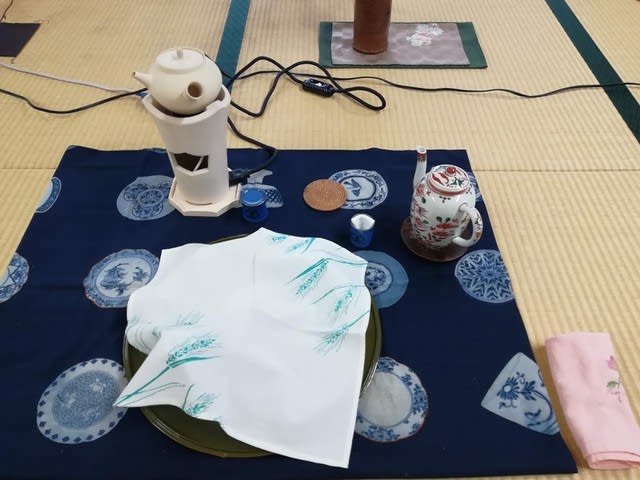
この状態で 覆いを外して 四分の一にたたんで
盆の左中央に置きます
その布の上に 茶芯壺 茶合をのせます

場所はこんな感じになります
茶たくは盆の外 右側中央に出します
急須はそのままで
お茶碗を 1から 上向けます
水を入れ 捨てて 茶巾でふきます
ボウフラを取り 茶碗・急須に湯を入れます
茶合を右手で取り左手に持ち換える
右手で茶入れを盆の中手前に取り込みます
茶壺と急須の間に蓋を置き
茶葉を茶合に出します
茶壺の蓋をして 元の位置の戻し
右手で急須の湯を捨て
茶合を持ちかえて左手で 急須の蓋を開けます
右手で 茶合の茶葉を 急須に入れ
そのままの手で茶合を 茶芯壺にかけておきます
ボウフラを取り 急須に湯を入れ 蓋をします
茶葉を蒸らす間に 湯飲みの湯を捨てます
5の茶碗から お茶を注ぎ
注ぎ終われば 茶たくを 盆の中に取り込み
急須を 盆の外右横に 出しておきます
急須のあった場所に 盆巾を半分におり 斜めにおいておきます
茶たくを取り 1のお茶碗から 盆巾で底をふき
茶たくにのせて 出します
お茶碗が全部出たら
盆金をたたんで お盆をふき 急須を盆の上にもどしておきます
一煎目のお茶碗が帰れば
お茶碗に湯を注ぎ 急須にも湯を入れておきます
ボウフラを おろして 水を足しておきます
同じように お茶を出した後は急須を外に出し 盆をふいて
急須は 盆の上に戻しておきます
二戦目のお茶碗が戻ると
お茶碗を 盆の中 茶たくは外
茶碗は水を入れ ふいておきます
5のお茶碗を 手前に取り その上に4のお茶碗
お盆の左外に お茶碗を出し
3のお茶碗を 手前に置き その上に 2 ・ 1 と三個重ねて
4・5のお茶碗の横に出しておきます
急須を外に出し 盆を清め
茶碗を1から順に伏せます
急須を戻し 茶たくは 盆中央
茶合を茶たくにかけ 茶壺は盆左手前に置きます
これではじめの写真の状態です
かぶせ布を取り お盆にかけておきます
今日のお稽古 メモです














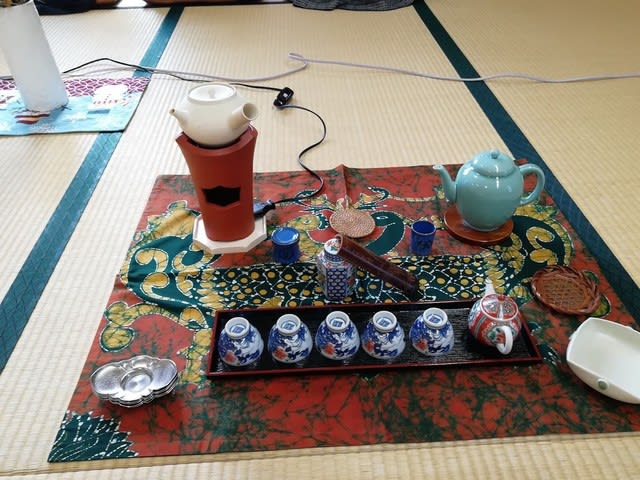
 右側を上にします
右側を上にします 右の輪を下にして重ねます
右の輪を下にして重ねます
 結びはじめ
結びはじめ



