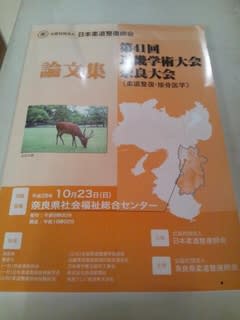皆様、こんばんは。
今日は京都の接骨院の会の秋の学術大会。
今回は、今年から全国の接骨院の会の都道府県で1番初めにしている、来るべき『地域包括ケアシステム』に向けての取り組み事業である京都府医療従事者資質向上研修が学会で、行われました。

講師は、京都府立医科大学『リハビリ医』の先生でした。
整形外科とまた違い、リハビリのドクタ-の話でした。
『ロコモティブシンドロ-ム』について講義をしていただきました。
ロコモティブシンドロ-ムとは、骨、関節、筋肉などの運動器の働きが衰えてくると暮らしの中の自立度が低下し、介護が必要になったり、寝たきりになったりする可能性が強くなっていきます。運動器障害のために、介護になったり、要介護になる可能性が強い状態がロコモティブシンドロ-ムというのです。
それをリハビリ医としてのデ-タや、デ-タから多い運動器疾患、場所(結論は腰でした)
また日頃、そうならないように行っているリハビリや、評価法など専門分野の話ではありましたが、接骨院と共通点も多い中身でした。
まずは、今日1時間半、総論で、来月に続く内容で・・・
その後、『保険講習会』が1時間、開催されました。
今年はいつもと違う講義に、また参加を促進する声換えが強く、かなり多くの参加者で、中丹支部もほぼ税イン参加の為、バスで送迎をしてもらいました。
今日は京都の接骨院の会の秋の学術大会。
今回は、今年から全国の接骨院の会の都道府県で1番初めにしている、来るべき『地域包括ケアシステム』に向けての取り組み事業である京都府医療従事者資質向上研修が学会で、行われました。

講師は、京都府立医科大学『リハビリ医』の先生でした。
整形外科とまた違い、リハビリのドクタ-の話でした。
『ロコモティブシンドロ-ム』について講義をしていただきました。
ロコモティブシンドロ-ムとは、骨、関節、筋肉などの運動器の働きが衰えてくると暮らしの中の自立度が低下し、介護が必要になったり、寝たきりになったりする可能性が強くなっていきます。運動器障害のために、介護になったり、要介護になる可能性が強い状態がロコモティブシンドロ-ムというのです。
それをリハビリ医としてのデ-タや、デ-タから多い運動器疾患、場所(結論は腰でした)
また日頃、そうならないように行っているリハビリや、評価法など専門分野の話ではありましたが、接骨院と共通点も多い中身でした。
まずは、今日1時間半、総論で、来月に続く内容で・・・
その後、『保険講習会』が1時間、開催されました。
今年はいつもと違う講義に、また参加を促進する声換えが強く、かなり多くの参加者で、中丹支部もほぼ税イン参加の為、バスで送迎をしてもらいました。