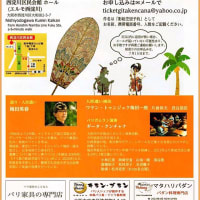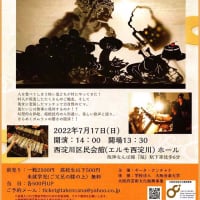若い頃の青山二郎。
白洲正子、といえば、青山二郎を思い出す。
白洲が骨董や古美術に入っていったのは、青山の影響は大きかった。そういう意味では、白洲の先生?だ。「じいちゃん」と呼んでいたらしいが。
青山は、早熟の目利きで、10代の頃から焼物や古美術を集めていたというから驚きである。そのやや破天荒だが天才的な審美眼というか鑑定眼、日本文化への思い入れは多くの人から教示を求められた人である。
そうとう口の悪い怖い人だったみたいだけど・・・みんな寄ってくるということは、それでも相当な本質をついていたんだろう。
白洲次郎も、ズバズバものをいうことで知られているが、白洲正子は、そういう華飾のない本質的な人が好きだったんでしょうね。

青山二郎(右)と小林秀雄(左)
で、青山の自宅はいつしか「青山学院」と呼ばれるようになったと昔、聞いた。名付けたのは大岡昇平らしい。
「青山学院」には、この大岡のほか、小林秀雄、中原中也、宇野千代、永井龍雄もいたし、北大路魯山人、加藤唐九郎なども頻繁に出入りしていたというから、明治に生まれ、大正の大震災、昭和の恐慌や戦争を経てつながる、昔のある種の交流社会はすごいね。
民芸運動には当初から加わっていたが、かなり早い時期に柳宗悦や浜田庄司とは決別したり、武原はんと結婚するも3年で別れたり、なかなか人生はアドベンチャーだ。
はんは、その後、新橋の芸者になり、大佛次郎などと交流して、なだ万を受け継いだあと、舞踊の道を極めていく。別れたとはいえ、はんもまた青山によって人生を開眼させられたひとりかもしれない。

武原はん
白洲もそうだけれど、とくに青山たちの育んできたもうひとつの日本の美、というのは、美大あたりではろくに教えることもしない。僕も教わったという記憶はない。
要するに、理論構築された西洋式の美の理論では、どうにも論理化するのが難しいのだ。だからその辺、小林秀雄などは貴重なのであるが、青山はそういうのがあまり好きではなかったのではないかとおもうことがある。
そもそも、柳たちと別れたのも、柳たちが民芸を理論化しようしてしたからではないだろうか。
そもそも、この歪んだ曲線がいい(姿)、とか、この垂れ具合(景色)が素晴らしい、とか、このコロ(大きさのこと)が絶妙などということの美意識の部分は、理論化できるものではない。
要するに、言葉にする前に、もっと実物と向き合え! もっと感じろ、その奥にあるものを観よ、といっているような気がする。そうすれば、「わかる日が来る」と言っているのだ。
人の手になる美とはそういう気魂の賜物なのだ。そういうことというのは一子相伝だからこそ、わざわざみんな青山に会いに行ったのかもしれない。

左から、柳、バーナード・リーチ、浜田。

駒場にある「日本民芸館」。学芸部長はよく知っているけど、いい人だ。
ま、白洲は貴族の出、青山は資産家の出だし、格差と階級社会とはいえ、漱石の高等遊民よろしく奔放な人生であるが、いつの時代も、教育がその差をわけるものだったかもしれない。
白洲は実は、僕の死んだ祖父と同い年である。片方は貴族、もう一方は農民だったが、最後はどちらも農民になった。
日本、その土地とともに生きる、とは、もう少し考えた方がいいかもしれない。
さ、じゃ、バリのことはどう考える?(は)