出勤途上の毎朝8時前後、名古屋市北区「名城公園」に立ち寄ってカメラ散歩をしている私は、
興味のある被写体に巡り合うとつい夢中になり、
そろそろ車に戻らなければいけない8時半を過ぎても気付かずに慌てることが
時々ですが、あります。
でも、
この時期はその心配がないんですよね。
なぜなら、
時間を気にしながら腕時計をたびたび見なくても、
ある「音」が、
おおよその時間を知らせてくれるからです。
「トトン、トトトン、トトトトトン、トトン、トトントントン………」
「名城公園」の南側、お堀を挟んだ向こうから
8時になると太鼓の音が聞こえ始め、
8時半にはそれが止みます。
先週の日曜日から始まり、
今週の日曜日に千秋楽を迎える大相撲名古屋場所が、お堀の向こう「名古屋城公園」内にある愛知県体育館で開かれていて、
期間中はその時間帯に、「寄せ太鼓」の音が聞こえてくるからです。
その「寄せ太鼓」を間近に聞きに、
今朝は櫓(やぐら)の下まで行ってきました。


5丈3尺(約16m)だそうです、櫓の高さは。
空中に突き出している2本の長い棹の先端に下げられているのは

「出しっ幣(だしっぺい)」と呼ばれる「御幣」の一種で、
天下泰平と五穀豊穣、そして場所中の晴天などを祈る意味があるそうです。
「相撲が開かれている場所を神様に教える目印というかアンテナみたいなもの」とどなたかがブログで喩(たと)えていっしゃいましたが、言い得て妙ですよね。

櫓の上で叩かれる太鼓には「寄せ太鼓」と「跳ね太鼓」の2つがあります。
「寄せ太鼓」は、街行く人々に、その日、相撲があることを知らせる太鼓です。
昭和初期までは、もっと早い明け方の時間帯に叩かれていましたが、
「安眠妨害だ」との苦情が増えてきたため、この時刻に繰り下げられたようです。
一方の「跳ね太鼓」は、その日の取り組みが終わったことを知らせ、「気をつけてお帰りください」「明日もまた来てください」の意味を持つそうです。
そこで、朝の「寄せ太鼓」と夕方の「跳ね太鼓」では、叩き方、リズム、テンポが微妙に違います。
とくに夕方の「跳ね太鼓は」、帰る客の背を見送りながら「テンデンバラバラ、テンデンバラバラ」と叩いているように聞こえるとは、よく言われることです。

ちなみに、相撲の櫓太鼓は小ぶりで、細いバチを使うため、独得の高音の音色と響きを出しますが、
これは本来「関西流」の太鼓で、
戦前は、盆踊りなどでよく見る大きな太鼓と太いバチで「ドドンガドン」と迫力のある音と響きを出す「関東流」の太鼓も使われていたことを、今回調べていて初めて知りました。
それが戦後なぜ「関西流」だけになったのかの理由は、分かりません。


「櫓太鼓」を叩くのは「呼び出し」の役目です。
主に若手が交代で櫓に登っているそうで、
今朝は、まだ20歳前後とおぼしき若い「呼び出し」さん2人が、途中で交代しながら叩いていました。

叩き終わって櫓から降りてきた「呼び出し」さんに声を掛けました。
「あんなに高い所で叩いていて、恐くありません?」
すると――
「もう慣れたから、大丈夫ッス」
やはり、「今時の若者」なんですよね、彼らも。
でも、神聖な櫓にTシャツで登り、太鼓を叩く姿を含めて、その「今時風」に眉をしかめるのはやめておきましょう。
なぜなら、
「呼び出し」として相撲界に就職した彼らは、
幕内力士の取組で土俵に上がれるようになるまでには原則「勤続30年以上」、
三役以上の取組なら「40年以上」の経験が必要という定めに従って、
まだまだ長い長い下積み生活を辛抱し続けなければならないんですから。
「ありがとうね。お疲れさま」と声を掛けると、
カメラに向かって返ってきたのは――

ピース・サイン?
………。
「今時風」のこれも、ま、よしとしましょうかね。

そして、もう1つ。
風になびく何本かの「幟(のぼり)」の中に、
意外なのを見つけてしまいました。

「幟」は、応援する「力士」だけでなく「行司」にも贈っていいものなんですね。
知りませんでした。
「第三十五代立行司 木村庄之助」に「幟」を贈っていたのは、
「宮崎県知事 東国原英夫」サン。
公費なんでしょうか、
それともポケットマネーなんでしょうか?
ちょっとだけ、気になりました。

--------------------------------------------------------------------------
興味のある被写体に巡り合うとつい夢中になり、
そろそろ車に戻らなければいけない8時半を過ぎても気付かずに慌てることが
時々ですが、あります。
でも、
この時期はその心配がないんですよね。
なぜなら、
時間を気にしながら腕時計をたびたび見なくても、
ある「音」が、
おおよその時間を知らせてくれるからです。
「トトン、トトトン、トトトトトン、トトン、トトントントン………」
「名城公園」の南側、お堀を挟んだ向こうから
8時になると太鼓の音が聞こえ始め、
8時半にはそれが止みます。
先週の日曜日から始まり、
今週の日曜日に千秋楽を迎える大相撲名古屋場所が、お堀の向こう「名古屋城公園」内にある愛知県体育館で開かれていて、
期間中はその時間帯に、「寄せ太鼓」の音が聞こえてくるからです。
その「寄せ太鼓」を間近に聞きに、
今朝は櫓(やぐら)の下まで行ってきました。


5丈3尺(約16m)だそうです、櫓の高さは。
空中に突き出している2本の長い棹の先端に下げられているのは

「出しっ幣(だしっぺい)」と呼ばれる「御幣」の一種で、
天下泰平と五穀豊穣、そして場所中の晴天などを祈る意味があるそうです。
「相撲が開かれている場所を神様に教える目印というかアンテナみたいなもの」とどなたかがブログで喩(たと)えていっしゃいましたが、言い得て妙ですよね。

櫓の上で叩かれる太鼓には「寄せ太鼓」と「跳ね太鼓」の2つがあります。
「寄せ太鼓」は、街行く人々に、その日、相撲があることを知らせる太鼓です。
昭和初期までは、もっと早い明け方の時間帯に叩かれていましたが、
「安眠妨害だ」との苦情が増えてきたため、この時刻に繰り下げられたようです。
一方の「跳ね太鼓」は、その日の取り組みが終わったことを知らせ、「気をつけてお帰りください」「明日もまた来てください」の意味を持つそうです。
そこで、朝の「寄せ太鼓」と夕方の「跳ね太鼓」では、叩き方、リズム、テンポが微妙に違います。
とくに夕方の「跳ね太鼓は」、帰る客の背を見送りながら「テンデンバラバラ、テンデンバラバラ」と叩いているように聞こえるとは、よく言われることです。

ちなみに、相撲の櫓太鼓は小ぶりで、細いバチを使うため、独得の高音の音色と響きを出しますが、
これは本来「関西流」の太鼓で、
戦前は、盆踊りなどでよく見る大きな太鼓と太いバチで「ドドンガドン」と迫力のある音と響きを出す「関東流」の太鼓も使われていたことを、今回調べていて初めて知りました。
それが戦後なぜ「関西流」だけになったのかの理由は、分かりません。


「櫓太鼓」を叩くのは「呼び出し」の役目です。
主に若手が交代で櫓に登っているそうで、
今朝は、まだ20歳前後とおぼしき若い「呼び出し」さん2人が、途中で交代しながら叩いていました。

叩き終わって櫓から降りてきた「呼び出し」さんに声を掛けました。
「あんなに高い所で叩いていて、恐くありません?」
すると――
「もう慣れたから、大丈夫ッス」
やはり、「今時の若者」なんですよね、彼らも。
でも、神聖な櫓にTシャツで登り、太鼓を叩く姿を含めて、その「今時風」に眉をしかめるのはやめておきましょう。
なぜなら、
「呼び出し」として相撲界に就職した彼らは、
幕内力士の取組で土俵に上がれるようになるまでには原則「勤続30年以上」、
三役以上の取組なら「40年以上」の経験が必要という定めに従って、
まだまだ長い長い下積み生活を辛抱し続けなければならないんですから。
「ありがとうね。お疲れさま」と声を掛けると、
カメラに向かって返ってきたのは――

ピース・サイン?
………。
「今時風」のこれも、ま、よしとしましょうかね。

そして、もう1つ。
風になびく何本かの「幟(のぼり)」の中に、
意外なのを見つけてしまいました。

「幟」は、応援する「力士」だけでなく「行司」にも贈っていいものなんですね。
知りませんでした。
「第三十五代立行司 木村庄之助」に「幟」を贈っていたのは、
「宮崎県知事 東国原英夫」サン。
公費なんでしょうか、
それともポケットマネーなんでしょうか?
ちょっとだけ、気になりました。

--------------------------------------------------------------------------


















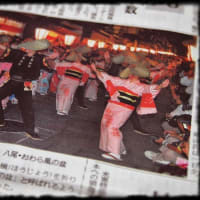

表しますよねぇ~・・・。
お琴でも、よくお師匠さんが
♪つくつくテン、つくつくテン。。
♪こぉ~ろりん……等と
仰って、お稽古してました
ま、お琴ではそのまんまの表現が多いんですよー。
音符にしても、漢数字で一~十・為(い)・斗(と)・巾(きん)の13本の玄を
表記されてるし。
ある意味ピアノの五線譜や、ギターのタブ譜より
覚えやすいかも?
それにしても・・・
すごい高いやぐら
あんな所に、こんな巨漢が2人と太鼓をあげるなんて
高さで怖いうえ、重みで落っこちないか?って
ダブルの恐怖があると思うんですけどー?
この辺りでは普通にゆかた姿のお相撲さんが歩いているんですね
上で太鼓を叩いている呼び出しさんの卵も、お仕事なんだから
ユニフォームではないけどゆかた着用でお願いしたいですね
色々問題が多い相撲界ですが
お近くの方は季節の行事みたいで楽しいでしょうね
「呼び出し」さんは定員が45名と決まっていて、空きがないとなれないそうです。「狭き門」なんでしょうかね。
時期になると以前勤務していた医療機関にも
力士が診療に来て 帰り際に「ごっつぁんです」
と言ったのには ちょっとビックリでした
体育館の側で毎朝こんな風に「寄せ太鼓」が
鳴らされていたなんて ちっとも知りませんでした。
目の付け所が違いますねぇ!!
なんだかんだいっても、伝統を感じます。
>行司、呼び出し 「勤続30年以上」、三役以上の取組なら「40年以上」の経験が必要という定めに従って、まだまだ長い長い下積み生活を辛抱し続けなければならないんですから・・・
好きでないと出来ない仕事かもしれませんね。なにせ、期間が長いです。
でも帰りの跳ね太鼓なら午後6時前ですから、その気になれば聞くことはできます。
ただし、跳ね太鼓は、明日はもう相撲がない千秋楽は叩かれませんから、注意しないとね。