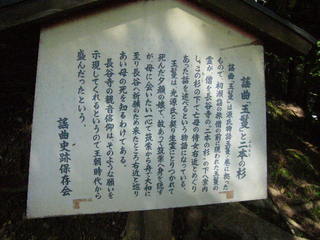王朝女人が詣でた長谷寺
奈良・桜井市にある長谷寺には藤原定家、俊成の記念碑があるということで行って参りました。 長谷の地は、その昔泊瀬、初瀬、始瀬、終瀬と云われ、瀬が始まるところ、または瀬が果てるところであった。 古くは神意を仰ぎ、「神河」と呼ばれていた。 初瀬は三方を山に囲まれ西方のみが開けた「隠国(こもりく)の里」であった。 5世紀に泊瀬の小野に遊んだ雄略天皇は雄渾な国褒めの歌を歌っています。
隠国の 泊瀬の山は 出で立ちの よろしき山 走りでの よろしき山の 隠国の 泊瀬の山は あやにうら麗し あやにうら麗し
三輪山のすぐ東に位置するこの古寺は、我が国最大の木造仏といわれる本尊十一面観世音菩薩像など、重要文化財が多々ある寺でもあり、草創については686年僧・道明が天武天皇のために銅板法華説相図を西の岡に安置し初瀬山の西の丘(現在、本長谷寺と呼ばれている場所)に三重塔を建立し、のち727年僧・徳道が聖武天皇の勅願により東の岡に十一面観世音菩薩を祀り、僧・行基が開眼供養し寺が成立したと考えられていますが、正史に見えず、伝承のようです。 四季折々の花が境内を美しく彩る寺でもあり、四月下旬から五月中旬にかけて牡丹の花が見事に咲くことでも知られています。 また、平安時代中期以降、観音霊場として貴族の信仰を集め、1024年には藤原道長が参詣しています。 古くから牡丹の花が咲き乱れ 「花の御寺」と称されていて、「枕草子」、「源氏物語」、「更級日記」など多くの古典文学にも登場します。 中でも「源氏物語」にある玉鬘の巻のエピソード中に登場する二本(ふたもと)の杉は現在も境内に残っています。
蜻蛉日記の著者である藤原道綱母(受領・藤原倫寧の娘で954年に藤原兼家と結婚)が初瀬詣を果たしたのは968年でした。 夫藤原兼家を振り切って少ない供と旅に出ます。 方違いを法性寺(今の東福寺)に定めて早朝出立し、伏見稲荷を横目に進み宇治で昼食後、木津川そばの橋寺(泉橋寺)に泊まり、 二日目は木津川を越えて春日大社を経由して椿市(今の桜井市近辺の海石榴市)に泊まります。 椿市は当時交通の中心地として栄え、枕草子や源氏物語にも登場しています。 行きはほとんど一人旅のようで、深い憂色に包まれているが、帰りは、宇治まで兼家が迎えにきており、蜻蛉日記には浮き浮きと明るい調子で描かれています。
仁王門


仁王門をくぐらずに境内図の前を右に進むと藤原定家塚・俊成碑へ


中央は藤原定家塚 左が俊成碑


源氏物語の「玉鬘」の巻に登場する二本(ふたもと)の杉
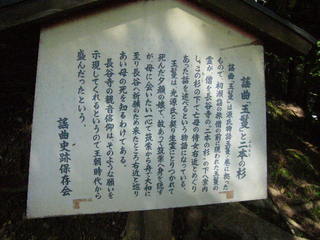

源氏復権後の栄華を極める生活の中の新たな物語です。夕顔の娘「玉鬘」(21歳)は、筑紫で美しく成人していました。 源氏は、その姫を探し出して引取りたいと考えていました。その夕顔の遺児「玉鬘」は、4歳のころ乳母一家に伴われて、立派に成人していました。その美貌に求婚者が殺到する中、乳母とその家族たちは、玉鬘を上京させて父の内大臣や母に巡り合わせたいと都へ上る決心をし、早船を仕立てます。神仏に願をかけ、長谷寺の御利益を頼みに、参詣の旅にでます。その旅の宿(海石榴市の宿)でかつての夕顔の女房右近とめぐりあいます。 右近は夕顔亡き後、源氏に仕えるようになってからも、夕顔の忘れ形見めぐりあいたいと、長谷寺に祈願をしていたのです。まさに長谷寺の引き合わせでしょう。この感動的な巡り合いをお互いに喜び、右近と乳母は語り合います。右近は、みすぼらしい身なりをしているものの、玉鬘の美しさに驚き、早速京に戻って源氏に報告します。源氏の驚きと喜びは大きく、早速玉鬘に文を送ります。源氏は、玉鬘を六条院に引取り、花散里のもとに預けます。 はじめて見る玉鬘は、夕顔の面影をそのままうつしており、源氏は満足です。夕霧は、玉鬘を姉と信じ、玉鬘を守って筑紫から上ってきた乳母の子も家司に迎えられ、思いがけない幸せの中に年の暮れを迎えました。
紫式部は「玉鬘」の中で長谷観音の霊験を 「仏の御中には、初瀬なむ、日本の中にはあらたなる験あらはしたまふと、唐土にだに聞こえあむなり」 と讃えています。
本堂 木造の十一面観世音菩薩が祀られています


本堂は代表的な江戸建築で、創建は奈良時代といい、平安時代には礼堂があったとされている。現本堂には巨大な十一面観音菩薩が祀られ、1650年に徳川家光によって再建された。
礼堂の前には舞台があり、紅葉の季節には幽玄のつどい「芸能奉納」が行われます。 また、紅葉の季節には舞台から見下ろす長谷寺全景の絶景が想像されます。実はこの「幽玄のつどい」、長谷寺に行って知ったのですが先週13:00から行われていました。 室町時代の貴族・武家社会には、幽玄(美しく柔和な優雅さのことをいいます)を尊ぶ気風がありました。 世阿弥は観客である彼らの好みに合わせ、言葉、所作、歌舞、物語に幽玄美を漂わせる能の形式「夢幻能」を大成させていったと考えられています。 世阿弥は将軍や貴族の保護を受け、特に摂政二条良基には連歌を習い、これは後々世阿弥の書く能や能芸論に影響を及ぼしたのです。 今回「夢幻能」が見れなかったのは誠に残念でした。


本堂と仁王門を結ぶ上登廊と上下登廊の中間にある蔵王堂


蔵王堂の横には紀貫之・古里の梅と一茶の句碑があります


仁王門への下登廊 観音万燈会時には上下の数百の燈籠に火が灯る