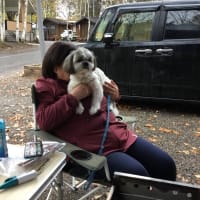シベリアへの道
ポーランド中部ワルシャワから約600Km東
ミカシェビッヂ(現ベラルーシ領)という小さな町があった。
その小さな町の片隅にヨアンナ(5歳)
という女の子が住んでいる。
髪の色は薄い黒が混じったきれいなグレーで、
瞳もグレー。夢見るような子で、
想像なのか現実なのか
近所の遊び友達への不満や夢の中の友との会話を
大好きな母マリアに話していた。
ヨアンナは雨の日以外
家の裏にある野の花に囲まれるのが日課。
そこは彼女の聖域だった。
そこではいつも事件が起きている。
今朝着づらく苦手だった服を
やっぱり今日も上手く着られなくて
ボタンも段違いになってしまった事。
靴を左右あべこべに履いてしまい、
見かねた父アルベルトに直されたこと。
嫌いなニンジンをどうしても食べられず、
母にじっと見られた事。
それらの失敗を野の隅の主、
小僧の石像に告白するのだった。
ヨアンナにとって小僧はただの石像ではない。
精霊なのだ。そして無二の友達だった。
昨日は小僧との会話を通りかかりの初老の婦人に
怪訝な目で睨まれ、
少し嫌な気分になった事。
一件おいて右隣りの
ヤンチャな男の子ヤンが意地悪をしてくる事。
母は絶えず縫物や洗濯の手を休めることなく、
娘の切実なそれらの大問題や
周囲のささやかな喜びの世界を見守っている。
そして時々母は澄んだきれいな声で
得意な曲を歌い、
ヨアンナと大切なひと時を過ごすのだった。
父アルベルトはというと、
街の片隅でつつましく眼鏡や時計の修理業を営んでいる。
仕事用の丸眼鏡をして頭に作業用バイザー、
腕カバーと長い前かけに身を包むのがトレードマークだった。
温和な人だが仕事の時だけは細かい作業に集中する分、
真顔で近寄り難い。
でも仕事の時以外は誠実で思慮深く、
母とは違った優しさで接してくれる、
その笑顔と大きな手と背中が印象的な人である。
父の丸眼鏡はヨアンナの魔法の入り口。
父の隙を見てはかけてみるのだった。
どうしてかける前と後では
こんなに世界が違うのか?
ヨアンナには大きすぎるその眼鏡は
大のお気に入りである。
ある時ヨアンナは父に聞いた。
「どうしてお父さんはこの眼鏡をかけるの?」
「それはヨアンナをよく見たいからさ」
「でもお仕事の時にもかけてるわ」
「だってお父さんがお仕事をしているときにも
ヨアンナは部屋の隅で
お父さんをじっと見ているじゃないか。」
「え?知ってたの?でもお父さんは
仕事に夢中でちっとも私を見てくれないわ!」
「そんな事ないさ!
この眼鏡は横だって後ろだって見えるんだぞ!
ヨアンナが何処に隠れ何をしているかなんて、
全部お見通しさ。」
そんな訳でお父さんの眼鏡は魔法のアイテムなのだった。
近所の顔中髭だらけのウォルフおじさんは、
野で遊ぶヨアンナを見かけるといつも上機嫌で
「ヨアンナおじょうさん、ごきげんよう!」
と浮かれた調子で挨拶してくる。
遊びに夢中だった手を止め、
ヨアンナもそれに負けず満面の笑顔で
「ごきげんよう、おじさん!」
と返す事にしていた。
するとおじさんはポケットから菓子を出し、
「お嬢さんは良い子だから、これをあげよう。」
そう言ってヨアンナの小さな掌に握らせ、
去っていくのが日課になっていた。
それからお向に住むアガタおばさんは、
大きな白いエプロンが目印で、
いつも大家族の洗濯物を干していた。
時々ヨアンナは母マリアに連れられ
近所のお店に買い物に行くとき、
アガタおばさんが頬ずりするような仕草をし、
ヨアンナに
「今日もお母さんと一緒にお買い物かい?
美味しい晩御飯を造っておもらいよ。」
という。
「ウン!」と元気に返事をすると、
「お母さんも頑張り甲斐があるねぇ」と笑った。
ヨアンナにとって日曜日は特別な日である。
何故ならお父さんの仕事が休みだから。
朝9時から始まる教会のミサに参加するため、
お父さんもお母さんも一張羅を着込み、
もちろんヨアンナは可愛いお人形さんのように着飾り、
教会のある街の中心部に向かって
いそいそと歩くのがとても楽しい。
両親に挟まれトコトコ歩くヨアンナには
至福の時間だった。
それが晴れの日、雨の日でもお構いなく
道すがら目にする家々の佇まいや
窓の下の小さな花壇の花々たち、
小鳥のさえずりや、道行く近所のよく見知った方々。
両親と一緒に歩いていると
それだけでウキウキした気持ちになり、
やがてミサが始まる教会の中の
荘厳な雰囲気に包まれても変わらなかった。
ヨアンナ一家はいつも決まった席に座る。
そこから良く見える
大きなステンドグラスが希望の光を放ち、
いつまで眺めていても決して飽きなかった。
髭の神父様が良く通るバリトンの声で祈りの言葉を捧げ、
ヨアンナには意味が分からなくても
心地良い歌のように響いてくる。
神父様はとてもやさしい。
ヨアンナにホスティア(薄いせんべい)をくれるもの。
そして祝福もしてくれる。
「慈愛に満ちたその目とお言葉で
語りかけられると、
幸せな気持ちになるの。」
ヨアンナの幼い言葉なりに打ち明けるのだった。
ミサが終わり家路につくと、
いつもお父さんは質問攻めにあう。
曰く、
「お父さん、神様って何処にいらっしゃるの?」
「神様って普段何をしているの?」
「神様はヨアンナをどう思っているのかな?
良い子?悪い子?」
「教会の窓のきれいな絵(ステンドグラス)って
神様なの?」
「神様っていつも私たちを守ってくださるの?」
「あのお花も、虫たちも、ワンちゃんも、猫ちゃんも
神様がお造りになったの?
だったらどうして近所のいたずらヤンは
あんなに憎たらしいの?
ヤンは神様とは関係ないの?」
次第に返答に困る質問になり、
父アルベルトは話題をはぐらかすのに苦労する。
横で母マリアは笑いを噛み絞め
夫が父として果たしてどんな答えを絞り出すか
助け船を出さずに
少し意地悪な静観を貫いた。
手に汗を感じたお父さんは、
話題を変えるために
天気の話や、お昼の過ごし方や、
唐突に歌を歌って誤魔化すのだった。
特に得意な『畑のポルカ』を。
あるよく晴れた平日の昼下がり、
母マリアが自慢のアップルパイを焼き上げ、
狭い裏庭のテラスで、
父アルベルトの仕事休憩の時間に
娘と共にティータイムを過ごした。
ヨアンナを真ん中に、父と母と娘の他愛ない会話。
「お母さん、このアップルパイ凄く美味しいね。」
「そ~ぉ?久しぶりに作ったのであまり自信なかったの。
そう言ってもらえるとお母さん嬉しいわ!」
「マリアの料理はいつも天下一品だと思うよ。
ねえヨアンナお嬢ちゃん?」
そう言って父アルベルトは受合った。
「お父さん、天下一品ってなあに?」
ヨアンナは不思議な顔で聞いた。
「そうだなぁ、天下一品って言うのは、
一番うまくできたってことさ。
この前ヨアンナが描いてくれた
お父さんの似顔絵も天下一品だったゾ。
お父さんとっても嬉しかったもの。」
「そうなの?絵ならいつでも描いてあげる。
ヨアンナ、お父さんもお母さんも大好きだもの。」
そう言ってコップのレモネードをゴクリと飲んだ。
それはささやかでありふれた日常。
でも贅沢でキラキラした時間として
幼いヨアンナの記憶として残った。
短い秋の訪れと共に家のうらの野の暮らしも
終わりに近づく。
今にも雨が降ってきそうな午前中、
いつものようにヨアンナが精霊小僧と会話をしていると、
いたずらヤンが背後からヨアンナに近づき、
集めた雑草の葉の束をパァ~っと頭から浴びせかけた。
驚いて振り返るヨアンナにヤンは、
はやし立てるように邪魔に入ってきた。
「やーい!ヨアンナは変な子!
石と話をして何が面白い?
頭がおかしいんじゃないか!」
ヨアンナは顔を真っ赤にして
「ヤンなんか嫌い!私の事はほっといて!
あっち行ってよ!馬鹿!」
ヤンはヨアンナの注意と関心を引きたいだけだった。
嫌われたいとの意図は勿論無い。
茫然と佇むヤン。
自分の行為が図らずも裏目の結果となり、
激しい後悔に襲われる。
なす術もなくその場に立ち尽くし、
間もなくヤンの心の中の雨が天を呼ぶ。
涙の雨はそこいら一面を濡らし、
ヨアンナは急いで家の中に去っていった。
ヤンの密かな想いが砕け散った瞬間。
そんな小さな大事件が際限なく繰り返される筈の
何気ない日常の暮らし。
だがヨアンナの小さな世界を超えた
大きな歴史のうねりはそれを許さなかった。
やがて戦争の暗雲が
ミカシェビッヂの街にも容赦なくやってくる。
ある日の日曜日。
いつものように一家で教会に行くと、
いつもより沈痛な面持ちで
神父様のミサが行われた。
それは押し迫る軍靴が近づく予兆だった。
異変を察知したミサの参加者たちは
その日を境に
いつもと違う真剣な祈りに変わり始める。
しかし神様へのそんな祈りの声は
とうとう届かなかった。
そして一家の平和で幸せな日々が
銃声の轟と共に無残に消え去った。
ロシア軍の足音がすぐそこまで迫る。
それまで攻勢だったポーランド軍は
体制を立て直したロシア軍を前に
退却するしかなかった。
ヨアンナの家もそんな災難から逃れられない。
逃げ惑う家の外の隣人たち。
やがて乱暴にドアを叩く音と共に
ロシア語のがなり立てる声が聞こえる。
ドアを蹴破りロシア兵がなだれ込み、
無人の部屋に火を放つ。
間一髪で難を逃れたが、
家を焼かれ取り残されたヨアンナ一家は
西へ向かうワルシャワへの避難路を絶たれた。
焦土と化した街はもう住み続けられない。
乱暴な大声で追い立てるロシア兵。
ロシア軍は逃げ遅れた街の残留ポーランド人を
いわば捕虜同然の扱いでシベリア地方開拓や
鉄道建設のため強制的に移動させた。
そこにヨアンナ一家も含まれ
過酷な運命へと引き込まれた。
幸せだった思い出の詰まる店舗兼住居を眼前で焼かれ
目に涙を流し、その地を立ち去る父と母。
両親の無念と絶望を胸に、
ヨアンナは両手を引かれ
東へ向かう列車に追い立てられながら乗った。
異動手段は鉄道は客車ではない。
異臭を放つ貨物車だ。
木製のそれは、隙間だらけで
合間から外の景色が見えるほどだった。
一日一度僅かな食料と水を与えられるだけで、
ひとりひとりがギリギリ座れる程度のスペースしかなかった。
極めて不衛生で脱走は不可能なほど
監視の目が行き届いてる。
列車の旅は混乱と不足と不安の渦巻く混沌の世界だった。
途中幾度となく異国の地で降ろされ、
休む間もなく父は強制労働に従事させられる。
開拓に必要なろくな装備もなく、
労働に適した作業着も無い。
食事は粗末で休憩も許されない。
更に徴用された彼らの多くは肉体労働未経験者で
全く仕事にならなかった。
いくつかの地をまわり試すが効率の悪さだけが際立った。
朝早く駆り出される父。
夜遅くに帰ってきても、
疲労困憊故のゆがんだ表情で
妻の用意した
具の無いスープに口をつけ、
直ぐに横になるのが日課になった。
いつもの朗らかな笑顔は消え去り、
全くの別人へと変容する。
ヨアンナも妻も、唯一の頼るべき大黒柱の
次第に窶(やつ)れ、
追い詰められる父アルベルトの身の心配と不安が
日増しに強くなってくる。
こんなことでは作業工期の目途も立たず、
開墾場所からの撤退続きで
上層部からの命令は遂行できない。
目論みが外れたロシア人担当たちは呆れ果て、
自らに課せられた使命を放棄する。
そして無責任にも徴用ポーランド人達を
見知らぬ地に何の手当もなく放逐した。
その地は当然未開のツンドラが広がる荒野。
木さえ生えない湿地帯が果てしなく続く草原の地。
残されたポートランド人たちは、
口々に不安を口にする。
今日これからどうすれば良いというのか?
自分は?家族は?
食料は?今夜の、明日の寝どころは?
議論を重ねるうち、
いくつかの方針と、
それに従うグループに分かれてきた。
この地に留まろうと主張する者、
戦乱続く西の祖国に帰ろうとする者、
いっそ、もっと東に向かおうとする者。
ヨアンナ一家も途方に暮れる中、
父アルベルトの決断で
安息の地を求めるグループに従い
同胞ポートランド人の住む東へ向かう決意をした。
しかし不足する食料。
宿泊に適さない環境。
先が見通せない不安。
次第に仲間内で荒れる空気不信と
エゴが先に立つようになる。
しかしその結果、ヨアンナを不安にさせてはならない。
父も母も務めてヨアンナに明るく振る舞おうとする。
一日一回、パン一切れの食事でも
ひもじさからヨアンナを泣かせてはならない。
食事の前の、
神様への祈りのその前に、
必ず元気づけに親子で歌を歌うようにしていた。
ヨアンナを楽しい気分にさせて
少しでも幸せを与えたい。
悲しい親心だった。
しかしとうとう脱出時持ち出した
商品用の金の懐中時計5個のうち、
最後の一個を生活費に充てるため
手放さなければならなくなった。
父はマリアに「これをお金に換え、食料の調達に行ってくる。
夕方までに帰る。」と云ったきり、
その日の夕方を過ぎ夜が明け、
次の日が過ぎても帰ってこない。
帰らぬアルベルトを待ち侘び、
不安と治安の悪さへの用心から、
眠れぬ夜が続いた。
「お母さん、お父さん帰ってこないね。」
「いつ帰るんだろうね。」
「ヨアンナ、このパンをお父さんのためにとっておくね。」
「きっとお腹を空かしているから。」
「今何処にいるのかな?」
「ヨアンナ、
神様にお父さんが早く帰ってくるようにお祈りするね。」
それらを黙って聞いていた母マリア。
不安の限界を過ぎた母は、
涙声を隠すように小さく震えた声で、
「そうね、一緒に祈りましょう。」
とだけ言った。
しかし残された妻と娘はそこに踏み留まり、
いつまでも待っているわけにはいかない。
飢えによる死はすぐそこに迫っているのだ。
彼女らがたどり着いたシベリア南部の原野は
短い夏になると意外にも気温30℃近くなることもあり
恐ろしいほどの蚊の大群が発生し
とても人がちょっとの間もいられない程の湿地帯が広がる。
そして短い夏は終わりいきなり冬が来る。
そこは人を寄せ付けない極寒の地。
気温マイナス40℃を下回る地であり、
人が暮らしていくには厳しすぎる生活環境である。
ただ、そんな過酷な場所にも人は住む。
流浪の民はその中に僅かに存在する
生活可能な場所を求め、
東行きを諦めた人々が、
集団を抜けバラバラに吸収されていく。
ヨアンナと母も父の帰還を諦める時が来た。
「おかあさん、お父さんはいつ帰ってくるの?」
母は悲しい表情でヨアンナを見つめる。
「お父さんはきっと早くヨアンナに会いたいと思って
お仕事を頑張っているのよ。
お母さんも早くお父さんに会いたいわ。
ヨアンナと一緒ね。」
そう言って力なく笑った。
それを聞いていた故国の仲間たち。
いたたまれない気持ちと差し迫った状況に促され、
明日の食料と居住できる場所を探し求め
直ちにポーランド同胞が多く住む
東のイルクーツクへ向かう決意をした。
この地に残っても、
ヨアンナとふたりでは
どう考えても定住は不可能と思えた。
後ろ髪をひかれながらその地を後にする。
父は帰らない。
待っても、待っても帰らない。
ヨアンナは立ち去るとき父の名を呼び、
母に泣いてすがった。
ここを去る、即ち父との今生の別れになることを
本能的に悟ったヨアンナは
到底その現実を受け入れられないのだ。
しかしヨアンナの心の中では
いくら泣いても無駄なことも分かっている。
自分に降りかかった悲劇が
自分だけではない事実を目撃してきたから。
少し前の冬のある日、
それまで行動を共にしていた集団の中に
ひとつ年下の娘がいた。
ヨアンナとはとても仲が良く
いつも一緒に遊んでいた子だ。
いつもコトコトと明るく笑い、
一緒にいるだけで辺りが明るくなる娘。
そんな幼い天使にも残酷な現実は襲いかかる。
あてどない旅の中、乏しい食料を娘に与え、
自らは何も口にしていない母がとうとう力尽き、
娘の明日を案じながら天に召された。
残された娘は母にすがりつき、
決して離れようとしない。
そして次第に弱りその娘も数日後母の待つ天へと旅立った。
すっかり冷たくなった母の亡骸。
その遺体に重なり旅立つ娘の傷ましい姿。
そんな悲しく壮絶な光景を目の当たりにしても、
周りの大人たちは何もしてあげることはできない。
自分たちも明日は我が身だから。
せめて最後は人間らしく、
心を込めてできる限り手厚く埋葬した。
ヨアンナは妹のように思っていたその娘の最後を
瞼に焼き付けるように見ていたが、涙は流さない。
ヨアンナにとって辛すぎるこの現実は、
暗黒の記憶として心を蝕んでいた。
やがて悲しい運命の順番が自分に廻ってきた。
母マリアの死期が迫ってきたのだ。
最後の食事を口にしてから幾日立っただろう?
もう思い出すこともできないほど、昔に思えてくる。
次第に意識が遠のく母
「ヨアンナ・・・、ヨアンナ・・・・、
私の大事な娘、子猫ちゃん・・・どうか生きて・・・。」
最後の言葉だった。
「神様。」
ヨアンナは心の中で呟いた。
心をそこに残しながらも
ヨアンナはそばにいた大人たちに引き離され、
先へ先へと手を引かれた。
どこまでも続く荒涼とした大地の中で。
数日後シベリアの中心地
バイカル湖のほとりイルクーツクにたどり着いた。
そこは長く弾圧の続くポーランド人の流刑地だった。
ようやく同族の多く住む安息の地にたどり着いたと思ったら、
そこもたどり着くまでの行程と同様、苦難の連続だった。
ロシア革命に続く内戦で食料の配給は滞りがち。
重労働と飢えと寒さは変わらず
死にゆくものたちは後を絶たない。
実際当時の革命後建国間もない
ソビエト社会主義共和国連邦は
続く戦乱と無謀で無能な農業政策、
天候不順により極端な不作が続き、
餓死者2000万人とも云われるピンチを迎えていた。
更に追い打ちをかけるように、
共産勢力への警戒と敵視で列強は次々とシベリアへ出兵、
当然のように食料救援は拒否された。
国際的に孤立し何処からも救援を望めない
ロシア人自身が極めて危機的状況にあった。
そして懲りることなく始まる新たな戦争。
ポートランド・ソビエト戦争が破壊の牙をむいたのだ。
長い支配から独立を果たしたばかりのポーランド。
一方革命後の混乱でまとまりのないロシア。
いずれも経済が破滅状態で
国民生活が困窮を極める中での両者の争いだった。
その戦争がヨアンナ一家の悲劇を生んだのだった。
ロシア人から見て敵国人と罪人である以前から
徴用されていたポーランド独立運動の政治犯や
愛国者などの外国人に施しが行き届くわけがない。
更にヨアンナのような親と死別した難民孤児たちは悲惨で、
空腹で身を寄せる場所もなく、
ただちに救済しなければなないほど切迫していた。
ヨアンナたち一行はようやくたどり着いた
イルクーツクの地も安住の地とではない事が分かった。
街は難民で溢れかえり自分たちの居場所はどこにもない。
やむなくその周辺の地に分散し、
それぞれ自らが生き永らえる手立てを見つけるしかない。
しかしそんな中でもヨアンナ達孤児は
誰も親身に面倒をみてあげられず、
その日その日を生きるのがやっとだった。
路頭に迷うヨアンナ。
もう彼女に愛情を注ぐものは愚か、
今の、そして明日の心配をしてくれる者はいない。
僅かに道連れの同郷者が見かねて
ギリギリのところで助けてくれるだけだった。
その時ヨアンナは悲しい習性を身に着けた。
大人の顔色を窺い、
食べ物を分けて貰えるか
悲愴漂う表情でただ立ちすくみ
ひたすら待つのだ。
戦争孤児特有の悲しい習性の臭いだった。
そんな状況をみかねて大陸極東の最果て
ウラジオストクのポーランド人達が立ち上がった。
ウラジオストクはイルクーツクと並び、
シベリアでポーランド人が
古くから暮らす拠点都市となっていた。
シベリア鉄道の土木技師を夫に持ち
ウラジオストクに居住する
アンナ・ビルケヴィッチ女史が中心となって
『児童救済会』が組織され、
せめて孤児たちだけでも助け出したいと行動をおこした。
と云っても当人たちも故国からロシア人に徴用され
シベリア鉄道建設に駆り出された者や、
流人として流されてきた者とその家族や子孫である身。
寄付を募っても孤児たちを救える額など集まるはずもない。
思い悩んで救済会が助けを求めた列強諸国は
誰も耳を閉ざし、助け舟を出さなかった。
追い詰められた救済委員会。
最後に藁をも掴む想いですがったのが日本だった。
でも彼女たち救済委員会のメンバーにとって日本とは、
ずっと昔キリシタン信徒を磔にした
非情で残忍な国との印象しかない。
そんな国に助けを求めるのは無駄と思われた。
その彼女たちを説き伏せたのは、
若い医師ヤクブケヴィッチ副会長だった。
シベリア流刑囚の息子である彼は
「私は日露戦争に従事した同胞を数多く知っています。
でもその中で日本や日本人を悪く言う人は誰一人としていません。
今年の春にわが軍のチューマ司令達を助け、
船を用意し窮地を脱することができたのは
日本軍のお陰だったと皆さんもご存じじゃないですか。」
そう発言し、メンバーの婦人たちを説得した。
委員会のメンバーは
説得を受け入れるしかなかった。
他に方法はない。
まず彼女らはウラジオストクの日本領事を訪ねた。
その建物の構えは彼女に冷たく、
よそよそしく思われる。
それはそうだろう、日本にとって
故国ポーランドの困窮した民や孤児を
救うべき理由など何処にもない。
彼女が救いを求めたそれまでの各国の対応は
冷徹な門前払いだったことを思えばなおさらだ。
それまですがった国は彼女たちにとって総て
欧米の白人国家という遠い同族意識の
微かな可能性に訴える事ができたが、
地球の反対側の全く異質な黄色人種の国に
そんな連帯意識を求めるのは無理な相談だ。
いわば絶望に近い望みであった。
日本への道
勇気を振り絞り
大きく重いドアをゆっくり開けた。
受付の堅苦しそうな係官に要件を告げる。
彼は東洋人によくありがちな
端正だが若干の細く吊り上がった目。
髪をきれいに7・3に分け、
落ち着いたとりすました佇まいで事務的な対応をした。
彼女は最悪、領事に会えず門前払いされる事を
覚悟していた。
3日後に若干の時間を割いてくれるとの回答を得た時、
皮一枚で運命の糸が繋がったと感じた。
そしてヤクブケヴィッチ副会長の言葉が蘇った。
「もしかして希望が持てる?」
それは、要件を聞かれ
必死でポーランド難民の、
とりわけ孤児の身に起きている悲劇を
訴えかけた彼女が係官の胸を打ったから
取り次いでもらう事ができたのだ。
感情を表に出さない係官からの
同情と賛同に気づけないでいた。
彼女の言葉には目的の重要な尊さと、
人の心を動かす強い説得力があることにも。
それは奇跡であり、
神から与えられた当然の結果でもある。
3日後の約束の時間、
アンナ女史は領事の執務室に通され、
分厚く敷き詰められた絨毯の奥にある
重厚な机の主(あるじ)に
自らの請願の内容を訴えた。
領事は整えられた短い髪、
鼻の下に少しだけ髭がある。
温厚そうな涼しそうな目元から
優しさをたたえじっと聞いていた。
彼女は語り始める。
「親愛なる日本の領事様、
私のような縁も所縁も利害関係もない
見ず知らずの外国人に目通りしていただき、
貴重なお時間をいただいたこと、
誠にありがたく存じます。
閣下のご厚意に心から感謝いたします。」
緊張な面持ちで、
しかしまっすぐな目で相手の眼を見据えながら話した。
領事はそれに笑顔で、
「ここに来るまでにさぞ勇気がいった事でしょう。
私の方こそ貴女のような崇高なご婦人とお会いでき
心から喜んでおります。」
そう言い終わると、控えの間から
熱いコーヒーが運ばれ出された。
その後彼女の口から熱心にシベリアでの同胞の苦難と
ここに至るまでの他の列強諸国から受けた
冷徹な扱いを聞き、
ここが最後の望みである事を
涙ながらに訴えた。
もし貴国に断られたら
シベリアで無残な死を迎えるしかない
哀れな孤児の運命を強く語る。
深い同情と正義感と慈愛の心、
人の上に立つ武士道精神の心得を持つ領事は、
「私には貴方達の
不幸な同胞の救済を決定する権限はありません。
しかし私にもできる事はあります。」
そう言うと机に向かい
引き出しの中から1通の書状を取り出し、
「これをお持ちなさい。」
そう言いアンナ女史に渡した。
「これを持って日本の外務省にお行きなさい。
きっと貴方達の助けになります。」
その時彼女の天を見上げ
喜びの表情で何かを呟くのを
そこに居合わした職員たちは目撃した。
今は一刻を争うとき。
救済委員会のアンナ女史たち一行は急ぎ渡航した。
領事館の紹介状と
極東ポーランド赤十字社からの紹介状を携えて。
1920年6月18日東京の外務省を訪れた。
対応した外務省の担当係官の助言により、
アンナ女史は翌日フランス語の
嘆願書及び状況報告書を携え再び外務省を訪れた。
アンナ女史は
在ウラジオストク領事館の時と同様
涙ながらに必死で訴えた。
勿論ポーランド人の孤児など遠く離れた日本に
人として国家としてこの窮状を知り、
見殺しにしても良いものか?
女史の訴えに深く同情し、
「アジアの盟主を目指す国家」
としてこうあるべきとの
指針と野心を持った日本。
どうすべきか決断と行動は早かった。
外務省は日本赤十字社に救済事業の立ち上げを要請、
ウラジオストクを拠点に同年7月救済活動を始動した。
アンナ女史の救済要請から17日後の事だった。
当時日本は、
シベリア出兵で列強最大の兵力を展開。
他の列強が撤退した後も、駐留を続けていた。
彼ら駐留日本軍は
アンナ女史の請願を許諾した日本政府の命を受け、
イルクーツクとその周辺に点在する
ポーランド人とその孤児たちを
軍の組織の総力を挙げ粘り強く捜索した。
その頃ヨアンナは
前年までのロシア革命後の混乱と
当時の革命ロシアの有力政治勢力である
ボリシェヴィキ、メンシェヴィキ間の政争やその後の
反革命軍(白軍)との闘争で
無人と化し荒れた農場の無人小屋に
ヨアンナを世話してきた2家族6人と
身を寄せていた。
その家族はヨアンナの父の最後を目撃し
助ける事も出来ず、
結果見殺しにしてしまった罪の意識から
残されたヨアンナを成り行き上、連れ歩いたのだった。
そんなある日の午後、
一脚の馬車が小屋の前で止まった。
少しの間、何やら話す声が聞こえ、
粗末なドアがノックされた。
部屋の中の誰もが固唾を呑んだ。
もう一度強めのノックに
勇気を出して返事をした。
「ここにポーランドからの孤児がいると聞いてやってきた。
もし居るのなら助けに来たのでドアを開けてほしい!」
ロシア語ではなくポートランド語が聞こえた。
助けとの言葉に反応し、
急いでドアを開けると、
ふたりの男が立っていた。
ひとりはポーランド人、ひとりは軍服を着た東洋人。
ポーランド人は極東救済委員会のメンバーで、
孤児の捜索と通訳を兼ね同行していた。
彼が手短にここに来た事情を伝え、
ヨアンナを連れ出すのを納得させた。
残る家族に当面の食料と金を残し
納得させた上で。
ヨアンナの目は不安で一杯だった。
私に用なの?
何処に連れて行くの?
お母さん、お父さん助けて!!
心の中で叫んだ。
東洋の軍人さんは怖そうだったが、
救済委員会の人は跪きヨアンナに優しく語りかけた。
「お嬢さんの名前はヨアンナって言うんだね?
おじさんはロベルト。
ヨアンナを助けに来たんだ。
もう大丈夫。
何も心配は要らないからね。
おじさんたちと一緒に
食べ物の心配のいらない所に行こう。
可愛そうに。
お腹が空いているだろう?
いつから食べていないの?」
「昨日のお昼。」
「じゃあ、昨日の夜も、今日の朝も
何も食べていないんだね?」
ウンと頷いた。
軍人さんがヨアンナを馬車に乗せると
用意してあったパンとミルクを与えた。
馬車が走り出し、
次第に小屋から遠ざかる。
とうとうヨアンナにとって
知っている人が誰もいない
孤独な旅が始まった。
数日かけイルクーツクの日本軍の駐屯所、
ウラジオストクの救済委員会が手配した
宿泊所などに泊まる。
数日後次第に集結した孤児たちで賑やかさが増すと、
日本行きの船の出航の準備が整った。
そこでヨアンナは近所の家にいた「いたずらヤン」と再会した。
彼はヨアンナを見つけると、
嬉しそうな表情になった。
しかし彼は重いチフスに罹り
床に伏している。
彼には渡航は無理であるのが一目瞭然だった。
彼は力なく言った。
「ヨアンナ、ごめんよ。僕・・・。
ヨアンナにまた会えてうれしいよ。
元気になったら、僕、ヨアンナと遊びたいな。
ごめんね、いつも意地悪ばかりして。」
ヨアンナはあの日までの嫌なことを一瞬で忘れた。
そして今、
唯一よく知っていた人に会えたことを素直に喜んで、
「また会えてよかったわ。
ヤン、一緒にお船に乗れるのね。」
だがそれは叶わなかった。
ヤンにとってウラジオストクが
短い人生最後の地となった。
それを知らないヨアンナは日本行きの船に乗る。
1920年(大正9年)7月下旬以降
第一回救済事業で375人が
陸軍輸送船「筑前丸」で東京へ。
しかも言葉や習慣の違う孤児たちの世話と
意思疎通の窓口に同じポーランド人が良いだろうと、
合計65人の大人のポーランド人を
付添人として一緒に招いた。
ポーランド人孤児たち一行を迎えるにあたり、
日本は国家の威信をかけ、
驚くべき短期間に総力を挙げて
迎える万全の準備をした。
寄港先の敦賀港では
多大な便宜が図られ港に到着後すぐに
長旅でボロボロになった着衣が煮沸消毒され、
代わりに真新しい浴衣を着させられた。
袂(たもと)いっぱいに飴や菓子を入れてもらい、
更に玩具や絵葉書などが差し入れられ子供たちを慰めた。
休憩、宿泊所に滞在したのは
1日という短期間だったが、
心のこもったもてなしを受け、
子供たちの心に強く残った。
ヨアンナは到着した敦賀港から
宿泊施設に向かう道すがら、
思わず吸い込まれてしまいそうな美しい花と
のどかな民家が見えた。
照りつく真夏の太陽、
初めて聞くうるさいぐらいの蝉の鳴き声。
ヨアンナにはそれらの音が何なのか理解できない。
彼女にとって異郷の地は珍しさで溢れていた。
この地に降り立った瞬間、
ここが今まで過ごした自分たちの世界とは
異なる場所だと感じた。
でも何故だか心地よい。
ここの人々の優しい眼差し、
何やら話しかけてくるが理解できない言葉の意味。
今まで口にしたことのない甘いお菓子!
「おとぎの国?」
そう、ヨアンナが
平和で幸せな家庭の中で
何不自由なく暮らせていた幼い記憶が残っていたら
夜ベッドで優しい母が読んでくれる、
グリム童話やアンデルセンの童話の絵本の中の
不思議なおとぎの国を思い出しただろう。
ヨアンナの父と母がまだ生きていた頃、
母はヨアンナの事を
「私の大事な子猫ちゃん。」
といつも呼んでいた。
あまりいつもそう呼ぶので
ヨアンナは
「私はヨアンナ!子猫ちゃんじゃない!」
ふくれて応えた。
でも母から笑顔が消えることはなく、
「そうねぇ、可愛い、可愛い大事な
ヨアンナ子猫ちゃんよねぇ。」
というので、それ以上反論するのを辞めた。
また父は、ヨアンナを天使のように扱い、
仕事の時以外ヨアンナが父のまとわりつくのを
咎めたり、煩そうな素振りを見せなかった。
そしていつも楽しそうにポーランド民謡の
『はたけのポルカ』を歌って聴かせた。
母同様、父も歌は上手だった。
ヨアンナにとって大切な両親の記憶。
思い出しながらも、
流れる景色と
道を曲がった先に咲き誇る草花が目に入り
ヨアンナは思った。
「まあ!なんてきれい!!きれい!!!きれい!!!!」
長かった辛い旅路にすっかり凍りついていたヨアンナの心。
たどり着いた日本の気候と
風習が作り上げた景色が、柔らかく、温かく、
心地よくほぐしてくれているのを無意識に感じた。
ヨアンナ一行は桃や当時日本でも珍しかったバナナなど、
目にしたことのない果物を食べ、
地元の子供たちと遊び、尋常高等小学校を訪れ、
夢のような楽しい時間を過ごした。
一日が経ち手配された列車に乗り、
揺れる車内で夢を見た。
「お母さん!ああ、お父さんも!!」
大粒の涙が流れ、声にならない声を出し、
両手を広げ駆け寄った。
「おお!ヨアンナ!待っていたよ、
よくここまで来ることができたね!偉い、偉い!」
「よく顔を見せてごらん。」
ヨアンナは父と母の間で顔を埋め、
いつまでもいつまでも甘えながら泣いていた。
朝になり・・・・
相変わらずの規則的なレールを走る音と揺れ。
「・・・・夢だった・・・。」
でもひとつ、これだけは現実である。
ヨアンナの顔に残る涙の跡と腫れた目元は。
列車の旅も終盤に差し掛かり、
車窓の外は連なる家、家、家・・・。
そして大きな駅にたどり着き、
「目的地に着きました、皆さん降りるように。」
と告げられた。
そして駅から歩くこと数分。
見た事の無い着物を着た
おびただしい人、人、人!
目前に奇妙なアーチがそびえ
その先にぶら下がる
幾列にも並んだガス灯と、
時折目にする店先の日本提灯。
異国の不思議な文字の看板たち。
人力車や大八車がところ狭しと
人と人の間を器用に縫い、行き交う表通り。
家の狭い庭先にささやかに植えられた鉢植えの草花。
船から降りた所とは全く異なる賑わいと
活気と喧騒に包まれていた。
福田会の生活
そしてとうとう東京渋谷の
「福田会(ふくでんかい)育児所」の門の前まで来た。
福田会は仏教系組織が立ち上げた施設。
受け入れの中心となった日赤本社の病院に隣接、
構内には運動場や庭園などの設備も整い、
子供たちに最適な環境の場所だった。
福田会育児所に到着すると、
受け入れ関係者や役人たちが待ち受け、
門の外には大々的な報道で知った
地元民たちが大勢歓迎の言葉と笑顔で出迎えた。
すでに全国から援助物資やお菓子、
義援金などが続々送り届けられている。
その総額は驚くほどで、
孤児たちの滞在費を賄って余りあるほどだった。
下は4歳から上は16歳まで
様々な年齢層の孤児たちは、
到着して間もなく医師の健康診断を受けた。
まず病気や栄養失調で弱っている子から。
長い苦難の放浪の結果、栄養失調や凍傷、
チフスなど様々な症状を抱える子。
ひとりひとりが死線を潜り抜けてきたのだ。
担当した医師の診断が終わると
要入院治療の子と一般宿舎の子に分けられ
新調された衣服と靴などが与えられた。
そして環境の整えられた部屋と食事、
担当した保母や看護師、医師の献身的扱いから
ようやく安息の地にたどり着けた事を本能的に感じ取った。
それまで抱いていた
親を失った寂しさ・孤独など
心の氷と闇からようやく解放されつつあるのを、
子供たちの輝いた
水色の笑顔が示していた。
診察が終わり、比較的健康で
一般宿舎での暮らしに耐えられる子たちは
付き添いの大人たちから
部屋割りを教えられ、それぞれの部屋へ。
もうすぐ6歳になるヨアンナの部屋は、
9歳のエディッタと7歳のハンナが同室だった。
エディッタはおちついたお姉さん口調で
もったいぶる癖があった。
ヨアンナと同室と分かると
「よろしくね、お嬢ちゃん!」と済まし声で言った。
また「私と一緒の部屋に居たいのだったら、
良い子でいる事よ。
私は煩くする子はキライですからね。」
彼女は孤児になる前、
特に母親の影響が強かったようだ。
彼女の口調はどこにでもいる、
口うるさい母親のそれである。
9歳にして年を取ったおばさんだったのだ。
ヨアンナは鼻持ちならないその雰囲気に
(少し感じ悪!)と心の中で思った。
ハンナはその逆で、
ヨアンナに対し満面の笑みを浮かべ
優しくハグをしながら、
「私はハンナ。ヨアンナちゃんの事,なんて呼んだらいい?
あとで一緒に庭にいってみましょ!
お夕食の前に!
あ~ぁ、少し疲れたけど、すぐにでも
ここを探検してみたいの。
あそこに池が見えたでしょ?
あの池に、お魚がいるか知りたいの!
だって何か泳いでいそうじゃない?
ヨアンナちゃんはどう思う?
そうそう、私たちの面倒をみてくれる舎監のレフさんって
何だかお魚のような顔してない?
私、心の中で笑っちゃった!
でも優しそうな人で良かった!
もし怖い人だったり、厳しい人だったら
毎日が楽しくないもん。
そうでしょ?ヨアンナちゃん。
ねえ、ヨアンナちゃんと呼んでよかった?」
マシンガン・ガールズトークでそうまくし立てた。
年上のお姉さんだし、少しその勢いに気おくれしたが、
「ええ、ヨアンナでいい、よろしく。」
とだけ言えた。
内心ヨアンナはここに辿り着くまでに仲良くなった
同年の友エヴァと
同室になれなかったことを残念に思った。
今日は長旅で疲れたでしょうから、
明日はゆっくり寝ていても良いと
舎監のレフさんに言われている。
ヨアンナ達は心にゆとりができ、
これから過ごすこの施設での暮らしに
期待と希望で胸が高鳴り、
興奮気味なのは仕方なかった。
部屋の様子は、
飾り気のない白い壁の8畳ほどの洋室にベッドが3つ。
カーテンは無地の薄い青色の予定だったが、
孤児たちの不安な気持ちを考え、
花柄に変更されていた。
そして人数分の机と椅子と箪笥。
そして窓辺には花瓶に心づくしの花が添えられている。
ベッドはパーテーションで仕切られ、
最低限のプライバシーは守られている。
窓の外には高い塀があったが、
ヨアンナの2階の部屋からは、
庭の中にあるごくありふれた一本の木が見える。
しかしその木は
春には大そうきれいに咲き誇るであろう桜であった。
それと桜の隣に小さく浅い池が見えた。
塀の外の家並みが
そこでの生活の匂いがしてくるような
異国の、しかし安心感のある佇まいを感じた。
部屋の少女たちは、ヨアンナを含め、
直ぐにそれぞれの気の合った友のところに行き、
自分たちの環境や様子の違いなどを確かめ合い、
やがて施設内の探検が始まった。
当然ヨアンナも友エヴァの元に。
しかしエヴァは栄養失調で治療が必要と判断され
ベッドでの療養生活を告げられていた。
彼女に限らず、孤児たちの多くは
身体に様々な問題を抱えていたので、
元気に動き回るわけにはいかなかった。
彼女ら孤児たちは
一番最初に心の回復を見せ、
一生完全に回復できないのも心だった。
「ここはお母さんの待っていてくれているところとは違う。」
ヨアンナは思った。
「でも、もういい。」
「だってあの夢を見た日からずっと、お母さんとお父さんが、
私のそばで見ていてくれているのが分るもの。」
「だからもう平気!お母さん、お父さん、これからも、
いつまでもずっとヨアンナの事見ていてね!きっとよ!!」
消灯の時間になり、ベッドに入ると
ヨアンナはいつも父と母と神様に「お休み」を言ってから
眠るのが日課となった。
エヴァは翌日ヨアンナの来訪をとても喜び、
その後ふくれた口調で訴えた。
「ねえ聞いて!
昨日お医者先生が私に特別にくれた栄養剤のお薬をね、
毎日1錠ずつ飲むようにとくれたの。
とてもおいしかったわ。
だけどそれを見ていたエミルとヤンにが
あっという間に私から取り上げ
昨日の晩のうちに残り全部を
食べちゃったのよ!
悔しいったらありゃしない!
あれはお菓子じゃなくお薬なのよ!
信じられない!!」
ヨアンナは深く同情したが、
内心「そんなにおいしいのなら
自分も食べてみたかった」と思った。
でも彼女の前では絶対口にはできない。
来日した孤児たちへの関心と同情は日ごとに高まり、
個人で直接慰問品や義援金を持ち寄る人、
無料で歯の治療や理髪を申し出る人、
学生音楽隊の慰問、
婦人会や慈善協会の慰問会への招待など
善意の支援は後を絶たなかった。
中には孤児たちの着ている衣服のみすぼらしさに驚き、
思わず自分の着ている一番きれいな服を脱ぎ、
渡そうとする者、髪のリボン、櫛、
ひいては指輪まで与えようとした者も
ひとりやふたりではなかった。
その中にヨアンナの記憶に強く残る少年がいた。
少年と云っても、ヨアンナにとっては兄のような年上の人。
彼の名は井上敏郎、当時の中学2年生。(現小学6年生)
孤児支援のため訪れた父についてきたのだった。
そして彼も慰問品を携えてきた。
用意した慰問品では足らず
持っている物は全て与えようと思っていた。
自分のカバンの中の
ノートや鉛筆と数枚の千代紙。
何故千代紙?
彼は聡明で気が利く少年だった。
慰問品だけでは心が通じない気がした。
特に幼い子たちは
きっと喜んでくれるだろう。
彼はその千代紙で折り鶴を折り、
幼い孤児ひとりひとりに渡した。
最後の1枚をヨアンナの手を取り
「これは鶴という幸福を呼ぶ鳥だよ。君にあげる。
幸せになってね。」
とまっすぐな眩しい笑顔で彼女の手のひらに置いた。
「キレイで可愛い!」ヨアンナは思わず笑顔になった。
じっと少年の顔を見つめ
不思議と心が華やぐ思いがした。
どうしてだろう?
このお兄さんにまたいつか会いたい。
そして美しく不思議な紙でできたこの鶴を、
その日まで大切に持っておこうと心に決めた。
年上の優しく素敵な少年の記憶と共に。
福田会(ふくでんかい)育児所の一日は
孤児たちにとって充実していた。
朝6時起床。顔を洗ってから朝の祈祷。
8時朝食。
午前中ポートランド孤児の付き添いの大人が教育係になり
年長者は国語や算数の勉強、
幼児は陽だまりの中や室内でおもちゃ遊び。
昼食後再び勉強し6時に夕食、祈祷、
8時就寝という規則正しい生活をおくった。
ヨアンナはおもちゃ遊びより、
本を読んだり、日本の言葉を知る事に興味を持った。
それと歌。父も母も歌は上手だったから。
年少なのに、よく年長者の教室の隅にチョコンと座り
先生の話を聞こうとしている。
先生も無理に追い出したりせず、
ヨアンナの気の済むようにさせている。
エヴァが完全に回復し
元気に走り回れるようになるまで
それは続いた。
ある日、
ひとりの子が腸チフスに罹り重体となった。
ダレックという男の子。
エミルとアレックの友だちだったが、
福田会にやってきた当初から衰弱が激しく
療養が続いていた。
日を追うごとに次第に元気を取り戻しつつあったが、
不運な事に完治する前にチフスに襲われる。
医師はもう助からないだろうとの診断を下す。
エミルとアレックは心配そうに様子を見に来るが、
うつってはいけないと病室内には入れて貰えなかった。
ふたりは毎日朝の祈祷の前に病室にやって来る。
来る日も来る日も決して会わせて貰えないのに。
彼らのそんな想いは
看病する医療関係者全員の心に伝わった。
その時患者に一番近い担当の若い看護師
松沢フミにも当然伝染する。
彼女は何としても応えてあげたいとの一心から
献身的に看病した。
いつまでも重体の子に寄り添いながら彼女は言う。
「自分の子供や弟が重い病になったら、
人は自分を犠牲にしても助けようとします。
この子には看てくれる父も母もいない。
死んでも泣いて悲しんでくれる親はいない。
せめて自分が母の代わりとなって死にゆく子の最後を看取り、
天国の父と母のもとに送り届けたい。」
そう言い、夜も抱いて寝た。
その結果自らも腸チフスに感染し命を落とした。
感染の危険も顧みず、
言葉通り本当に親のように接し看病した彼女。
その甲斐あってか
重体だったその子は奇跡的に回復、
フミの真心の献身的看病が実り
チフスから生還することができた。
この若き看護師松沢フミの死は
関係者と孤児たちに衝撃を与えた。
事情を理解できない幼子たちは
目の前から姿を消した彼女、
優しかった彼女の名前を呼び続け、
周りの大人たちの涙を誘ったという。
彼女のそうした自己犠牲を伴う献身的看病は
今の医療の世界では勿論許されない。
院内感染は絶対避けなければならない
重要な対策であるのは言うまでもないのだ。
しかし当時の彼女の行為を一体誰が非難できたか?
感染対策の徹底より
献身的な看護が美徳とされた当時。
医療現場に於ける『仁』は必要不可欠な姿勢であり
考え方だったのだと思う。
彼女のそうした自己犠牲を伴った看護の姿勢が
ここで暮らす孤児たちを絶対死なせない。
全員を元気な姿で故国に返す。
それこそが究極の目的であり、
福田会の全てのスタッフの決意と覚悟となった。
そうした経緯もあり、
食事は付き添いのポーランドの大人たちと
福田会の赤十字担当常駐スタッフが
栄養と個々の好みを考え作るようになった。
毎日おやつも出た。
健康で幸せな生活の提供。
彼らの想いと努力はその一点にあった。
そうした日々の生活を重ねるにつれ、
やがて孤児たちは健康を回復し
元気を取り戻しつつあった。
そうした状況を見極めつつ、
次第に生活の中に彩りを加える工夫がされる。
福田会に着いて最初の行事は
唐突に決まった盆踊りであった。
通常東京のお盆は7月であるが、
地方出身者が多く流入する土地柄か、
旧暦の8月に行われる町内会もいくつか存在した。
入所した時期がお盆前であり、
その周辺の町内で孤児とは無関係に
毎年恒例の盛大な盆踊りが開催されることになっている。
当初、福田会として全く参加の予定はなかったが、
夕方から聞こえ始める太鼓とお囃子の音に
異国の子供たちの興味をひかない筈はなかった。
当然ヨアンナも音の方向に行ってみたいと思った。
先生と舎監のレフさんの所に行き、
他の子たちと熱心に懇願したのは言うまでもない。
訴えを聞いた大人たちは困惑しながらも
スタッフ間で話し合ったあと、
「今夜は特別1時間だけ外出許可を出します。
ただし、私たちの引率が条件です。」
そう言って希望者を募り
総勢20人ほどが急遽盆踊り見物に出かけた。
ヨアンナはエヴァが居なくとも
太鼓の音や笛の音、
音頭に合わせて一糸乱れず踊りの輪に魅了された。
いつまでも踊りながら回り続ける様子に
吸い込まれそうになり、
無数の提灯のぼんやりした灯りがもたらす
異国の幻想的な光景に圧倒され、
心から「楽しい!」と思った。
盆踊り飛び入り参加の一件をきっかけにして、
時々開催される慰問会の合間に、
近くの公園へのピクニックが計画、
実行される事となった。
ヨアンナは前日、
夕食前に他の全員と一緒に
ピクニック用に新たに設えられた花柄の洋服と
外履き用の新しい靴をもらった。
よそ行きのきれいな服は
ヨアンナの心を浮き立たせ、
嬉しくて、待ち遠しくて、なかなか寝付けなかった。
神様に明日は晴れるよう、
心から祈った。
雨が降ったらどうしよう?
いつものようにお部屋で遊ぶのも悪くないけど、
ピクニックって何てワクワクする響きでしょう!
きっととても素敵な場所で
楽しい事がいっぱい詰まった時を過ごせるわ!
エヴァも元気になったし、
一緒にお花を摘んで髪飾りを編んでみたい。
ああ、それにおやつのアイスクリーム!!
舎監のレフさんが
明日のピクニックのおやつの事
言ってたけど
どんな食べ物かしら?
今までおやつで出された
羊羹や大福や雷おこしも
もちろん美味しかったけど
アイスクリームって
何て特別な響きでしょう!
きっと特別な食べ物なんだわ。
考えるだけで楽しくて胸がはちきれそう!
部屋の窓には赤十字のお姉さんに教わって作った
テルテル坊主が吊り下げられ、
夜空を見上げ手を合わせ明日の晴れを祈った。
やがて夜も更け興奮冷めやらぬ中、
昼間の疲れから次第に瞼が重くなり
ヨアンナが眠りにつけたのは
就寝時間から2時間以上過ぎた後だった。
翌日の朝はヨアンナの必死の願いを
神様が聞き届けてくれたのか、
小鳥のさえずりと共に
さわやかな秋晴れの目覚めに迎えられた。
起床の合図に目覚め
まだ少し眠いと感じていたヨアンナだったが、
『今日はピクニック!!』
思い出すと同時にベッドから跳ね起きた。
「テルテル坊主さんありがとう!」
テルテル坊主さんも照れた笑顔で返した。
「どういたしまして。ピクニック楽しんでね。」
確かにヨアンナの心の耳には届いた。
祈祷の時間ももどかしく、
他の皆もソワソワしているのを感じた。
ヨアンナはそれでもしっかり
神様の他、お父さんとお母さんにも
報告するのを忘れなかった。
出発の時間。
付き添いの大人たちが
整列を促し、ヨアンナは回復したばかりの
仲良しのエヴァと手をつなぎ
道すがら初秋のまだ青い樹木の景色に包まれながら
楽しく会話しながら歩いた。
ヨアンナがエヴァに、
「今朝私の部屋のエディッタ姉さんとハンナ姉さんが
私に言うの。
エディッタ姉さんったら、
『あんまり興奮し過ぎちゃだめよ!
私は興奮し過ぎておなかを壊した人を知ってるのだからね。
そうなったら初めからおいて行かれるか
途中で連れ戻されるのよ。
そんなの嫌でしょ!
だからちゃんと最後まで参加したいのなら
心を静めて良い子でいる事よ!』
だって!
そんな事できる訳ないじゃない!」
まだ「興ざめ」とか「無粋」とか「余計なお世話」とかいう
言葉を知らないヨアンナ。
「それに下のハンナ姉さんなんか
同い年の男の子の話ばかりするの。
特にエミルなんか虫にしか興味を持たないし、
どうやったら私に振り向いてくれるんだろう?とか、
私も虫に興味を持とうかしら?
でも私大の虫嫌いだから
やっぱり無理!とか
アイスクリームを一緒に食べたいな!とか・・・。
好きにして!!って言いたいわ!
どうしてそんなに男の子なんか気になるのかしら?
がさつでヤンチャで汚いだけなのに。」
「この前なんか、エミルが大きな黒い虫を取ってきて
ハンナ姉さんの目の前にいきなり出してきたんだって。
『私びっくりして泣いちゃった。』
って言うの。
あれカブトムシって言うんだって。
私もそんな大きな虫をいきなり見せられたら泣いちゃうかも?
それにエミルは年上だけど、年下に思えるもの。
どうかしてるわ!
ねぇ、そう思わない?」
ヨアンナがおしゃべりになったのは、
同室で身近なハンナ姉さんの影響なのかもしれないと
エヴァは思った。
福田会から程よい距離の広い公園には
小さな小川のせせらぎと
レンガの並びで仕切られた花壇があり
訪れた者の目を楽しませてくれた。
到着してすぐ、
仲良しごとに小さな布を敷き、
一休みする事にした。
引率の係の大人ではない別の係の大人が
前の日にクッキーを焼いてくれていた。
もし不慣れなアイスクリーム作りに失敗しても
最悪おやつなしで終わるのを避けるためだった。
しかし戸惑いながらも何とか成功し、
幸いなことに子供たちは
アイスクリームとクッキーを同時に食べる事ができた。
でもそのせいでランチのサンドイッチを
残す者が多数出た。
「これは問題だ。次はおやつと弁当のバランスを考えなきゃ。」
と係の大人の言葉を
ヨアンナは聞き逃さず思った。
(次があるのね?楽しみ!)と。
無事盛況にてピクニックを終え、
福田会の宿舎に戻ると、
部屋に入るなり
エディッタ姉さんが
「ただいまぁ!ああ、やっぱり家が一番ねぇ!私疲れちゃった。」
と云い、
ハンナ姉さんが
「エミルったら、私とアイスクリームを食べている間中、
小川の小魚の話ばかりするの!
『私と一緒の間だけは虫の話はやめてね。』って言ったら
目の前の小川の魚の話をするのよ!
失礼しちゃう!もう男の子なんて嫌い!」
と吐き捨て、ベッドのうえで服のまま寝転がった。
しかし翌日、そんな事はなかったかのように
満面の笑顔でエミルに駆け寄るハンナ。
筋金入りの根性を見せ、ヨアンナを呆れさせた。
それからひと月が経ち、
あれほどやせ細っていた子供たちも
運動に耐えるほどの回復をみた。
そこで大人たちは日本人スタッフの助言に耳を傾け
ささやかな運動会を企画した。
運動会と云っても
そんなに激しいものではなく、
お遊戯や椅子取りゲーム、
『もしもし亀よ』などを合唱したり、
パン喰い競争や借りもの競争、
ヨアンナ達幼少部は
飴喰い競争で
真っ白いデンプンの中から手を使わず
口だけで飴を探し顔中真っ白けになり
見る者の笑いを誘った。
当のヨアンナは鼻の穴にデンプンが入り
思い切り何度もくしゃみをして
飴を探すのに時間がかかり
ビリから2番目と振るわない成績に終わり
景品の狙っていたお絵描きノートを貰い損ね、
内心残念に思った
競技の最後は綱引きで
力の限り引きあった。
これには大人たちも全員参加で
向かい合う左右前列が子供たち、
少し間を取り後列に大人たちが
紅組白組に別れ子供たち同様、
大人と大人の意地がぶつかり合う
たいそう盛り上がった大会となった。
その結果屋外での昼食が
大評判だったのは言うまでもない。
やがて落ち葉の季節となり、
紅葉を愛でながら
当時出来たばかりの動物園にも遠征した。
トラやライオンや象さんに驚き、
キリンの首の長さに目を見張った。
ただ、檻の向こうの動物たちは
親がいて子がいた。
親に対し子供たちが
何不自由なく当たり前に甘える様子に
一抹の寂しさが見る者を襲い、
ふいに涙が出そうになる。
目を背け俯(うつむ)く
孤児たちのそうした姿に
引率の大人たちは子供たちを
動物園に連れて来た事を少し後悔した。
やがて冬となりクリスマスの季節がやってくる。
その頃ヨアンナには夢ができていた。
毎日が楽しいここでの暮らしを
忘れる事の無いように記録をとりたいと思った。
でも写真機が欲しいとか、
そう言う事ではない。
見たものを絵にかき、
文字を覚え、感じたことを書き止めたかったのだ。
ヨアンナは午前午後と積極的にポーランドの国語を習い
夕方福田会の図書室で
日本の子供向けの本を読むようにした。
日本での経験はヨアンナにとっての
かけがえのない宝物となっていた。
クリスマスの日、
彼女の願いが通じたのか、
サンタさんから飛び切りのプレゼントが貰えた。
こんな極東の地にも、サンタはやって来るのだ。
「サンタさんはどの子の所にもやって来るの?」
「いいや、そうしたいが現実はそうではない。
私が来られるところは、愛が溢れるところ。
愛を心から欲しがる子がいるところ。
愛を欲しがらない子の所には
行きたくてもいけないんだよ。」
「どうして?」
「それはね、愛は貰うだけじゃなくて、
あげるためのものでもあるからさ。
愛をあげるには、愛を知らなくてはいけない。
愛を知ると云う事は、愛の心を持つと云う事なのだよ。
愛を知ったら、愛をあげたくなる。それが愛。
貰うだけじゃダメなんだ。
うわべだけ良い子なだけじゃダメ。
愛を持った良い子になって、
廻りの人を幸せにしたいと思わなきゃね。
ヨアンナも亡くなった両親を喜ばせたいとか、
笑顔になって欲しいと思ったことがあるだろう?
今も友達のエヴァや他の子たちと仲良く、
楽しく暮らしたいと思うだろう?
喜ばせたいと思うだろう?
その心が愛。
だから私、サンタはやって来たのさ。」
何となく、目元が魚っぽい、
どこかで見たことのあるような、
聞いた事のあるような声でサンタさんは言った。
プレゼントは前から欲しいと思っていた
何でも自由に書き留めることができるノートと鉛筆。
ヨアンナは天にも昇る気持ちになり、
できる限りの表現で思い出を残そうと思った。
天の父と母に見せるために。
そんなヨアンナのすることを横目で見ていた
エディッタとハンナは
自分たちの父と母を思い
自分も何かしなければ!と思い始める。
そして一念発起。
お正月のお雑煮を食べ、
初夢をみた後、
習いたての日本語で書き初めに挑戦した。
お題は「ポーランド」。
やはり祖国は祖国。
年の初めの想いは、
やはり望郷の念が自然とテーマになった。
それでも筆を持ち慣れない子供たちは、
キャッ、キャッ言いながら
思い思いに筆を運ばせた。
エディッタは袂に墨が付き、それに気づくと
「ギャー!!」と叫ぶ。
そして「もう嫌!!」と投げ槍に言い放つも
無心に筆を執るヨアンナを見て
気を取り直し、年長者である自分の不明を恥じ、
一番上手な書を書き上げることができた。
男の子たちはもっと酷く、と言うか悲惨で、
ふざけ半分だったため、
着ている服だけでなく、手も顔も墨だらけに。
お互いの顔を見てはゲラゲラ笑って
とても書き初めとは言えない状態になっていた。
それでも下手くそながら
ひとり一点は完成させることができた。
大人たちはそんな姿を見て
やって来た頃の貧相で病弱で
暗さの漂っていた孤児たちが
明るく元気で楽し気に過ごす様子と
成長に目頭が熱くなった。
そして全員無事に還してやろうと
改めて強く思った。
やがて節分の豆まきを経て
桃の節句がやってきた。
ホールに飾られたひな壇は
ひときわヨアンナの目を引いた。
お内裏様やお姫様の他、
三人官女やぼんぼりがあでやかで
いつまで眺めていても飽きる事がない。
ほのかに明るいぼんぼりは
ヨアンナの心を照らす希望の光にも思える。
憑かれたようにその場から離れない。
ヨアンナは心から美しいと思った。
その後10年以上経過し、
祖国ポーランド暮らしに慣れたはずの
若い娘に成長した彼女はお雛様の影響を
強く受けたのではないかと思われるほど
落ち着いた美を匂わしていた。
そして桜が満開の季節となり、
来た当初は全く目立たなかった庭の桜が
驚きの変化を見せ、
町中の桜も一斉に咲き誇るようになる。
福田会でも当然ささやかなお花見が催され
庭の桜ではなく、外の桜の名所を巡った。
ヨアンナはその圧倒的な美しさに
すっかり心を奪われてしまう。
エヴァとの会話も気もそぞろ。
夢心地の世界で夢遊病者と化していた。
お花見もお開きとなり、
渋谷の福田会に帰ろうとした時、
ヨアンナの姿が見えない。
さあ、ヨアンナはどこに行った?
お花見の会場の
何処を探しても見当たらない。
もしかして人さらい?
引率の大人たちは青くなって真剣に探し出した。
小一時間かけ探しても見つからず、
とりあえず最小限の大人を残し、
他の子どもたちを宿舎に返すことにした。
やがて日が暮れだし、
大人たちは焦ってきた。
「ヨアンナ~!どこにいる~?」
どうしても見つからず、
最後の手段で警察に捜索願いを出すことにした。
最寄りの警察署に向かう道すがら、
引率の日本人スタッフが
ある違和感を覚えた。
黄昏から暗さが増し
街に灯りがともる。
表通りの街灯や家が明るくなり、
通りから奥の家へ続く細道に
何気なく目を送りつつ歩いていると、
細い道の奥に家から漏れる光が映す
小さな影を見つけた。
その影は人の様であり
しかも小さく見える。
「あんな所に人影?」
スタッフは直感から確かめる事にした。
一度通り過ぎた小路へ戻り
速足で歩いた。
他のメンバーは「何?」と云いながら後に続く。
やがて皆はその先に佇むヨアンナを見つけた。
「ヨアンナ!」と叫んだ。
「・・・・・・。」
ヨアンナは言葉なくこちらを振り向いた。
「どうしてこんな所にいるの?心配したのよ!」
口々に「良かった、良かった!」だの、
ダメよ心配かけちゃ!」だの声をかけ、
一同、心からホッと安堵した。
「どうしてこんな所に立っているの?」と聞くが、
ヨアンナが返事をしようとしないので、
「まあ、良いわ。もう暗くなったから早く帰りましょ。」
詳しい事情は帰ってからゆっくり聞くことにし、
まずは施設の全員に無事を知らせるのが先決だと思った。
施設に着くと
心配して待っていたエヴァや大人たちから
一斉に歓声が上がった。
舎監のレフから別室に誘われたヨアンナは、
テーブルに置かれたコップ一杯の水を飲み干し、
心を落ちつかせるとポツリポツリ話し始めた。
「私たちがおやつのクッキーを食べていると、
向こうで私と同じくらいの年の女の子が
こっちを見ていたの。
ジーっと見ていたので気になって
その子の所に駆け寄って声をかけてみたの。
その子は私を睨むだけで何も話してくれないから、
私が持っていたおやつのクッキーをあげようとしたの。
そしたらその子は首を振り、受け取ろうとしてくれない。
そして『いらない!』
私がどうして?って聞くと、
『知らない人に物をもらってはダメって
お母ちゃんに言われているから。』
私も知らない人だからダメなの?
このお菓子を受け取ってはくれないの?
その子は『ウン』と頷くの。
私、その子はお菓子を食べたくない?
いやそんな事はないと思ったわ。
それに楽しそうにしているのが羨ましいのかも?
私はその子と話したかった。
でもその子は私に背を向けて走っていったわ。
だから私は追いかけたの。
私はその子に何か悪いことをした?
あの子を傷つけてしまった?
だったら謝ろう。そう思ったの。
「ヨアンナが立っていたのがその子の家?」
レフが聞いた。
「そう、あの子はもう出てきてくれなかった。
私は悪いの?」
「そんな事はない。ヨアンナは優しい子だから
その子の事が気になったんだね。
でももう気にするのはやめなさい。
その子にはその子の生き方があるのだから。」
ヨアンナは納得できない。
「あの子はきっとクッキーを食べたいのかと思ったわ。
だって食べたそうだったもの。
私なら食べたいと思っている物を
もらえるのは嬉しいと思うのに。
あの子のお母さんはどうして
貰ってはダメだって言うの?
あの子はどうして我慢しなければならなかったの?
私には分からないわ!
私だって今まで知らない人たちに
たくさん、たくさん助けてもらったわ!
それはいけないこと?
私はいけない子?」
「そんな事はない!絶対にない!
ヨアンナはとっても良い子だよ!
自分の事そんな風に思ってはいけないよ。
ヨアンナや他の子もそうだけど、
この施設の子たちは
皆育ててくれる、守ってくれる
両親がいないからここにいるんだ。
親が大切に育てなければならないのに
守ってくれる筈の親が
天に召されてしまったら、
守ってくれる人は居ないでしょ?
だから代わりに周りの大人が何とかしなくちゃいけない。
ヨアンナ達を守るのは、私たちの責任なの。
でもその子には親がいるんでしょ?
だったらその子を守ってくれるのは
その子の親なのだよ。
きっと家が貧しくて
満足にお菓子を与えてあげられなかったのかもしれない。
でも我慢するのがその子の意地だったのだと思う。
どんなに羨ましくても、
父も母もきっと一番その子を愛して
その子の事を思って
その時できる一番良い事をしてくれる。
それを信じているから、
父と母のそんな気持ちを裏切りたくなかったのだろう。
私はそう思うよ。分かる?ヨアンナ。
ヨアンナの今の保護者は私たち大人なのだから、
ヨアンナは私たちを信じて
今は立派に成長するように頑張るのが
あなたたちのお仕事なのだよ。
だからもうあの子の事を気にするのは止めなさい。
でもその優しい気持ちと気遣いはとても尊いと思う。
だからその気持ちだけは無くさないようにね。」
魚を連想する顔でレフは言った。
ヨアンナは諭された内容を
半分も理解できたか怪しかったが、
その日の夜、祈祷の後、ベッドに入るまで
何かを考え続けているようだった。
ヨアンナには特別な力が備わっている。
それは自分が経験した悲劇や痛みを
かけがえのない学びに変える事。
他人の痛みをわが身に置き換え知る事。
その能力が後の運命を切り開く事となる。
そしてヨアンナ以外の孤児たちも
大きな成果が見られた。
次第に福田会での生活も終盤に近付き、
健康と協調と規律を身に着けてきたのだった。
それぞれの孤児たちの成長を
スタッフの誰もが強く感じるほど活気に満ち
福田会は彼らの王国と変容していた。
後編へ続く