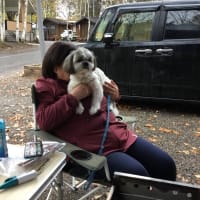#14 イラストのリクエスト〜『シベリアの異邦人〜』の小説から - snow drop~ 喜怒哀楽 そこから見えてくるもの…
新たな旅立ち
東京での彼らの生活が1年ほど続いた
別れの日。
当初のスタッフの決意の通り
誰ひとり欠けることなく
故国ポーランドに帰国できるまでになった。
孤児全員に全員に衣服が新調され、
航海中の寒さも考え毛糸のチョッキも支給された。
しかし特別船の出航が大幅に遅れる。
ヨアンナたちは横浜港から出港するときになって、
本当の母親のように親身にお世話をしてくれた
保母たちとの別れを悲しみ
乗船を泣きながら嫌がったからであった。
ヨアンナもその中のひとり。
彼女はゆりかごのような第二のふるさと日本と、
優しく接してくれた保母さんや他の大人たちと別れ、
大切に心に秘めていた
父と母さえも残してゆくような気がして、
涸れるほど泣いた。
涙も枯れ、ふと空を見上げると、
そこに父と母の気配がした。
優しい声が聞こえた気がした。
「きっとお父さんもお母さんもついてきてくれる。」
「きっとそうだ!」
別れの辛さも、寂しさも、
不安も少しは和らいだ気がする。
いつまでも出立(しゅったつ)を嫌がる
ヨアンナの背中を押すかのように、
新たな門出を促すかのように、
お父さんとお母さんは出てきてくれたのだ。
避ける事の出来ない
辛い別れを悟った孤児たちだったが、
福田会で習い、
毎日歌っていた「君が代」を斉唱し、
幼いながら精一杯の感謝の気持ちを込め
「アリガトウ」を何度も繰り返した。
大勢の見送りの人たちも涙を流しながら、
孤児たちの幸せな将来を祈りつつ、
見えなくなるまで手を振り続けたという。
船の中で船長は
夜ごと孤児たちのベッドを見て廻り、
毛布を首まで掛けなおし、
頭を撫で熱が出ていないか確かめていた。
その手の温かさを覚えていると
孤児のひとりは後になって述べている。
幾日も船上で過ごすヨアンナたち。
いつも船室に閉じこもってばかりもいられず、
良く晴れた凪の日は甲板で過ごすのが日常となっていた。
日本滞在で身に着けた習慣を維持するためにも
規律正しい生活と学びに機会を無駄にせず
有意義な毎日にするために、
随伴の大人たちも、日本人クルーも注意深く見守っていた。
波をかき分け、軽快に進む船旅は、
見方によっては最高の環境だったのかもしれない。
午後の授業も終わり
孤児たちが船室に戻っても
ヨアンナはエヴァと海を眺める事が多かった。
「ねぇエヴァ、私海を眺めるのが好きかもしれない。
だってどこを見てもぜ~んぶ海なんだもの!
何もないって凄いと思わない?
何もないのに全然飽きないって凄いって思わない?」
「そうね、私も好きだわ、何も話さなくても
ヨアンナと一緒なら何だか楽しいの。
変ね、変だけど、ちっともつまらなくないわ。」
エヴァはにっこり笑って受合った。
航海も一週間を過ぎ、2週間を過ぎた頃、
夕方ひとりで甲板に出てくるヨアンナの姿が
見られるようになった。
甲板には必ず転落防止の見張りが立っている。
夕方の時間帯は初老の甲板員が受け持っている。
ヨアンナはエヴァといる時と同じく、
高い手すりの中間の綱につかまり、
流れ続ける波と水平線をただただじっと見ていた。
甲板おじさんはそんなヨアンナを注意深く見守っている。
「お父さん、お母さん・・・・。」
呟く声は波に消され聞こえなかったが、
甲板おじさんの心には確実に届いていた。
そんな光景が3日を過ぎた頃、
おじさんがいつものように
海を見つめるヨアンナに声をかけた。
「お嬢ちゃん、海は好きかい?」
「うん、だってとっても広いんだもの!」
「そうか。ワシも海がすきなんじゃ。
海はいいのう。お嬢さんと一緒じゃな。
でもどうしてひとりなのかな?
この時間は風も冷たくなってくるし、
寂しいじゃろ?」
「ええ、でも今はひとりが良いの。」
「友達と喧嘩でもしたのかな?」
「いいえ、違うわ、エヴァとはいつまでも友達よ!
今の時間はお母さん、お父さんとお話がしたいの。
ヨアンナのお母さんもお父さんも天国に行っちゃったけど、
海を見ているとお話ができる気がするの。
でもいくら呼びかけてもお母さんの声も聞こえないし、
お父さんの姿も見えないの。
ねえ、おじさん、どうしたら会えるのか教えてくれる?
もう会えないのかしら?」
「そうさなぁ・・・。
それはお嬢ちゃんの心次第なのかもなぁ。」
暫くの沈黙の後、
意を決したように甲板おじさんは語り始めた。
「わしの経験を聞かせてあげよう。
お嬢ちゃんにはチイと難しいかもしれないが聞いてくれるか?」
「ウン!お母さんとお話ができるなら、ヨアンナちゃんと聞くわ。」
「そうかい、なら話そう。
ワシの経験談にどれ程の効き目があるか分からが・・・。
ワシにも若い頃はあっての。
そんな昔々の話じゃ。」
遠い目をしながら語り始めた。
「こんなワシにも好きな娘(こ)がおっての、
ワシには太陽のような存在じゃった。
でもな、その娘とは長続きすることなく
離れ離れになってしもうた。
ワシの家も、あの娘の家も貧しくての、
どうしても一緒になれなんだ。
毎日毎日涙を流して身の不幸を嘆き悲しんだ。
だけども悲しんでばかりもいられなくての、
生活があるから一生懸命働くようになった。
それこそ死にもの狂いでな。
そうしてようやく一人前になれて
人並みに嫁さんを貰えるようになった。
でもその時はすでにあの娘は
他の家に嫁にいった後だった。
ワシはそれはそれは落胆したが、
やがて別の話が降って湧いての。
全く別の女(ひと)がワシの女房になってくれたさ。
時間が経って可愛い娘が生まれての。
ワシはとっても嬉しかったなぁ。
でもそのワシの女房は訳ありでの。
次第に夫婦仲は悪くなったんじゃ。
ワシの仕事もうまくいかなくなって
生活が立ち行かなくなっての。
情けない事にワシは女房と幼い娘を置いて
家を出ることにした。
女房には、ワシと一緒になる前からの
心を通じた男が居っての。
その男に女房と娘を託すしかなかったんじゃ。
悔しくて、惨めで、悲しかったが
手放すしかなかった。
ワシが家を出て間もなく女房は
その男と一緒になっての。
ワシは自暴自棄になって
暫くあてのない放蕩生活に堕ちてしまった。
そんな時ワシの心の奥に仕舞っていた
大切な思い出の娘と偶然出会ってな。
と云っても再会した時にゃいい歳になっておったが。
小料理屋の女将になっていた彼女は、
こんな身も心もボロボロなワシを
無様な生き様から救い出してくれたんじゃ。
彼女もワシ同様、旦那と別れ
慎ましく女手ひとつで切り盛りしておった。
豊かではないが、
ワシはようやく心の安らぎを手にしたんじゃ。
でもな・・・・・・。
引き換えにかけがえのない大切な娘を失ってしまった。
再婚したワシとは二度と会ってくれなんだ。
きっと捨てられたと思ったんじゃろ。
父親に捨てられたと考えたら、
さぞかし悲しかったろ、辛かったろ、寂しかったろ。
でもな、ワシは毎日毎日娘の事を忘れたりせん。
忘れる事なんでできるわけがない。
今でも会いたくて仕方なくての・・・。
それが親の気持ちと云うもんじゃ。
分かってくれるか?
だからお嬢ちゃんの両親も天国できっと同じ気持ちじゃろ。
ワシはそう思う。
ワシが死んでこの世から居なくなっても
あの世で絶対娘に会う方法を探すじゃろ。
例え草葉の陰からひっそり一目見るだけでも良い。
いつも、いつも、いつまでも
見守っていたいと必死になるわな。
ワシでさえそうなのだから、お嬢ちゃんの両親が
お嬢ちゃんのそばにいない筈はない。
そうは思わんか?」
ヨアンナには難しい話だったが
ヨアンナなりに深く深く考えた。
「そうね、ヨアンナのお父さんもお母さんも
あんなにヨアンナの事を可愛がってくれたもの。
きっとおじさんが言うように
傍にいてくれているんだと思う。
そう信じてみるわ。
ありがと、おじさん。」
甲板おじさんは満面の笑みを浮かべ
大きく頷いた。
しかし甲板おじさんは
自分がどうしてこんな幼い娘に
身の上話をしたのか、戸惑いと後悔の中にいた。
どんなに親しい人にも、こんな話は打ち明けられない。
絶対に!!
きっとヨアンナには打ち明けたくなるような
人をひきつける力があったのだろう。
幾日も船に揺られながら
故郷の国ポーランドに戻ってきた。
幼かったヨアンナにとって
父の生まれ育った国、母の生まれ育った国、
そして自分が生まれた国。
そう思ったら、何だかここも愛おしく感じる。
ヨアンナは心に誓った。
もう不安な心は捨てよう、
天国の父のため、母のため、一所懸命、精一杯生きて、
自分が天国に行ったとき胸を張って会えるように。
ヴェイヘローヴォ孤児院
長い、長い船旅の末、
孤児一行はバルト海沿岸の
ヴェイヘローヴォ孤児院に引き取られ保護された。
入所後、何と驚くべきことに、
首相や大統領までが駆け付け歓迎してくれたという。
更に施設では毎日朝、
庭に入所孤児が集まり「君が代」を斉唱する決まりがあった。
孤児院出身者の中には医者、教師、法律家など
国の復興の最前線で活躍する人材が数多く育った。
他国からの侵略を受け、そして独立。
苦難の道のりは民衆だけでなく、
国家そのものの運命でもあった。
何もかもが再生・復活の対象の中、
ヨアンナ達帰国孤児にとって生活環境と
教育環境の持続的改善が最重要課題だった。
荒廃と再生。
学校の建設と再生を急ピッチで進めなければならない。
ヴェイヘローヴォ孤児院の周辺の教育環境も
当然満足できる環境とは程遠かった。
しかも当時、子供が教育を受けるには、
一般的にそれなりの負担も必要だった。
教育は無料。そんな現在の常識は
通用しない時代である。
孤児にとって過酷な環境なのは
ここでも変わらない。
でも逆境で歯を食いしばり、
頑張って跳ね返そうとする気質は
頑固なポーランド人の特性かもしれない。
教育が将来の国家の運命を決するとの思いは
ヴェイヘローヴォにも息づいていた。
ヨアンナ達孤児の帰還は、
同時に国家復興の担い手でもあったのだ。
ヴェイヘローヴォ孤児院は
福田会託児所とは環境が全く違ったが、
自分たちが力を合わせて作り上げていく
明るい希望に満ちていた。
服従と戦乱が奪った誇りと活力を
再び取り戻した喜びに満ちていた。
孤児たちは船中生活に引き続き、
孤児院内にあっても
福田会滞在中の習慣や
学びを忘れずにいた。
それは子供たちだけでない。
日本に同行した大人たちの中からも、
特に教育に携わったメンバーが中心になり、
急ごしらえの学校をつくり、
孤児や周辺の子供たちの教育にあたった。
ヨアンナも当然学校に通う。
仲良しのエヴァと机を並べ、
「学校で授業を受けるのは新たな楽しみ。」
帰国という環境の変化に順応する格好の手段となった。
福田会時代の舎監のレフは校長に、
保母さんの何人かは先生兼、
ヴェイヘローヴォ孤児院の世話役になっていた。
ヨアンナが日本でいう小学校6年生相当になった頃、
不安定だった学校の環境も軌道にのり
日本での経験と学びを活かした授業も
少しずつ実践できるようになった。
同室だったエディッタ姉さんとハンナ姉さんは
やがて先輩卒業生として学校運営に関わるが、
相変わらず運動会やピクニックなどの行事に熱心だった。
ヨアンナは得意な歌で年少さんの心を掴む。
特にポーランドに古くから伝わり、
父がよく歌った『はたけのポルカ』と
日本で覚えた『七つの子』は十八番で
人気が高かった。
はたけのポルカ
いちばんめの はたけにキャベツをうえたら
となりのひつじが むしゃむしゃたべた
はたけのまわりで ポルカを おどろう
ひつじをつかまえて ポルカを おどろう
にばんめの はたけに じゃがいも うえたら
となりの こぶたが ぱくぱく たべた
はたけのまわりで ポルカを おどろう
こぶたを つかまえて ポルカを おどろう
さんばんめの はたけに こむぎを うえたら
となりの にわとりが コッコッコココ たべた
はたけのまわりで ポルカを おどろう
にわとり つかまえて ポルカを おどろう
七つの子
からす なぜなくの
かわいい 七つの子
があるからよ
かわい かわいと
からすは なくの
かわい かわいと
なくんだよ
山の 古巣へ
いってみて ごらん
まるい 目をした
いい子だよ
ヨアンナにとって
このふたつの歌は終生
悲しい時、寂しい時の心を癒してくれる
『心の歌』であった。
そうして初等教育、中等・高等教育で
優秀な成績を収め卒業した
ヨアンナは美しい少女へと成長した。
10歳を過ぎた頃
先生からクッキーの焼き方を習ったヨアンナ。
それから毎年学校と
孤児院合同ピクニックの前の日になると
お菓子を焼くのが恒例となった。
女子たちが競ってクッキーを焼くと
楽しみにしていた男子が群がる。
お礼にその日のために覚えたダンスや歌を
女史のために懸命に披露した。
ヨアンナの
クッキーをアレンジしたお菓子は人気が高く、
いつも最初に完売になる。
そして終盤の合唱では
やはりヨアンナが中心だった。
誰からも好かれるヨアンナ。
当然男子からのお誘いも経験している。
特筆なのはエミルからの告白。
放課後孤児院に帰る前のひとりの時を狙って
モジモジしながら待ち受けていた。
「ヨアンナ、ええと・・・、ええと・・・」
「何?」
「ええと・・・、話がある。」
「だから何?」
虫男エミルもそれなりに成長していたが、
ヨアンナにとって彼は変わらず
ハンナ姉さんの恋人であり、
虫男の印象が消えないでいた。
多少ぞんざい気味の扱いになるのは仕方ない。
彼はめげずに意を決して
「僕はヨアンナが好きだ!」
ヨアンナはびっくりした。
何と応えよう?
「エミル、あなたはハンナ姉さんと付き合っているじゃない?
それなのに、どうして私にそんな事言うの?」
「ハンナは僕と仲良くしてくれるけど、
付き合っちゃいないさ。
僕の好きなのはヨアンナだもの。」
「酷い!!ハンナ姉さんが可愛そう!!
よくそんな事が言えるわね!」
そう言って睨みつけた。
エミルはそう言われると明らかに怯(ひる)み
スゴスゴと引き下がった。
しかし暫くの間、未練タラタラな態度を見せ
ヨアンナを困惑させる事となった。
エヴァの結婚
ヨアンナに青春時代があったように
エヴァにも眩いばかりの娘時代があった。
恋愛が青春の総てとは言わないが、
男は女の事ばかり考え、女は男の事ばかり考える。
一般的な青春群像とは得てしてそんなもの。
この物語を読む皆さんはこの物語の流れから
性懲りもなくトンチンカンに生きる
エミルの存在を思い浮かべるかもしれないが、
残念!!
違いました。
ヨアンナとは違った魅力を持つエヴァ。
彼女は誠実で現実主義で、
透き通った青い目を持っていた。
そして何より思慮深く、
誰に対しても慈愛に満ちた笑みを浮かべる。
彼女に見つめられた男は
たちまち恋に堕ちる魔力があった。
ヴェイヘローヴォ孤児院の周辺で
評判の娘ふたり、
孤高のヨアンナと愛嬌のエヴァ。
いつも一緒に行動するふたりであったが、
男どもの熱い視線は不思議と重なる事がなく、
上手く住み分けられていた。
やがてエヴァの信奉者たちは自然淘汰され
最後には近所のピアニスト兼ピアノの先生兼、
調律師のツェザリと、
小学校時代から成績が良かったボレスワフが
彼女の愛を競っていた。
男として線の細いツェザリは
善意で小学校に寄贈された
古いピアノの調律で度々訪れ、
エヴァと知り合った。
さすがショパンの国。
彼の弾くピアノには気品が感じられ、
『調律』と称し、
エヴァに愛の曲を送り続けるツェザリであった。
それを苦々しく睨むボレスワフ。
彼はエヴァと同じ中学の生活委員会に属する事で
親しい関係を構築し、
学校行事や孤児院での課外学習でも
何かというと傍(かたわら)に居ようとした。
年上のツェザリと同級生のボレスワフ。
エヴァにとってどちらも大切な存在だったが、
そのどちらともつかない関係が
いつまでも許される訳もなかった。
エヴァとヨアンナが17歳のクリスマス。
既に孤児院の世話役的存在のふたりは、
先輩のエディッタとハンナの協力もあり、
慎ましくささやかな中にも、盛大さを感じさせる
華やかな祝いの舞台が整えられた。
そこで居合わせた誰もが忘れる事の出来ない
大事件が起こった。
優雅にピアノをつま弾くツェザリ。
負けじと孤児院と学校運営について
盛んにエヴァに語りかけるボレスワフ。
突然ツェザリのピアノが止まる。
ふたりの前にツカツカと歩み寄り、
彼は言った。
「君、私が心を込めて弾くピアノの邪魔をしないでくれたまえ!」
ボレスワフは眦(まなじり)をキリッと上げ、
年上の彼にきっぱりと云った。
「あなたこそ、今エヴァと大切な運営の話をしているので
入ってこないでください。」
「君、今ここはクリスマスのパーティーなのだよ!
パーティーに無関係なくだらない話は
いつでもできるだろう?
そういう事は終わった後にしてくれないか?」
「あなたの方こそ、
神聖なクリスマスにふさわしいとは思えない
下世話な曲を弾くのは止めてもらえませんか?」
どうやら炎の目をしたふたりには、
周囲の戸惑いと野次馬的好奇心と、
エヴァのどうしたら良いか分からない
困惑した表情が入ってこないらしい。
一部始終を目撃していたヨアンナが一言。
「言い争いは外でしてくださらない?
ここには幼い子供たちも居るのよ。
貴方達ふたりとも、
クリスマスに相応しくない争いをしているのに
お気づきになりませんか?」
はたと我に返ったふたり。
振り上げたこぶしを治めるには
あまりに難しい状況になっていた。
ここでエミルが登場する。
ヨアンナに未練を残す彼は、
ここぞとばかりに気が利いた提案をし、
名誉を挽回したいと思い、
両者に向かって言い放った。
「君たち!私たちが幼い頃行った日本では、
神様の前で物事の決着をつける「相撲」という
決闘があるそうだ。
衆目の面前で決着をつけ、
恨みっこなしとするのはどうか?」
エミルは簡単に相撲のルールを教え、
ここにいる全ての参加者に証人となるよう
呼びかけた。
するとたちまち皆の興味をそそり、賛同を得た。
「それこそクリスマスのパーティーには相応しくないわ!
エミルの馬鹿!!」
ヨアンナは思ったが、時すでに遅かった。
あとに引けないふたり。
エヴァは結果、
自分がふたりの勝負の賞品になってしまうのに気づき、
言葉にならない金切り声をあげたが
後の祭りだった。
エミルの馬鹿!が行司となり、
真剣勝負が始まった。
ポーランド語で「はっけよい!のこった!」
とは何と云えばよいのか分からないが、
エミルなりの怪しい行司により
一進一退の勝負は続いた。
もう見ていられないエヴァは
両手で顔を隠すが、
指の隙間から両目が覗いていた。
やがて年下ながら、体力に物を云わせた
ボレスワフが上手をとり、
ツェザリを豪快に投げ飛ばした。
決着がつくなり、一気に会場が湧きたった。
ボレスワフが勝鬨を上げると、
力なく立ち上がったツェザリは
歪んだ顔で睨みつける。
ボレスワフは右手を差し出し握手を求めたが、
歪んだままで固まったツェザリを見て
強引に右手を掴み握手した。
いたたまれなくなったツェザリは走り去り、
会場を後にしたまま、二度と姿を見せなかった。
「エッ?!私はボレスワフのものになったの?」
焦りと狼狽がエヴァを襲った。
残ったふたりを祝福する声・声・声!
「エミルの馬鹿ァ!」
エヴァは二度目の金切り声をあげ、エミルを罵った。
結局エミルの評価は上がることなく、
エヴァはボレスワフのものとなり、
2年後結婚する事となった。
しかし、日本の風習の何と恐ろしい事か!
いや、そんなことはないから!!!
馬鹿げた誤解に騙されないで!
エミルの馬鹿ァ!!
こうしてヨアンナとエヴァの青春の幕は開けた。
そしてその頃からヨアンナは
ある活動に興味を持ち始め、次第に没頭した。
『極東青年会』と『イエジキ部隊』
ここにひとりの重要人物がいる。
彼の名はイエジ・ストシャウコフスキ。
自ら孤児出身でありながら、
孤児院で働きワルシャワ大学を卒業。
孤児教育の道へと志した。そして17歳の時、
シベリア孤児の組織を作ることを提唱。
ポーランドと日本の親睦を図ることを目的に
「極東青年会」を結成し、自ら会長になった。
最盛期には640名にも上ったという。
ヨアンナは彼の行動力に惹かれ
「極東青年会」のメンバーとなり、
できる限りの貢献をして頑張ろうと考えた。
恋愛感情とは別の憧れを持っての行動だった。
ヨアンナの他、成長した孤児たちは皆日本との絆絶ち難く、
在ポーランド日本公使館との交流を大切にした。
そして日本国政府もこの絆を大事にした。
勿論人道的な結びつきによる、
当然の好意の延長もあるが、実はそれだけではない。
大人の事情があった。
それは日本にとってロシアは常に仮想敵国であり、
国の動向と
予測の分析・対策の構築が国是であった。
歴史を少し遡(さかのぼ)るが、
日露戦争当時ロシア支配下のポーランドには、
二人の指導者がいた。
対ロシア武装蜂起派のユゼフ・ピウスツキと、
武装蜂起反対派のロマン・ドモフスキ。
ふたりは日本の当時参謀本部長 児玉源太郎、
福島安正第二部長に面会し提案した。曰く、
「極東地域のロシア軍の三割はポーランド人である。
戦闘の重大局面でのポーランド兵の離反、
シベリア鉄道の破壊。
その対価として、
ポーランド兵捕虜に対する特別な待遇を願いたい」
と申し出たのだった。
その提案を受け入れた証拠のように、
四国松山に収容されたポーランド捕虜は、
ロシア捕虜と別の場所にて特別待遇を受け、
とても捕虜とは思えない
厚遇と心温まるもてなしを受けた。
更に対ポーランドの実質窓口となった
明石元二郎大佐が中心となり、
ポーランド武装蜂起支援、
武器購入資金提供を実行、
日露戦争勝利後はポーランド独立を助けている。
ポーランドと日本はそうした関係にある。
「極東青年会」の活動が持つ意義は
単にイエジという青年の理想に留まるものではない。
100年後のポートランドと日本の関係の礎であり、
祖国再興と他国の侵略からの防衛の役割を
担う事になる組織であった。
そうした歴史的結びつきを背景にしながらも
国際連盟脱退、
日中戦争勃発と孤立化した日本。
その延長線上に日独伊三国軍事同盟がある。
日本にとってこの同盟は
ただ単に国際的孤立を避けるためだけではなく、
対ソ政策でもあったのだ。
当時日本は前述したとおり、
泥沼の日中戦争の真っ最中。
関東軍が作戦展開中、
満州国境沿いに対ソ守備隊を多数配置していた。
やがて二度にわたるノモンハン事件を経験する。
事件というが、実質的な戦争であった。
手痛い敗北を喫した日本。
益々情勢が厳しくなる中、
中国大陸に覇権を広げる日本に警戒し、
圧力を強めるアメリカの野望も見えてきた。
今後予想される対米戦のためにも、
満州の守備隊の活用準備は絶対必要だった。
そのため、ドイツには対ソ戦略で頑張ってほしい。
ソ連軍の極東守備隊を
ヨーロッパ戦線に差し向けさせるためにも
同盟は必要だった。
ただそのためにドイツとソ連の中間に位置する
ポーランドは結果的に犠牲になる。
それは日本の望むところではないが、
大国間の領土争いに口出しできるほどの
国力も影響力も日本にはない。
ポーランドが
武力で蹂躙されるのを阻止する
ことはできないのだ。
それならせめてポーランドに対し
できる限りの支援をすること。
日本はその道を選んだ。
そう、日本はドイツと軍事同盟を結んでおきながら、
水面下でポーランド支援も行うという、
二重政策を遂行していた。
そしてポーランドに対し支援をする理由はもうひとつ。
ポーランド人を味方につけ、ドイツの動向、
ソ連の動向の情報収集の諜報活動家として
活用する事も目的だった。
そうした事情から、
日本の大使館・領事館などの在外交機関は、
現地法人の保護・管理の他、
日本の国策遂行・実行部隊としての側面も帯びていた。
大使館員は文官と武官が存在するが、
多かれ少なかれ、
いずれも諜報・特務を使命のひとつとして活動していた。
しかもそれは官僚にみに留まらず、
民間にも特務機関からの要請を帯び、
その対価として
事業の支援を受け現地でビジネスを展開する者、
邦人・外国人を問わず
ビジネスの実態を伴わない
実質諜報員的な民間人も存在した。
そんな情勢の中、
孤児たちの主催する行事は公使館の館員も大切にし、
できるだけ全員参加を原則にして応援した
しかし世相は暗く厳しく悲しい時代。
大きな戦(いくさ)が孤児たちの前に立ちはだかっていた。
1939年ナチスドイツが突然電撃作戦で、
ポーランド国境を越え侵攻してきた
イエジ青年は極東青年会を臨時招集し、
レジスタンス運動に参加することを決定した。
部隊の名を青年の名をとり、
『イエジキ部隊』と呼ばれるようになった。
さてヨアンナだが、
彼女も成長し可憐な乙女時代を過ごし、
当然の流れの中「極東青年会」の一員として
不動の活躍の場を確保している。
彼女はその聡明さと明るさ、
そして人を引き付けるような美しい娘になっていた。
彼女自身は福祉事業家を目指す仲間の孤児に共鳴し、
行動を共にしながら、
青年会の活動では中心的存在だった。
彼女が青年会に本格的に顔を出すようになったのは
17~8歳の頃から。
それ以前にも参加してはいたが、
正式なメンバーとして加入するには
歳が足らなかった。
そういう訳で20歳を過ぎた頃には
すっかり青年会の花となり、
いつも彼女は人々の中心にいた。
エヴァはヨアンナとは別の道を選び、
結婚し幸せな家庭を築くが、
生涯変わらずヨアンナの友として
時には一番の支援者となっていた。
ちょうどその時、
日本の公使館に出入りするようになった青年がいる。
井上敏郎。福田会に孤児支援に来た
当時中学2年生だった少年だ。
彼はどこで覚えたか
ポーランド語、ドイツ語、ロシア語を駆使し、
複数の公使館館員と深い交流のある民間人だった。
彼は少年時代の面影を残しながら、
長身の好青年になっている。
彼は他の大使館・公使館員と共に
よく青年会の催しに参加した。
機知に富み、ユーモアで人を笑顔にし、
それでいて隙の無い所作。
館員の誰よりも洗練されていた。
時々会話する青年会のメンバーも
彼には一目置いている。
彼は一体何者?
日本人には珍しくポーランド語を話し
日本の商社の社員と云っていたけど、
他の社員など見た事無い。
公使館員と深いつながりがありそうで、
何故だか分からないが好感が持てる。
青年会のメンバーの彼に対する評価だった。
ただもし彼が特務機関員だったとしたら、
彼にはひとつ大きな弱点がある。
それは善良過ぎる事。
幼少期そのままに真っ直ぐ育った彼は
人の道に反する行為とは無縁の場所にいた。
そんな彼がヨアンナと接する機会は少なくない。
彼女を最初に見たのは彼女が初めて顔を出した頃。
多分17~8だったのだろう。
可憐な彼女を一目見た時、青年敏郎は
「なんて素敵な人だろう!」
感嘆符付き(!)で見とれてしまった。
彼は自分が少女だった彼女に
昔折り鶴を贈った事を覚えていない。
そして彼女も自分に折り鶴をくれた年上の少年が今、
そばにいる彼だとは気づかなかった。
『イエジキ部隊』が地下レジスタンス活動を活発化させた頃、
ヨアンナも当然のように参加するようになる。
しかしそれは命がけの行為であり、バレたら命はない。
周囲の青年会メンバーは彼女を心配し自重を求めた。
しかし彼女は引くつもりはない。
何故なら彼女は孤児として
沢山の人から受けてきた恩に報いる時と考えたから。
今守るべきもの
それは彼女が生きてきた証。
彼女を守るため、父が母が命を落とし、
シベリアから救出されるまで
数え切れない助けがあった。
更に日本滞在中受けた善意。
ピクニックで見かけた近所の子の
両親に対する信頼と意地、プライド。
ヴェイヘローヴォ孤児院や学校での生活。
祖国ポートランドを蹂躙する者への抵抗は
それらに恩を返し、自分を救ってくれた行為は
価値があった事の証明にしたいから。
勿論安全なところで幼い孤児たちの世話をすることも
尊い行為ではある。
でも命を懸けて自分を守ってくれた人々に比べたら、
遠く及ばないように思う。
比べる必要はない。
人はそれぞれ役割がある。
自分にふさわしい最善の行為で報いるのが
ホントは正解なのかもしれない。
自分を守ってくれた人達は
ヨアンナが命を危険に晒す任務に就くことを望んではいない。
幸せに生きてほしいのだ。
人生を全うするのが一番の望みである事も分かっている。
だがそれでも燃え滾る使命感の火を
消すことはできなかった。
ある日の催しは戦局厳しい状態にもかかわらず、
慈善事業の寄付金を募る恒例のパーティーを決行。
つつましくも華やかな晩餐会とダンスが展開された。
しかし、さすがに日本公使館が
バックアップしているだけある。
この日もいつものように内外の有力者、
著名人などが集まり、盛況だった。
この日も敏郎の姿が見える。
グラスを持ちながら、
見かけないある人物と何やら熱心に立ち話をしていた。
離れた場所で、しかも難しい日本語だったので、
聞き取れず何を話しているのか分からない。
ヨアンナは敏郎が気になったが、
時々チラッと見るだけで、
近づいて話しかける勇気はなかった。
でもあの方の事は勿論そうだが、
あの方が話されているのが
誰なのかも気になって仕方ない。
ヨアンナは心の中の小さな勇気をかき集め、
馴染みの公使館員に聞いてみた。
「今日はあの方もお見えなのですね。
楽しんでいただけているかしら?
あの熱心にお話しされていらっしゃるのはどなたでしょう?」
視線を敏郎に向けながら、
公使館員に自然な調子で声をかけてみた。
まるで賓客を気遣うマダムのように。
彼女の心の中を知ってか知らずか、館員は、
「いつも貴女(あなた)は心遣いが細かいのですね
ああ、敏郎が話している相手は、杉原さんです。
リトアニアに赴任した領事。
きっとこれからもあなたたちと関りがあるかもしれないから、
覚えておいてもいいと思いますよ。」
「杉原さん?」
「そう、杉原千畝領事。」
彼女はじっとふたりを見つめているのだった。
翌日会場の片付けと後始末の残りを終えたヨアンナは、
昨夜の宴の場から家路への帰途の歩みを早めていた。
短い夏も終わり、
秋を飛び越え一気に冬の風を感じ始める頃、
こちらに向かう見覚えのある
いや、このような偶然を心のどこかで
いつも待ちわびていたある姿に焦点が合った。
「あの方だ!」
歩きながら全身がワナワナ小刻みに震えるのを感じた。
数秒後、向こうも私に気がついたようだ。
歩調が心なしか早まりながらも、
「落ち着け!落ち着け!!」と念じ距離を縮めていった。
ふたりの間に石でできた古い橋が一脚。
向こうとこちらに近づいた時、
彼の方から声をかけた。
「やあ、昨晩はどうも!」
「こちらこそ、いらしていただき、
感謝しております。」
普通の会話だった。
本来そこで終わる筈だった。
でもここで何か話さなければ!
お互いがそう思ったが、
押し黙る沈黙が無限の長さに感じた。
「そうそう、昨晩の、」
「あの時のあの方、」
不意に同時に発した互いの不自然な雰囲気と
少々浮ついた語調に可笑しさを感じ、
目が合ったふたりは笑いを押し殺していたが、
こらえきれず思わず吹き出し、
声を出して笑い合った。
同時にその時お互いが他の人達に対してとは違う、
特別な感情を抱いてくれているのを感じた。
「今なんて言おうとなさったの?」
ヨアンナは少し時間をおいて改めて聞いた。
「えぇ、昨晩のパーティーはとても楽しかったです。
そう言おうとしました。貴女は?
「・・・昨夜は楽しそうにお話されていましたね。
いつもとはちょっと違う貴方を見たような気がしましたわ。」
「そうですか?私は貴女に見られていたのですね。」と
はにかむような笑顔で応えた
「昨夜は私にとって、
もとても有意義な時間を過ごせました。
私の話していた相手は
人生の目標のような人で、
私の価値観に大きな影響を与えてくれた方なのです。」
「そうだったのですか。
そんな大切な機会に関われて、
とても嬉しく思います。」
「ところで私、いつも感心しているのですが、
井上さんはとてもポーランド語がお上手ですが、
どちらで学ばれたのですか?」
「上手だなんて、お恥ずかしい。
私は父の仕事の関係でポーランドに居る期間が長く
その間に覚えたのです。」
「そうですか、
日本の方がこちらでお仕事なさっているのは珍しいですね。
御父上様は外交とかのお役人様なのですか?」
「いえ、今の私と同じ商社の社員です。
父は仕事の関係で、
様々な国を渡り歩く放浪者のような人でした。
私も今は拠点をこちらに於いていますが、
実質的な特派員なので、
現地社員は私だけ、気軽なものです。」
そう言ってまたハハハと笑った。
「ところでヨアンナさんは極東青年会の活動をされていますが、
日本に来られた事があるのですか?」
「はい、東京で一年お世話になっています。」
「そうでしたか、
私も一度福田会の施設を訪れたことがあるのですよ。」
ヨアンナは驚き、改めて目を見開いた。
「皆様にとても良くして頂いて、
私にとって夢のような日々でした。
たくさんの方が色々な物をくださったのよ。
ほら、こうして今でもあの時から大切にしている物があるの。」
そう言って手にした小物バッグから何やら取り出した。
それは長い年月の間に
すっかりくたびれてしまった鶴の折り紙だった。
それを目にしたとき、
敏郎は忘れていた
昔の記憶を呼び覚ました。
「その折り鶴、見覚えがある!
そう、もしかして私が作った物?」
「ええ?私は年上の日本のお兄様からいただいたの!
もしかして
貴方はあの時の日本の親切で優しかったお兄様?」
「そう言われるとお恥ずかしい!
ああ、あの時のお人形さんのように可愛かった
幼い女の子のひとりだったのですね?」
「そうおっしゃられると、
私こそ顔から火が出そうなほど恥ずかしく思います。
こんな奇跡のような偶然って本当にあるのですね!
とても嬉しいです。」
「私もそう思います!
まさかあの時作った折り鶴を今でも
こんなに大切に持っていてくれた方がいたなんて!
しかもそれが貴女だったなんて!!
何という、何という・・・」
驚きと喜びで敏郎は言葉に詰まった。
しばし無言で橋の真ん中から
川の流れに目をやりながら、
彼女の悲劇のドラマのような人生に思いをはせ、
「貴女は生まれてからずっと、
茨のような苦難の道を歩まれてきたのですね。
貴女にとって日本に滞在した時間は
ほんの短いものだったと思うけど、
他に何か覚えていますか?」
「短いい時間?とんでもない!
私にとってとてもとても大切な思い出です。
日本の記憶?
そう、日本の記憶は私の宝。
私が今生きているのも、
希望を捨てないのも、日本で過ごせた記憶があるから。
確かにポーランドと日本じゃ環境が全然違います。
帰国して辺りを見渡しても、
日本を思いだせるものなんて何もない。
でも私にとってどんなに距離が離れていても、
変わらない大切なものがこの鶴の他三つあるの。」
「へえ、それは何ですか?」
「それはね、お月さまとお星さま。」
「『お』と『様』をつけて呼ぶのは
お月さまとお星さまだけ。
それにお月さまを見ては想い、
お星さまを見ては願うようになったのは
日本でお世話になってから。」
「日本では太陽のことをお日さまと呼びますけど、
こちらの太陽は低くて暗いの。
あまりお日さまと呼べるような実感が湧かない
私、日本でお世話になっているとき、
窓の外に映るお月さまを見ては父と母を思い出し、
お星さましか見えない夜は願うの。
『どうか父と母が夢に出てきてくれますように』って。
その習慣は、
この地に帰ってきてからも変わらず続けているわ。
可笑しい?いい歳した娘が、
月や星にそんな事思うの。
それから三つめは思い出。
とても大切な思い出を
日本は私に数え切れないほどくれたわ。
日本とポーランドじゃ何もかも違うけど、
変わらないのを持ち続けるのは素敵なことだと思う。
だから私にとって、
とても大切な思い出や、
あのころからの習慣は宝物なのです。」
橋の欄干から遠くを見据えるように彼女は言った。
敏郎には、
すぐ隣にいる筈のヨアンナが愛おしく、愛おしく、
しかし、潜り抜けてきた苦難を
理解も実感も想像もできない分、
もどかしい距離を感じた。
暫く無言のまま時間が過ぎ、
橋の向こうを見つめながら敏郎は言った。
「大切にしてくれてありがとう。
うん、ありがとう・・・。
僕は今日、ここで、
この橋の上で逢えた時間をいつまでも忘れない。
一生忘れない。
目の前の美しい景色を忘れない、
今感じているこの気持ちを決して忘れない。
いつまでも。」
ヨアンナも敏郎にまっすぐ向き合い、
「私も。」
万感を込めた眼で一言そう言った。
戦乱は激化し、
イエジキ部隊もさらに危ない活動に日々を費やした。
また日本の外交官たちもその身に危険が迫ってきた。
まず、リトアニア領事がロシアから
退去の最終勧告を受け
帰国の憂き目を見ることになった。
後に有名な『いのちのビザ』の発給に
杉原千畝領事はギリギリまで全精力を注いでいた。
その行為は国策に反し、
召喚されたら厳しい処罰が待っていることも覚悟の上。
自分の信念に従った彼は
微塵も後悔していないのだった。
リトアニアはバルト海沿岸に位置する。
ヴェイヘローヴォ孤児院もバルト海沿岸。
地理的に近い好条件もあり、
敏郎との親交から、
度々領事と情報交換をしていたが、
最終勧告を受けた日の晩、
偶然にも訪れていた敏郎と
二人だけのささやかな送別会が行われていた。
そして翌日から彼の退去の列車に乗り込むまで続いた
命のビザとの戦いが始まったのだった。
一方イエジキ部隊は
シベリア孤児を中心に彼らが面倒をみてきた孤児たち、
今回の戦災で家族を失った新たな孤児たちも加わり、
一万数千人まで膨れ上がり一大組織に成長している。
戦争による悪化に伴い
地下レジスタンス活動が激化し、
イエジキ部隊に対する
ナチス当局の監視と警戒の目が厳しさを増した。
イエジキ部隊は隠れ蓑に孤児院を使っていたが、
突然ナチスからの強制捜査があった。
急報を受けて駆け付けた日本大使館の書記官は、
「この孤児院は日本帝国が保護する施設である。
その庇護下の施設が
日本と同盟する貴国を害するはずはない。
疑いを解き速やかに退去されたし!」
そう威厳をもって言い放ち、抗議した。
しかしそう簡単に納得できないドイツ兵は
「しかし我々も確かな情報に基づき行動している。
子供の遣いでもあるまいし、
はいそうですかとそう簡単に撤収するわけにはいかない。
とにかく納得するまで捜索させてもらう!」
と突っぱねる。
そこで書記官の後ろに控えていた敏郎が
不安におびえる孤児院に向かい、
「大丈夫!君たちが怯えることは何もない!」
そして孤児院院長を兼ねたイエジキ部隊長に向かい、
「君たち!
このドイツ人たちに日本の歌を聴かせてやってくれないか!」
と呼びかけた。
イエジたちは意を決し、
立ち上がると日本語で「君が代」や
「愛国行進曲」などを大合唱した。
その様子にあっけにとられ、
圧倒されたドイツ人たちは立ち去った。
その頃のドイツは先に述べたように
日本との軍事同盟下にある。
日本大使館には
一目も二目も置かざるを得ない状況にあった。
そして日本大使館はその同盟を最大限活用し、
イエジキ部隊を幾度となく庇護した。
しかし兵力で圧倒的に勝る
ナチスドイツ軍への抵抗は長くは続かず、
部隊の関係者は徹底的に逮捕され処刑された。
そして運命の日。
ドイツ軍部隊が
イエジキ部隊の拠点に踏み込み
多数の死者と逮捕者が出た。
報に接し、
急いで拠点に駆け付けようとするヨアンナ。
ほぼ同時に報を耳にしてヨアンナの
もとに向かう敏郎。
ふたりは隠れ家の手前で遭遇した。
眼前の銃声と叫び声、
破壊の轟音にヨアンナは取り乱し、
敏郎の静止を振り切り止めさせようと駆けだした。
その様子に気づいたドイツ兵が
振り向きヨアンナに銃口を向けた。
救出の仲間が現れたと思うドイツ兵。
相手が女性でも冷静さを欠き
容赦なく冷徹な行動に出る。
そして向けられた銃口が火を噴いた。
咄嗟にヨアンナを庇い、前に出る敏郎。
しかし銃弾に晒されても彼は倒れなかった。
思わず悲鳴を上げるヨアンナに
正気を取り戻したドイツ兵は、
引き金を戻したがもはや全ては遅かった。
誤って東洋人を撃ってしまった。
その場に立ち尽くし、
ヨアンナとようやく崩れる落ちる敏郎を見ていた。
ヨアンナは半狂乱で敏郎にすがり、
その名を呼び続けた。
ヨアンナの腕の中、
敏郎は宙に目をやり、
最後に空の青さと
ヨアンナの顔を焼き付け
静かに目を閉じた。
つづく