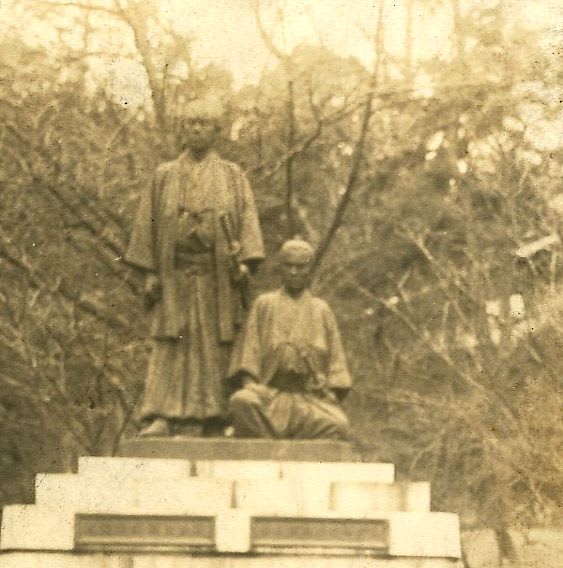京都御苑の9門の一つ、天明の大火(1788年)の際に初めて開門されたこ とから「焼けて口開く蛤」にたとえられ「蛤御門」・・・・禁門の変[きんもんのへん](蛤御門の変[はまぐりご もんのへん])1864年8月20日(元治元年7月1日)長州藩と幕府軍の激戦であった。
「天皇に弓ひく者」(長州藩)ということで門扉(右)には銃弾の跡が保存された。

 新婚旅行で坂本竜馬とお竜(おりょう)がが立ち寄った露天風呂
新婚旅行で坂本竜馬とお竜(おりょう)がが立ち寄った露天風呂

 寺田屋でお龍は風呂から裸のまま2階へ階段を駆け上がり危機を知らせた。龍馬は主に銃で反撃。左手の親指を負傷した、西郷隆盛の斡旋により薩摩領内に潜伏する。
西郷隆盛や家老の小松帯刀(たてわき)たちが、薩長同盟のあと寺田屋で襲われてケガした龍馬に保養してもらおうと招待する。
塩浸温泉を訪れ10日ほど滞在し寺田屋で受けた 傷を癒したといわれています「龍馬手帖摘要」谷間に龍馬も入ったという今は使われていない2.3人入れる露天風呂が当時を忍ば せている日本で始めて新婚旅行をした、坂本竜馬とお竜(おりょう)が立ち寄ったところで有名である。
お竜の生涯
龍馬は慶応元(1865)年9月9日、乙女とおやべ宛てに長文の手紙を書いている。禁門の変が 起き、京都は焼かれ弟妹は四散、売られようとした妹を救出するお竜の雄婦ぶりを描き、 「右女ハまことにおもしろき女」「私のあよふき時よくすくい候事どもあり」「名はお竜と申、私し ニにており候」と知らせ、「乙大姉の名諸国ニあらハれおり候」と乙女を持ちあげて帯や着物を つかわして下さい、とねだっている。慶応2(1868)年1月、薩長同盟成立後に起きた伏見寺田 屋事件では、入浴中のお竜は風呂から飛び出して注進し、薩摩屋敷にも急を知らせるなど、 龍馬の危機を救う働きしている。
美人で花を生け香をきき茶の湯を致す教養を持ち、気丈な男勝りの京女は、海援隊士らに 「姉さん」と呼ばれたが、土佐藩大監察佐々木高行は日記に「有名ナル美人ノ事ナレ共、賢婦 人ヤ否ヤハ知ラズ、善悪共ニ為シ兼ネル様ニ思ヒタリ」と表している。
龍馬の没後しばらくは、三吉慎蔵の世話になり、明治元年、龍馬の高知の実家に迎えられた。
だた、一年ほどで京都に戻り、龍馬の墓のかたわらに庵室を結んだ。お竜が土佐を去るとき、 たくさんあった龍馬からの手紙は、この手紙は人に見せたくないからと、すっかり焼いてしまっ たようだ。
やがて西郷らを頼って東京に出、明治8年に旧知の大道商人西村松兵衛と再婚し、西村つる と名乗り、晩年は横須賀三浦郡豊島村の観念寺裏長屋で夫とくらし、貧窮の中で、明治39 (1906)年に没している。享年66歳。墓は(龍馬の有志人々により)神奈川県横須賀市大津3 丁目信楽寺(しんぎょうじ)門前に「贈正四位阪本龍馬之妻龍子之墓」とある。
寺田屋でお龍は風呂から裸のまま2階へ階段を駆け上がり危機を知らせた。龍馬は主に銃で反撃。左手の親指を負傷した、西郷隆盛の斡旋により薩摩領内に潜伏する。
西郷隆盛や家老の小松帯刀(たてわき)たちが、薩長同盟のあと寺田屋で襲われてケガした龍馬に保養してもらおうと招待する。
塩浸温泉を訪れ10日ほど滞在し寺田屋で受けた 傷を癒したといわれています「龍馬手帖摘要」谷間に龍馬も入ったという今は使われていない2.3人入れる露天風呂が当時を忍ば せている日本で始めて新婚旅行をした、坂本竜馬とお竜(おりょう)が立ち寄ったところで有名である。
お竜の生涯
龍馬は慶応元(1865)年9月9日、乙女とおやべ宛てに長文の手紙を書いている。禁門の変が 起き、京都は焼かれ弟妹は四散、売られようとした妹を救出するお竜の雄婦ぶりを描き、 「右女ハまことにおもしろき女」「私のあよふき時よくすくい候事どもあり」「名はお竜と申、私し ニにており候」と知らせ、「乙大姉の名諸国ニあらハれおり候」と乙女を持ちあげて帯や着物を つかわして下さい、とねだっている。慶応2(1868)年1月、薩長同盟成立後に起きた伏見寺田 屋事件では、入浴中のお竜は風呂から飛び出して注進し、薩摩屋敷にも急を知らせるなど、 龍馬の危機を救う働きしている。
美人で花を生け香をきき茶の湯を致す教養を持ち、気丈な男勝りの京女は、海援隊士らに 「姉さん」と呼ばれたが、土佐藩大監察佐々木高行は日記に「有名ナル美人ノ事ナレ共、賢婦 人ヤ否ヤハ知ラズ、善悪共ニ為シ兼ネル様ニ思ヒタリ」と表している。
龍馬の没後しばらくは、三吉慎蔵の世話になり、明治元年、龍馬の高知の実家に迎えられた。
だた、一年ほどで京都に戻り、龍馬の墓のかたわらに庵室を結んだ。お竜が土佐を去るとき、 たくさんあった龍馬からの手紙は、この手紙は人に見せたくないからと、すっかり焼いてしまっ たようだ。
やがて西郷らを頼って東京に出、明治8年に旧知の大道商人西村松兵衛と再婚し、西村つる と名乗り、晩年は横須賀三浦郡豊島村の観念寺裏長屋で夫とくらし、貧窮の中で、明治39 (1906)年に没している。享年66歳。墓は(龍馬の有志人々により)神奈川県横須賀市大津3 丁目信楽寺(しんぎょうじ)門前に「贈正四位阪本龍馬之妻龍子之墓」とある。