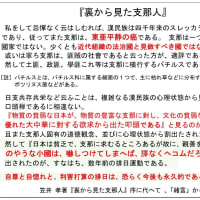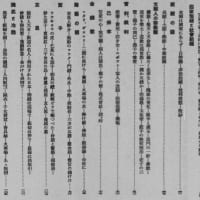大川周明『日本精神研究』
第一 横井小楠の思想及び信仰
一 横井小楠の思出
紛々たる世間の是非は、決して人間真個の価値を損益するものでない。遇へるが故に貴きを加へず、知られざるが故に失ふなしと云ふは、何人も異存なかる可き真理である。それにも拘らず吾等は、識徳一代の師たるに余りある人が、住々にして坎(カン、あな)珂(か)【カンカ、①行きなやむさま、②世に認められないさま】不遇の間に終へたるを見る時、心に深き悲みを覚えざるを得ない。仮今玄徳の三顧なかりしとしても、孔明は依然として孔明である。さり乍ら草蘆に膝を抱いて朗吟するのみが、決して彼れの全面目でなく、漢室を既に絶えたるに起して大義を天下に明かにせるところ、大丈夫の本領最も如として居る。又は太公望にしても、直鈎を垂れて渭水の浜に釣ることが、決して其の全面目でなく鷹掲として天地の塵を払ひ、周室八百年の基礎を築けるところ、英雄の本領、最も煥然たるを見るのである。
虚心にして偉人の言に聴き、自在に其の経論を行はしめ、以て天意を地上に実現させることがまさに吾等の務めでなければならぬ。吾等には容易に見えぬ真理を把握し、吾等の容易に能くせぬ正気を体得し、万人に先ちて見、万人に先ちて導くことは、実に偉大なる魂のみ之を能くする所である。
或時子貢が孔子に問ふた――『茲に美しい王があると致します。之を筺底に秘蔵して置いたものでしやうか、それとも眼のある買手を求めて売ったものでしやうか』と。言ふまでもなく孔子を美玉譬へての質問である。而して孔子は言下に之に答へて『之を沽(買う、売る)らんかな之を沽らんかな、我は賈を待つ者なり』と言って居る。そは恐らく孔子衷心の感懐であったらう。夢に屢々周公を見たのも、一代の希望が冶国平天下に在りしが故である。『苟くも我を用ゐる者あらは、朞月にして已に可ならん、三年にして成ることあらむ』と云ふのが、実に孔子の政治的抱負であり、拱手して道を講ずるは其の本旨でなかった。
夫れにも拘らず、孔子は世用られなかった。啻に其の経綸を天下に施し得ざりしのみならず、却って陳蔡の野に飢死せんとし、性急多血の弟子子路をして、君子も亦窮することあるかと言はしめたほどであった。而して夫れにも拘らず、聊かも世を恨み憤ることなかった。論語には孔子の起居を形容して『申々如たり夭々たり』と言ひ、孔子自身は自家の心境を『坦蕩々たり』と言って居る。かくて弟子に向っては、己れさへ誠に学ぶ所あれば決して人の知ると知らざるとに心を悩ますなと教へた。而して自ら省みては、人に知られざるを憂へず人を知らざることを憂へた。『人知らずして慍らずまた子ならずや』――等此の一句を読む毎に感概無ならざる得ない。
横井小楠が其の雄渾なる抱負を世に行ふ術(すべ)もなく、閑居して僻村に在りし頃、論語を講じたことあった。開巻学而章の講義のみ、僅かに弟子の筆記に残り収められて小楠遺構の中に在る。上の一句を講じて下の如く説いたーー『これ古人己れが為にするの学にして、存養の工夫なり。
一通りの人にして時に用ゐられざるを慍らずとも、未だ弟子と称するに足らず。努力の積リて信従するもの多く、一代の碩儒とも云ふ可きほどの人才にして、世に用られず九王に明にふ時、少しも慍らざることこそ、真の君子と云ふ可きなれ』。
此の解秋は、決して前人の未発を言へるものでない。而も吾等之を読んで常に心を打たれるのは、小楠木自身が世に遇はすして僻居せる間の講義なるが故であゑにもまた知られざる偉人の一人であった。
明沿を維新の前後、英雄雲の如く多くある。而も最初に指を屈せらるべき三人は、恐らく南州海舟小楠である。西郷南州及び勝海舟は、仮令其の真直目を解するもの甚だ多からずとするも、尚ほ国民全般に景仰思慕せられ辺村の児童能く其名を知って居る。
独り横井小楠木に至りては、国民の多数に忘却せられ、其名を口にする者だに少ない。
熊本の東ニ里ばかり、沼山津と呼ぶ小村がある。小楠が閑居して日夜同志と講学したるところ。
小楠木の誌に『曠原大沢西東に接し朝靄暮霞風光殊なり』
とあるのは、沼山津の景色を詠じたるものである。未だ村に入らずして小さを自然石の墓、詣でる人もなく淋しげに路傍の田圃に立って居る。既に村に入れば、目馴れぬ一棟の造作、清流に面して建てられたるがある。初夏の頃に行かば、村人の蚕を此処に飼ひつつあるを見るであらう。墓は実に小楠の髻塚であり、養蚕部屋は実に小楠講学の塾舎の跡である。
一顧して長望すれば既に十八年の昔となった。笈を熊本に負ふて五高の一学生たりし頃、或いは吾れ一人、或いは友と打連れ、沼山津の閑村を訪ふて小楠の俤を偲びたりしこと、幾度びなづしかを知らぬ。或る時は寮禁を破って、深夜窃に窓より寄宿を脱け、沼山津に至りて小楠墓前に黎明まで坐したることもある。満地の霜を踏んで帰りしことを想へば、晩秋か初冬の頃であったらう。青春多感の年ごろのことなれば、熊本の人々が彼等の間より出でたる最も偉大なる一人に対し、其の墳墓を草莽に委し、其の塾舎に蚕を飼はしむるを見て、聖書に『予言者その家郷にては敬重(たふと)まるるものに非ず』とある言葉など思ひ合せ、窃に涙を催したこともあった。総て予に取りて忘れ難き思出を新たにしつつ、横井小楠の志操と 信仰とを探り、其の体達せる悟得と、其の徹底せる識見とを学び且味はひて、吾等の衷なる日本精神の長養に努めるであらう。
ニ 英雄的精神の把持
『五尺の短身 一竹昻
千山万水 去って蹤なし
平生の心事 知る何れの処ぞ
寄せて在り 英蓉第一峯』
安政末年か交久初年の頃である。さなきだに落日の如かりし徳川驀府の運命は、米国軍艦の來航、大震災の頻発と矢継早の内憂外患に、一層衰亡を早められた。勤王党と佐幕党との拮抗、攘夷党と開国党との激論は、日に日に、深刻激越となり、天下騒然、人心恟々たる時であった。王佐の志き抱きつつ、而も超然として熊本城東沼山津に退閑して居た小楠の寓居に、鮫島と云ふ若侍が、江戸に上ると云ふので暇乞に来た。革命的熱情抑え難く、東上して改造運動に奔走しようと云ふ青年であった。茲に掲げた七絶は、其時鮫島に贈れる小楠の詩である。
小楠は其門に集まる諸士に向って、常に『人間は第一等を心がけぬばならぬ』と訓誡して居たが、いま鮫島と云ふ青年にも、日頃の訓誡を詠じて餞(はなむけ)としたのである。小楠の伝紀に『「先生身材中人に及ばず』とあるから、随分小男であったに相違ない。さてこそ『五尺の短身一竹筇』である。
年少藩命を受けて江戸に遊学し、先年また中国から近畿東海北陸諸国を経めぐって、山と云ふ山、川と云ふ川の数々を踏破したが、総じて心に残る跡とてもなく、一顧茫々夢の如しである。
乍併唯だ一つ、はっきりと心に刻まれて居るのは富士山だけ、そして吾心は常に其の富士至高の絶巓に寄せてある。
『寄せて在り芙蓉第一峯』――小楠はこれから国事に奔走しようと云ふ血気の青年に、此の覚悟を求めたのだ。成功を祈ると言わず、高名を揚げよとも言はない、たヾ人間として至極の覚悟を求めたのだ。而して其覚悟とは、取りも直さす清高明朗なる精神――最も剴切に富士によって象徴せられる至高の日本精神を、徹底して把持することである。
この訓誡は、今日の吾等に取りて、一層切実な意義がある。英雄的精神を鼓吹する教育は、畸形児を養成する所以として批難せられる当今である。合衆国の教育に『良民』を造るのが目的である、日本も今後は凡人教育で行かねばならぬなどと、埒もなき議論が真面日に主張せられる時代である。生物としての生存競争に有能であることが何よりも重んぜられ、感情を喜ばす快楽が何よりも持囃(ソウ、はやし)され、金銭に換算し得る利益が何よりも貴ばれ、それ以外のものは総じて当世にそぐわぬものとして斥けるられる時代である。革命改造を志す人々も、概ね外面的制度の更新により、自働的に向善の世界が現出するかに考へ、憂国愛人の気を専ら各種の制度改革運動に傾け、動もすれば至極の一大事を忘れ去らんとする。
さり乍ら、個人と言わずまた国家と言はず、其の最後の根底は竟に拠り立つところの精神に在る。一切の外画的制度は、所詮精神の具体的発現に外ならぬ故に、日本国家を改造すると云ふことは、取りも直さす吾等の精神を改造することである。面して精神を改造すると云ふことは、真価の日本精神に復帰すること――常に心を芙蓉の第一峯に寄せることである。
さて小楠の日本精神とは、決して偏狭にして矜高なる島国根性のことでない。攘夷が天下の興論となり、国民は或は極度の猜疑を以て外人を待ち、或いは極度の侮蔑を以て之に対して居た時、独り小南は卓然として主張したーー『外人もまた一天の子でないか、然る以上は之を待つに天地仁義の大道を以てせねばならぬ』と。かくて水戸一派の保守的慷漑家に対しては、実に下の如き痛棒を加へて居るーー『格別見識もなく、従って大策もなく、ただ大和魂とやらを振廻す人々は、外人を以て直ちに無道の禽獣となし、最も甚しきは初より之を仇敵視して居る。天地の量、日月の明を以て之を見るならば、何と云ふことであらう。この頑冥固陋が、国家蒼生を過らんとすることは、痛嘆限りなき次第である。』。
日本は栄螺のやうに蓋を鎖ぢて、小さくなって居るべき国でない。富国強兵を理想とする人があるけれど、富国強兵に止まりては役に立たぬ。日本の使命は実に『大義を四海に布く』ことに在る。
貴舜孔子の道を明かにし、石洋の技術を吾有とし、日本の国家を一新して西洋に普及するならば、道義を基礎とする真実の世界的平和が、必ず招徠せられるであらう。而して『此道本朝に興る可し』と言ふのが実に小楠の堅き信念であった。されば其の敬愛せる弟子元田永孚に向かって、下の如き抱負を洩らしたことがある――『苟くも吾を用ゐる者であらば、吾れ当に使命を奉じて先づ米国を説き、一和協同の実を挙げ、然る後に各国を説き、遂に逐に四海の戦争を止めるであらう』。
こは元田が驚嘆したるが如く『『遥かに世論の外に出でたる見識』である。小楠は如何にして是くの如き徹底せる見識を養ひ得たか。固より天禀の俊秀が大いに与って居る。而も小楠の詩に『斯道懐に在る三十年』とあり、また『終身堅苦の力を尽し得て、雲霧を披いて青天を見んと欲す』とあるによつて知られる如く、そは実に久しき行蔵、濃かなる鍛練の賜の外ならなかつた。
『功利に流れず、大丈夫の心聖人賢を希ふ』――小楠は此心を以て厚く自ら修めたのである。
功利に流れずに禅に流れずと云ふ一句、意味最も深長である。日本精神の真個の具現者は、皆な功利に流れずに禅にれざる人格者であった。自雲の地に托して天に遊ぶが如き風格は、恐らく日本独特のもので中らうか。真如の光明を捕へつつ煩悩界中に拮据し、世を超越して而も世と離れて而かも世と離れない。功利主義者現実主義者の典型のやうに思はれて居る徳川家さへ、其の晩年は天海僧正の法談を無上に楽しんで居た。たまたま、駿府から江戸に出る。色々と政治向きの用事を以て目通りを願ふ重き役人も、天海の法談が済むまでは、更に相手にされなかった。さればとて家康は決して仏いちりばかりの好々爺になり了うせたのではない。満腹の経綸は年と共に精緻となったのだ。
平野国臣と言へば、剣気覇気に満ちたる志土を想像するかも知れぬ。然らば先づ下に引く彼の歌を読め――
君が代の安けかりせば予てより
身は花守となりけむものを
と。彼れもまた徒らに狂狷乱を好む所調実行家肌の人ではなかった。花守ともならまほしき清高隠逸の心を抱きながら、止むに止まれす君国の大羲のために剣を執って起つたのだ。事成らすして斃れたとは言へ、彼の此の精神は、啻に明治維新の基礎となりしのみならず、長久に国士の魂に宿って生きるであらう。実利に没頭して魂を忘れ、彼岸に憧憬して現実を軽んずるは、両つながら竟に日本精神の真面目でない。かかる二元的態度を脱却し、天理を明かにして心を当世に尽すことこそ、げに日本英雄児の本領である。