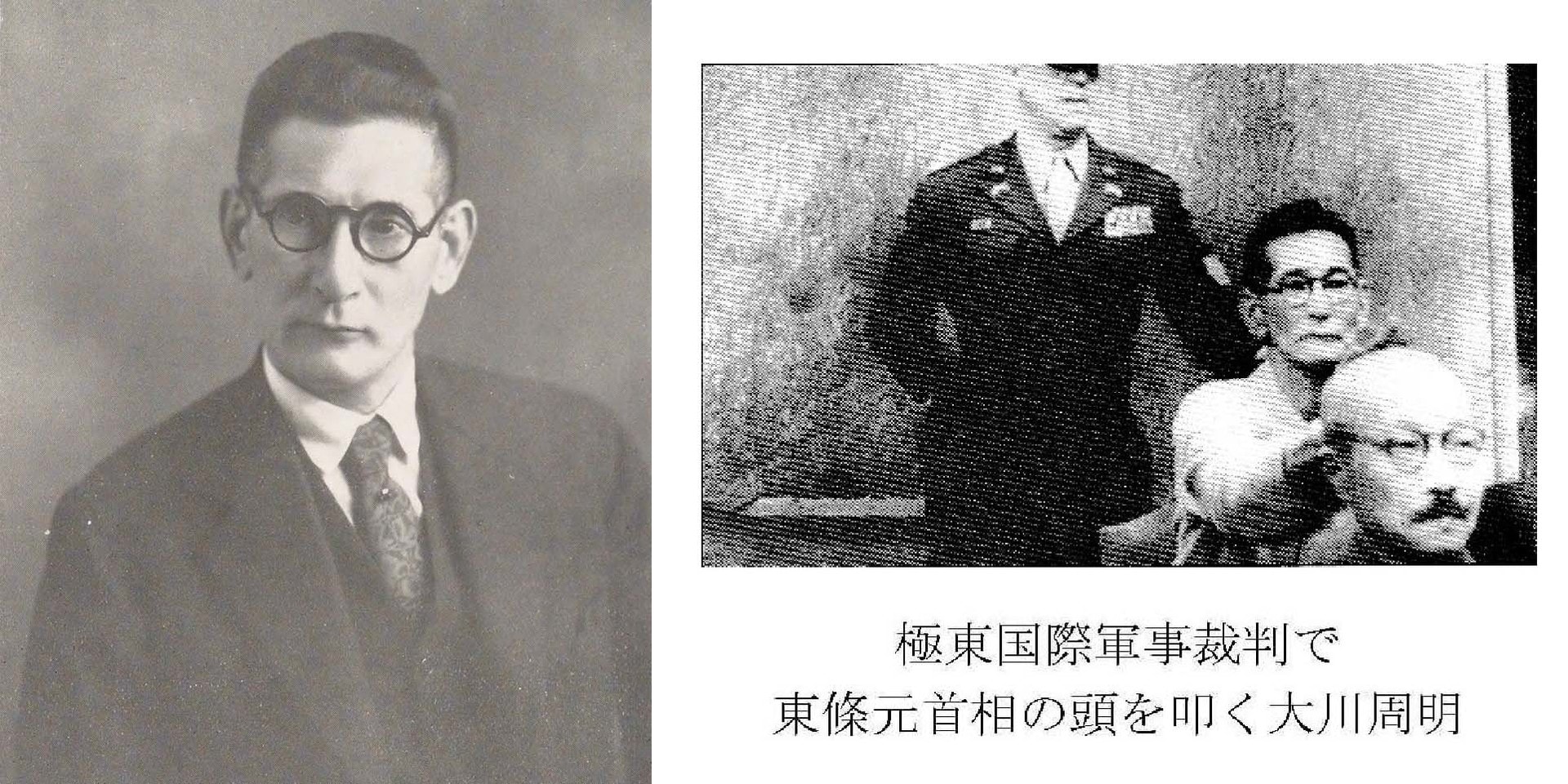大川周明
大東亜戦争第二段に入る
イギリス東洋制覇の牙城シンガポールは、世界地図の上から永遠に其影を没し、復興亜細亜の根拠とし湘南島が芽出度くて誕生するに至った。世界維新のための戦としての大東亜戦は、僅かに宣戦以来七旬にして、其の最も光栄ある第一段が終了した。
大東亜戦の第二段階は、イギリスの桎梏からビルマと印度とを解放することである。日本政府は、ビルマ人および印度人に向って、彼らの独立のための努力に満幅の援助を与ふべきことを世界の前に宣言した。倒英という抽象的なる標榜は、此の宣言によって初めて適確なる具体的内容を賦与された。
自由を獲たる印度と覚醒せる支那が日本と相結ぶことによって、大東亜共栄圏の確立は初めて可能であり、新しき世界文化の創造もまたはじめて可能である。多年に亘って鉄鎖に縛られ来れる不幸なる民よ、起って其の鉄鎖を寸断せよ。それによって自らを救い、且新しき世界の出現に参与せよ。
(昭十七・一)
清朝創業の教訓
徳川幕府の初期は、特に寛永二十一年、越前国三国港の商民が、蝦夷松前に向ふ途中、暴風のために満州に漂着した。
時恰も支那に於ては明朝の社稷脆くも崩れ、清朝入関の順治元年に当る。一行五十八名のうち四十三名は土民のために惨殺され、残りの十五名は満州官吏によって韃靼国の都奉天に護送され、暫く此の処に滞留の後、更に北京に転送、留燕一年の後に朝鮮を経て日本に送還された。彼らが江戸に召喚されて『数多委細に相尋ね』られたのに対する『口上の段々』を書留めたのが即ち『韃靼漂流記』である。此書は種々なる点に於いて吾等の興味を惹くものであるが、最も深く吾等の心を打つことは、彼等の目に映じたる満漢人の相違、即ち満州人の漢人に対する道徳的優越である。彼等は当時の満州人に就いて下の如く述べて居る。『御法度万事の作法、ことの外分明に正しく見へ申候。上下共慈悲深く、正直にて候。偽申事一切無御座候。金銀取ちらし置候にても盗取様子無之候。如何にも慇懃に御座候。』
然るに漢人は甚だしく彼等と異なる--。
『北京人お心は韃靼人とは違ひ、盗人も御座候。偽も申候。慈悲も無之かと見へ申し候。去りながら惟今は韃靼の王北京へ御入座候に付、韃靼人も多く居申候。御法度万事韃靼の如く能成候はんと、韃靼人申候』
満洲人が支那四百余州に君臨するに至れるは、世人が往々にして想像する如く、決して武力によったのではない。漢民族をして彼等に臣附せしめた最大の原因は、実に彼等の優れたる徳性である。いま大東亜の指導者たらんとして居る吾等に取りて、清朝創業当時の歴史は深甚なる教訓を含む。吾等は専ら欧米の植民政策に学ぶことを止めて一層誠実に東洋に於ける異民族統治の跡を顧みる必要がある。
(昭和十七・四)
大東亜建設の歩調
赫々たる皇軍の戦果を確保すべき南方諸地域の建設は、既にその人的配置や機構の配備を終り、着々と進捗している。大東亜戦争は漸く建設戦の性質を帯びて来たのである。
建設の第一要諦は自衛のために不可欠の物資を開発流通せしめると同時に、長く英・米・蘭等支配勢力の桎梏下にあった南方諸民族の心田を啓発するにあることは言ふまでもない。単に従来の英・米向け物資が東方に回帰する、といふだけでわれわれの目的は半ばをも達したといふことはできない。磁針がつねに北を指すごとく、南方諸民族が日本を中心には高度の物質文化・精神文化に朝宗するとき、大東亜新秩序の建設が初めて実現せられるのである。
乍併、既に其処に現存する物資の開発や流通を図るのと異なって、民族精神に方向を与え、秩序を樹てることは、決して短日月に行われるのではない。それは永遠の目標を高く掲げて進むべき世界史的な創造を意味する。従って、大東亜建設の同町にもそれぞれ緩急自在の用意あるべきことを忘れてはならない。指導者は常に民衆の心とともにあり、而も一歩を擢んで全体を推進せしめるところに使命と名誉を担ふのである。我々は大いなる建設に直面して、長短自在のコースを走破すべき活力と歩調を自ら整えざるを得ないのである。
(昭十七・五)
大東亜戦の理想
偉大なる真個の尺度は空間でない。真個の偉大は何間何尺と測らるべきものではない。国のの理想は単に表面に於て拡がるだけでなく、高さに於て昂まるべきものである。一国が領有するのは土地だけでなく、一国を形成する人間である。その人間は発達すべきものである。その発達とは、数の増加だけでなく、実に価値の向上である。
最も偉大な国家とは、其の領土と人口との大に加えて、其の国内に於て『道』が至高の発揮を見る国家である。大東亜の理想は、古今に通じ中外に施して侼らざる『道』を大東亜に確立することでなければならぬ。理想は往々にして単に唱えられるだけで、その実行を見ざるを常とする。日本は断じてその轍を踏んではならぬ。若し然らずば、過去に於て国豊に権威張り、四方を征服して領後の拡大を誇り、而も今は廃墟となれる諸帝国の跡を追ふこととなるでろう。
(昭十七・六)